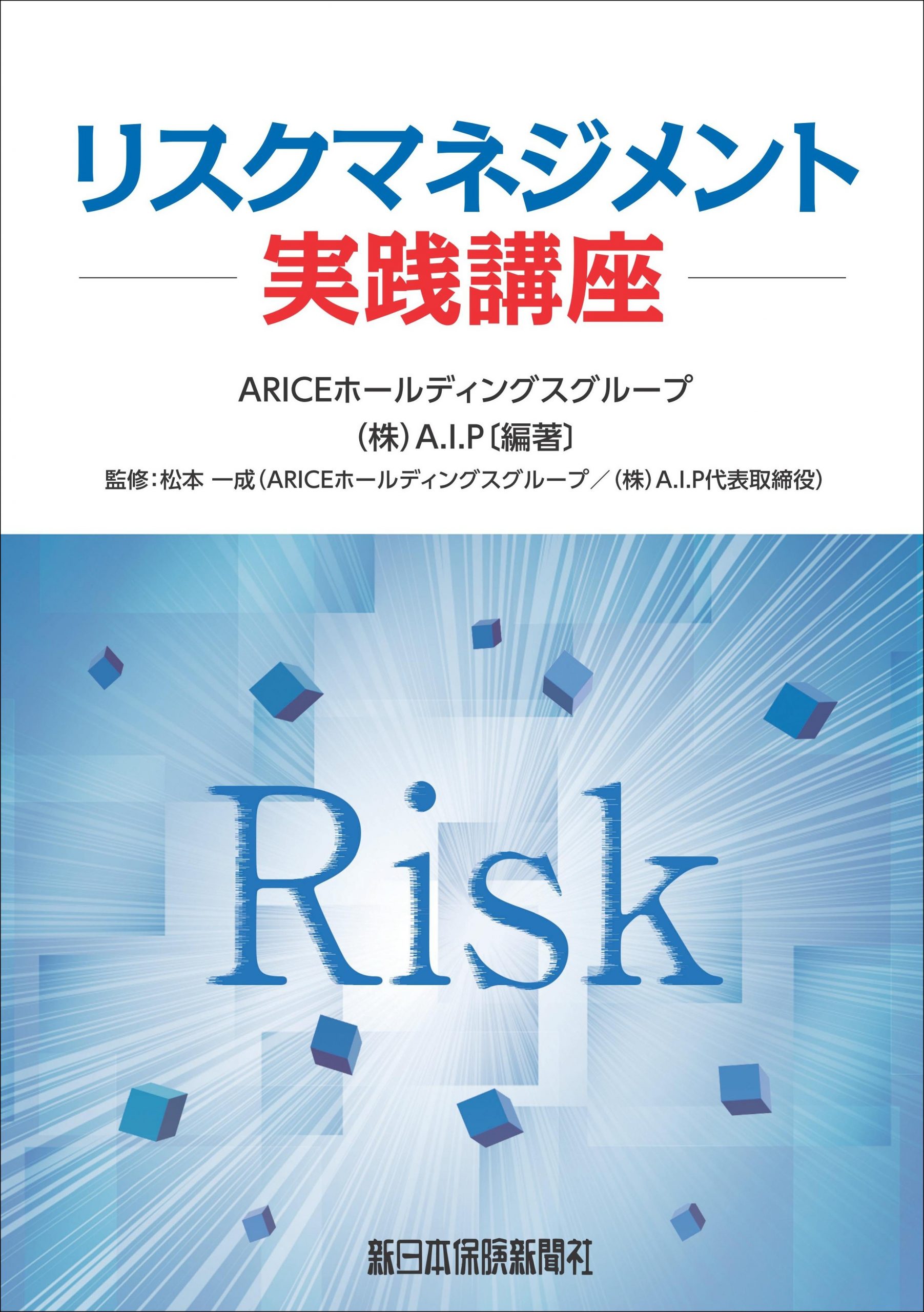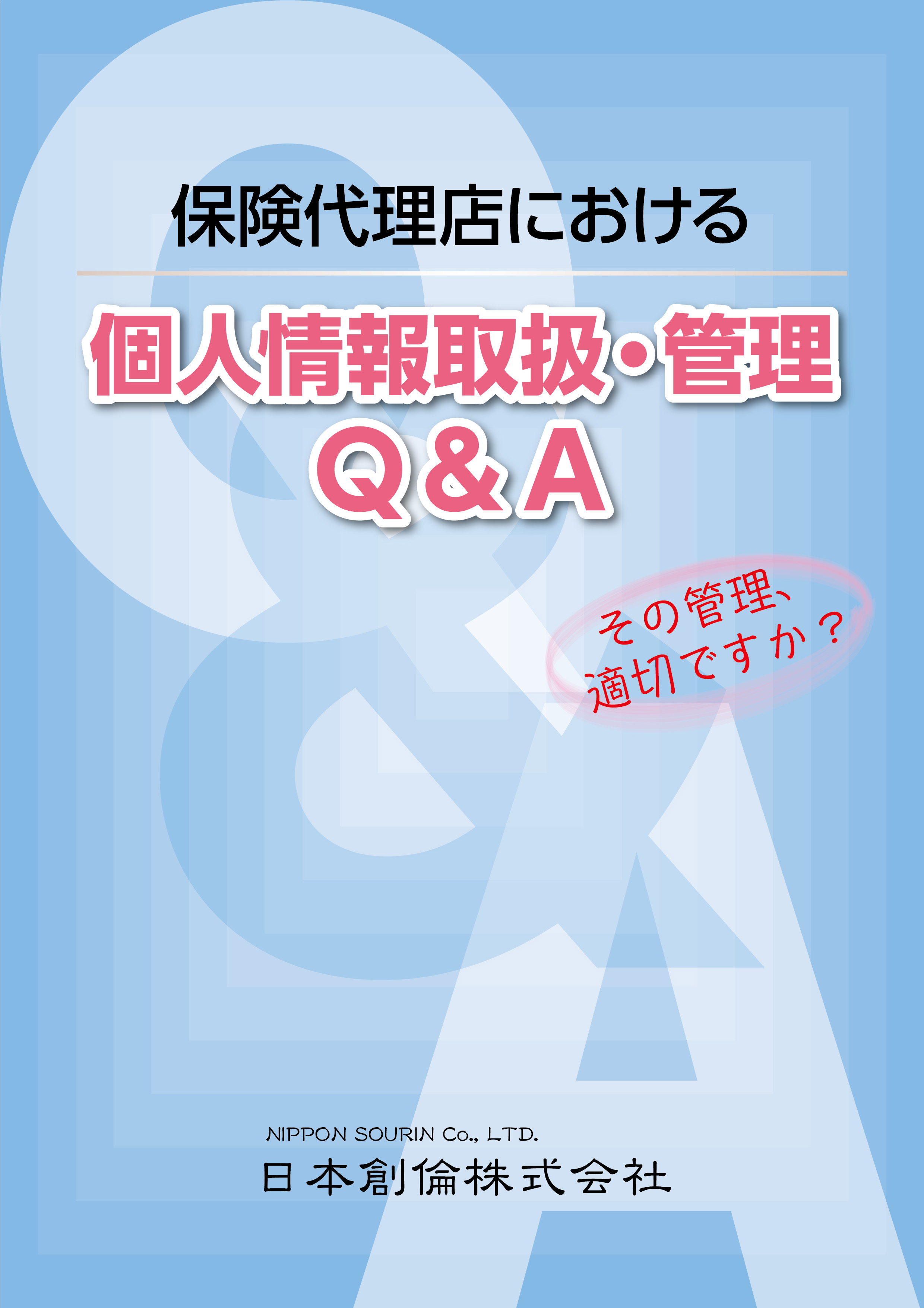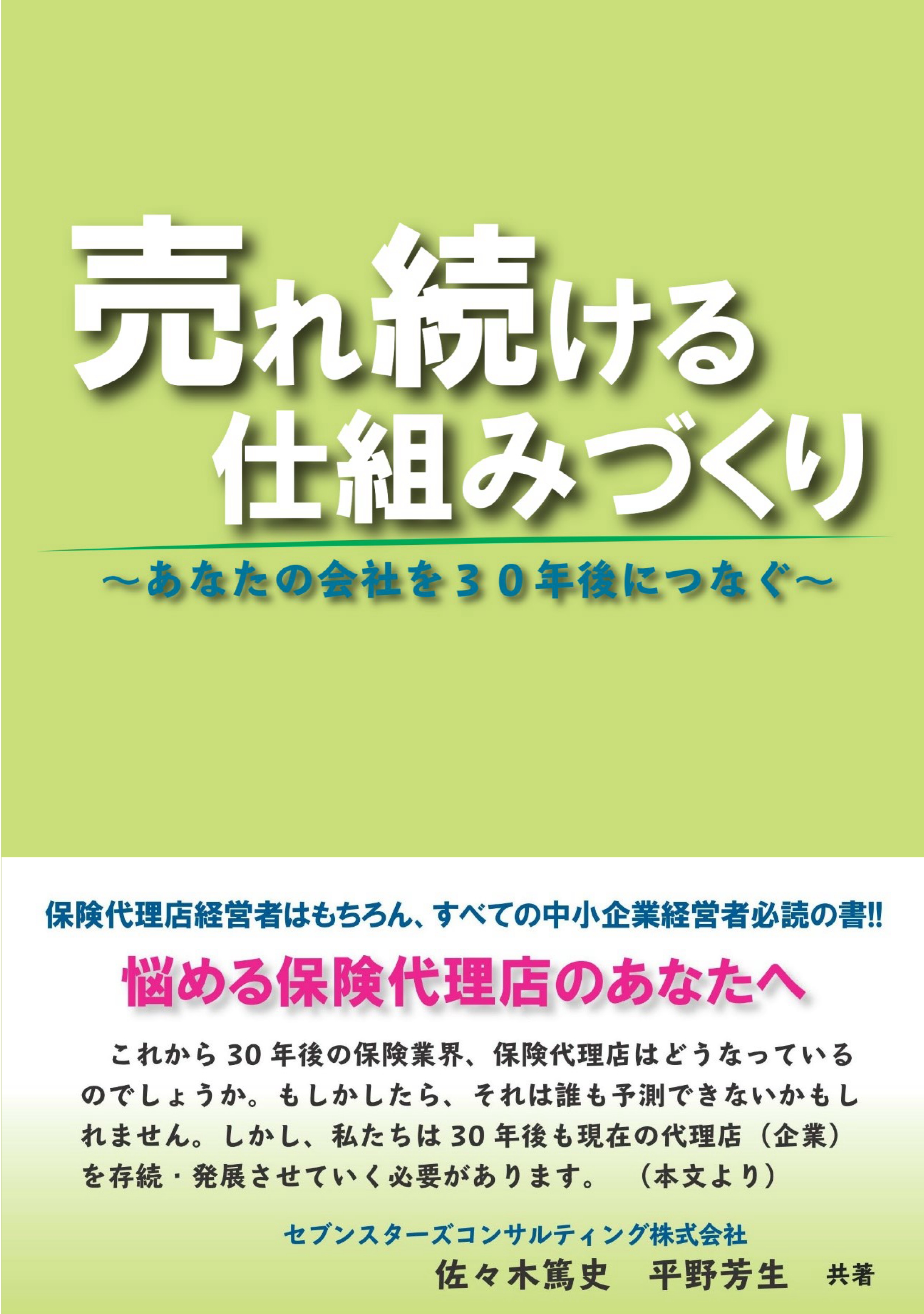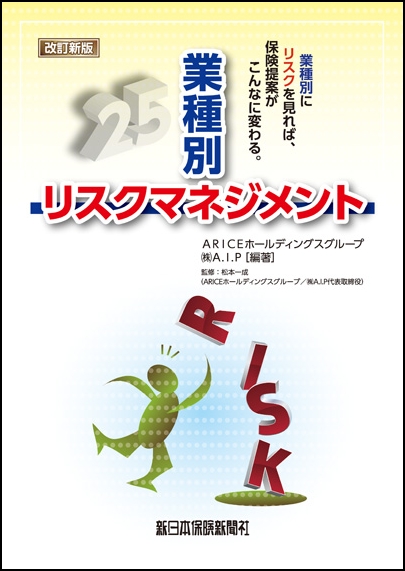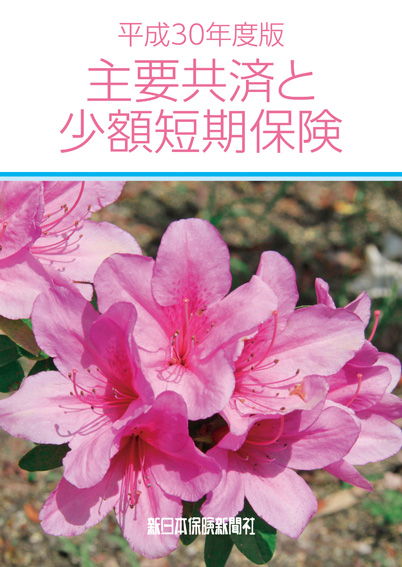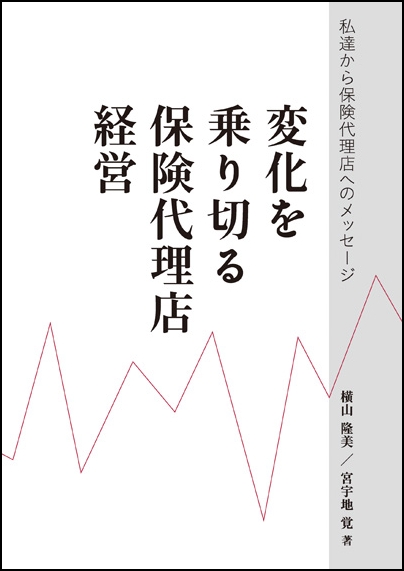損保料率機構、防災科研と雹(ひょう)災リスク評価に関する共同研究契約を締結
損保料率機構は、国立研究開発法人防災科学技術研究所【略称:防災科研】と、雹(ひょう)災リスク評価に向けて、損害保険データと気象レーダを活用した網羅性のある降雹データセットを整備するための共同研究契約を締結した。
【共同研究の背景】
近年、大規模な雹災害が相次いで発生している。これを受け、雹災リスクの適切な評価とともに、この災害の多発が昨今の気候変動によるものなのか、また気候変動にともなって今後どのようにリスクが変化していくのかといった点への関心が高まっている。これらの点を明らかにするためには過去の降雹域やその強度(雹の大きさ)に関する綿密なデータが鍵となる。しかしながら雹は局所的な気象現象であること、間もなく融けて痕跡が残りにくいことなどから降雹の実態把握が難しく、網羅的な観測データが極めて不足している状況にある。最近では高性能な気象レーダを活用した降雹域を推定する技術が開発・実用化されつつあるが、検証データの不足から、この推定精度の評価は限定的なものとならざるを得ない状況だった。
■近年の降雹災害と損害保険の支払状況
発生日と主な被害地域/支払保険金
2024年4月16日 兵庫県/1360億円※1
2023年7月31日~8月1日 群馬県/735億円※2
2022年6月2日~6月4日 関東地方/1154億円※2
※1 損保協会の集計
※2 損保料率機構の集計
【共同研究の概要】
降雹により自動車や家屋に被害が生じた場合、損害保険の契約によって保険会社から保険金が支払われる場合がある。この保険金のデータは、降雹に関する観測データを検証するものとなりえる。本共同研究では、損保料率機構がもつ損害保険のデータおよび防災科研の気象レーダによる降雹推定技術を活用することで、その推定手法の検証・高度化に取り組み、網羅性のある降雹データセットを整備する。これら成果等を活用し、降雹の地域性や頻度を把握することが可能になる。
【今後の展開】
これにより生み出される降雹域等のデータセットは、雹災リスク研究に対する極めて有用な検討素材を提供することになる。その成果によってリスクをより適切に評価することが可能となり、ひいては合理的かつ妥当な保険料率算出への活用が期待できる。また、他のさまざまな気象データ等と合わせて分析して得られる降雹予測の精度向上、気候変動の影響評価といった将来のリスク予測などにより、防災減災につながるものと期待される。

 ログイン
ログイン 関連記事(保険業界ニュース)
関連記事(保険業界ニュース) 関連商品
関連商品