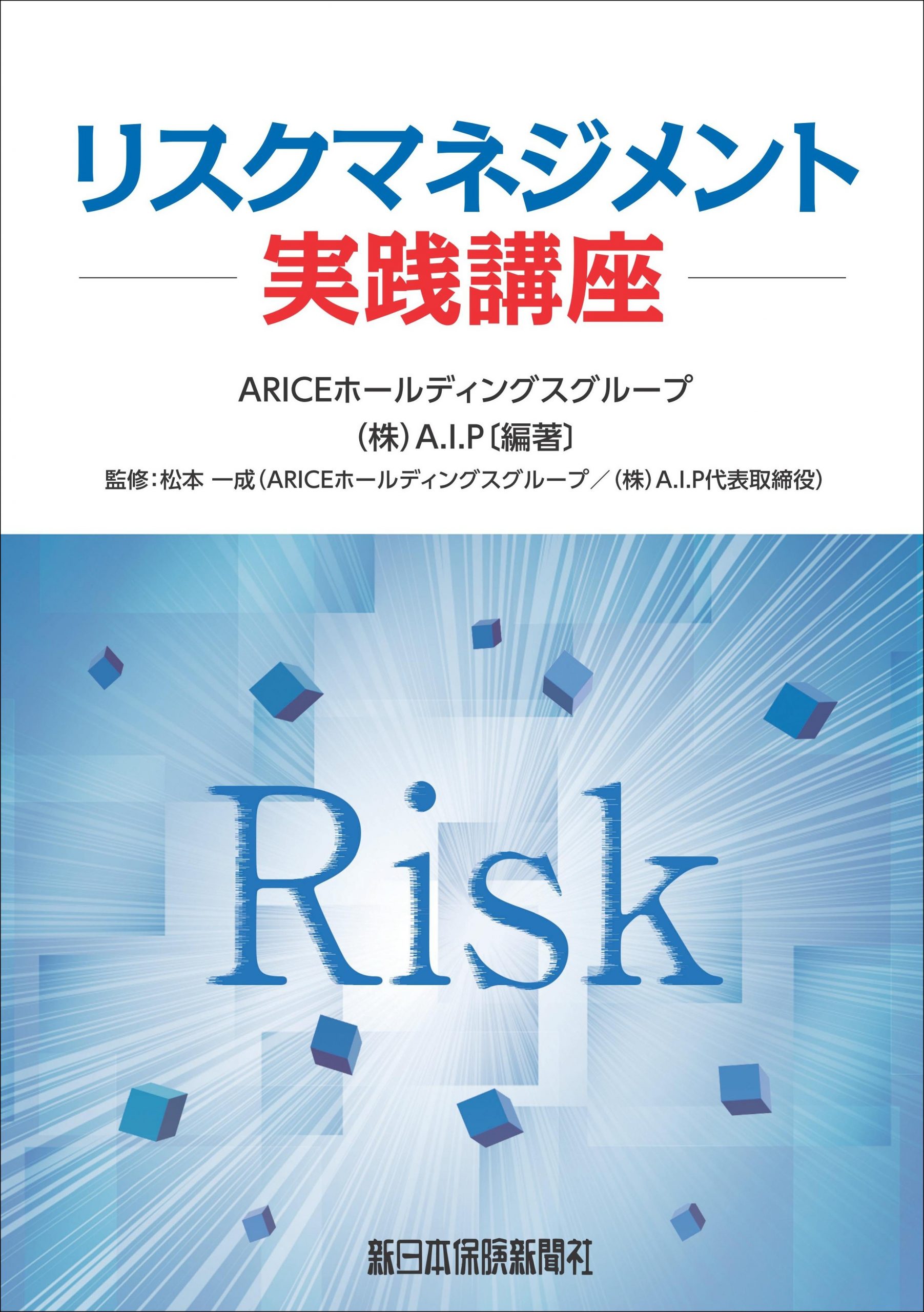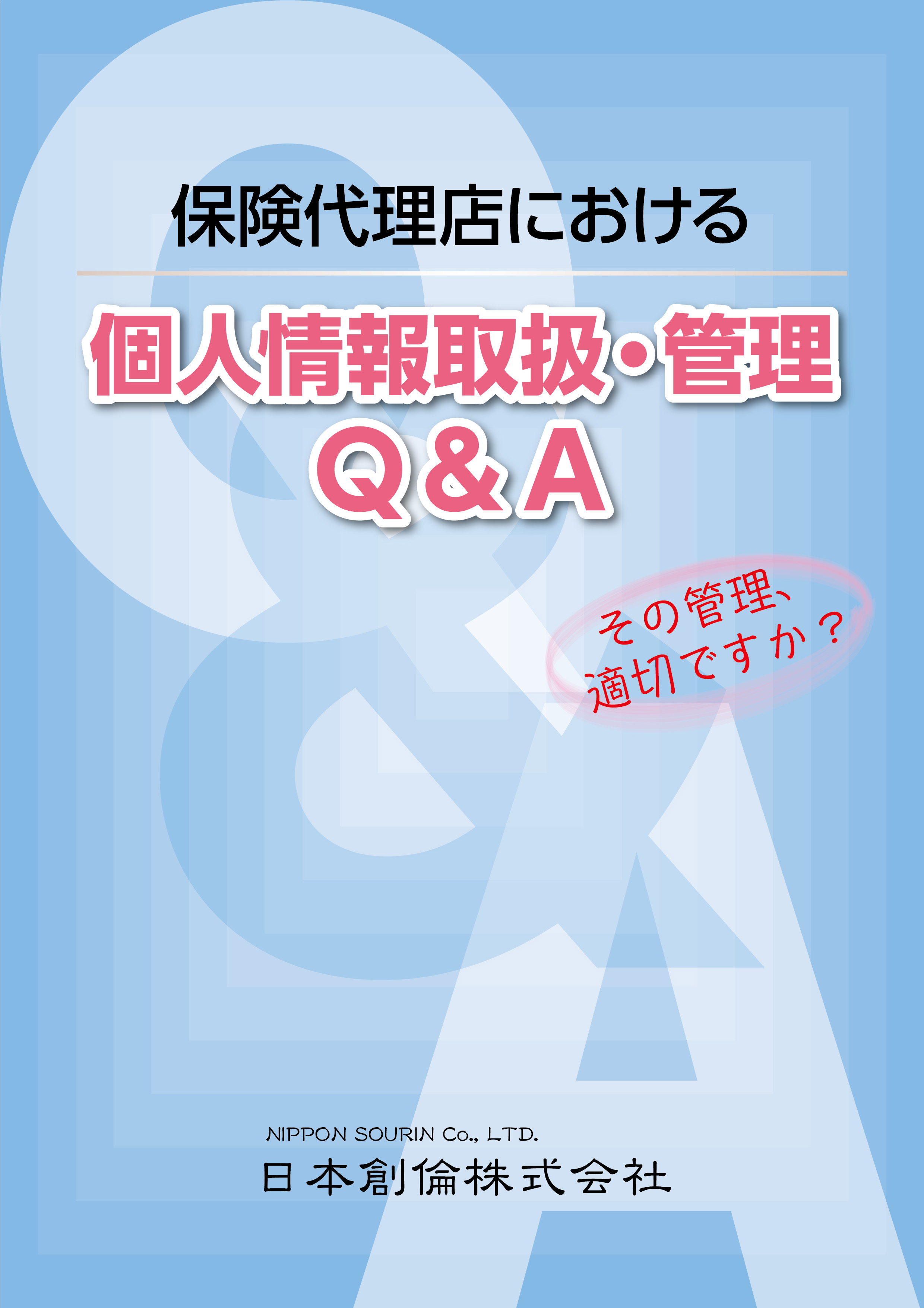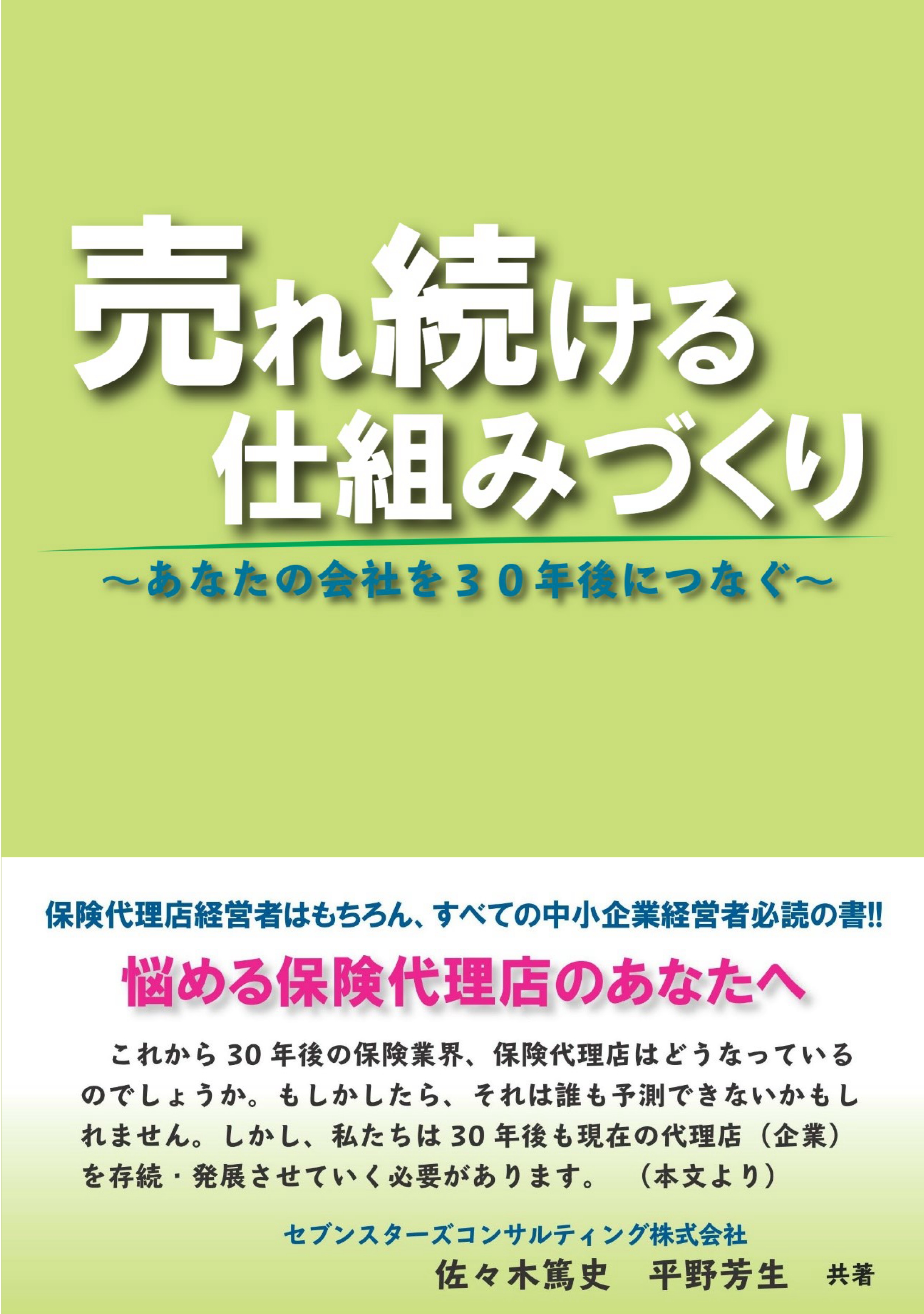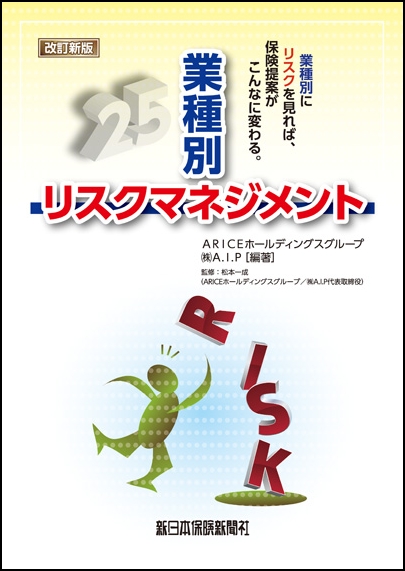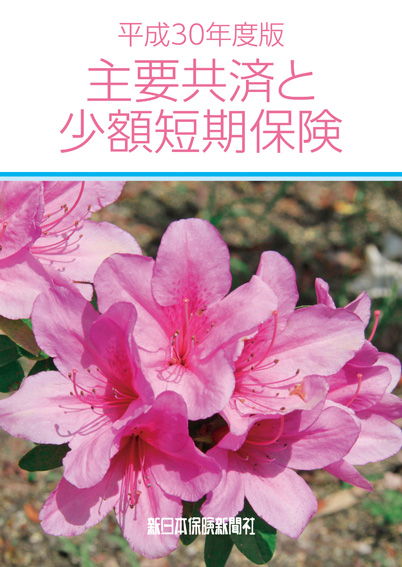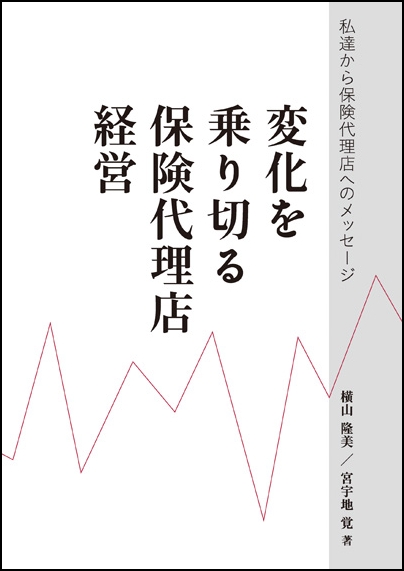あいおいニッセイ同和損保、自動車の走行データを活用した「交通安全EBPM支援サービス」を開始
あいおいニッセイ同和損保は、テレマティクス自動車保険契約を通して蓄積した地球約138万周分※1の自動車走行データを活用し、地方公共団体の交通安全対策の立案・効果検証を支援する「交通安全EBPM※2支援サービス」を2022年5月から提供を開始する。
※1 2022年3月末時点。
※2 Evidence-Based Policy Making(証拠に基づく政策立案)の略。政府にて推進されており、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータの活用が求められている。
同社はテレマティクス※3自動車保険のパイオニアとして、2018年よりテレマティクス自動車保険の販売を開始した。2022年3月には契約台数が140万台を突破するなど、テレマティクスが普及することで大量の自動車走行データが蓄積されてきた。また、「CSV×DX※4を通じて、お客さま・地域・社会の未来を支えつづける」ことを目指しており、お客さま・地域・社会とともにリスクを削減し、社会・地域課題解決に資する商品・サービスの検討を進めてきた。
今般、社会・地域課題解決に向けた新たな価値提供として、地域の危険箇所を可視化する「交通安全マップ」※5を開発し、2022年4月より全国の地方公共団体へ提供を開始した。また、交通安全マップによる危険箇所の「現状把握」にとどまることなく、把握した危険箇所を分析し、具体的な交通安全対策の「立案」と「効果検証」が可能な「交通安全EBPM支援サービス」の提供を2022年5月より開始する。
※3 「テレコミュニケーション」と「インフォマティクス」を組み合わせた造語で、カーナビやGPS等の車載器と移動体通信システムを利用して、様々な情報やサービスを提供する仕組み。
※4 CSV…Creating Shared Value(社会との共通価値の創造)
DX…Digital Transformation(データやデジタルを活用し、価値提供を変革させること)
※5 個人情報を含まない形で自動車走行データの加工・統計化を実施。
●取り組み概要
(1)「交通安全マップ」の特長
同社のテレマティクス自動車保険のデバイスから取得した走行データを活用し、交通量に対して急ブレーキなど危険な運転挙動の発生頻度が高い地点を最小約120mメッシュで地図上に可視化する。「危険挙動発生件数」のみでは、幹線道路と生活道路など規模の異なるエリア間の比較は困難である。しかし、発生件数に加え、「交通量」のデータも活用した「危険挙動発生率」による危険箇所候補の判別を行うことで、規模に依らずに評価することが可能である。また、同社の走行データは約1秒間に一度の頻度でデータ取得を行っており、一台一台の車両の挙動を詳細に分析できる。
(2)「交通安全EBPM支援サービス」の内容
「交通安全マップ」から選定した危険箇所候補の詳細分析を通じ、最適な交通安全対策メニューを提案する。加えて、対策メニューの効果検証を通じ、政策の継続・見直し等を提案し、政策の有効性向上を支援する。これら「交通安全EBPM支援サービス」を通じて、機動性の高い、また持続性のある「安全・安心なまちづくり」の実現に寄与する。
●今後の展開
今後、事故データの活用、新たな危険運転挙動の定義化、国立大学法人埼玉大学との産学連携等を通じて、本サービスの更なる高度化を図っていく。加えて、地方公共団体だけではなく、交通安全対策(標識設置等)に関連する事業者との協業も進めていく。
また、本サービスを通じて、お客さま・地域・社会とともに共通価値を創造し、社会・地域の交通安全に関する課題の解決への貢献を目指す。

 ログイン
ログイン 関連記事(保険業界ニュース)
関連記事(保険業界ニュース) 関連商品
関連商品