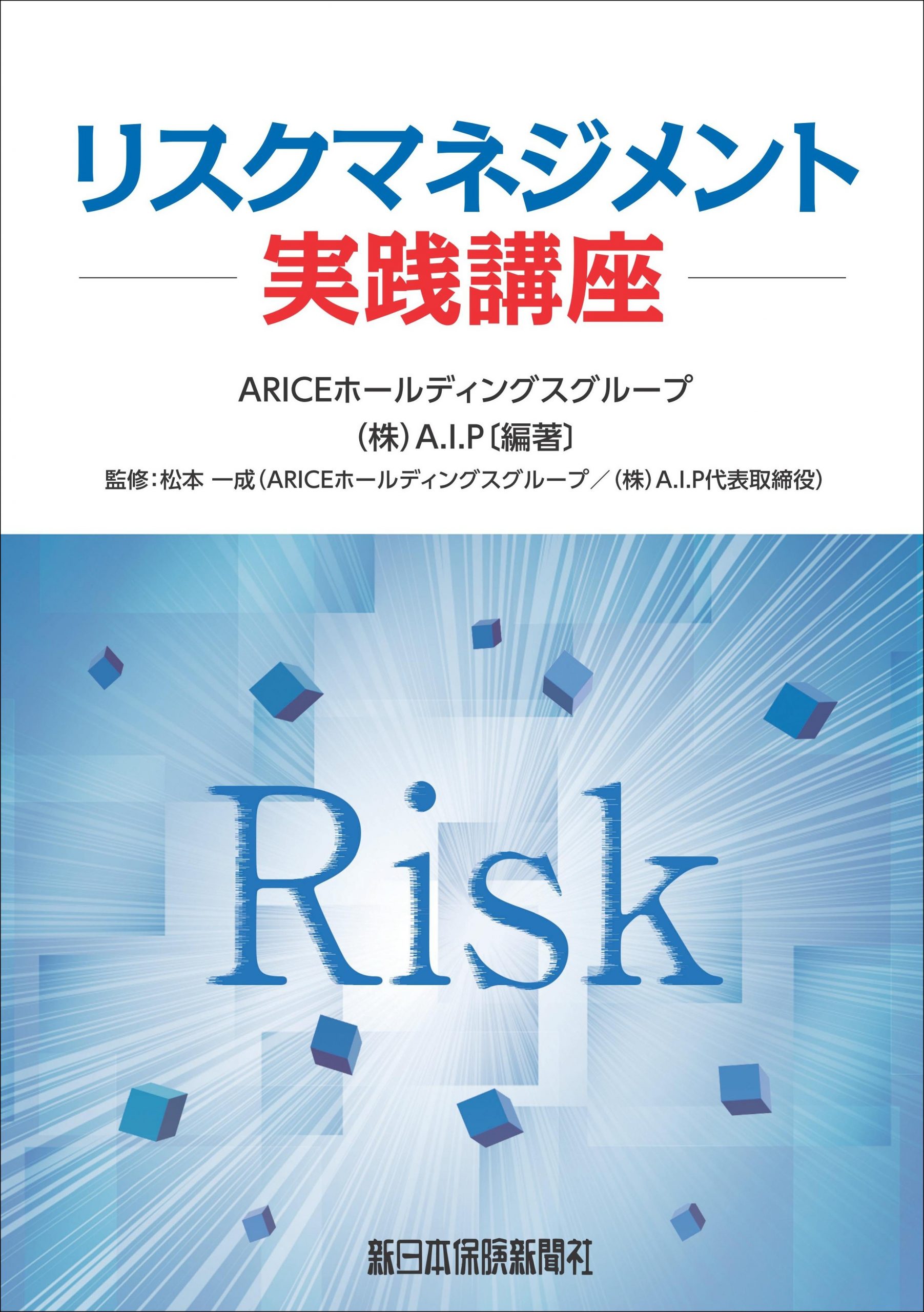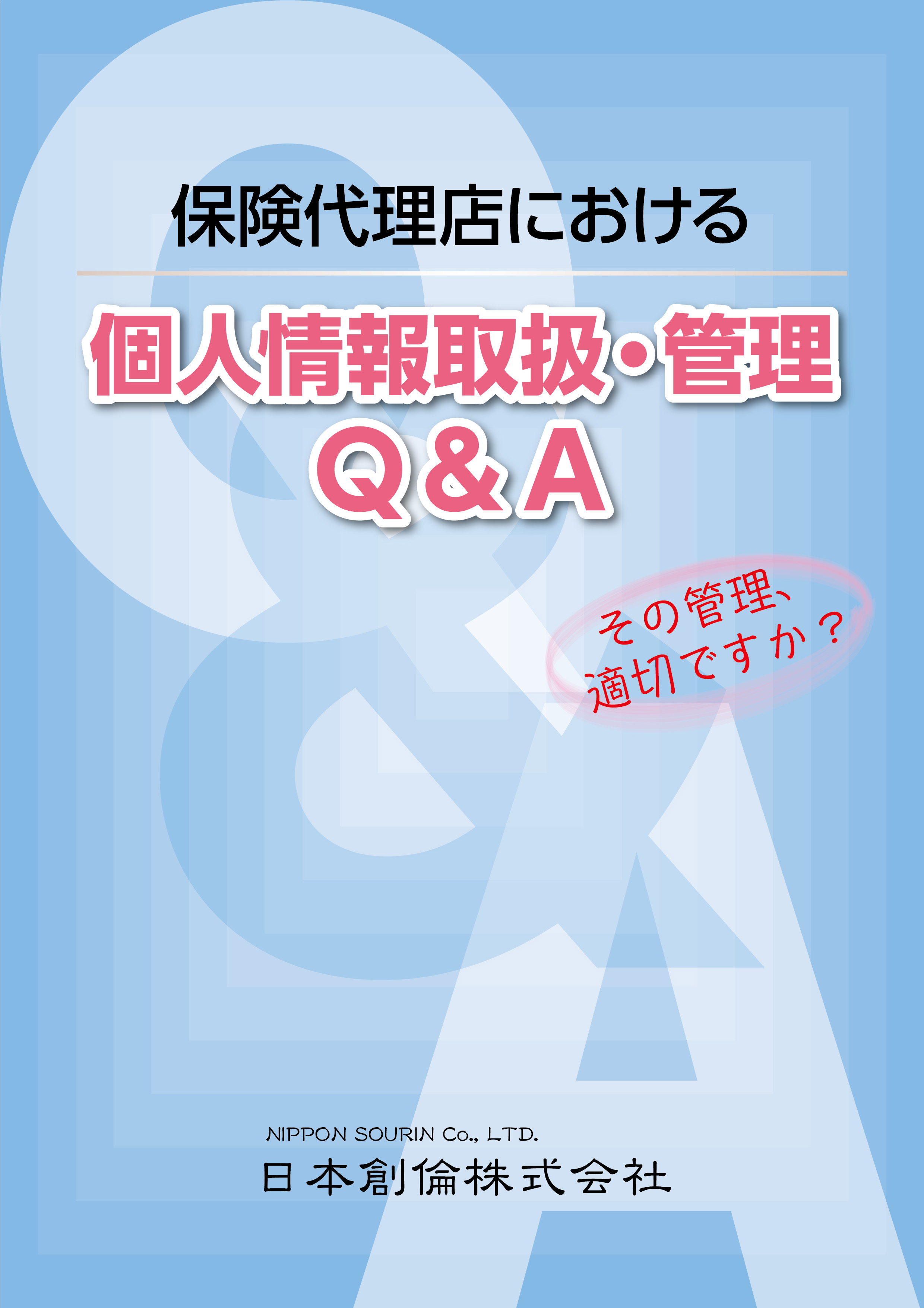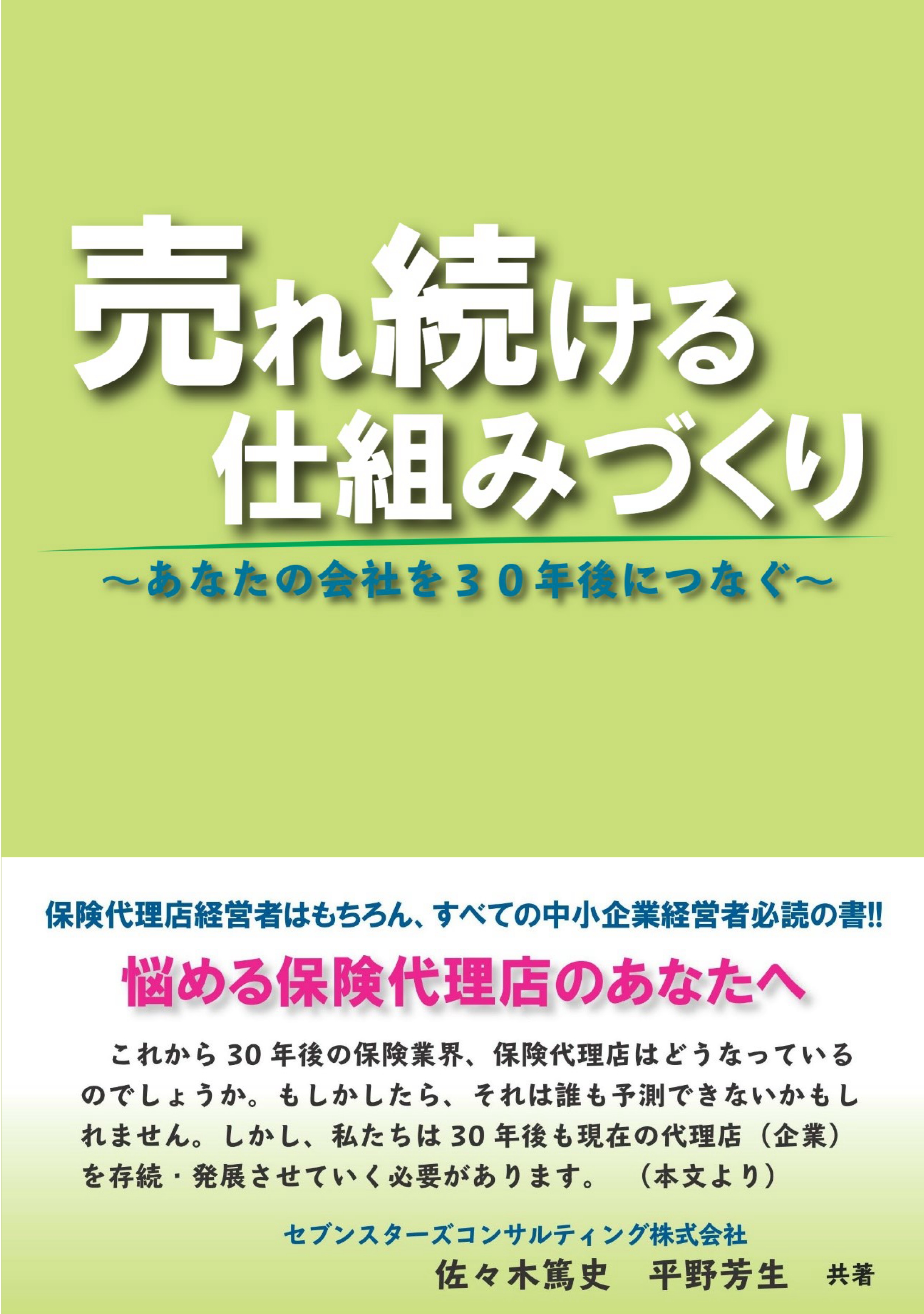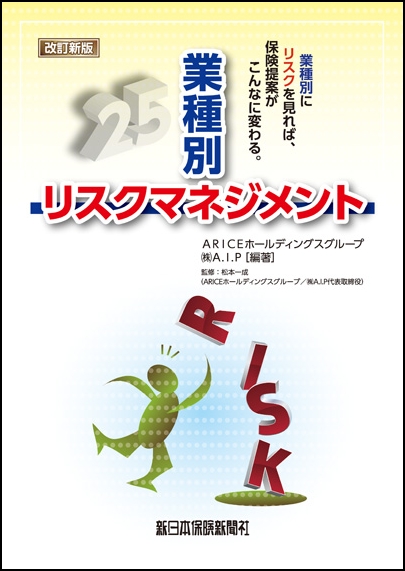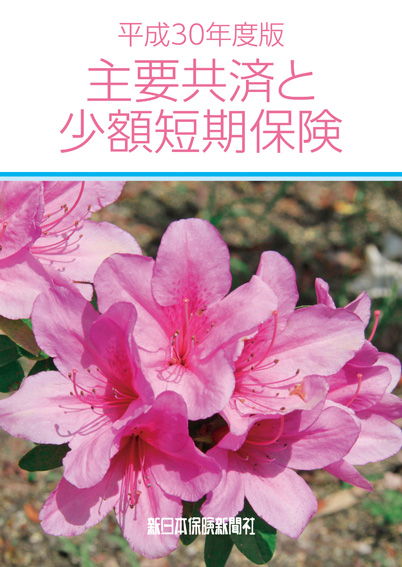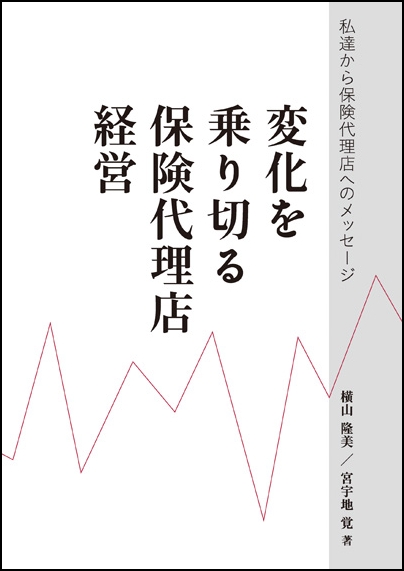あいおいニッセイ同和損保、テレマティクスデータとジオフェンシング機能を活用し安全で安心なマイクロモビリティ走行エリアを構築
あいおいニッセイ同和損保と、電動キックボード「TOCKLE」などのマイクロモビリティ・シェアリングサービスを展開するBRJ株式会社(以下「BRJ」)は、電動キックボード等のマイクロモビリティの安全運行の実現を目的に、ジオフェンシング機能※1におけるノーライドゾーン※2設定にテレマティクスデータを活用することで、適切な走行エリアを構築し、安全性の強化を図る取り組みを2025年9月1日より順次進める。
※1 GPSの位置情報に基づき、マイクロモビリティの自動走行制御を行う機能
※2 モビリティが侵入すると自動で走行を停止するエリア(歩行者が集まるエリアや交通事故リスクが高いエリア等)
1.背景
昨今、電動キックボードをはじめとするマイクロモビリティは、地域におけるラストワンマイルの移動課題の解決、観光地における回遊性の向上、さらには環境負荷の軽減といった多様な価値を持つ新たな交通手段として注目を集めている。一方で、利用の拡大に伴い、道路交通法違反やそれに起因する交通事故が増加傾向にあり、マイクロモビリティの安全かつ安心な普及に向けて、交通ルールの啓発や安全な走行環境の整備が求められている。
こうした背景のもと、あいおいニッセイ同和損保とBRJは、2023年8月に資本業務提携契約を締結し、電動キックボード専用ナビゲーションの実装に向けた実証実験や、正しい交通ルールの普及・啓発を目的とした「一般社団法人多様なモビリティの安全性向上推進協会」の共同設立など、マイクロモビリティの安全な普及に向けたさまざまな取り組みを進めてきた。
このたび両社は、BRJが展開するマイクロモビリティ・シェアリングサービスのさらなる安全性向上に向け、あいおいニッセイ同和損保が保有するテレマティクスデータを活用し、地域内のエリアごとに交通事故リスクを分析し、ジオフェンシング機能によるノーライドゾーンの設定を開始する。
2.取り組み内容
あいおいニッセイ同和損保が保有するテレマティクスデータ(累計走行距離:地球約706万周分(2025年3月時点))をもとに、自動車の急ブレーキなど危険挙動の発生頻度を125メートルメッシュで分析し、交通事故リスクの高いエリアを特定する。該当エリアをマイクロモビリティが侵入した際に自動で停止させるノーライドゾーンに設定することで、より高い安全機能の設計が可能となる。
今般、千葉県流山市におけるマイクロモビリティ・シェアリングサービス「TOCKLE」に本機能を実装し、2028年までにBRJがサービスの展開を予定している172のエリアでの展開を予定している。
<流山エリアにおける展開概要>
対象エリア:流山エリア(展開台数:約100台)
開始時期:2025年9月1日~
新たに設定するノーライドゾーン:クリーンセンター内 流山おおたかの森駅北口 等
3.今後の展開
今後も両社は、マイクロモビリティのさらなる安全性・利便性の向上に取り組み、地域社会に根ざした移動手段としての普及・定着を目指すとともに、テレマティクス自動車保険のノウハウ等を活用し、自治体など地域のパートナーと安全・安心な町づくりを目指す「SAFE TOWN DRIVE」の実現に取り組んでいく。

 ログイン
ログイン 関連記事(保険業界ニュース)
関連記事(保険業界ニュース) 関連商品
関連商品