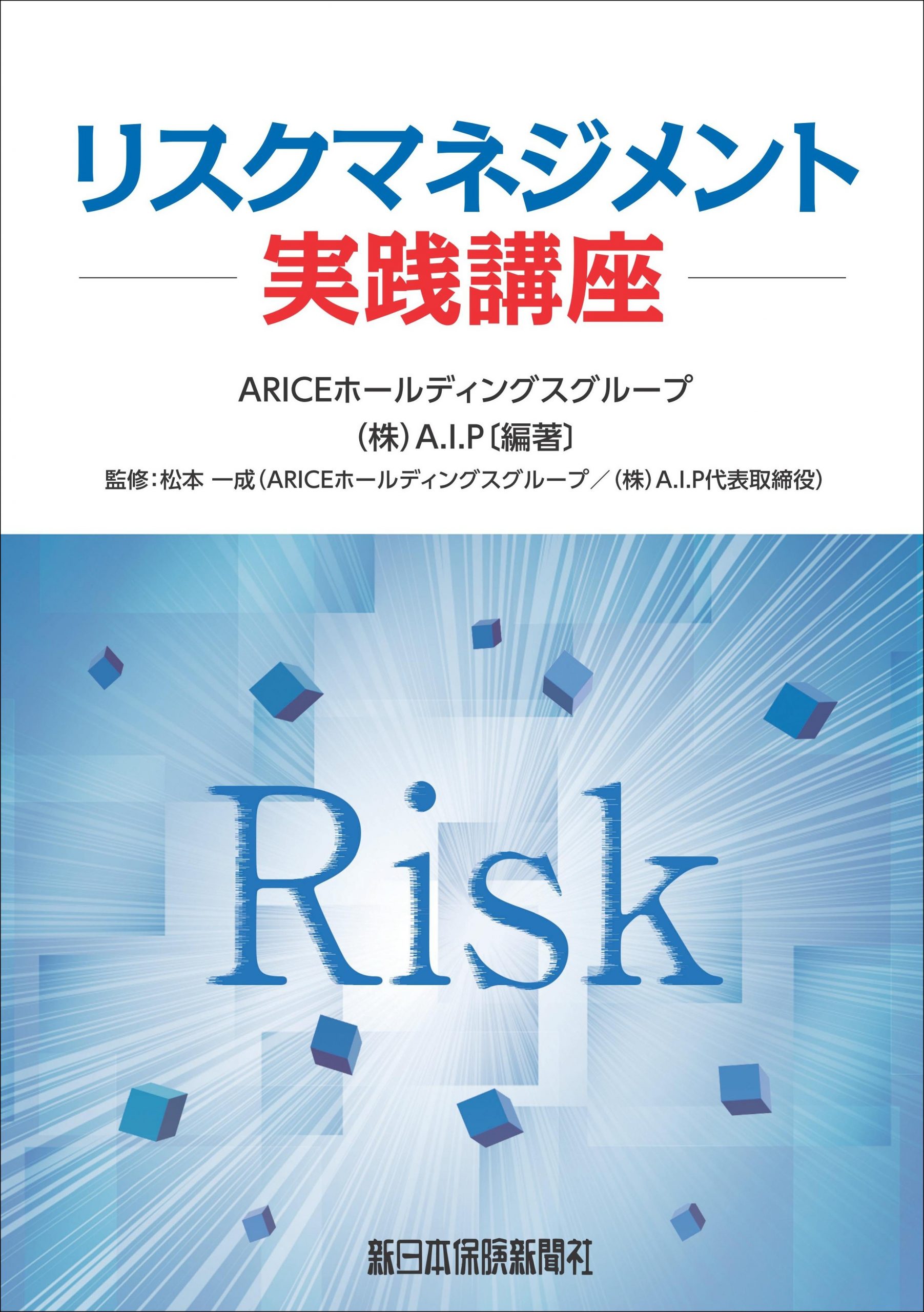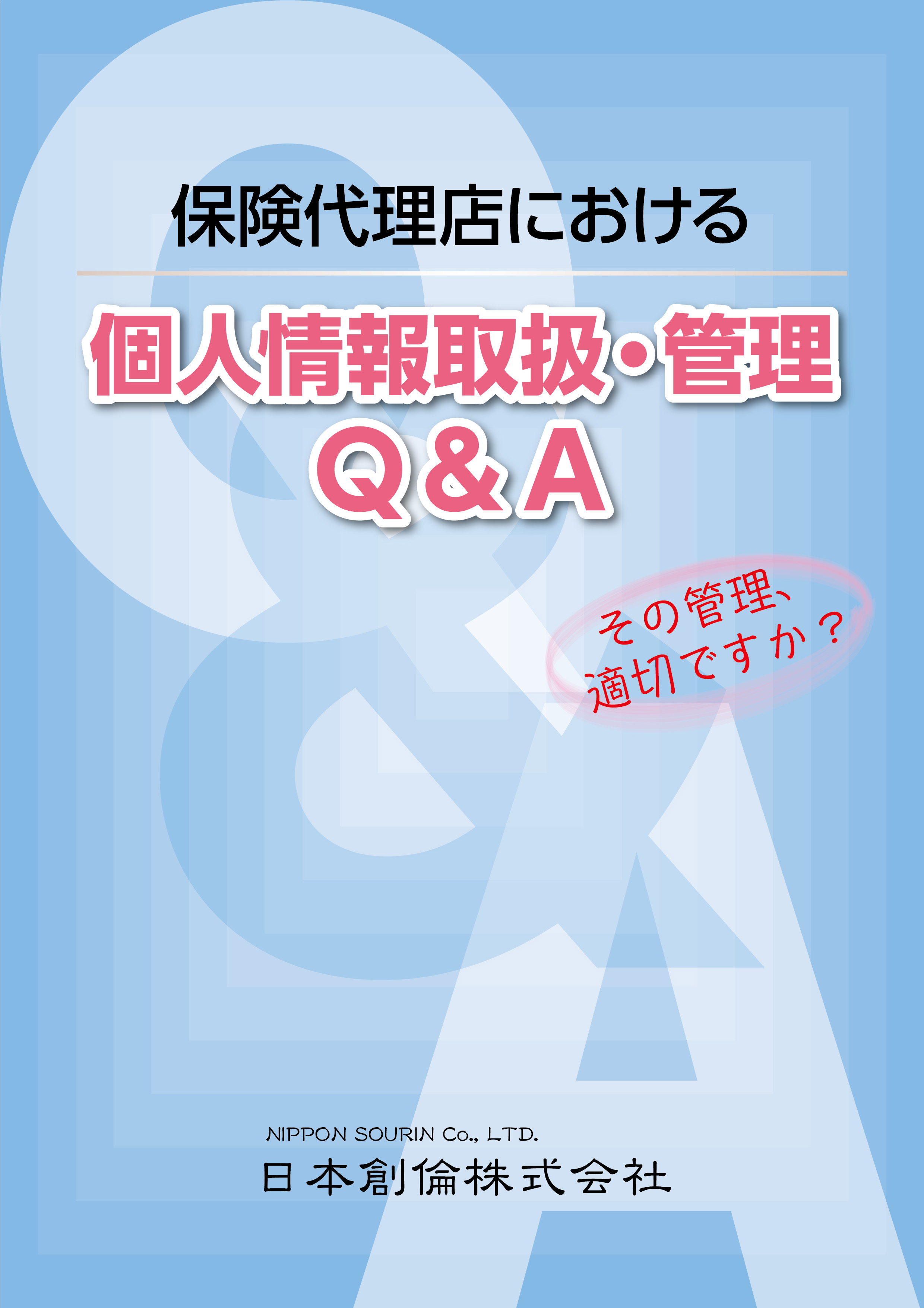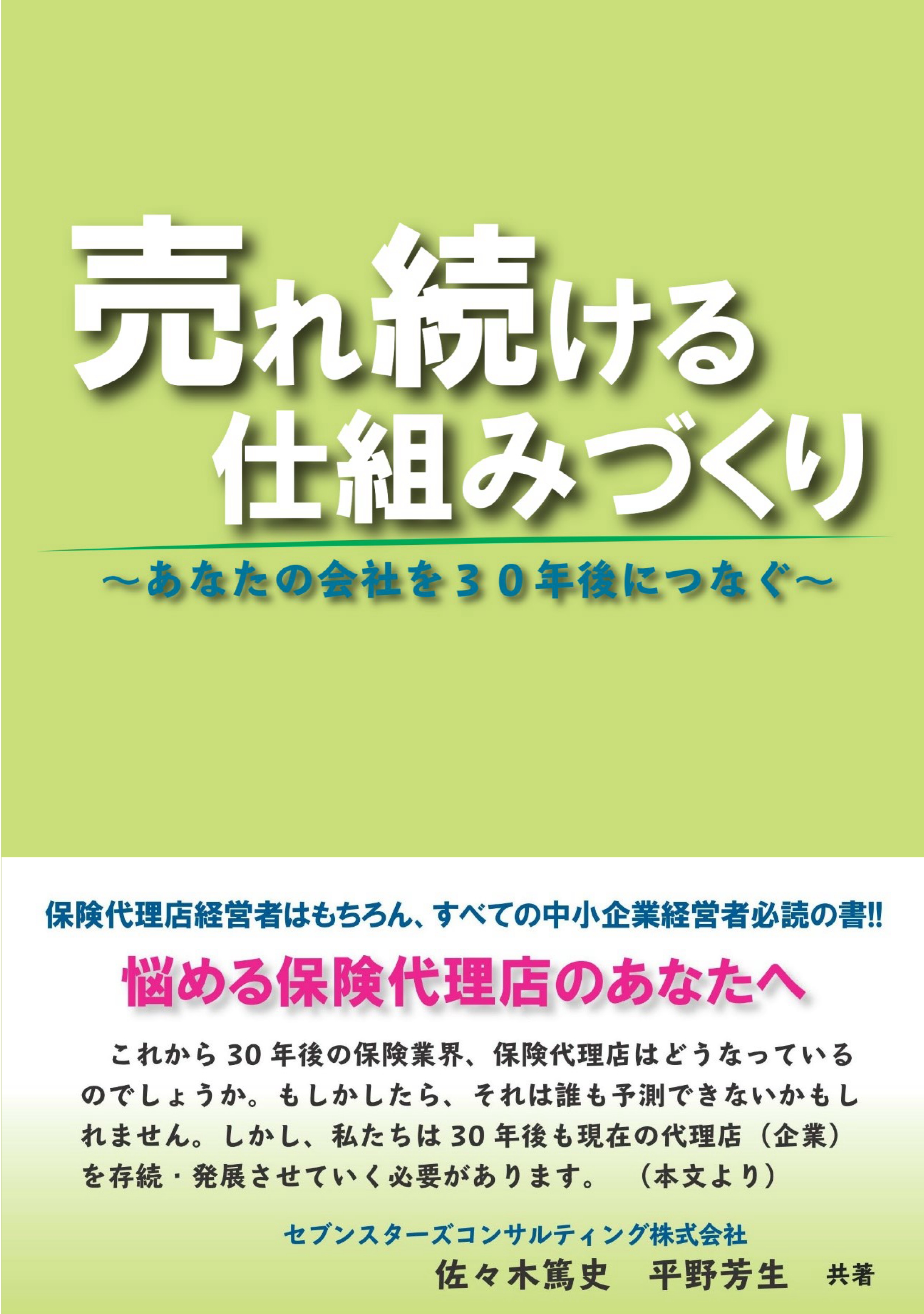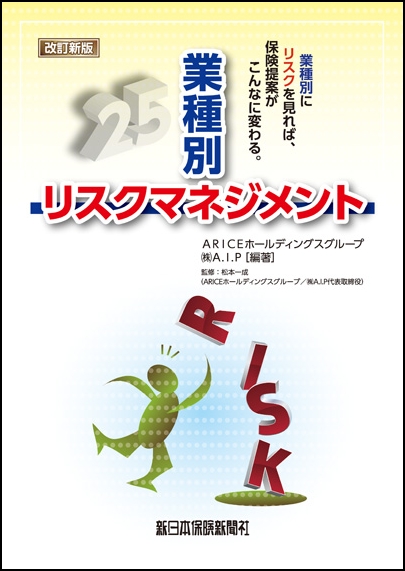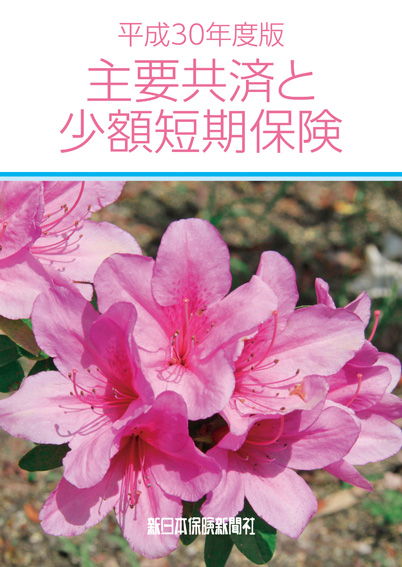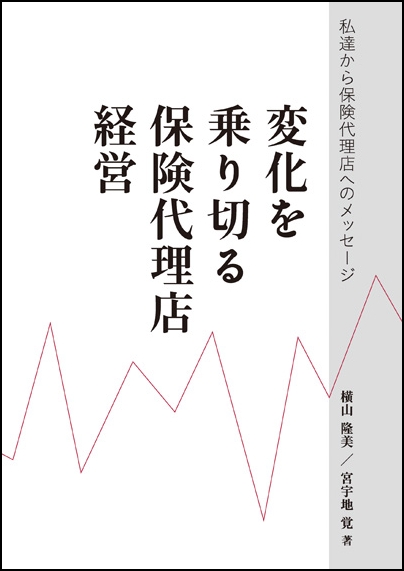あいおいニッセイ同和損保、自動運転車の走行データを活用した走行ルートリスク評価ツールを開発
Tag:あいおいニッセイ同和損保
あいおいニッセイ同和損保は、群馬大学とのこれまでの共同研究成果を基に、滋賀大学※1と自動運転車の走行ルートリスク評価ツールを開発した。3月以降に行われる自動運転の実証実験等から提供を開始し、実用化に向けて取り組みを進めていく。
自動運転車の走行データを活用した走行ルートリスク評価ツールは国内初※2となる。
※1 同社と滋賀大学が設置した日本セーフティソサイエティ研究センター(データ分析等を行う研究機関)において実施
※2 現在、特許出願中(2023年3月時点)
1.背景
自動運転技術は、交通事故の削減や高齢者等の移動支援、ドライバー不足といった様々な社会課題の解決策として期待されている。政府は、限定エリアにおける無人自動運転移動サービスの実装を2025年までに全国40カ所以上に拡大する目標を掲げており、4月からは、改正道路交通法の施行により自動運転レベル4の公道走行が可能となる予定である。今後、各地で無人自動運転移動サービスの導入検討の本格化が見込まれるが、導入に際しては自動運転車の性能を踏まえた安全対策が必要となる。
同社は、2017年より群馬大学と自動運転の社会実装に向けた共同研究を開始し、2020年からは群馬大学および群馬大学発スタートアップである日本モビリティと共同で、無人自動運転移動サービスの導入を計画から実装まで一気通貫で支援する「無人移動サービス導入パッケージ」を展開している。全国各地で実証実験を積み重ねる中、自動運転車の走行リスクが車両の性能のみならず、走行ルートや走行環境の影響を強く受けることを究明し、リスク軽減に向けた研究を続けてきた。
今般、同社では、こうした共同研究で得た知見や群馬大学および日本モビリティが全国の実証実験を通じて蓄積した膨大な自動運転車の走行データを基に滋賀大学と数理モデルを組み立て、自動運転車の走行環境から走行ルートのリスクを評価するツールを開発した。
2.自動運転車向け「走行ルートのリスク評価ツール」について
(1)ツールの概要
本ツールは、自動運転車固有のリスク傾向を踏まえ、リスクと相関の高い走行環境要因(交差点やその通行方法、歩車分離の状況、交通量等)の分析に基づき、走行ルートのリスク評価を行う。
走行ルート上の走行環境リスクを可視化し、ルート全体のリスク評価を行うとともに、候補となる走行ルート間の比較や事故の未然防止に向けたアドバイス、導入時の計画策定に有効な情報を提供する。
(2)ツールのリスク評価精度の向上
走行ルートのリスク評価に使用する数理モデルは、全国各地で走行する自動運転車から収集した走行データの解析を通じて組み立てている。同社は、群馬大学・日本モビリティとの共同研究を通じ、1走行ごとに走行データを自動的にクラウド上にアップロードする仕組みや解析する環境を構築している。
今後もこれらの高度化を図り、自動運転技術の進化や実装レベルの進展に伴うリスク変化を迅速・適切にツールに反映させていくとともに、同社が世界各国で展開するテレマティクス事業を通じて蓄積した累計951億km(地球238万周分)※3の走行データも活用しながら、一層の精度向上に取り組んでいく。
※3 2022年12月末時点
3.無人自動運転移動サービスの実装に向けた導入コンサルティングサービスの提供
同社は、日本モビリティと共同で「無人移動サービス導入パッケージ」を展開している。本ツールも有効に活用しながら、自動運転車の特性や地域における既存の交通インフラ等を踏まえた最適な導入に向け、計画段階から実装段階まで一気通貫で支援していく。

 ログイン
ログイン 関連記事(保険業界ニュース)
関連記事(保険業界ニュース) 関連商品
関連商品