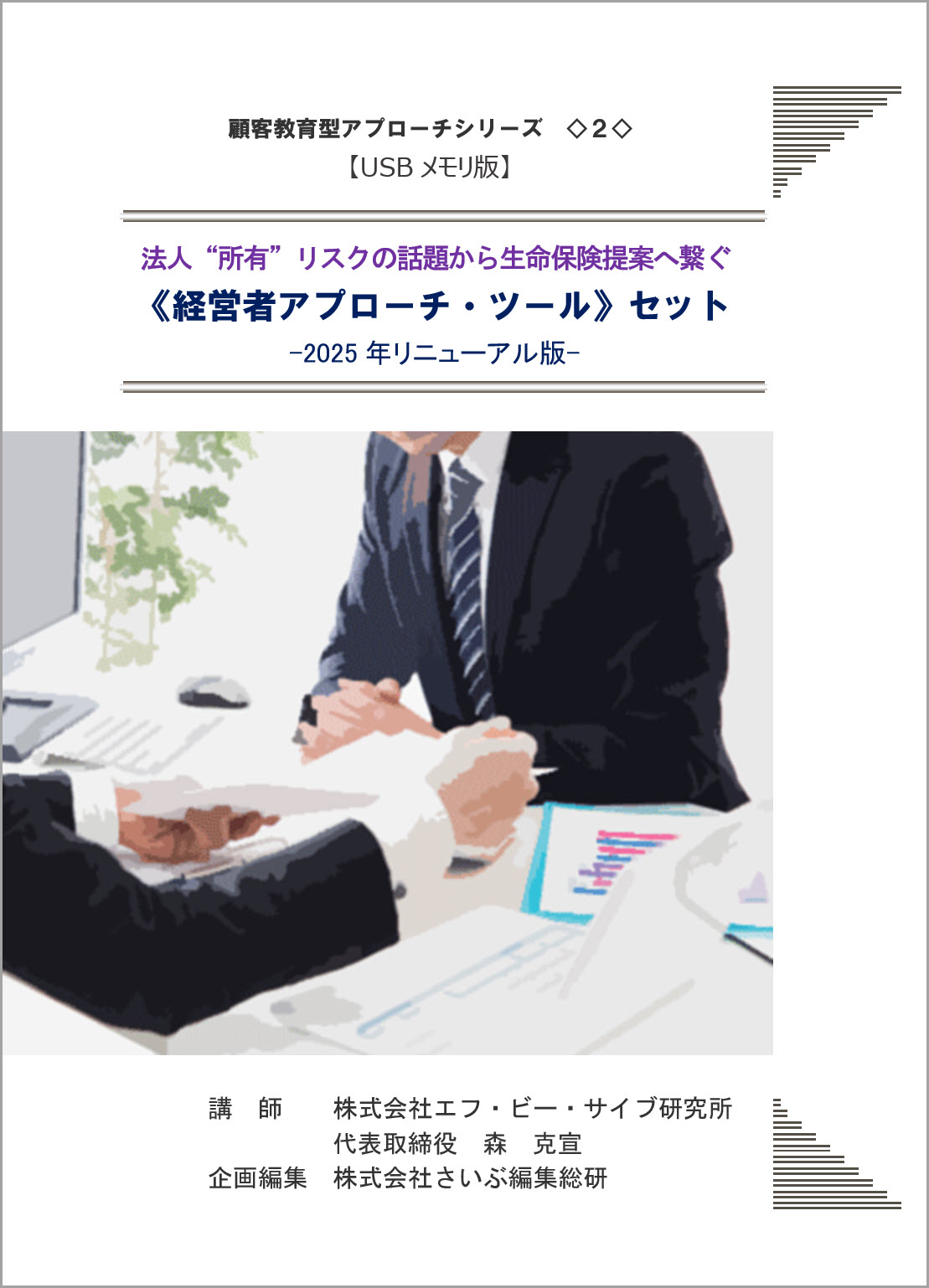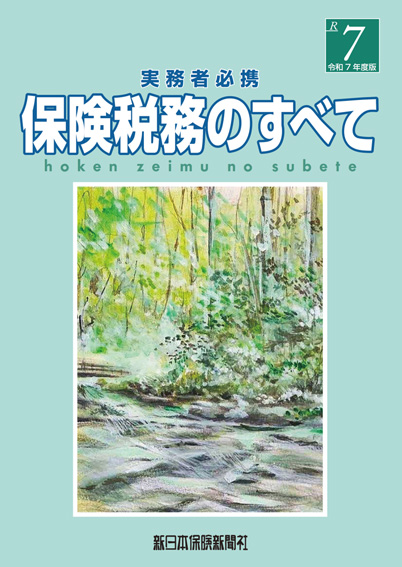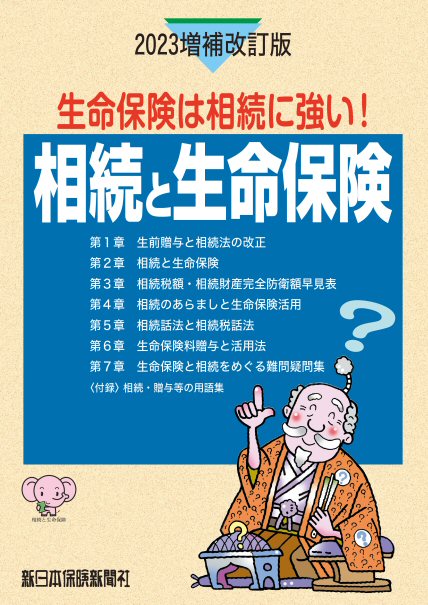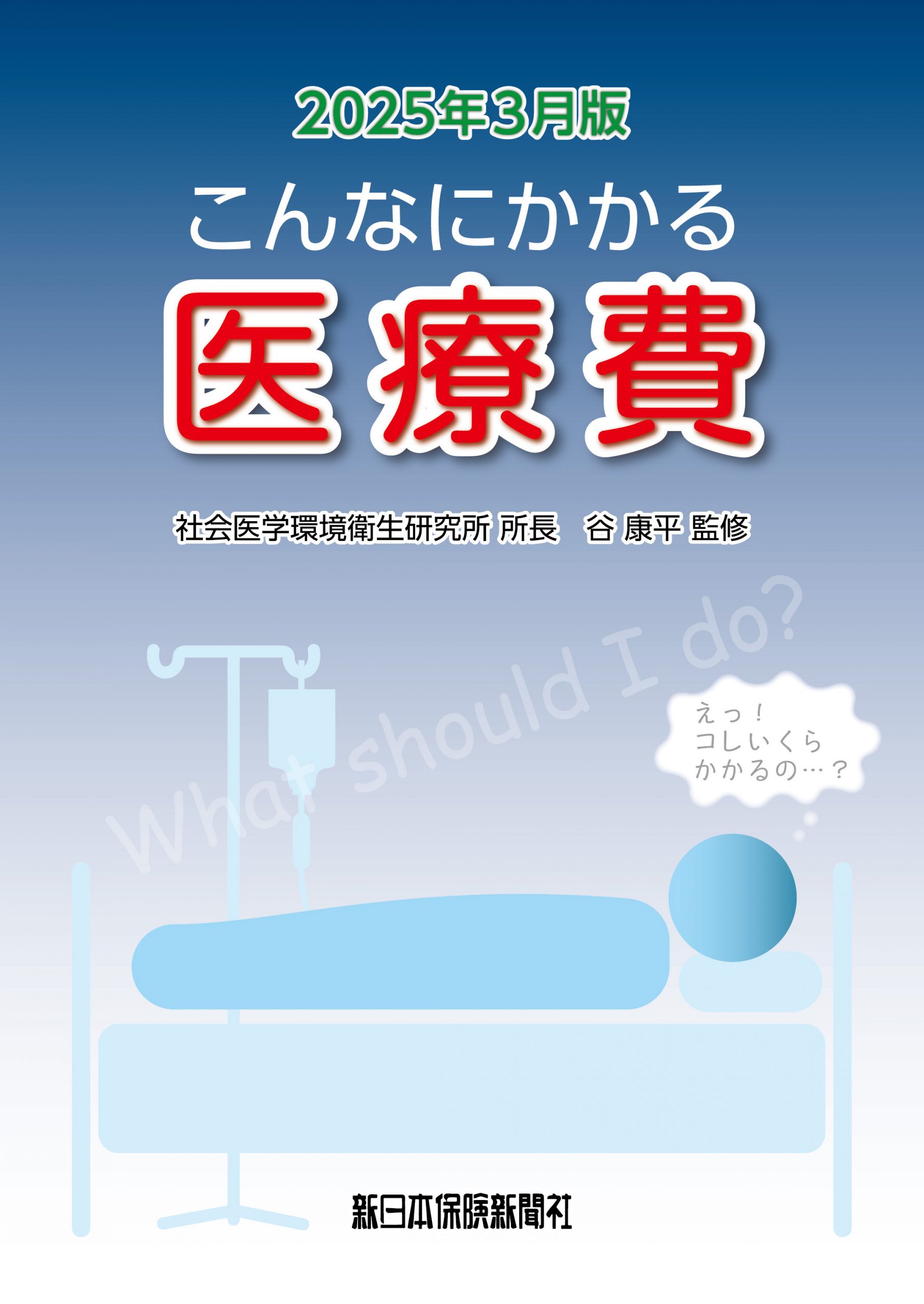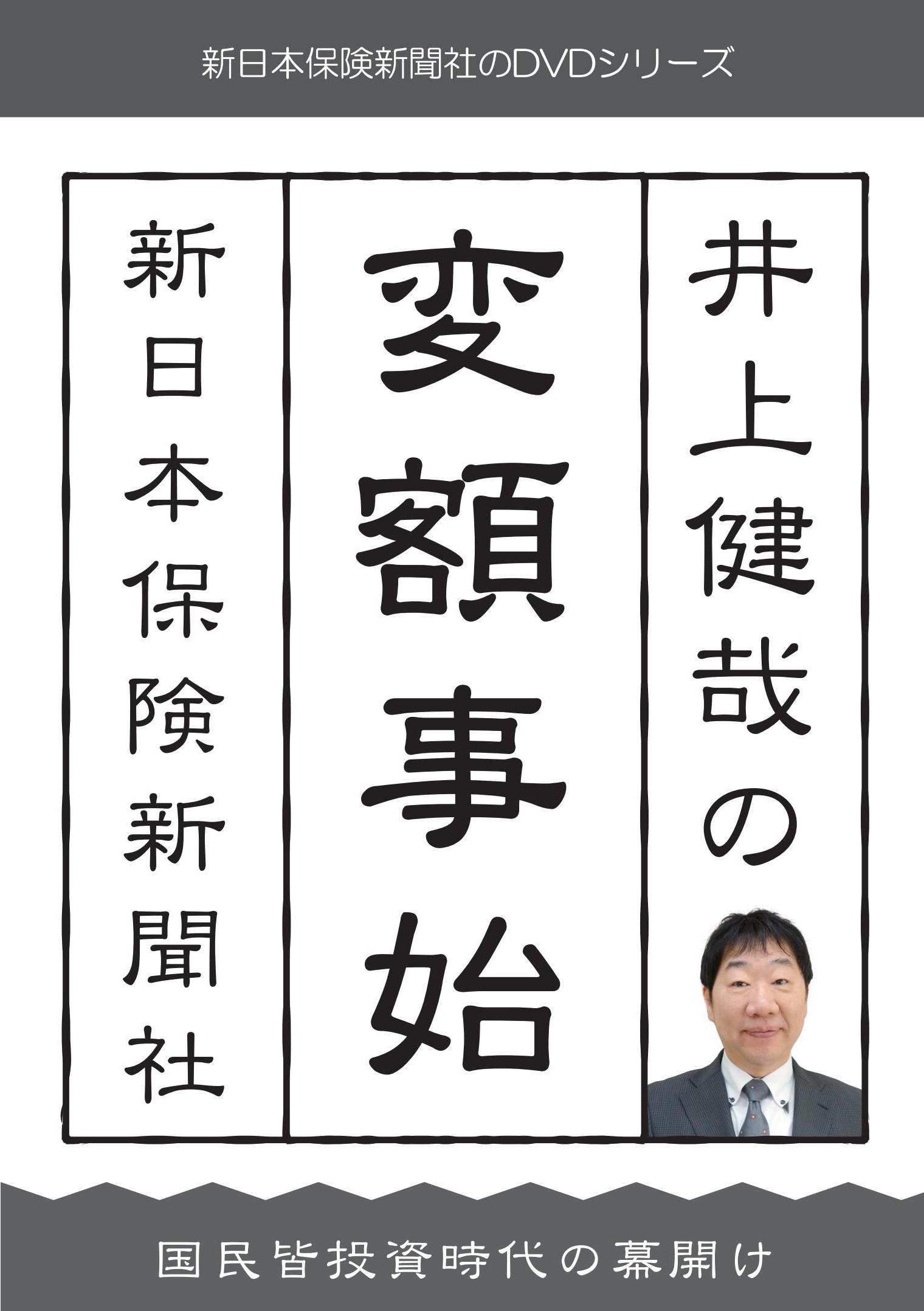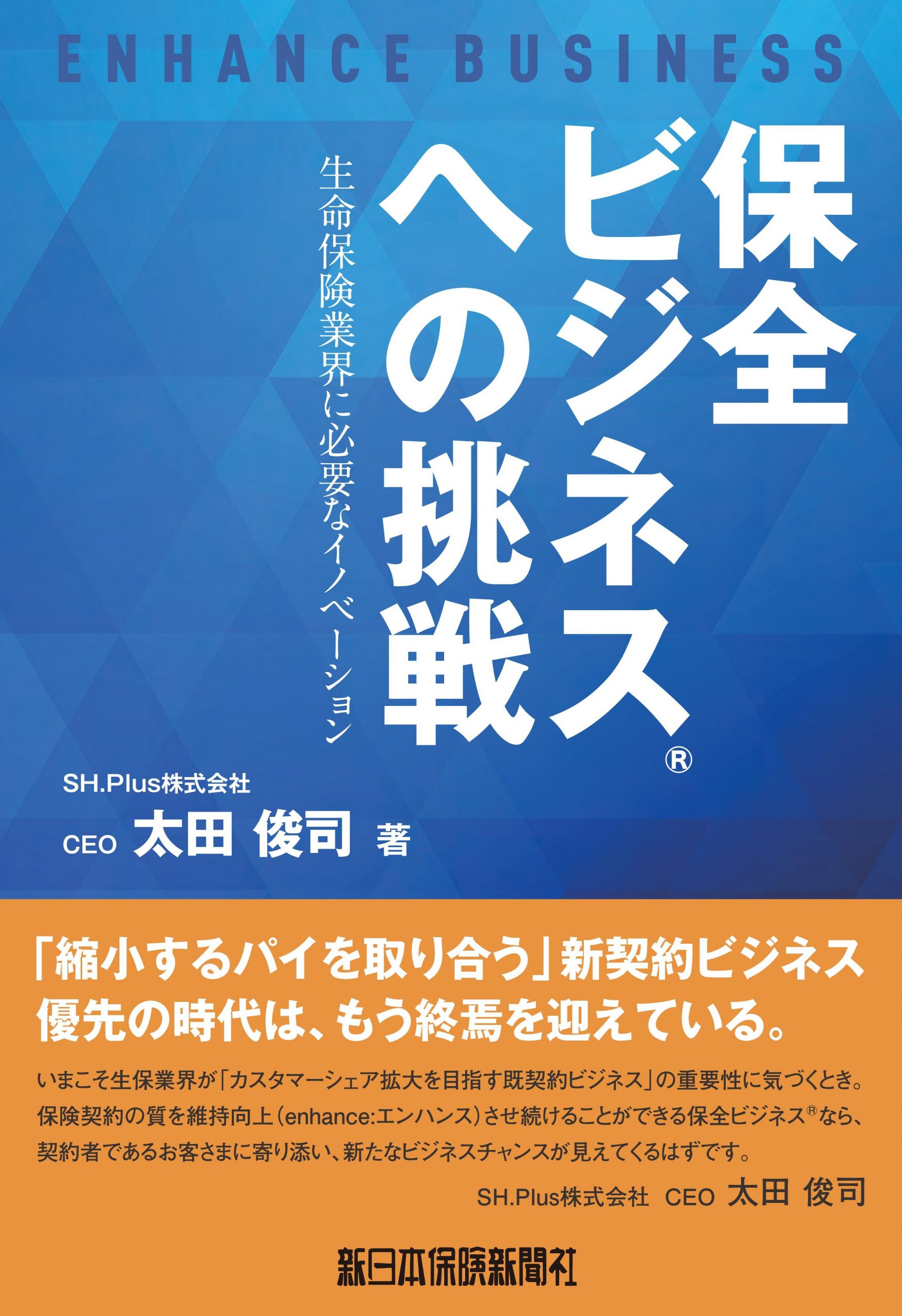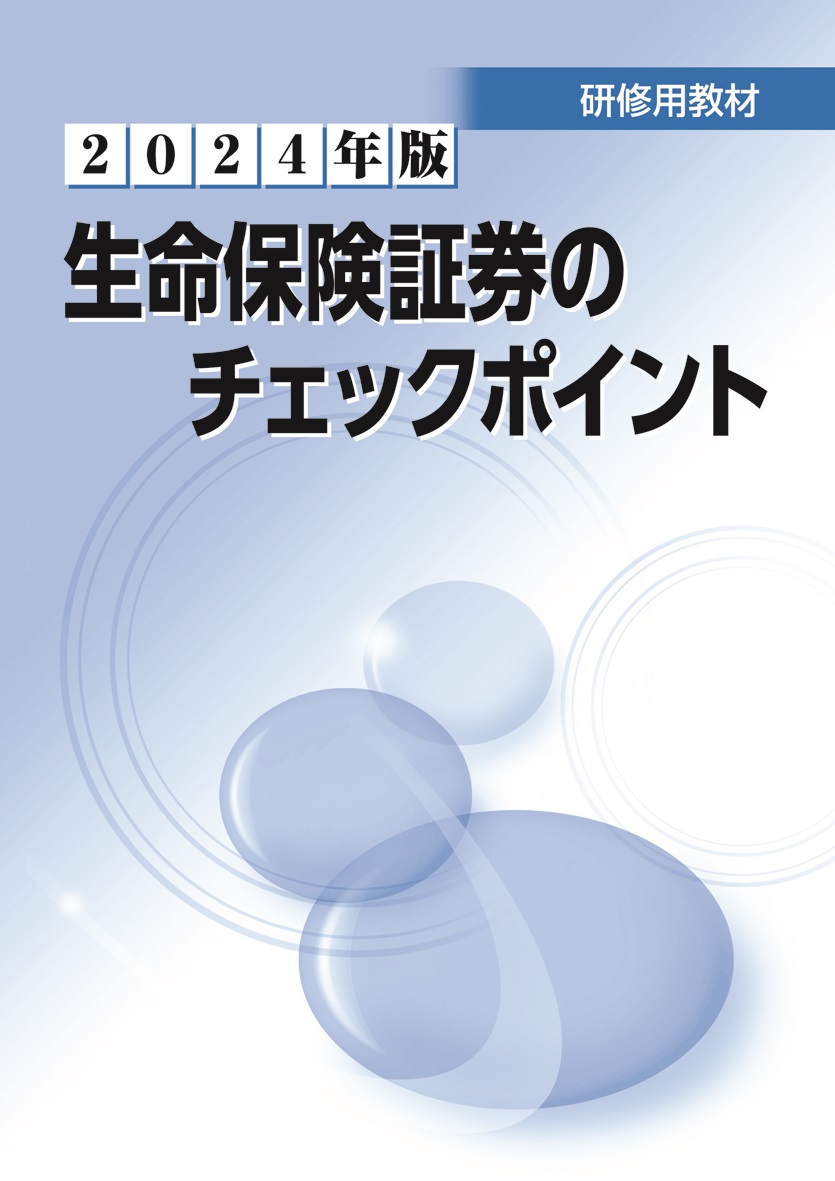ニッセイ・ウェルス生命、出向者による不適切な手段での情報取得事案に係る調査結果を発表
Tag:ニッセイ・ウェルス生命事件・事故
ニッセイ・ウェルス生命は、同社から金融機関への出向者が出向先金融機関の内部情報を出向先の許可なく持ち出していた事案に関して、これまで全容の解明に向けた調査を進めてきたが、調査が完了した。
同社では、このような事案を発生させたことを重く受け止め、発生原因を踏まえた再発防止策に全社を挙げて取り組むことで、信頼回復に努めていく。
1.調査および調査結果の全体像
事案の全容解明に向けて、金融機関への出向者、ならびに出向元所属および管理組織の関係者へのヒアリング、スキャンデータ等の調査、キャビネットおよび個人ロッカー等の調査、ファイルサーバー保管ファイルの調査、メール等のデジタルフォレンジック調査等を実施した。この結果、以下の事実関係が判明した。
<金融機関への出向者による不適切な手段での情報取得の状況>
対象代理店数:2金融機関代理店
件数:943件
取得情報の内容:
・他社商品、利率一覧表・設計書、研修資料等の他社情報
・販売方針、社内評価基準、販売実績等の(金融機関)社内情報
・従業員情報等
主な目的:
同社の金融機関本部担当者・営業担当者が、各金融機関の保険販売にかかる体制・特性・執行方針等の理解を深めるほか、販売状況を把握するなど、営業推進・営業支援策の検討を行う目的で活用していた。
発生期間:2019年4月~2025年4月
今般の調査によって判明した、不適切な手段によって情報を取得した出向者および情報を受領した金融機関本部担当者等の行為は、不正競争防止法における営業秘密保護および個人情報保護法の趣旨に照らして適切ではなかったものと考えている。
出向者による不適切な手段での情報取得に関し、金融機関本部担当者の求めに応じて出向者が情報取得を行っていたが、その他関係者による明示的な指示は認められなかった。
個人情報については、金融機関の従業員情報の取得が確認された。また、顧客情報の取得が1件確認されたが、不正な目的で取得したものではなく、即座に廃棄していたことが確認された。
なお、金融機関内部の情報および個人情報のいずれについても、同社から同社グループ会社以外の第三者への共有は確認されていない。
2.事案概要
2019年4月から2025年4月にかけて、同社から金融機関への出向者が、出向先金融機関の営業実績や利率表・設計書、他の保険会社の商品情報等に係る内部情報を出向先の許可なく、紙媒体の持出やスマートフォンで撮影した画像データの送信によって同社の金融機関本部担当者に提供していた。
金融機関の内部情報を受け取った金融機関本部担当者は、提供された情報の一部を部門の会議において参加者へ口頭で伝達、また要約した内容を資料に記載するなど、営業部門内の役員・社員等に共有していた。また、利率表・設計書については、商品部門にも連携していた。
また、金融機関本部担当者は、収集した情報を、各金融機関の体制・特性・執行方針等の理解を深めるほか、販売状況を把握するなど営業推進・営業支援策の検討等に活用していた。商品部門においては、商品開発等の情報について、基本的には公表前の情報は活用してなかった※。
金融機関本部担当者は、自身が担当する金融機関への販売促進や販売支援等を行うことで、担当金融機関の販売実績につなげる役割を担うなか、担当金融機関の販売状況や販売方針といった情報を収集することも自身の役割と考えており、出向先金融機関の情報にアクセスできる出向者から情報収集を行っていた。
出向者は、出向先の金融機関のために働くことが自身の役割であると認識するなか、慣習的に金融機関本部担当者の求めに応じて情報提供を行っており、資料持ち出しにかかる出向者自身の意図や目的は認められなかった。
※他の保険会社の公表後の情報については、同社商品開発等における参考情報の一つとしている。
3.発生原因
同社営業部門では、金利・為替などの市場環境や競合他社との利率比較により、お客さまニーズが変化していく銀行窓販ビジネスにおいて、情報収集が重要であるとの認識があった。この点、情報収集にあたっては、金融機関本部担当者が相対するプロパーの社員との関係構築に努め、適切なコミュニケーションの範囲で情報収集を行うべきであるが、安易に出向者に資料提供を求めるようになったことが背景にあったと考えている。
本件の発生原因の詳細は以下のとおりである。
(1)経営機密情報への認識の甘さ
経営機密情報にかかる機密性や重要性については、一義的には情報を保有している企業等が判断するものであり、外部ではその重要性等を判断・認識できない情報も存在する。この点、出向者ならびに金融機関本部担当者は、出向者がアクセスできる情報について、出向先にとっての重要性あるいは機密性の高さに意識が及ばず、また、その可能性も考えることなく、安易且つ軽率に取扱っており、経営機密情報への認識の甘さがあったものと考えている。
(2)コンプライアンス意識の不十分さ
出向者は、不適切な手段で入手していた資料について出向先から許可を得られないと考えていた。また、金融機関本部担当者は出向者が許可なく持ち出していることを認識していた。
上述した経営機密情報への適切な認識があれば、無許可で資料等を持ち出すことを抑止できたとも考えられる。しかしながら、安易に不適切な方法にて情報を持ち出しており、経営機密情報への適切な認識のみならず、関係者のコンプライアンス意識が不十分であったと考えている。
(3)出向者や金融機関本部担当者をはじめとする関係者への教育不足
コンプライアンス部門では、経営機密情報に関する研修の実施やコンプライアンス・マニュアルへの掲載などを行い、周知を図っていたが、本件事象発生を踏まえると、これまでの取組では十分ではなかったと考えている。
具体的には、これまでの教育・研修は、同社内の経営機密情報・個人情報の取扱いに焦点を当てた内容に留まっており業務上知り得た出向先の経営機密情報等の取扱いに係る内容の徹底が十分でなかったこと、金融機関と同社における情報取扱等の対応ルールを出向者に十分示せていなかったこと等が挙げられる。
(4)組織・風土の問題
これまで、コンプライアンス意識の向上やリスクカルチャーの醸成に資する取組みを進めてきたが、本件事象が発生したことについては、前例踏襲意識の存在と、世間一般の常識と照らして問題ないかを意識し、気付く姿勢の不足が依然として残っていると考えている。
また、コンプライアンス部門、リスク管理部門の第2線組織、あるいは内部通報制度を担当する法務部門においては、当該取組みや内部通報制度の活用促進に取組んでいたが、本件事象を受け、従前の取組が十分であったとは評価できず、更なる強化の余地があると考えている。
4.再発防止策
上述した「事故発生原因の分析・問題認識等」の4つの視点への対応として、以下の再発防止策を実施する。
(1)出向政策の見直し
金融機関本部担当者が同社からの出向者に安易に期待し、これを受けて出向者がアクセス可能な出向先の資料を許可なく持ち出していたことを踏まえ、募集代理店への出向政策を見直すこととし、募集代理店への出向にかかる内規を策定した。なお、現出向者については、2026年3月末までに帰任させる予定である。
(2)情報取得・取扱ルールの整備と徹底
出向先や取引先にかかる経営機密情報に関する教育を実施するとともに、適切な情報取得・取扱にかかるルールを整備し、その周知徹底を図る。また、不適切な情報取得等による関係法令等への抵触についても理解を深め、適切な情報取扱に関する意識の向上を図る。[2025年11月~]
(3)ディフェンスライン:第1.5線※2の整備・機能強化
コンプライアンス部門(第2線)による営業部門(第1線)への教育や牽制に取組んできたが、本件事案の発生を踏まえ、第1線内にコンプライアンスやリスク管理を担う第1.5線機能の体制整備を組成し、強化する。[2025年12月~]
※2 いわゆる「第3線(スリーライン)ディフェンス」(金融機関の内部統制とリスク管理を、①事業部門(第1線)、②コンプライアンス・リスク管理部門(第2線)、③内部監査 部門(第3線)の3つの役割に分類し、それぞれに責任と機能を分担させる考え方)における、①事業部門(第1線)内のコンプライアンス・リスク管理機能。
(4)全社的なコンプライアンス意識の醸成と内部通報制度の拡充
本件ではコンプライアンス意識を欠いた行為が認められたことから、情報取得・取扱ルールの遵守のみならず、倫理・道徳的な観点においてもコンプライアンス意識を高める教育を継続的に実施する。また、コンプライアンス上の不安や疑義がある場合には、周囲への相談だけでなく、内部通報制度の利用などを促し、問題の未然防止に取り組む。[2025年10月~]
なお、内部通報制度に関しては、半期ごとに社内のイントラネットで情報発信を行うほか、全従業員へのアンケートの実施などを通じた利用促進策を進める。

 ログイン
ログイン 関連記事(保険業界ニュース)
関連記事(保険業界ニュース) 関連商品
関連商品