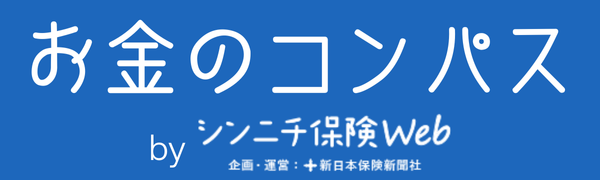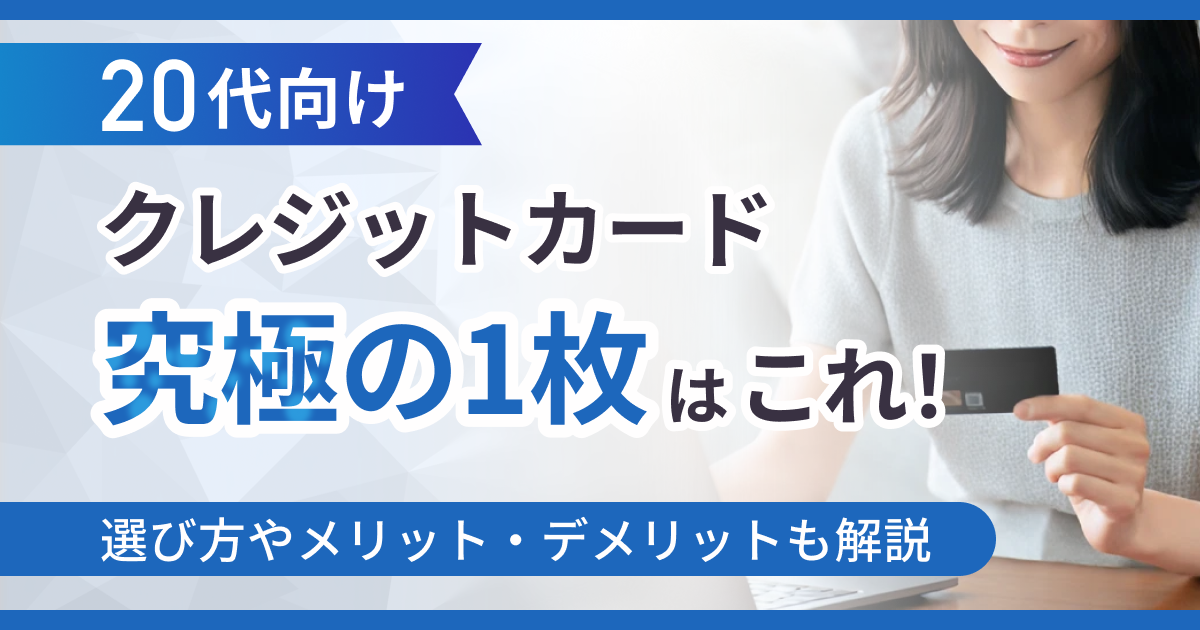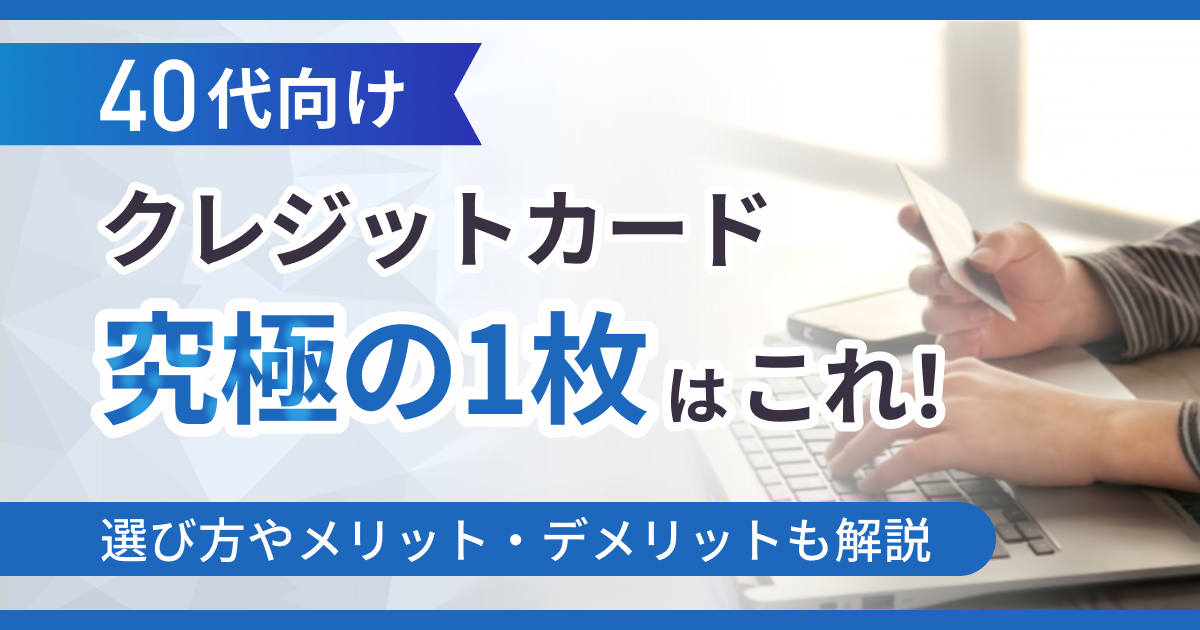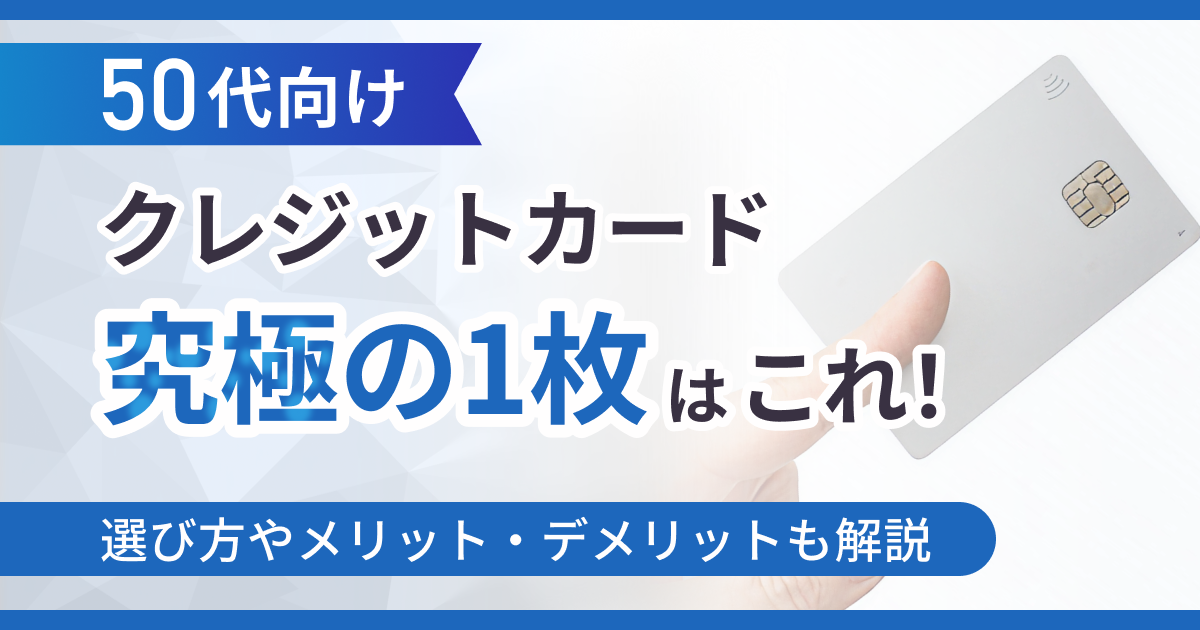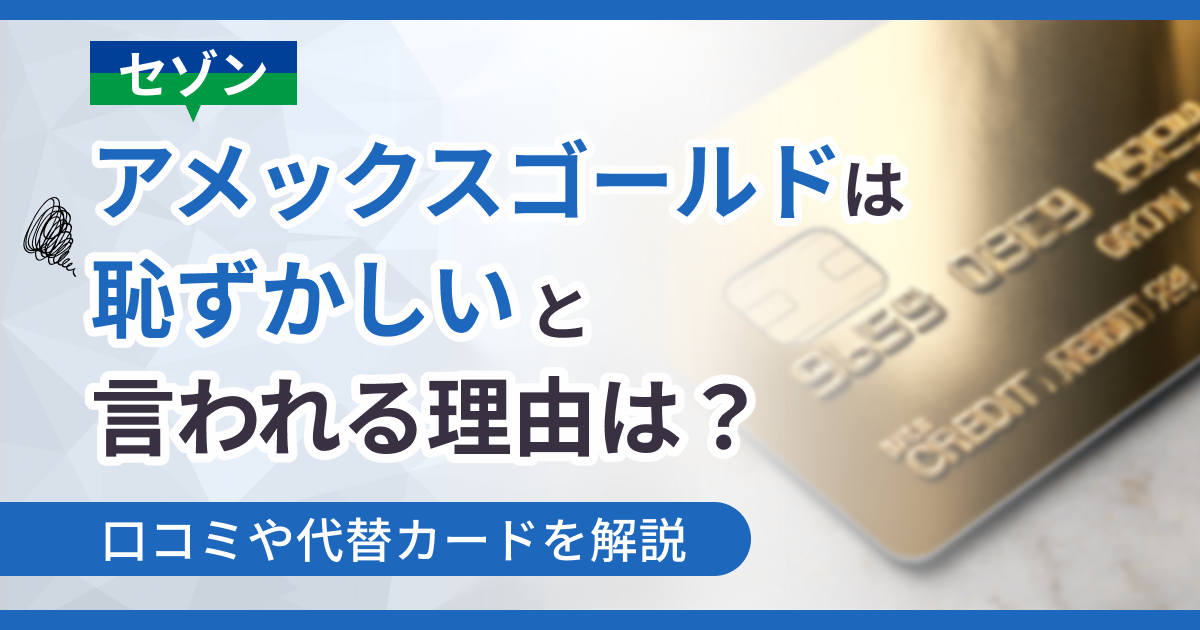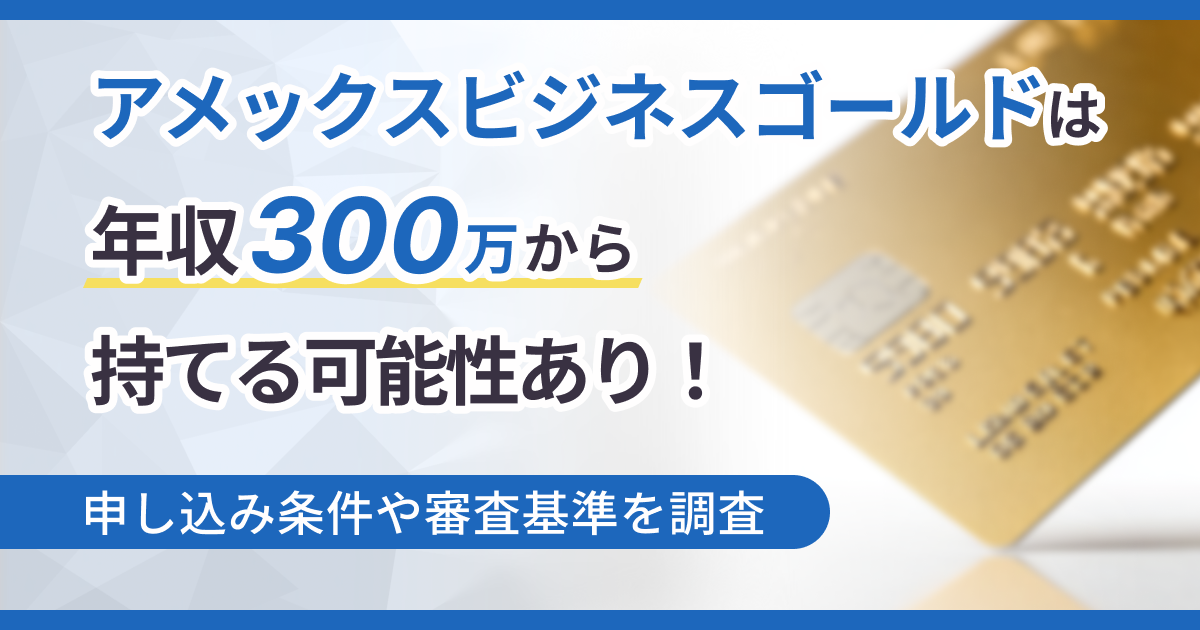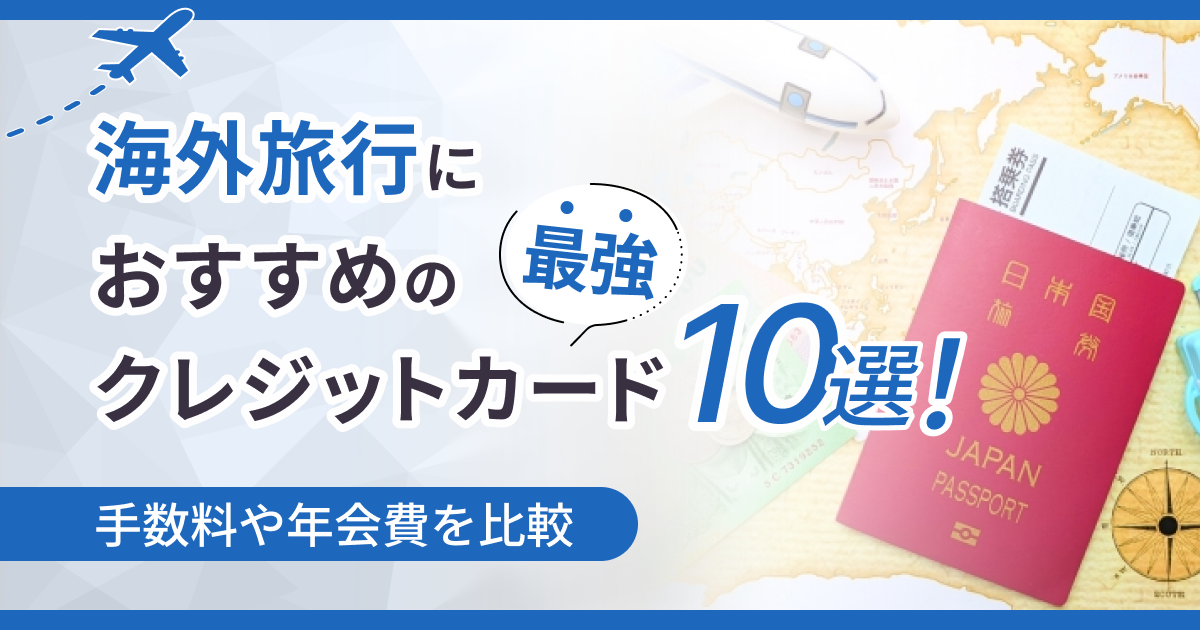60代に入り、定年退職や年金受給の開始に伴って「今からでもクレジットカードは作れるの?」「収入が年金だけでも審査に通る?」と不安に感じている方は少なくありません。
結論からお伝えすると、60代でも問題なくクレジットカードは作成可能です。多くのカード会社では申込資格を「18歳以上(高校生を除く)」としており、年齢の上限自体は設けられていないケースがほとんどだからです。
とはいえ、現役時代に比べて収入が変化したり、年金収入のみになったりすることで、審査のハードルが少し上がってしまうカードがあるのも事実。やみくもに申し込むのは避けたほうが無難です。
そこで本記事では、そんな不安を解消すべく、シニア世代でも申し込みやすくメリットの大きい、60代におすすめの「最強の2枚」を厳選してご紹介します。
この記事では、元銀行員としてクレカ選びや家計相談を受けてきた筆者が体験談を交えながら、次の内容を解説します。
- 60代のクレジットカードの選び方
- 60代におすすめな最強の2枚の組み合わせ
- クレジットカードを2枚持ちするメリットと注意点
60代のクレジットカード最強の2枚の選び方
60代に入ると定年を迎えたり、働き方が変わるなど収入が減少しやすい傾向があります。一方で、自由になる時間が増えるため、趣味を楽しむなどライフスタイルが大きく変化する人も多いでしょう。
このため、60代はクレジットカードを見直すのに最適な年代といえます。
ここでは、60代にとって最強の2枚を選ぶときにチェックすべきポイントを4つ紹介します。
コスパで選ぶ:60代は収入が下がる傾向
収入が減少しやすい60代にとって、クレジットカードの年会費は、ぜひ抑えたい支出の1つです。
保有する上での「コスパのよさ」は、カード選びの大きなポイントになるでしょう。
- 年会費永年無料のカード
- 条件付きで年会費が無料になるカード(年1回の利用など)
- 年会費以上の特典があるカード(付帯保険やサービス、割引など)
また、一般カードを中心とした低コスパのカードは入会基準が低い傾向にあり、収入が減っていても審査に通りやすいという点も見逃せません。
これまでカードに高い年会費を払ってきた人は、カードをすべて見直し、低コスパのカードへ切り替えるのもよいのではないでしょうか。
カードを見直す場合は、新しく作るカードが発行されてから見直すカード(古いカード)を解約するのが原則です。
退職後や収入が減っている場合、必ずしも新しいカードが審査に通るとは限らないからです。
セキュリティの高さで選ぶ:不正利用額は年々増加
60代がカードを選ぶうえで、セキュリティの高さも大切なポイントです。
一般社団法人日本クレジット協会がまとめた調査によると、クレジットカード不正利用の被害は年々増加しており、直近の2024年(1月〜12月)は、被害額が555億円と過去最高でした。
不正利用の内訳は「番号盗用被害額」が513億円と圧倒的に多く、主な原因は偽のインターネットメールや詐欺サイトを通じた情報漏洩だと考えられています。
これらの不正利用を防ぐには、次のように高いセキュリティを持ったカードを選ぶとよいでしょう。
- カード番号やセキュリティコードが記載されていないナンバーレスカード
- カード利用をメールやアプリのプッシュ通知で知らせるカード
- 本人認証サービス(3Dセキュア※)を導入しているカード
※ネット利用時にワンタイムパスワードによる本人確認を行うサービス
参照 : JCB 3Dセキュア(J/Secure)
筆者も3Dセキュア対応のカードを利用しています。ネット決済のたびにワンタイムパスワードを入力するのは少し手間ですが、これで不正利用を防げると考えると、決して面倒だとは感じません。
付帯特典やサービスで選ぶ:60代ならではの特典を
これまで仕事での利用や、ステータス性を重視してカードを選んできた60代の人は、付帯特典やサービスでカードを選ぶのもおすすめです。
特にプライベートの時間が増える人には、趣味や旅行、ショッピング面で付帯特典の多いカードがおすすめです。
最近では、シニア限定の特典やサービスを展開しているカードも多いので、自分の趣味やライフスタイルに合わせたカードを選ぶとよいでしょう。
- ビューカード 大人の休日倶楽部ジパングカード(※):満65歳以上はJR東日本・JR北海道のきっぷが3割引
- ANAカード:満65歳以上はスマートシニア空割が受けられる
- イオンカード(G.G)マーク付き:55歳以上は毎月15日「G.G感謝デー」で5%オフ
筆者の両親は定年を機に、「大人の休日倶楽部ジパングカード」を作成し、年に数回国内旅行を楽しんでいます。定期的によりお得な会員限定きっぷも販売されるので、旅行好きな人におすすめです。
ポイントの貯まりやすさで選ぶ:60代は決済額も高額
年収が減少しやすい60代ですが、 2022年度版クレジットカードに関する総合調査によると、カード決済額の面では男性が毎月平均で約10万8千円、女性は約9.9万円。
他の年代に比べると高額です(1枚目・2枚目に多く使うカードの合計)。
これは、キャッシュレス決済がシニアにも浸透しているためと考えてよいでしょう。
仮に毎月の平均カード利用額が10万円の人であれば、ポイント還元率によって次のとおり1年間に貯まるポイントが異なります。
- 還元率0.5%のカード : 6,000円
- 還元率1.0%のカード : 12,000円
- 還元率1.5%のカード : 18,000円
また「コンビニや飲食店のタッチ決済で7%」「スタバの利用で最大10%還元」など、特定の店舗で還元率の高いカードもあるため、用途による使い分けもおすすめです。
- 三井住友カード(NL) : 対象のコンビニ・飲食店の利用で最大7%還元
- Amazon Mastercard : 対象のコンビニの利用で最大7%還元(タッチ決済の場合)
- JCBゴールド : スターバックスの利用で最大10%還元
60代におすすめのクレジットカード最強の2枚
ここまでカード選びのポイントを解説してきましたが「実際にどのカードの組み合わせがよいの?」と疑問に感じた方も多いのではないでしょうか。
60代はカードの決済額が多い一方で「収入が減りやすい」「プライベートな時間が増える」などライフスタイルが変化しやすいため、利用目的に合った2枚持ちがおすすめです。
コスパを抑えながら、1枚目は日常使いのポイント還元率や利便性、2枚目は付帯サービスや特典の充実度を基準に選べば、バランスの取れた60代に最強の組み合わせが実現できます。
楽天カード × JCBカード S : 楽天ユーザーにおすすめ
| カード名 | 楽天カード | JCBカード S |
|---|---|---|
| 券面 | 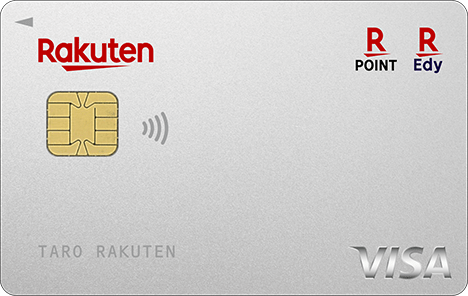 |  |
| 年会費(税込) | 永年無料 | 永年無料 |
| 還元率 | 基本1.0% 楽天市場3.0% | 基本0.5% 提携店1.5%〜10% |
| 国際ブランド | VISA/Mastercard/JCB/AMEX | JCB |
| 申込条件 | 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上、安定した収入がある人 |
| 付帯保険 | 海外旅行保険:2,000万円 ※利用付帯 | ・海外旅行傷害保険:2,000万円 ※利用付帯 ・JCBスマートフォン保険:年間最高3万円(自己負担1万円あり) |
| 特徴 | ・楽天ユーザーに有利 ・国際ブランドが豊富 ・ナンバーレスカード | ・優待店で高いポイント還元率 ・国内外20万ヶ所で優待あり ・ナンバーレスカード |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト |
- 楽天市場や楽天関連のサービスをよく利用する人
- プロパーカード(国際ブランドが直接発行するカード)を持ちたい人
- 年会費無料で実用性と一定のステータス性をカバー
- 楽天関連のヘビーユーザーほど高いポイント還元率
- ナンバーレスカードで高いセキュリティ
銀行員時代、お客さんの間で「楽天カード+プロパーカード(※)」の組み合わせが非常に多く見られました。※カード会社や国際ブランドが直接発行するカード
楽天カードは、楽天関連のサービスを利用するほどポイント還元率が高くなるため、楽天ユーザーには絶対のおすすめです。
一方、JCBカード Sは年会費永年無料で持てるJCBのプロパーカードです。
最高2,000万円の海外旅行傷害保険やスマホ保険が付帯しており、優待店で高いポイント還元率・国内外20万ヶ所で優待が受けられるのは、JCBプロパーカードならではのメリットといえるでしょう。
- スターバックス : 最大10%
- ニッポンレンタカー : 3%
- ユニバーサル・スタジオ・ジャパン : 5%〜
- セブン-イレブン : 1.5%
また楽天カードとJCBカードは、ともにセキュリティが高く、ネットショッピングも安心して利用できる点もポイントです。
カード会社発行のプロパーカードには、次の特徴があります。
・提携カードと異なり、提携企業の都合によるサービス終了がない
・利用状況しだいで上位カードへの招待を受けられる(カード会社による)
・ステータス性が高くカードのデザインがよい
三井住友カード(NL)カード × リクルートカード:ポイント還元重視の人におすすめ
| カード名 | 三井住友カード(NL)カード | リクルートカード |
|---|---|---|
| 券面 |  |  |
| 年会費(税込) | 永年無料 | 永年無料 |
| 還元率 | 基本0.5% コンビニ・飲食店タッチ決済で最大7% | 基本1.2% |
| 国際ブランド | VISA/Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 申込条件 | 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) |
| 付帯保険 | ・海外旅行傷害保険:2,000万円 ※利用付帯 ・選べる無料保険:旅行傷害保険から変更可能 「スマホ安心プラン/ゴルフ安心プラン」等 | ・海外旅行損害保険:2,000万円 ・国内旅行傷害保険:1,000万円 ※どちらも利用付帯 |
| 特徴 | ・コンビニや飲食店で最大7%還元 ・選べる無料保険 ・年会費無料で三井住友カード ゴールド(NL)へアップグレード可能 | ・公共料金支払いでも1.2%の還元 ・リクルート関連サービスで高いポイント還元率 ・付帯保険が充実 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト |
- 日常の支払い・固定費支払いで効率よくポイントを貯めたい人
- じゃらんやホットペッパーグルメなど、リクルート関連サービスを利用する人
- カードの使い分けでポイント還元率が高い
- 「選べる無料保険」を利用して補償を充実できる
- 無料で一般カードとゴールドカードの2枚持ちが可能(利用額による)
三井住友カード(NL)は、コンビニや飲食店のタッチ決済で最大7%の還元が受けられるため、日常の支払いに最適なカードです。
旅行傷害保険を「スマホ安心プラン」「ゴルファー保険」「ケガ安心プラン」など7種の保険へ変更できるため、海外・国内旅行傷害保険が付帯しているリクルートカードとの組み合わせで、充実した補償が受けられます。
また、年100万円以上の利用でゴールドカードへアップグレードできるため、年会費無料でゴールドカードを持ちたい人におすすめです。
リクルートカードは、じゃらんやホットペッパーグルメなどリクルート関連サービスの決済で3.2%、公共料金や携帯料金など固定費支払いで1.2%の還元が受けられます。
無料カードながら、海外・国内旅行傷害保険やショッピング保険が付帯しているほか、国際ブランドが豊富な点も特徴です。
公共料金や家賃、飲食費は家計に占める割合が大きいため、それぞれ還元率の高いカードを利用すると年間で数万円〜10万円単位のキャッシュバックを受けられます。
「カードはいくら使ったか分かりにくい」と敬遠される人もいますが、アプリを活用して上手にカードを使い分けるのがおすすめです。
エポスカード × 楽天ゴールドカード:コスパよく付帯特典が満載
| カード名 | エポスカード | 楽天ゴールドカード |
|---|---|---|
| 券面 |  |  |
| 年会費(税込) | 永年無料 | 2,200円 |
| 還元率 | 基本0.5% ポイントアップサイト経由で最大15% | 基本1.0% 楽天市場3.0% |
| 国際ブランド | VISA | VISA/Mastercard/JCB |
| 申込条件 | 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険:3,000万円 ※利用付帯 | ・海外旅行傷害保険:2,000万円 ※利用付帯 ・カード盗難保険 |
| 特徴 | ・ポイントアップサイト経由で最大15%還元 ・10,000店舗で優待が受けられる ・年会費無料でエポスゴールドカードへアップグレード可能 | ・楽天ユーザーは圧倒的に有利 ・コスパのよいゴールドカード ・旅行関連の特典が豊富 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト |
- マルイや楽天市場をよく利用する人
- コスパよくゴールドカードを持ちたい人
- 年間2,200円で一般カードとゴールドカードを利用できる
- 低コスパながら特典が満載
- 旅行傷害保険をはじめ旅行関連の特典が一通り付帯している
エポスカードは基本還元率が0.5%ながら、ポイントアップサイト経由の買い物で最大15%の還元が受けられます。
- さとふる : 2.5%
- Hotels.com : 4.5%
- マカフィーストア : 15%
- ショップジャパン : 8.5%
また、居酒屋やカフェ、ホテル、カラオケ店など全国10,000店舗で割引やポイントアップ・優待が受けられるほか、年に4回、会員限定の「マルコとマルオの7日間」で期間中何度でも10%オフで買い物できます。
他にも、利用状況によって年会費無料のままゴールドカードへアップグレードできるため、ゴールドカードを2枚持ちしたい人におすすめです。
公式ページによると「携帯電話・公共料金・ネットショッピングなど毎月ある支払いをまとめると招待を受けやすい」とされています。
参照 : エポスネット
楽天ゴールドカードは、楽天市場をはじめ、楽天関連のサービスをまとめるほど高いポイント還元が受けられます。
筆者も楽天ゴールドカードを利用していますが、通常利用でも1.0%の還元が受けられるため、もっとも利用頻度の高いカードとなっています。
また楽天ゴールドカードは、旅行関連の補償や特典が多く付帯しており、低コスパで旅行への備えをできる点も特徴です。
- 国内主要空港のラウンジを年間2回まで無料で利用可能
- 楽天カードトラベルデスクを利用可能
- 最高2,000万円の海外旅行傷害保険が付帯
ただし楽天ゴールドカードは、旅行関連の特典やETCカード無料以外に大きな特典がないのも事実です。
これらの特典が不要であれば、年会費無料の楽天カード(一般カード)を検討するのもよいでしょう。
イオンカードセレクト(GGマーク付き) × セブンカード:ふだんの買い物でお得な組み合わせ
| カード名 | イオンカードセレクト(GGマーク付き) | セブンカード |
|---|---|---|
| 券面 | 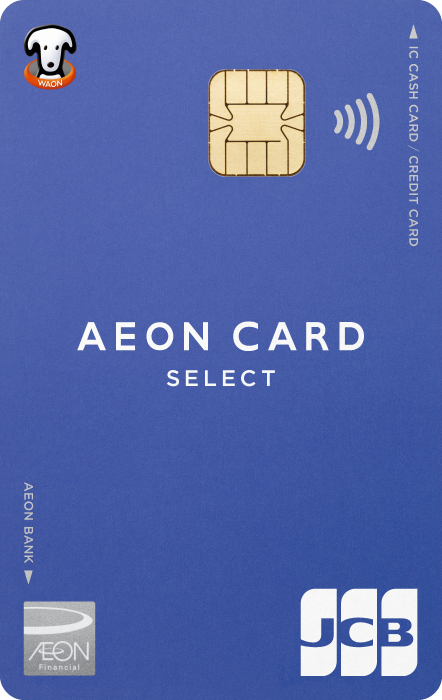 |  |
| 年会費(税込) | 永年無料 | 永年無料 |
| 還元率 | 基本0.5% イオングループで1.0% | 基本0.5% セブン&アイグループで最大10% |
| 国際ブランド | VISA/Mastercard/JCB | JCB |
| 申込条件 | 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上で本人または配偶者に安定した収入がある人 18歳以上の学生(高校生除く) |
| 付帯保険 | ショッピング保険 | ショッピングガード保険(海外) |
| 特徴 | ・イオン系列店でポイント2倍 ・55歳以上は毎月15日「GG感謝デー」に5%オフ ・年会費無料でゴールドカードへアップグレード可能(条件あり) | ・セブン-イレブンで最大10%還元 ・イトーヨーカドー「ハッピーデー」で5%オフ ・年会費無料でゴールドカードへアップグレード可能(条件あり) |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト |
- イオンをよく利用する人
- セブン&アイグループ(セブン-イレブン・イトーヨーカドーなど)をよく利用する人
- イオンやセブン&アイグループのお店で割引や高いポイント還元率
- どちらも電子マネー一体型カード
- 年会費無料のままゴールドカードへステップアップ可能
イオンカードセレクト(GGマーク付き)は、イオン系列のお店で毎月20・30日の「お客さま感謝デー」、55歳以上の人は毎月15日の「GG感謝デー」にも5%の割引が受けられます。
- お客さま感謝デー : 毎月20・30日
- GG感謝デー : 毎月15日(55歳以上の人)
また、イオンシネマの映画料金が割引きになるほか、HISやHotels.comなどの旅行関連サービスで割引が受けられます。
一方、セブンカードは、セブン&アイグループのお店で最大10%の還元が受けられるほか、イトーヨーカドーで毎月8日・18日・28日の「ハッピーデー」に5%の割引が受けられる点が特徴です。
- セブン-イレブン : 最大10%還元
- イトーヨーカドー・デニーズなど : 税抜200円につき2nanacoポイント(カード払いの場合)
イオンカードセレクト(GGマーク付き)とセブンカードは、ともに利用状況に応じて年会費無料のままゴールドカードへステップアップ可能です(セブンカードはセブンカード・プラス)。
ただし、どちらのカードも一般カードのままでは旅行保険が付帯していません。
旅行が好きな人は別途、旅行保険付きのカードを持つか、旅行の際に保険会社の旅行保険に申し込むほうが良いでしょう。
セゾンカードインターナショナル × 大人の休日倶楽部ミドルカード : 旅行好きな人におすすめ
| カード名 | セゾンカードインターナショナル | 大人の休日倶楽部ミドルカード |
|---|---|---|
| 券面 | 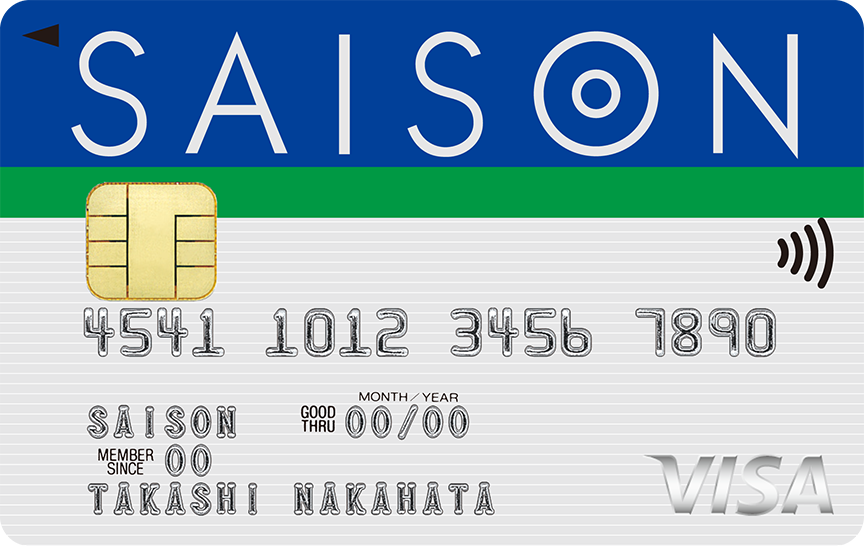 |  |
| 年会費(税込) | 永年無料 | 2,624円 初年度無料 |
| 還元率 | 基本0.5% ポイントモールで最大15% | 基本0.5% モバイルSuicaで5% |
| 国際ブランド | JCB/VISA/Mastercard | JCB/VISA/Mastercard |
| 申込条件 | 18歳以上(高校生除く) | 国内在住で満50歳以上64歳までの人 |
| 付帯保険 | なし | ・国内旅行傷害保険:1,000万円 ・海外旅行傷害保険:500万円 ※ともに利用付帯 |
| 特徴 | ・ポイントの有効期限なし ・ポイントモールで最大15%還元 ・ナンバーレスカードを選べるためセキュリティ面で安心 | ・JR東日本・JR北海道の運賃が5%オフ ・「大人の休日倶楽部パス」や会員だけのお得なきっぷあり ・モバイルSuicaへオートチャージ可能 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト |
- ポイントを利用しきれずに失効しがちな人
- 新幹線を含めJR東日本やJR北海道をよく利用する人
- 通常の決済とJRの決済に分けてお得に利用できる
- 豊富な国際ブランドから選ぶことができる
- どちらのカードもセキュリティが高い
セゾンカードインターナショナルは、ポイントの有効期限がない永久不滅ポイントなので「よくポイントを失効してしまう人」「長期間ポイントを貯めたい人」におすすめです。
▼元銀行員目線のアドバイス
ポイント利用方法の1つとしておすすめなのが「ポイント投資」です。実際に銀行窓口では、クレカの「ポイント投資」について相談を受ける機会が多くありました。セゾンカードでは最低200ポイントから投資信託や株式に投資できます。
大人の休日倶楽部ミドルカードは、新幹線旅行が好きな人、JRをよく利用する人におすすめのカードです。
JR東日本・JR北海道のきっぷが5%オフになるほか「大人の休日倶楽部パス」など、お得なきっぷや会員限定ツアーが利用できます。
- JR東日本全線5日間乗り放題 : 18,800円(税込)
- JR東日本全線+JR北海道全線5日間乗り放題 : 26,740円(税込)

なお、満65歳以上の人であれば、よりお得な「大人の休日倶楽部ジパングカード」が利用できます。
「大人の休日倶楽部ジパングカード」は、JR東日本線・JR北海道線のきっぷがいつでも30%オフとなるため、旅行好きな人は、ぜひ利用を検討されてはいかがでしょうか。
60代がクレジットカードを2枚持ちするメリット
60代は退職を迎えたり、働き方が変わったりと生活環境やお金の使い方が大きく変化する年代です。
また、自由な時間が増えるため趣味や旅行に時間を費やす人も多いのではないでしょうか。
このため、カードを2枚持ちすると次のとおりさまざまなメリットがあります。
カード2枚分の利用可能枠を持てる
クレジットカードは職業や年収により利用可能枠が設定されます。60代は退職や収入減少によって利用可能枠が低く設定されるケースも珍しくありません。
また、すでに利用しているカードであっても、途上与信(※)によって利用可能枠が減額される可能性もあります。
※定期的に契約者の信用状態や職業・年収などを調査すること
このため、2枚持ちによって「カード2枚分の利用可能枠を使える」のは、大きなメリットです。
筆者は、退職者された人に銀行でカードを作ってもらった際、「海外旅行へ行くのに限度額が少なくて困る」と相談されたことがあります。結果的に別ブランドのカードも作成してもらい、満足していただけました。
ポイントを最大限貯められる
クレジットカードは、基本ポイント還元率が異なるだけでなく、特約店や特定のお店・サービスでポイントアップが受けられます。
たとえば、三井住友カード(NL)は対象のコンビニや飲食店で最大7%還元、JCB カード Sはスターバックスで最大10%の還元が受けられるといった具合です。
このため、よく利用するお店やサービスごとに還元率の高いカードを利用すれば、ポイントを最大限に貯められます。
代表的なカードの得意分野と還元率アップ例をまとめると次のとおりです。
| カード名 | 得意分野 | 還元率アップ例 |
|---|---|---|
| リクルートカード | 特になし | 基本還元率1.2% (公共料金や携帯料金もOK) |
| 楽天カード | ネット通販(楽天カード) | 楽天市場で最大18% |
| 三井住友カード(NL) | コンビニ・ファミレス・カフェ | タッチ決済利用で最大7% セブン-イレブンで最大10% |
仮に毎月の決済額が10万円(年間120万円)の人であれば、カードの使い分けによって年間のポイント獲得額で数万円〜10万円程度の差が出ることも珍しくありません。
各カードのデメリットを補いメリットを活かせる
クレジットカードには、それぞれメリットとデメリットがあるため、2枚持ちすることで各カードのデメリットを補い、メリットを活かせます。
たとえば、セブンカードはセブン&アイグループで最大10%のポイント還元が受けられますが、旅行保険は付帯しません。
このため、旅行保険が充実したカードと組み合わせれば、デメリットを補い、メリットである高いポイント還元率を最大限に活かせます。
また国際ブランドがJCBの場合、国内では加盟店が多いものの、ヨーロッパなど海外の一部では加盟店が少なく利用できないケースもあります。
このため、海外で加盟店が多いVISAやMastercardと2枚持ちすれば、JCBのデメリットを補うことができます。
筆者は銀行員時代、ほとんどの人へJCBとVISAをセットで勧めていました。特に海外旅行へ行った人から「勧められたVISAを持って行ってよかった」との声をいただいています。
家計管理が楽になる
60代に入り、実生活面だけでなく趣味の支払いでカードを利用する機会が増える人も多いでしょう。
しかし、1枚のカードですべて決済していると、カードの明細をみて「何にいくら使ったか」を把握できないケースも出てくるはずです。
この点、2枚のカードを「生活費」「趣味の支払い」と分ければ、カード明細が家計簿代わりになり、家計管理が楽になります。特に年金生活となれば、支出はしっかり把握したいものです。
また、キャッシュレス決済が当たり前になった現在、家計簿アプリを利用すればカード決済以外の支払いを一元管理し、支出内容を可視化できます。
筆者も家計簿アプリを利用していますが、銀行口座残高やカードの次回引き落とし情報まで確認できるのでとても重宝しています。
60代がクレジットカードを2枚持ちする際の注意点
クレジットカードの2枚持ちには、さまざまなメリットがある一方で、いくつか注意すべき点もあります。
特に60代は仕事や収入面で変化が生じやすい年代のため、おもに審査やカードの管理面で注意が必要です。
ここでは、実務で経験した注意点を交えて、銀行員目線で次の注意点を解説します。
- キャッシング枠を設定しない
- 管理が煩雑になる
- 年会費と特典のバランスに注意
キャッシング枠を設定しない
60代がクレジットカードを2枚持ちするうえで、まず注意すべきなのは、キャッシング枠を設定しないことです。
キャッシング枠を設定すると、より厳しく信用状況や他社借入状況がチェックされるため、審査落ちする可能性が高まるためです。
使い道が決まっているショッピング枠に比べ、キャッシング枠は現金貸付で使途が自由のため貸倒れリスクが高く、より審査が厳しく行われます。
キャッシング枠が必要な場合でも、できるだけ低い金額で設定するとよいでしょう。
また、すでに持っているカードでキャッシング枠が設定されている場合は、キャッシング枠をなくすか減額することで、これから申し込むカードの審査で有利になる場合もあります。
管理が煩雑になる
クレジットカードを2枚持ちすると、次の項目で管理が煩雑になります。
- 支払い日
- 支払額
- 返済口座の残高
- 暗証番号
- アプリや会員ページのログイン情報
特に支払日や支払額、返済口座の残高を正しく把握しておかないと、返済遅れにつながりかねないため注意が必要です。
ただし管理を楽にしたい場合でも、セキュリティ面を考えれば、暗証番号や会員ページログイン情報の使い回しは好ましくありません。
面倒でもカードごとに異なる暗証番号やログイン情報を設定するのがおすすめです。
銀行窓口では、特に高齢の人にカードの情報をスマホのメモアプリでまとめておくようアドバイスをしていました。
スマホのメモアプリは、開くのに暗証番号や生体認証を設定できるのでセキュリティ面でも安心です。また、支払い日や支払額の管理では、家計簿アプリの利用も便利です。
年会費と特典のバランスに注意
カードの2枚持ちでは、年会費と特典のバランスに注意が必要です。
年会費無料のカードであれば問題ありませんが、ゴールドカードやプラチナカードはおおむね次のとおり年会費がかかるため、特典を有効に活用できないとムダな出費となるためです。
- ゴールドカード : 5,000円〜15,000円程度
- プラチナカード : 20,000円〜35,000円程度
ただし、ゴールドカードの中には条件付きで年会費が無料になるものもあります。
- エポスゴールドカード : カード会社からの招待で年会費永年無料
- イオンゴールドカード : カード会社からの招待で年会費永年無料
- セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード : 年1回の利用で年会費無料
- 三井住友ゴールドカード(NL) : 年間100万円以上の利用で年会費無料
「特典をあまり使わない」「年会費が気になる」という人は、これらのカードを利用すれば、カード2枚持ちのメリットを最大限に活かせます。
必要のないカードを何枚も保有している人、年会費がかさんで困っている人は、60代を迎えるのを機にカードの整理を行うのもおすすめです。
保有しているカードを把握しきれていない人は、信用情報の開示を行えば契約しているすべてのカード情報を確認できます。
まとめ:60代はコスパと特典のバランスがとれたカードの2枚持ちがおすすめ
「定年を迎える」「自由な時間が増える」など、60代は生活スタイルが大きく変化しやすい年代です。
コスパと特典のバランスがとれたカードを2枚持ちすることで、より快適で便利な生活が送れるのではないでしょうか。
- 60代のカード選びではコスパや付帯特典のバランスが大切
- セキュリティの高さ、ポイントの貯まりやすさも重視しよう
- カードの使い分けで家計管理をしやすくなる
- 2枚持ちで各カードのデメリットを補いメリットを活かすことができる
- 60代以降は審査の通りやすさを重視しよう
ぜひ、この記事を参考にして最強のクレジットカード2枚をみつけてください。