「タマホームなら、500万円で新築の家が建てられるって本当?」
このような疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。
インターネットで検索すると、今なお関連情報が出てくるため、その真相が気になっている方も少なくないはずです。
しかし結論から言うと、2025年現在タマホームで500万円の家を建てることはできません。
この記事では、かつての「500万円」が意味した費用の内訳、ウッドショックや人件費高騰といった販売終了の背景、そして現在のタマホームが提供する「シフクノいえプレミア」のような魅力的な低価格帯商品まで解説していきます。
ぜひ最後まで参考にしてみてくださいね。
本文に入る前に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えしておきます。
家づくりで一番大切なこと、それは「気になっているハウスメーカーを徹底的に比較検討すること」です。
よくある失敗パターンとして、住宅展示場に行って営業マンの巧みなトークに流されその場で契約をしてしまうというケースがあります。実際に、「もしもしっかりと比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
だからこそ、きちんとした比較検討をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
ではどのように比較検討すればいいのでしょうか。
その方法は、「ハウスメーカーのカタログをとりあえず集めてしまうこと」なんです!

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、全ての会社に連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのようにカタログを集めていいのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしい無料で利用できるサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「プロのアドバイザーに実際に相談できるサービス」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の2つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトSUUMOが運営する注文住宅相談サービスです。全国各地のハウスメーカー・工務店とのネットワークも豊富。スーモカウンターの最大の特徴が、店舗またはオンラインでアドバイザー相談が可能なことです。住宅の専門家に相談ができるので、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はまずはスーモカウンターに相談することがおすすめです。 |
上記の2サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
後悔のない家づくりのために、上記のサービスを活用しながら、1社でも多くの会社を比較検討してみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
タマホームの「500万円の家」とは

「500万円で家が建つ」というイメージがあるタマホームですが、このキャッチフレーズがなぜこれほどまでに注目を集めたのか、その理由を深く掘り下げていきましょう。
この価格の正体は、2011年頃から2016年頃という特定の期間に販売されていた「大安心の家5シリーズ」というキャンペーン商品でした。
低価格を実現した「規格住宅」
この「大安心の家5シリーズ」が驚きの低価格を実現できた最大の理由は、その商品が「規格住宅」であった点にあります。
家づくりの方法には大きく分けて「注文住宅」「建売住宅」「規格住宅」の3つがありますが、それぞれの特徴を理解することが、価格のからくりを解き明かす鍵となります。
「注文住宅」は、間取りから内装、設備に至るまでゼロから自由に設計できる一方、設計コストや建材コストがかさみ、価格は高くなる傾向があります。
「建売住宅」は土地と建物がセットで販売される完成品で、価格は明瞭ですが、設計の自由度は全くありません。
それに対し「規格住宅」は、ハウスメーカーが予め用意した複数のプラン(間取りやデザイン、仕様)の中から、自分の好みに近いものを選んで建てるセミオーダー方式です。
設計の自由度は注文住宅に劣るものの、プランを規格化することで設計プロセスを大幅に効率化できます。
また、使用する建材や設備を統一してメーカーから一括で大量に仕入れることで、大幅なコストダウンが可能になります。
「大安心の家5シリーズ」は、この規格住宅のメリットを最大限に活用した商品でした。
特に最も安価なプランは、平屋の1LDKで建坪20坪以内という、独身者や夫婦二人暮らし(DINKs)といった世帯をターゲットにしたミニマムな設計となっており、過剰な広さや設備を求めない層のニーズに的確に応えていたのです。
「500万円」に含まれない費用とは
そして、最も重要な点が「500万円」という価格の内訳です。
この金額は、あくまで建物を建てるための「建物本体価格」の最低ラインを指すものでした。
家を建てて実際に住み始めるまでには、この他に「付帯工事費」と「諸費用」という、合計で数百万円にもなる費用が別途必要になります。
これはタマホームに限った話ではなく、住宅業界における価格表示の慣習でもあります。
付帯工事費の内訳例
付帯工事費とは、建物本体以外の工事にかかる費用のことです。
例えば、敷地に上下水道やガスの管を引き込むための「給排水・ガス工事」、電柱から電気を引き込む「屋外電気工事」、駐車スペースや庭、フェンスなどを整備する「外構工事」などが含まれます。
また、家を建てる前の「地盤調査」は必須であり、もし地盤が弱いと判定されれば、安全のために「地盤改良工事」が必要となり、これだけで100万円以上かかるケースも珍しくありません。
これらは快適で安全な生活に不可欠な工事であり、総額で200万円~300万円程度かかるのが一般的です。
諸費用の内訳例
諸費用とは、工事費以外で発生する手続き上の費用のことです。
具体的には、建築計画が法規に適合しているかを確認する「建築確認申請費用」、土地や建物の権利を明確にするための「登記費用」、住宅ローンを組む際の「事務手数料」や「保証料」、「火災保険料」や「地震保険料」、契約書に貼る「印紙税」など、多岐にわたります。
これらの諸費用も、総額で100万円以上になることが一般的です。
このように、「大安心の家5シリーズ」の実際の総額は、建物本体価格500万円に、これらの付帯工事費と諸費用を加えた約900万円から1,000万円程度になるのが実情でした。
もちろん、土地を持っていない場合は、さらに土地代が加わります。
「500万円」という価格は、家づくりのスタートラインに立つためのきっかけとしては非常に魅力的でしたが、その金額だけでマイホームが完成するわけではなかった、というのがその真相なのです。
500万円の家の販売終了の背景
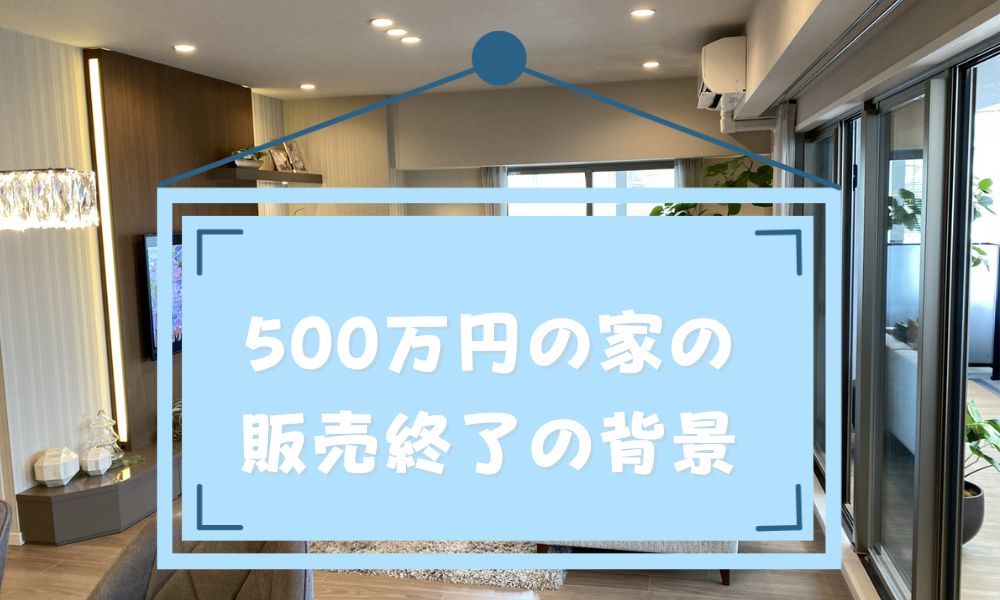
あれほどまでに注目を集めた「大安心の家5シリーズ」が、なぜ現在は販売終了となってしまったのでしょうか。
建築資材の価格高騰
まず最大の要因が、建築資材のグローバル規模での価格高騰です。
特に2020年以降、住宅業界は「ウッドショック」と呼ばれる未曾有の事態に見舞われました。
これは、コロナ禍における世界的な巣ごもり需要の急増や、リモートワーク普及による郊外住宅ブームがアメリカや中国で発生し、木材の需要が爆発的に増加したことに端を発します。
一方で、海上輸送のコンテナ不足や港湾作業の遅延といった供給網の混乱が重なり、需給バランスが崩壊。
木材価格はかつてないレベルまで跳ね上がりました。
さらに問題は木材だけに留まりませんでした。
世界的なインフレの波は鉄鉱石にも及び「アイアンショック」を引き起こし、鉄骨や建材金物の価格も高騰。
加えて、半導体不足は給湯器やIHクッキングヒーターといった住宅設備の納期遅延と価格上昇を招きました。
人件費の上昇圧力
資材価格と並行して、住宅価格を押し上げているのが「人件費の高騰」です。
これは、日本の建設業界が抱える構造的な問題に起因します。
少子高齢化による労働人口の減少は、特に体力と技術を要する建設現場で深刻化しており、大工や左官、電気工事士といった専門職人の高齢化と後継者不足は、もはや危機的な状況です。
熟練の職人が引退していく一方で、若手の入職者が少ないため、労働力の需要と供給のバランスが崩れ、一人当たりの人件費、つまり労務単価は上昇し続けています。
法律が求める住宅性能のレベルアップ
見落とされがちですが、現代の住宅価格が上昇している背景には、法律によって求められる「住宅性能の基準が格段に上がっている」という事実もあります。
これは単なる値上げではなく、住宅の「価値の向上」と捉えるべき側面です。
例えば、地球環境への配慮から、2025年以降に建てる全ての新築住宅には「省エネ基準」への適合が義務化されました。
これにより、断熱性能の高い断熱材や、熱の出入りを抑える高性能なサッシ(窓)の使用が必須となります。
また、頻発する地震への備えとして、耐震基準も年々厳格化する傾向にあります。
より強固な構造計算や耐震金物の使用が求められるなど、安全性を確保するためのコストは増加しています。
こうした高性能な建材や設備は、当然ながら従来のものより高価です。
つまり、昔と同じ仕様の家は、もはや法律上建てることができなくなっており、安全で快適な暮らしを実現するために必要なコストが、住宅の基本価格を底上げしているのです。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
タマホームの現在の低価格帯商品

かつての「500万円の家」は姿を消しましたが、タマホームの「良質低価格な住宅を、日本中に提供する」という企業理念は今も健在です。
規格住宅「シフクノいえ」
現在のタマホームで、最も価格を抑えた主力商品が「シフクノいえ」です。
このシリーズは、かつての「大安心の家5シリーズ」のコンセプトを受け継ぎつつ、現代の住宅性能基準に合わせて進化した規格住宅と言えるでしょう。
最大の魅力は、土地購入費を除く建物本体価格、付帯工事費、そして一部の諸費用まで含んだ「コミコミ価格」を提示している点です。
家づくりでは「見積もりを取ったら想定外の追加費用が次々と発生した」というケースが少なくありませんが、この商品は初期段階で総額に近い費用感が把握できるため、資金計画が立てやすく、予算オーバーのリスクを低減できるという大きな安心感があります。
木麗な家
「規格住宅では実現できない、自分だけのこだわりを形にしたい。
でも、予算はできるだけ抑えたい」という層に絶大な支持を得ているのが、タマホームのロングセラー商品「木麗な家」です。
この商品の最大の特徴は、坪単価40万円~45万円程度という、大手ハウスメーカーの注文住宅としては破格の価格帯で「完全自由設計」が可能な点です。
平屋「GALLERIART」
近年、子育て世代からシニア層まで幅広い世代で人気が高まっている「平屋」。
そのトレンドに応えるべく、タマホームが投入した平屋専用の商品が「GALLERIART(ガレリアート)」です。
この商品は、単に価格を抑えるだけでなく、デザイン性と暮らしの豊かさを追求している点が特徴です。
商品名は「GALLERY(ギャラリー)」と「ART(アート)」を組み合わせた造語であり、その名の通り、まるで美術館のように美しく、アートな空間で暮らすことをコンセプトにしています。
500万円で家を建てるときの注意点
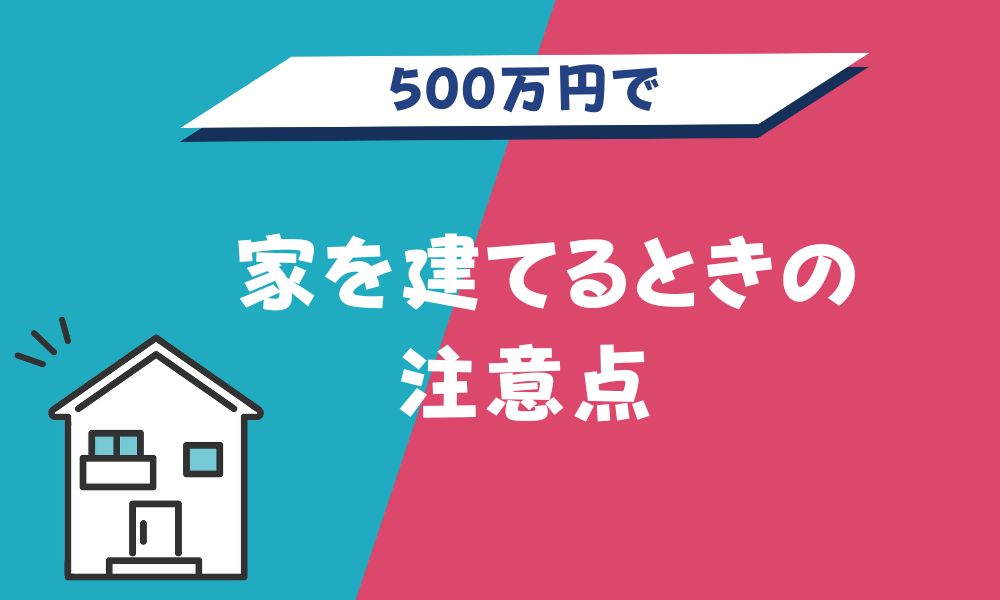
「タマホームでは無理でも、どこかなら総額500万円で家が建つのではないか?」という期待を抱く方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、土地代や諸費用をすべて含めた「総額500万円」で新築住宅を建てることは、2025年現在の日本では極めて困難です。
しかし、建物の工事費である「建物本体価格」を500万円台に設定している住宅商品は、一部の地域密着型工務店や特定の住宅メーカーで存在します。
500万円台の家
では、建物本体価格が500万円台の家とは、具体的にどのような家なのでしょうか。
その特徴は「徹底したコストカット」に集約されます。
超コンパクトなミニマム設計
まず、建物のサイズは極めてコンパクトになります。
延床面積で10坪~15坪(約33㎡~50㎡)程度が一般的で、間取りは1LDKや、場合によってはワンルーム+ロフトといった構成が中心です。
これは、都心のワンルームマンション程度の広さに相当し、一人暮らしや、夫婦二人でのシンプルな暮らし、あるいは母屋の隣に建てる離れや趣味の小屋といった限定的な用途を想定したサイズ感です。
凹凸のないシンプルな箱型デザイン
コストを抑えるため、建物の形状は正方形や長方形のシンプルな「箱型(キューブ型)」が基本となります。
複雑な凹凸のあるデザインは、材料が増えるだけでなく、施工の手間(人件費)も増大させるためです。
屋根も、施工が容易で安価な片流れ屋根や陸屋根が採用されることが多く、外観の装飾はほとんどありません。
内装も同様で、部屋数を最小限にして間仕切り壁を減らすなど、徹底したシンプル化が図られます。
設備は必要最低限のベーシックグレード
キッチン、ユニットバス、トイレといった水回り設備は、機能性を重視した最もベーシックなグレードのものが標準仕様となります。
例えばキッチンは、賃貸アパートでよく見られるような幅120cm~150cm程度のミニキッチンが採用されたり、バス・トイレ・洗面が一体となった3点ユニットバスが使われたりするケースもあります。
これらの設備を一般的なファミリータイプの住宅で採用されるようなシステムキッチンやセパレートタイプのバスルームにグレードアップしようとすると、それだけで数十万円から100万円以上のオプション費用が発生し、当初の予算を大幅に超えてしまう原因となります。
実現可能性のある選択肢と注意点
こうした500万円台の住宅は、主に特定の地域で事業を展開する工務店や、新しい技術を用いたベンチャー企業などによって提供されています。
例えば、3Dプリンターで家を造るセレンディクス社の「Fujitsubo」(49平米で500万円)、新潟県の平屋ベース(本体価格498万円~)、熊本県のヒラキハウジング「建つんです500」などがその例です。
これらの商品は全国どこでも建てられるわけではなく、施工エリアが限定されている場合がほとんどなので注意が必要です。
契約前に注意するデメリットとリスク
魅力的な価格の裏側には、必ず理解しておくべきデメリットが存在します。
価格だけで判断すると、後々「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があります。
品質・耐久性とメンテナンスコスト
価格を抑えるために、どの部分でコストカットが行われているのかを冷静に見極める必要があります。
例えば、断熱材の性能や厚み、構造材の等級、外壁材の耐久年数などが、一般的な注文住宅よりも低い水準に設定されている可能性があります。
ネット上の口コミはあくまで個人の感想であり、悪い評判の方が目立ちやすい傾向はありますが、一部で「価格相応の品質」といった指摘が見られるのも事実です。
初期費用は安くても、外壁や屋根のメンテナンスが短期間で必要になるなど、長期的に見ると維持費(メンテナンスコスト)がかさみ、結果的にトータルコストが高くつくリスクは考慮しておくべきです。
アフターサービスと保証体制
住宅は建てて終わりではありません。
大手ハウスメーカーが提供するような、30年、60年といった手厚い長期保証や、定期的な無料点検といった充実したアフターサービスは、ローコスト住宅では期待できない場合が多いです。
保証期間が法律で定められた最低限の10年のみであったり、アフターサービスの体制が整っていなかったりするケースも考えられます。
万が一、雨漏りなどの不具合が発生した際に、迅速で誠実な対応をしてもらえるのか、契約前に保証内容と会社の体制をしっかりと確認することが不可欠です。
住宅性能とランニングコスト
断熱性や気密性といった住宅性能は、日々の快適性と光熱費に直結します。
法律で定められた最低限の省エネ基準は満たしていても、ZEH(ゼッチ)に代表されるような高性能住宅と比較すると、性能が見劣りするのは否めません。
その結果、夏は暑く冬は寒い家になり、冷暖房効率が悪く月々の光熱費が高くなってしまう可能性があります。
「初期費用は安かったが、住んでからのランニングコストが高い」という状況は避けたいところです。
自由度の低さ
これらの住宅は規格住宅が基本のため、間取りの変更や仕様のカスタマイズにはほとんど対応できません。
少しの変更でも高額なオプション料金がかかったり、そもそも対応不可とされたりすることが多いです。
「この価格だから仕方ない」と割り切れるかどうかが、満足度を大きく左右します。
また、非常にコンパクトな設計のため、将来、子どもが生まれるなどの家族構成の変化に対応するのは難しく、リフォームや増築が困難な構造である可能性も考慮しておく必要があります。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
予算を抑えて理想の家を建てるためのポイント

「総額500万円」という予算は現実的ではありませんが、工夫次第で建築コストを賢く削減し、予算内で満足度の高い理想のマイホームを実現することは十分に可能です。
設計段階がコストダウンの最大のチャンス
家づくりの総費用は、設計段階でその大部分が決まります。
後から変更することが難しい構造や間取りの工夫こそが、最も効果的なコストダウンに繋がります。
形状は「シンプル・イズ・ベスト」
建築費を大きく左右するのが、建物の形状です。最もコスト効率が良いのは、凹凸のない正方形や長方形の「総二階建て」です。
同じ床面積でも、L字型やコの字型など複雑な形状の家は、外壁の面積が増え、角の部分(コーナー)が多くなるため、材料費も施工の手間(人件費)も増大します。
屋根も、複数の面を組み合わせた複雑な形状より、シンプルな切妻屋根や片流れ屋根の方がコストを抑えられます。
まずは「シンプルな箱」を基本に考えることが、予算を抑える第一歩です。
間取りは「仕切らない」発想
室内の壁を一枚作るだけでも、壁材や下地材、クロス、そして施工費がかかります。
子ども部屋などを将来的に仕切ることを想定し、最初は大きな一部屋として作っておく「フリースペース」の発想は、初期費用を抑える有効な手段です。
また、廊下を極力なくし、リビングを介して各部屋にアクセスするような間取りにすれば、廊下分の床面積と建材費を削減し、その分LDKや居室を広くすることができます。
水回りは一箇所に「集中配置」
キッチン、浴室、洗面所、トイレといった水回りの設備は、できるだけ一箇所に集約して配置しましょう。
配管が分散すると、その分だけ給排水管の長さが必要になり、工事費が高騰します。
例えば、1階のキッチンの真上に2階のトイレを配置するなど、上下階で位置を揃えることで、配管ルートを最短にでき、大幅なコスト削減に繋がります。
仕様・設備の選択に「メリハリ」をつける
全ての建材や設備をハイグレードにすると、予算はあっという間に膨れ上がります。
家族のライフスタイルを鑑み、こだわりたい部分と、妥協できる割り切りポイントを明確にすることが重要です。
グレードの優先順位を決める
例えば、「家族が一番長く過ごすリビングの床材は、足触りの良い無垢材にしたい。
その代わり、寝室や子ども部屋の床は標準仕様のフローリングで構わない」「毎日使うキッチンは、食洗機付きの最新モデルにこだわりたいが、トイレは温水洗浄便座さえあればシンプルな機能で十分」といったように、予算を投下する部分と節約する部分に優先順位をつけましょう。
人目に付きやすい玄関ドアやリビングのクロスには少し良いものを、パントリーや収納内部のクロスは安価な量産品にする、といった細かな工夫も有効です。
施主支給を賢く活用する
照明器具やカーテンレール、タオルハンガー、表札といった一部の設備やアクセサリー類は、ハウスメーカーに依頼せず、自分でインターネットや専門店で購入して現場に持ち込み、取り付けてもらう「施主支給」という方法があります。
ハウスメーカー経由よりも安価に手に入れられる場合が多く、デザインの選択肢も広がります。
ただし、商品の保証責任が自分になる、取り付け費用が別途かかる、工事のスケジュール調整が必要になるなど注意点もあるため、事前にハウスメーカーの担当者と相談し、施主支給が可能な範囲とルールを確認しておくことが不可欠です。
補助金と相見積もりで資金計画を最適化
家づくりの最終段階で大きな差がつくのが、情報収集と交渉力です。
使える補助金はすべて活用する
国や自治体は、省エネ性能の高い住宅(ZEH支援事業など)や、子育て世帯向けの住宅取得(こどもエコすまい支援事業など)に対して、様々な補助金・助成金制度を用意しています。
これらの制度は年度ごとに内容が変わり、申請期間も限られているため、常に最新情報をチェックすることが重要です。
補助金の活用は、数十万円から百万円以上の直接的なコスト削減に繋がるため、利用しない手はありません。
ハウスメーカーの担当者にも積極的に確認し、使える制度がないか相談しましょう。
「相見積もり」は必須
家づくりで最も重要なプロセスの一つが、複数のハウスメーカーや工務店から同じような条件で見積もりとプランを取り寄せ、比較検討する「相見積もり」です。
1社だけの話では、提示された価格やプランが適正なのか客観的に判断できません。
最低でも3社以上から話を聞くことで、各社の強みや弱み、提案力の違いが見えてくるだけでなく、おおよその相場感を掴むことができます。
それは、価格交渉を行う際の強力な材料にもなります。
手間と時間はかかりますが、このプロセスを丁寧に行うことが、最終的に数百万円単位の差を生むこともあり、後悔のない家づくりを実現するための絶対条件と言えるでしょう。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
まとめ
この記事では、かつて話題となったタマホームの「500万円の家」について、販売終了の背景、そして2025年現在における現実的なマイホームの作り方まで掘り下げてきました。
結論として、「500万円の家」は過去のキャンペーン商品であり、現在は存在しません。
しかしタマホームは現在も「シフクノいえ」や「木麗な家」など、良質低価格な住宅を提供し続けています。
ぜひこの記事の情報も参考にしながら、理想の家づくりを目指してみてくださいね。


コメント