「賃貸か、それとも持ち家か?」
多くの人がこのように感じたことがあるのではないでしょうか。
インターネットを検索すれば、「持ち家は1,300万円もお得になる」という数字が目に飛び込んでくる一方で、「家を買う時代は終わった」と断言する著名人の声も聞こえてきます。
友人や親からは「早く家を買って安心した方がいい」とアドバイスされ、SNSでは「賃貸で身軽に生きるのが最高」というライフスタイルが良いように見える。
あまりにも多くの情報が溢れる中で、一体何を信じ、どう判断すればいいのか、迷ってしまいますよね。
そこでこの記事では、この「1,300万円の差」について解剖し、シミュレーションや体験談をもとに、みていきますよ。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
本文に入る前に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えしておきます。
家づくりで一番大切なこと、それは「気になっているハウスメーカーを徹底的に比較検討すること」です。
よくある失敗パターンとして、住宅展示場に行って営業マンの巧みなトークに流されその場で契約をしてしまうというケースがあります。実際に、「もしもしっかりと比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
だからこそ、きちんとした比較検討をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
ではどのように比較検討すればいいのでしょうか。
その方法は、「ハウスメーカーのカタログをとりあえず集めてしまうこと」なんです!

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、全ての会社に連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのようにカタログを集めていいのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしい無料で利用できるサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「プロのアドバイザーに実際に相談できるサービス」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の2つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトSUUMOが運営する注文住宅相談サービスです。全国各地のハウスメーカー・工務店とのネットワークも豊富。スーモカウンターの最大の特徴が、店舗またはオンラインでアドバイザー相談が可能なことです。住宅の専門家に相談ができるので、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はまずはスーモカウンターに相談することがおすすめです。 |
上記の2サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
後悔のない家づくりのために、上記のサービスを活用しながら、1社でも多くの会社を比較検討してみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
1,300万円の差とは
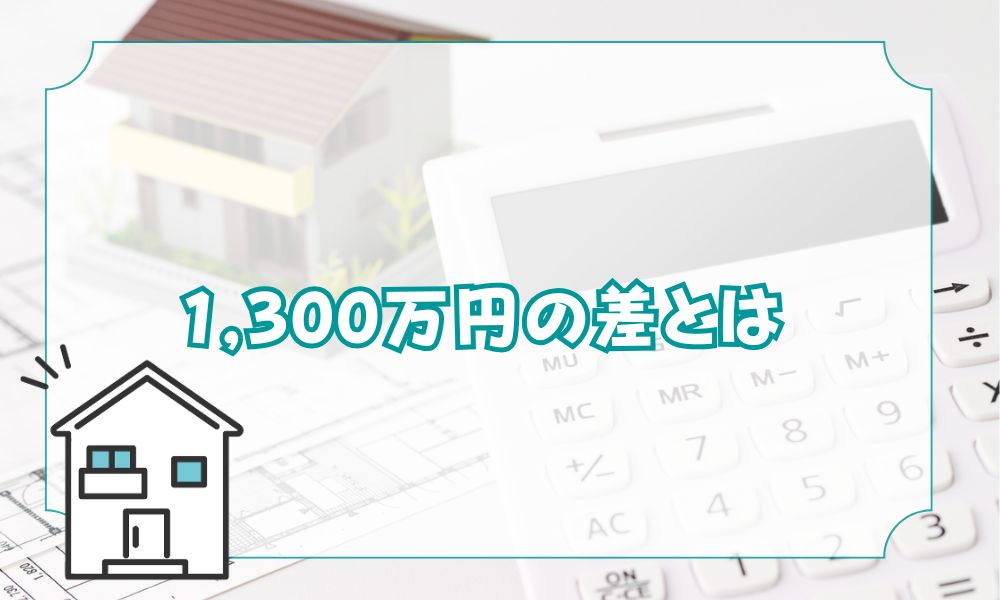
「持ち家と賃貸では生涯コストに1,300万円もの差が出る」という話があります。
ここでは、この「1,300万円」という差額がどのように算出されているのか解説します。
老後の家賃負担
1,300万円という差額が生まれる最も大きな要因は、現役時代ではなく、リタイア後の「老後の家賃負担」にあります。
多くの人が65歳で定年を迎え、公的年金が主な収入源となる生活が始まります。
このタイミングで、住居費がどうなっているかが、生涯コストに決定的な差をもたらすのです。
具体的に考えてみましょう。
仮に65歳から平均寿命に近い85歳までの20年間、月々7万円の家賃を支払い続けるとします。
その総額は「7万円 × 12ヶ月 × 20年 = 1,680万円」となります。
もし80歳までの15年間だとしても、総額は1,260万円に上ります。
これは、収入が大幅に減少する年金生活において、非常に重い負担です。
現役時代には問題なく支払えていた家賃が、老後の家計を圧迫する「時限爆弾」となり得るのです。
一方で、住宅ローンを現役時代に完済した持ち家の場合、この期間の住居費は固定資産税や計画的な修繕費のみとなります。
もちろんゼロではありませんが、毎月決まって出ていく家賃という大きな固定費がなくなることは、計り知れない経済的・精神的な安心感につながります。
将来のインフレによる家賃上昇のリスクも回避できるため、支出計画が立てやすい点も大きなメリットです。
見えないコスト差
もう一つの要因は、現役時代に発生する月々の支払い額の差です。
一見すると、同じような立地・広さの物件であれば、住宅ローンの月々の返済額と家賃はさほど変わらないように思えるかもしれません。
しかし、ここにも構造的な差が存在します。
例えば、東京都内で3,000万円の1LDK物件を35年フルローン(金利1.5%と仮定)で購入した場合、月々の返済額は約92,000円です。
これに対し、同等の物件を賃貸で借りると、家賃相場は約12万円程度になることがあります。
この差額、月々約28,000円がどこから生まれるかというと、それは家賃の価格設定の仕組みにあります。
家賃には、建物の維持管理費や税金だけでなく、大家さんの利益、空室発生時の損失補填、将来のリフォーム費用、そして事業用であるアパートローンの高い金利などが上乗せされています。
つまり、賃貸に住むということは、これらのコストを間接的に負担していることになるのです。
この月々約28,000円の差は、35年間続くと合計で「28,000円 × 12ヶ月 × 35年 = 1,176万円」という巨大な金額に膨れ上がります。
この差額を貯蓄や投資に回すことができれば、さらに大きな資産形成につながる可能性もあります。
短期的に見ればわずかな差に感じられても、長期的な視点では無視できない「見えないコスト差」となるのです。
1,300万円は絶対的な数字ではない
ここまで解説してきた通り、「1,300万円の差」には明確な根拠があります。
しかし、この数字はあくまで特定の条件下でのシミュレーション結果であり、誰にでも当てはまる絶対的なものではないことを強く認識しておく必要があります。
この数字は、以下のような多くの変動要因によって大きく変わります。
- 地域差: 物件価格や家賃相場は、首都圏と地方では全く異なります。地方都市では持ち家と賃貸のコスト差が縮まる、あるいは逆転するケースも考えられます。
- 金利の動向: 持ち家は金利変動リスクを伴います。特に変動金利でローンを組んだ場合、将来金利が上昇すれば返済額が増加し、シミュレーション以上のコストがかかる可能性があります。
- 物件の条件とメンテナンス費用: この試算では、持ち家の突発的な大規模修繕(外壁塗装や給排水管の交換など)の費用が十分に考慮されていない場合があります。戸建てかマンションか、新築か中古かによっても、維持管理にかかる費用は大きく異なります。
したがって、「1,300万円お得だから持ち家を選ぶ」という短絡的な判断は危険です。
この数字はあくまで一つの判断材料として捉え、ご自身のライフプランや価値観、そして将来のリスクを多角的に検討することが、後悔のない住まい選びにつながるのです。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
生涯コストの具体的なシミュレーション

持ち家と賃貸、どちらが経済的に有利かを判断するためには、具体的な数字に基づいたシミュレーションが不可欠です。
郊外ファミリー向け「戸建て」の生涯コスト比較
まずは、元の記事でも紹介されていた大阪府堺市南区での実例を参考に、より詳細な内訳を想定してコストを分解してみましょう。
持ち家(新築建売3,680万円)の総コスト内訳(35年間)
- 物件関連費用: 物件価格3,680万円 + 購入諸費用(登記費用、ローン手数料等)約250万円 = 3,930万円
- ローン金利: 約1,050万円(元利均等、金利1.5%、35年で試算)
- 税金: 固定資産税・都市計画税 約420万円(年間12万円と仮定)
- 維持管理費: メンテナンス・修繕費 約250万円(外壁塗装、給湯器交換等を想定)+ 火災保険料 約30万円
- 概算合計:約5,680万円
賃貸一戸建て(家賃16万円)の総コスト内訳(35年間)
- 家賃総額: 16万円 × 12ヶ月 × 35年 = 6,720万円
- その他費用: 更新料(2年毎に家賃1ヶ月分)約272万円 + 火災保険料(2年毎に2万円)約34万円
- 概算合計:約7,026万円
このシミュレーションでは、持ち家の方が賃貸よりも約1,346万円お得という結果になります。
ここで注目すべきは、賃貸の「更新料」です。
2年に一度の支払いですが、35年間という長期間では約272万円もの大きな出費となります。
さらに重要なのは、持ち家側には「住宅ローン控除」という強力な税制優遇がある点です。
条件によりますが、10年以上にわたって年末のローン残高に応じた税金が還付されるため、実質的なコスト差はさらに数百万単位で広がる可能性があります。
都市部向け「マンション」の生涯コスト比較
次に、マンションのケースを見ていきましょう。
マンションは戸建てと異なり、「管理費」と「修繕積立金」という特有のコストが発生するため、生涯コストの構造が大きく変わります。
持ち家(購入価格4,000万円)の総コスト内訳(45年間)
- 物件関連・金利費用: 物件価格4,000万円 + 諸費用約280万円 + ローン金利約1,140万円 = 5,420万円
- 税金: 固定資産税・都市計画税 約675万円(年間15万円と仮定)
- 維持管理費: 管理費・修繕積立金 約1,620万円(月額3万円と仮定)+ 火災保険料 約40万円
- 概算合計:約7,755万円
賃貸(同等グレード家賃15万円)の総コスト内訳(45年間)
- 家賃総額: 15万円 × 12ヶ月 × 45年 = 8,100万円
- その他費用: 更新料(2年毎に家賃1ヶ月分)約330万円 + 火災保険料等
- 概算合計:約8,430万円
この場合、持ち家の方が約675万円有利という結果になります。
戸建てのケースよりも差が縮まっているのは、マンション特有の「管理費・修繕積立金」が大きな要因です。
45年間で1,600万円以上にもなるこの費用は、持ち家の大きな負担となります。
特に修繕積立金は、建物の老朽化に伴い、将来的に値上がりするリスクも考慮しておく必要があります。
賃貸と持ち家のメリット・デメリット

ここでは賃貸と持ち家、それぞれが持つ独自のメリットとデメリットを深く掘り下げていきましょう。
賃貸のメリットとデメリット
賃貸の最大の魅力は、その「身軽さ」と「柔軟性」に集約されます。
これは、変化の激しい現代において非常に大きな価値を持ちます。
メリット1:住み替え力とライフステージへの適応性
賃貸の最も強力なメリットは、ライフステージの変化に迅速かつ柔軟に対応できる点です。
例えば、結婚を機に広い部屋へ、子供が生まれれば子育てしやすい環境へ、子供が独立すれば夫婦二人にちょうどいいサイズへ、といった家族構成の変化に合わせて住まいを最適化できます。
これは、急な転勤や転職といった仕事上の変化にも同様に対応できることを意味します。
さらに、この「住み替え力」はリスク回避の観点からも有効です。
万が一、近隣トラブル(騒音、人間関係など)に悩まされたり、住んでいる地域の治安や環境が悪化したりした場合でも、「引っ越す」という選択肢でリセットが可能です。
近年では、災害リスクを考慮して住む場所を選ぶ人も増えており、状況に応じてより安全な場所へ移れるフットワークの軽さは、賃貸ならではの強みと言えるでしょう。
メリット2:コスト管理のシンプルさ
賃貸は、家計管理が非常にシンプルです。
毎月の支出は、基本的に「家賃+管理費」で固定されており、将来の資金計画が立てやすいのが特徴です。
持ち家のように、突然の給湯器の故障で数十万円、数年後の外壁塗装で百万円以上といった突発的な高額出費に備える必要がありません。
建物のメンテナンスや修繕は、すべて大家や管理会社の責任と費用で行われます。
また、毎年納税義務が発生する固定資産税や都市計画税の支払い、火災保険や地震保険の詳細な検討と契約手続きといった、所有者ならではの煩雑な手間からも解放されます。
この「コスト管理のシンプルさ」は、家の維持管理に頭を悩ませたくない人や、毎月のキャッシュフローを安定させたい人にとって、大きな精神的安らぎをもたらします。
デメリット1:資産にならない
賃貸の最大のデメリットは、どれだけ長期間、高額な家賃を支払い続けても、その住まいが自分の資産にはならない点です。
支払った家賃は、持ち家のローン返済のように資産に変わることはなく、純粋な「消費」として消えていきます。
ローンには「完済」というゴールがありますが、家賃の支払いには終わりがありません。
これは、「自分のためではなく、大家さんの資産形成を手伝っている」という感覚につながり、特に家賃が高額になる都市部では「もったいない」という感情を抱く大きな要因となります。
デメリット2:「窮屈さ」と老後の不安
賃貸物件では、所有者ではないため、住まいに対する自由度が大きく制限されます。
壁に穴を開けて棚を取り付ける、ペットと一緒に暮らす、趣味の楽器を演奏する、といった行為は規約で禁止されていることがほとんどです。
自分好みの壁紙に変えたり、最新のシステムキッチンに入れ替えたりといったリフォームも当然できません。
この「自分らしく暮らせない」という制約は、住環境にこだわりたい人にとっては大きなストレスとなり得ます。
さらに深刻なのが、「老後の契約リスク」です。
現役時代は問題なくとも、年金生活に入り収入が減少すると、家賃の支払い能力を懸念され、新規の賃貸契約が難しくなるケースがあります。
また、保証人が見つけにくい、孤独死のリスクを大家側が懸念する、といった理由で入居を断られる可能性もゼロではなく、将来の住まいの確保に不安がつきまとう点は、賃貸の大きなデメリットです。
持ち家のメリットとデメリット
持ち家がもたらす価値は、単なる「マイホーム」という言葉の響き以上に、経済的・精神的な安定と豊かさにあります。
メリット1:資産形成と社会的信用力
持ち家の最大のメリットは、住宅ローンを完済すれば土地と建物が紛れもない「自分の資産」になることです。
この資産は、将来売却して老後の資金にしたり、子供に相続させたり、リバースモーゲージ制度を利用して生活費を受け取ったりと、様々な形で活用できます。
インフレで物価が上昇すれば、不動産価値も連動して上昇する傾向があるため、インフレヘッジとしての機能も期待できます。
さらに、不動産という確固たる資産を所有していることは、「社会的信用力」の向上にもつながります。
例えば、子供の教育ローンや自身の事業資金など、別のローンを組む際に、持ち家が担保として有利に働く場合があります。
これは、賃貸暮らしでは得られない、持ち家ならではの経済的な強みです。
メリット2:自由度
法律の範囲内であれば、リフォームやリノベーションを自由に行い、理想の住空間を創造できます。
子供の成長に合わせて間取りを変更したり、趣味のオーディオルームや書斎を作ったり、年齢を重ねた際に備えてバリアフリー化したりと、ライフステージの変化に家を合わせていくことが可能です。
庭があれば家庭菜園やバーベキューを楽しんだり、ペットを気兼ねなく飼ったりと、賃貸では実現が難しかった豊かな暮らしが手に入ります。
この「暮らしを自分で創り上げる」という喜びと絶対的な自由度は、何物にも代えがたい持ち家の魅力と言えるでしょう。
デメリット1:流動性の低さと売却リスク
持ち家は「不動産」という名の通り、簡単に動かすことができません。
この「流動性の低さ」は、持ち家の最大のデメリットです。
急な転勤が決まっても、賃貸のように簡単には引っ越せません。
家を売却するにしても、買い手を見つけるまでに時間がかかりますし、仲介手数料などのコストも発生します。
また、市況の悪化や近隣環境の変化により、希望した価格で売れる保証はなく、「売却損」を被るリスクも常に伴います。
賃貸に出すという選択肢もありますが、その場合も空室リスクや入居者管理の手間といった新たな問題が発生します。
デメリット2:維持管理の責任とコスト
家を所有するということは、その建物の状態を維持する全責任を負うことを意味します。
外壁塗装や屋根の防水工事(10〜15年周期で100万円以上)、給湯器やキッチン・浴室といった水回り設備の交換(15〜20年周期で数十万円〜)など、計画的な修繕が不可欠であり、そのための資金を長期的な視点で積み立てておく必要があります。
また、毎年課される固定資産税・都市計画税の支払いは、ローン完済後も続きます。
マンションの場合は、これに加えて管理費・修繕積立金の支払いや、管理組合の理事といった役割が回ってくる可能性もあり、金銭的・時間的な負担が継続的に発生することを覚悟しなければなりません。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
それぞれに向いている人・向いていない人
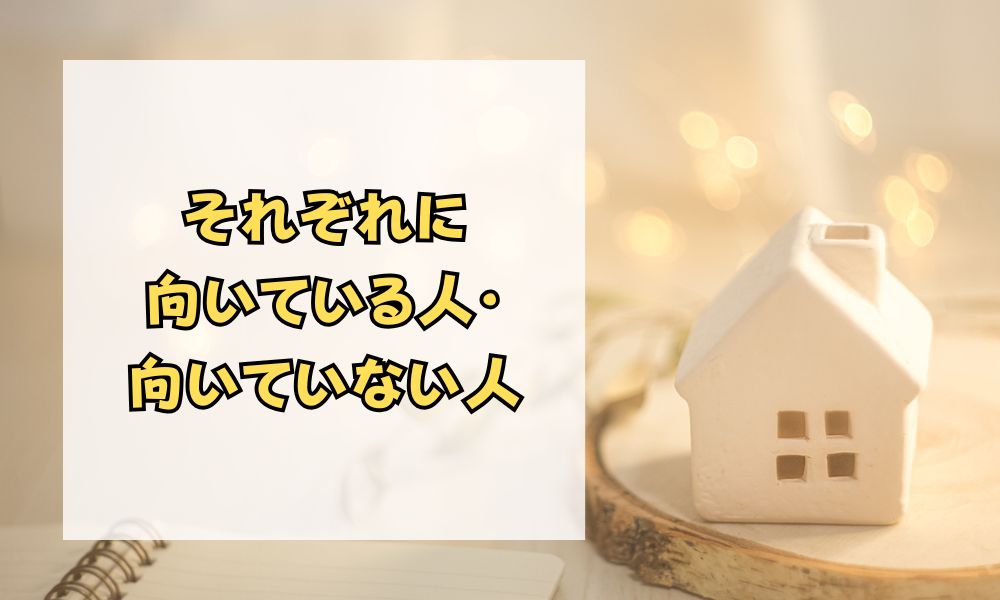
ここでは、より具体的な人物像(ペルソナ)を想定し、どのようなライフスタイルや価値観を持つ人がそれぞれに向いているのかを深く掘り下げていきます。
賃貸が向いている人
賃貸の持つ「柔軟性」「身軽さ」「シンプルさ」は、特定の価値観を持つ人々の人生をより豊かにします。
- キャリアと変化を追求する「フットワーク重視型」:あなたは、キャリアの可能性を最大限に追求したいと考えていませんか?国内外の転勤や、より魅力的な企業への転職、フリーランスとしての独立など、キャリアパスが流動的な方にとって、持ち家は時に足かせとなり得ます。「良い話があるけれど、家があるから動けない」という状況は、大きな機会損失につながりかねません。賃貸であれば、住居に縛られることなく、自身のキャリアにとって最善の選択を追求できます。住まいを「コスト」と割り切り、その分を自己投資や新しい経験に回す。そんなフットワークの軽さを重視するあなたには、賃貸が最適なパートナーとなるでしょう。
- リスクを避けシンプルを愛する「安定志向のミニマリスト型」:数千万円もの住宅ローンを背負うことや、不動産価格の変動、金利上昇といったコントロール不能なリスクに、強い心理的ストレスを感じるタイプではありませんか?また、家のメンテナンス計画を立てたり、管理組合の活動に参加したりすることに、貴重な時間や労力を割きたくないと感じるかもしれません。このような「安定志向」の方にとって、賃貸は精神的な平穏をもたらします。支出が「家賃」に集約され、将来のキャッシュフローが見通しやすいシンプルさは、何にも代えがたいメリットです。所有することの煩わしさから解放され、心穏やかにミニマルな生活を送りたいあなたには、賃貸という選択が心地よくフィットします。
- 多様な経験を重視する「体験価値追求型」:あなたは、「所有」することよりも、人生で様々な「体験」をすることに価値を見出すタイプではないでしょうか。子供が独立したら、憧れの海の見える街へ。数年後には、歴史ある城下町で古民家暮らしを。そして最後は、利便性の高い都心のコンパクトなマンションへ。このように、住まいを「終の棲家」ではなく「人生を彩る舞台装置」と捉え、ライフステージや気分に合わせて住環境を変えることを楽しみたい方にとって、持ち家は不向きです。賃貸なら、住みたい場所に住み、新しい環境での暮らしを体験するという、豊かで刺激的な人生を送ることが可能です。
持ち家が向いている人
持ち家がもたらす「資産性」「自由度」「安心感」は、また別の価値観を持つ人々の幸福度を大きく高めます。
- 家族との時間を育む「コミュニティ・子育て重視型」:あなたにとって、家族との安定した生活は何よりも大切ですか?子供の足音や泣き声を気にすることなく、のびのびと成長できる環境を整えてあげたい。学区を固定し、地域に根差した友人関係を育んでほしい。庭でバーベキューをしたり、ペットと一緒に暮らしたり、家族の歴史を刻む「我が家」が欲しい。このような想いが強いなら、持ち家は最高の選択肢です。持ち家は単なる「住む箱」ではなく、家族の思い出が積み重なる拠点となり、子供の精神的な安定にもつながります。地域コミュニティの一員として、腰を据えて暮らしたいあなたにとって、持ち家はかけがえのない価値を提供します。
- 自分だけの空間を創造する「こだわりDIY・カスタマイズ型」:あなたは、住まいを自己表現の場と捉え、自分好みの空間を創り上げることに喜びを感じるタイプではありませんか?既成の壁紙や間取りに満足できず、賃貸の「原状回復義務」が常に頭をよぎることにストレスを感じるなら、持ち家はあなたの創造性を解放するキャンバスとなります。壁の色を塗り替え、キッチンを最新モデルに交換し、自分の手でウッドデッキを作る。住宅ローンを「理想のライフスタイルを実現するための投資」とポジティブに捉え、QOL(生活の質)の向上を追求するあなたには、持ち家の絶対的な自由度が不可欠です。
- 将来を見据えた「計画的資産形成型」:あなたは、物事を長期的な視点で捉え、計画的に目標を達成することに長けていますか?「家賃を払い続けるのは、穴の開いたバケツに水を注ぐようなものだ」と感じ、経済合理性を重視するなら、持ち家は強力な資産形成ツールとなります。住宅ローンを計画的に返済し、老後の住居費負担をゼロにすることで得られる将来の安心感。団体信用生命保険による万が一の備え。住宅ローン控除を活用した税制メリット。これらを理解し、家計をコントロールしながら着実に資産を築いていくことに充実感を覚えるあなたにとって、持ち家は最も賢明な選択と言えるでしょう。
体験談(口コミ)から見る選択の決め手

ここでは、SNSや掲示板などで語られるリアルな体験談をもとに、人々がどのような価値観を背景に選択の「決め手」としたのかを深く探っていきます。
持ち家を選んだ人の声
持ち家を選択した方々の体験談には、「長期的な安心感」と「暮らしの自由度」という共通したテーマが流れています。
それは、住宅ローンという大きな責任を果たした先にある、豊かな暮らしへの実感です。
- 「ローン完済後の世界は想像以上だった」という経済的・精神的安堵感:「現役時代は夫婦で必死に働いてローンを返済。正直、大変な時期もありましたが、60歳で完済した時の解放感は忘れられません。今は年金生活ですが、毎月の家賃負担がないというだけで、心の余裕が全く違います。固定資産税はかかりますが、現役時代の家賃に比べれば微々たるもの。旅行に行ったり、孫にお小遣いをあげたりできるのも、この安心感があってこそ。この未来のために頑張ってきて本当に良かったと、心から思います。」
- 「子供の笑顔が最高の報酬」という子育て環境の価値:「以前住んでいた賃貸アパートでは、子供が走り回る音で階下の方に気を遣い、毎日『静かにしなさい!』と叱ってばかりで親子ともにストレスでした。思い切って郊外に戸建てを購入してからは、家の中でも庭でも子供が思いっきり遊べるようになり、笑顔が格段に増えました。汚しても騒いでも『うちだから大丈夫』と言える。この環境は、どんなにお金を積んでも得られない価値があったと感じています。」
- 「自分だけの城を創る喜び」という自己実現:「壁の色、キッチンの仕様、庭の植栽まで、すべて自分たちの好みで作り上げました。賃貸では絶対にできなかったことです。週末に夫婦でDIYで棚を作ったり、庭で育てたハーブで料理をしたり。『家を育てる』という感覚は、持ち家ならではの喜びです。この家と共に、家族の歴史が刻まれていくのが何よりの幸せです。」
賃貸を選んだ人々の声
一方で、賃貸を選択した方々は、「所有」という概念から自由になることで得られる「軽やかさ」と、人生のステージに合わせて住まいを「最適化」していくことに価値を見出しています。
- 「いつでもリセットできる」というリスク回避:ネット上の口コミは様々な私見で溢れていますが、中には「以前住んでいた分譲マンションで、生活音をめぐる隣人トラブルに長年悩まされました。売却しようにもすぐには買い手がつかず、精神的に追い詰められた経験から、二度と不動産は所有しないと決めました。賃貸なら、万が一問題が起きても引っ越せばいい。この『リセットできる』という選択肢が、心の保険になっています」という声も見られます。
- 「人生のフェーズに合わせた最適解」という合理性:「20代は通勤に便利な都心のワンルーム、30代の子育て期は公園が近い郊外の3LDK、子供が独立した今は、夫婦二人で管理が楽な駅近のコンパクトマンション。その時々のライフスタイルに最適な間取り、立地を選べるのが最高です。常に築浅物件を選べば最新の設備が使えますし、引っ越しのたびに断捨離できるので、家もスッキリします。」
- 「”所有”という重圧からの自由」という価値観:「地震や水害などの自然災害が多い日本で、一つの土地に全財産を投じるのはリスクだと感じます。家の資産価値が将来どうなるかも不透明ですし。賃貸なら、そうした心配から解放され、家賃以上のコストはかからない。家を維持管理する手間やローン返済のプレッシャーから自由になって、その分のエネルギーを旅行や趣味、自己投資に使って人生を楽しみたいです。」
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
まとめ
ここまで、「1,300万円の差」という数字の真相から、具体的な生涯コストのシミュレーション、そしてそれぞれのメリット・デメリットまで、多角的にみてきました。
最終的に、どちらを選ぶべきかは、あなたの価値観やライフプランによって変わります。
ぜひこの記事も参考に、納得のいく選択を行ってみてくださいね。
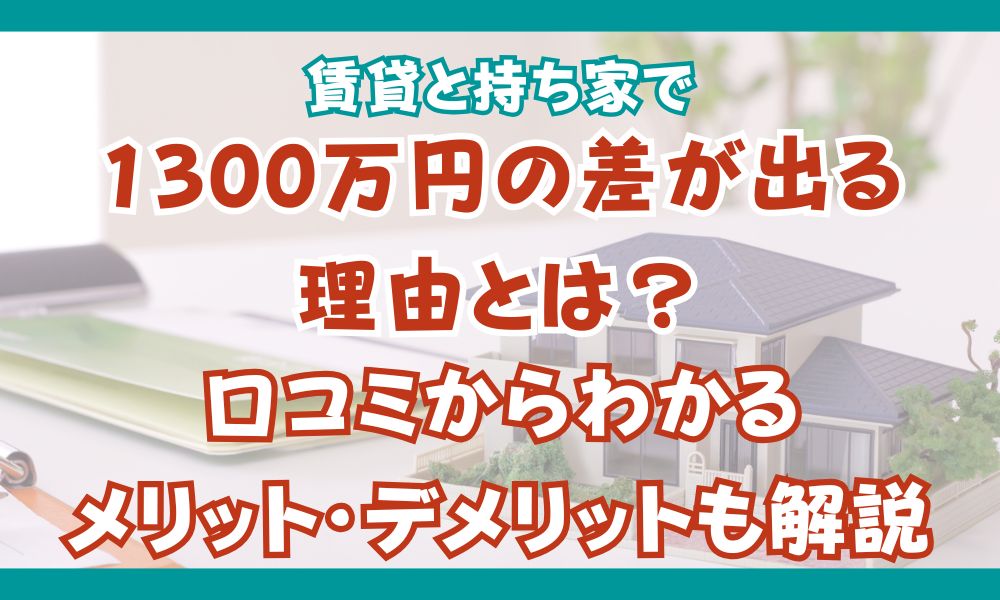

コメント