「今、この状況で家を買うなんて信じられない」
「5年後、10年後には絶対に後悔する」
インターネットや周囲から聞こえてくるこのような声に、不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、「今、家を買うと大変なことになる」と言われる7つの理由について、一つひとつ深掘りしていきます。
ぜひ最後まで参考にしてみてくださいね。
本文に入る前に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えしておきます。
家づくりで一番大切なこと、それは「気になっているハウスメーカーを徹底的に比較検討すること」です。
よくある失敗パターンとして、住宅展示場に行って営業マンの巧みなトークに流されその場で契約をしてしまうというケースがあります。実際に、「もしもしっかりと比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
だからこそ、きちんとした比較検討をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
ではどのように比較検討すればいいのでしょうか。
その方法は、「ハウスメーカーのカタログをとりあえず集めてしまうこと」なんです!

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、全ての会社に連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのようにカタログを集めていいのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしい無料で利用できるサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「プロのアドバイザーに実際に相談できるサービス」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の2つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトSUUMOが運営する注文住宅相談サービスです。全国各地のハウスメーカー・工務店とのネットワークも豊富。スーモカウンターの最大の特徴が、店舗またはオンラインでアドバイザー相談が可能なことです。住宅の専門家に相談ができるので、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はまずはスーモカウンターに相談することがおすすめです。 |
上記の2サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
後悔のない家づくりのために、上記のサービスを活用しながら、1社でも多くの会社を比較検討してみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
経済状況の悪化と物価の高騰
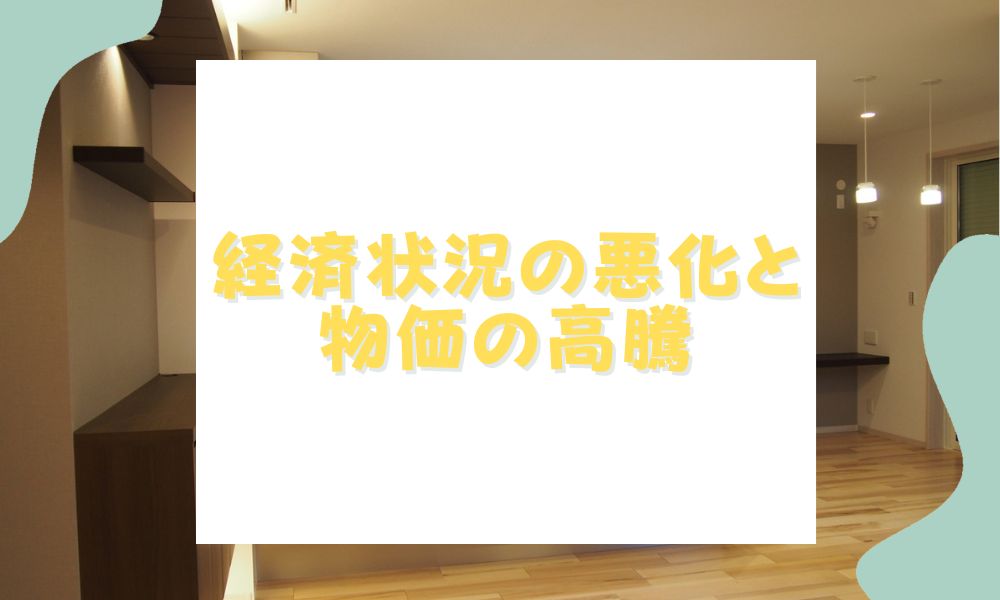
「今、家を買うべきではない」という意見の根底には、多くの人が肌で感じている「経済の不透明さ」と「物価高」への強い懸念があります。
住宅価格を押し上げる
現在の住宅価格高騰は、一過性の現象ではなく、複数の要因が重なった構造的な問題です。
- 資材価格の暴騰(建材ショック):記憶に新しい「ウッドショック」では、コロナ禍からの経済再開に伴う世界的な住宅需要の急増やコンテナ不足が重なり、2020年から2022年にかけて木材価格が倍以上に跳ね上がりました。しかし、問題は木材だけにとどまりません。ウクライナ情勢などを背景とした鉄鉱石の価格高騰による「アイアンショック」、原油価格の上昇に伴う石油化学製品(断熱材や塩ビ管など)の値上がりなど、建築に必要なあらゆる資材が高騰する「建材ショック」とも呼べる状況が続いています。
- 歴史的な円安:住宅に使われる建材や設備は、私たちが想像する以上に輸入に依存しています。構造材やフローリングに使われる木材、アルミサッシ、ユニットバス、キッチン設備、照明器具や配線に使われる銅など、その範囲は多岐にわたります。例えば、1ドル110円の時に1万ドル(約110万円)で輸入できた資材が、1ドル150円になると150万円を支払う必要があります。この差額40万円は、そのまま建築コストに上乗せされるため、円安が続く限り、住宅価格の上昇圧力は弱まりません。
- 高止まりする人件費:建設業界は、長年にわたる深刻な人手不足と職人の高齢化に直面しており、人件費は上昇傾向にあります。これに追い打ちをかけているのが「建設業の問題」です。働き方改革関連法の適用により、時間外労働に上限が設けられ、事業者は労働環境の改善を迫られています。これは労働者にとっては望ましいことですが、企業側から見れば、工期の長期化や人件費のさらなる上昇につながり、最終的に建築コストとして施主に転嫁される一因となっています。
住宅ローン返済を圧迫する支出
住宅価格そのものの上昇に加え、日々の生活コストの増加も住宅購入の大きな障壁となっています。
電気、ガス、水道といった光熱費、ガソリン代、そして毎日の食料品や日用品まで、あらゆるものの値段が上がり、家計における固定費はじわじわと増加しています。
問題なのは、給料の上昇が物価高に全く追いついていない「実質賃金のマイナス」が続いている点です。
つまり、私たちの手元に残り、自由に使えるお金(可処分所得)は実質的に目減りし続けているのです。
このような状況で高額な住宅ローンを組むとどうなるでしょうか。
毎月の返済額は固定されていても、生活費が上昇し続けることで、家計に占める「住宅ローン+生活費」の割合が雪だるま式に膨れ上がっていきます。
これにより、貯蓄に回すお金がなくなったり、子どもの教育費や自分たちの老後資金の準備が滞ったりと、ライフプラン全体に深刻な影響を及ぼす危険性があるのです。
「節約すれば何とかなる」というレベルを超えた物価高が、長期的な返済計画の土台そのものを揺るがしています。
将来の収入不安
35年といった長期にわたる住宅ローンの返済計画は、「将来にわたって安定的かつ継続的な収入があること」を大前提としています。
しかし、その大前提が大きく揺らいでいるのが現代です。
近年、急速に進化するAI(人工知能)は、これまで人間が行ってきた事務作業やデータ分析、さらにはデザインや文章作成といったクリエイティブな業務さえも代替する可能性を秘めています。
これは、特定の職種に限った話ではなく、多くのホワイトカラーの仕事が将来的に失われたり、求められるスキルが大きく変化したりするリスクがあることを意味します。
金利上昇のリスク
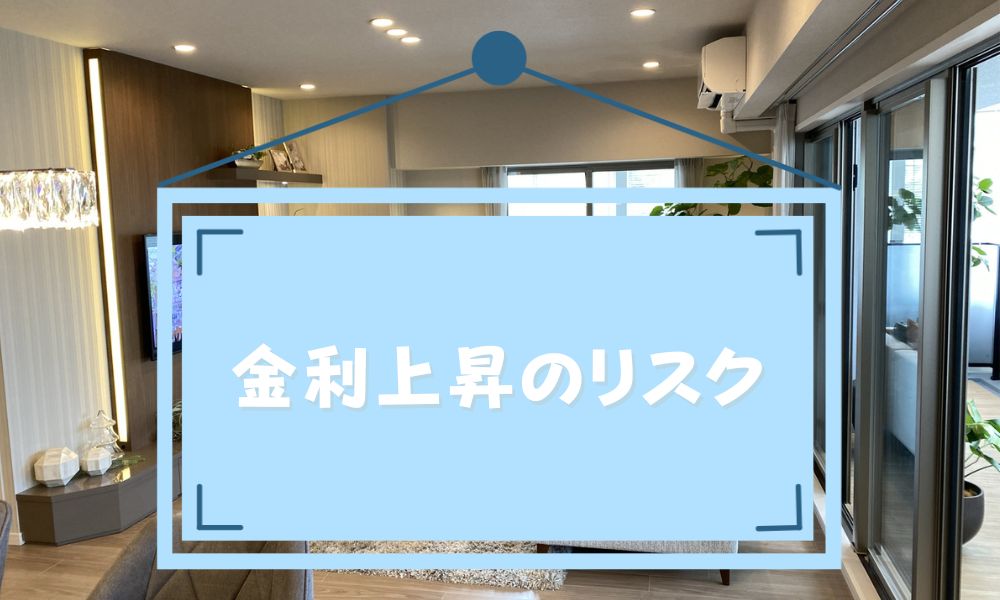
住宅購入における最大の懸念事項の一つが、住宅ローン金利の先行きです。
なぜ金利は上がるのか?
なぜ今、金利が上昇する可能性が高いのでしょうか。
その背景には、国内外の複合的な要因があります。
- 日銀の政策大転換:日銀は長年、「物価安定の目標」として2%のインフレ率を掲げ、それを達成するために「異次元の金融緩和」と呼ばれる超低金利政策を続けてきました。しかし、近年の物価高騰と、それに伴う賃金上昇の兆しが見えてきたことで、ついに政策の「正常化」へと舵を切りました。これは、これまで無理やり抑え込んできた金利を、経済の実態に見合った水準に戻していくプロセスに他なりません。つまり、これからの金利上昇は「もしも」の話ではなく、既定路線と考えるべき状況なのです。
- 円安と海外からの圧力:日本が超低金利を続ける一方で、アメリカをはじめとする主要国は、インフレを抑制するために大幅な利上げを行いました。この内外の金利差が、記録的な円安を引き起こした最大の要因です。円安は輸入物価を押し上げ、さらなる物価高を招く悪循環を生みます。この状況を是正するためには、日銀もある程度の利上げに踏み切らざるを得ないという、海外からの無言の圧力がかかっています。
「5年ルール」と「未払い利息」
住宅ローン利用者の7割以上が選んでいるとされる「変動金利」。
金利が低い間は返済額を抑えられる魅力的な選択肢ですが、金利上昇局面ではその様相が一変します。
多くの金融機関が採用している「5年ルール」と「125%ルール」には、一見すると利用者を守るセーフティネットのようでありながら、実は深刻なリスクが隠されています。
- 5年ルール:適用金利は半年ごとに見直されるが、毎月の返済額は5年間変わらない。
- 125%ルール:5年後の返済額見直し時でも、上昇幅は直前の返済額の1.25倍まで。
このルールによって、金利が急上昇しても、月々の支払額がすぐに跳ね上がることはありません。
しかし、これが最大の罠です。返済額は変わらなくても、水面下では金利が上昇しているため、返済額に占める「利息」の割合がどんどん増えていきます。
その結果、本来支払うべき利息額が毎月の返済額を上回ってしまうと、支払いきれなかった利息、すなわち「未払い利息」が発生します。
具体例で考えてみましょう。
仮に4,000万円を35年、当初金利0.5%で借りたとします。
5年後に金利が2.0%に急上昇した場合、毎月の返済額は5年間変わりませんが、その内訳は利息の支払いが大半を占め、元本はほとんど減りません。
さらに10年後に金利が3.0%に上がれば、「125%ルール」が適用されても、支払額が利息額に追いつかず、「未払い利息」が着実に蓄積していくことになります。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
資産価値の低下と空き家の増加

かつて、日本の社会には「土地神話」が根強く存在し、マイホームは人生における成功の証であり、子や孫に残せる最も確実な「資産」だと信じられていました。
しかし、その常識は「人口減少」によって覆されようとしています。
今、安易に家を持つことは、将来、価値がゼロになるどころか、解体費用や固定資産税だけがかかり続ける「負の不動産」を抱え込むリスクと隣り合わせとなっています。
2025年問題
「2025年問題」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
これは、1947年〜1949年生まれの「団塊の世代」約800万人が75歳以上の後期高齢者となり、社会保障費が急増するという問題として語られがちですが、不動産市場にとっては別の意味を持つ「時限爆弾」でもあります。
- 「大相続時代」:2025年以降、高齢者人口の増加に伴い、死亡や介護施設への入居などを理由とした「相続」が爆発的に増加します。親世代が所有していた持ち家が、一斉に子世代へと引き継がれる「大相続時代」が本格的に到来するのです。これが意味するのは、中古住宅市場における「供給」の急増です。
- 需要の絶対的な先細り:一方で、その住宅を引き継いだり、新たに購入したりする側の「需要」はどうでしょうか。深刻な少子化により、住宅の主な買い手となる若い世代の人口は絶対的に減少しています。親が住んでいた地方の実家を、都会で暮らす子どもが引き継いで住むケースは稀で、多くは売却を選択せざるを得ません。
空き家問題
この需給バランスの崩壊を象徴するのが、全国で深刻化する「空き家問題」です。
総務省が発表した2023年の「住宅・土地統計調査」の速報値によると、国内の空き家数は過去最多の899万戸に達し、総住宅数に占める空き家率は13.8%と、実に日本の住宅の7戸に1戸が空き家という衝撃的な実態が明らかになりました。
なぜ、これほどまでに空き家は増え続けるのでしょうか。
- 管理・活用の困難さ:相続した実家が遠隔地にあるため、管理の手間やコストをかけられず放置される。
- 高額な解体費用:木造家屋一軒を解体・撤去するには200万円以上の費用がかかることもあり、負担の大きさから解体をためらう。
- 税制の矛盾:これまでは、古い家でも建っていれば「住宅用地の特例」で固定資産税が最大6分の1に減額されたため、更地にするよりも放置した方が税金が安いという矛盾がありました。
加速する「二極化」
将来、日本の不動産価値は一様に下落するのではありません。
むしろ、価値が維持・上昇する一部のエリアと、無価値同然にまで暴落するその他大多数のエリアとの選別が進む「二極化」が加速します。
- 価値が維持・上昇するエリア:人口が集中する都心部、ターミナル駅の徒歩圏内、大規模な再開発が進むエリアなど、利便性が極めて高く、需要が底堅い場所です。こうした一等地は、国内外の富裕層や投資マネーの受け皿となり、希少価値から今後も価格が維持、あるいは上昇する可能性を秘めています。
- 価値が暴落するエリア:一方で、人口減少が著しい地方都市、最寄り駅からバス便となるような郊外の住宅地、インフラの老朽化が進むニュータウンなどがこれにあたります。スーパーや病院、銀行が撤退し、バス路線が廃止されるなど、生活インフラそのものが維持できなくなる「スポンジ化現象」が進行し、一度価値が下がり始めると、その下落に歯止めがかからなくなる危険性があります。
自然災害のリスク

日本は、その地理的・地形的特性から、世界でも類を見ない「自然災害大国」です。
地震、台風、豪雨、洪水、土砂災害、火山噴火など私たちは、常にこれらの脅威と隣り合わせで生きています。
マイホームを持つということは、単に建物を所有するだけでなく、その土地が持つ災害リスクを丸ごと引き受けることを意味します。
巨大地震と残存リスク
日本の住宅購入において、地震リスクは避けては通れない最重要課題です。
政府の地震調査委員会は、今後30年以内に、マグニチュード7クラスの首都直下地震が約70%、マグニチュード8〜9クラスの南海トラフ巨大地震が70%〜80%という非常に高い確率で発生すると予測しています。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
「倒壊・崩壊しない」ことは、「無傷である」ことを意味しません。
建物は倒れなくても、基礎に深刻な亀裂が入ったり、壁や柱が損傷したりして、継続して住むことが困難な「全壊」「大規模半壊」と判定されるケースは十分にあり得ます。
さらに、本震で耐えたとしても、繰り返し襲ってくる余震によってダメージが蓄積し、最終的に倒壊に至る可能性も否定できません。
水害の日常化
地震と並んで、近年その脅威を増しているのが、台風や線状降水帯による豪雨が引き起こす「水害」です。
地球温暖化に伴う海水温の上昇により、日本に接近・上陸する台風はより強力になり、一度に降る雨の量も記録的なレベルになっています。
これまで「数十年、百年に一度」と言われていた規模の豪雨が、毎年のように日本のどこかで発生しており、洪水や土砂災害はもはや特別な災害ではなく、私たちの生活のすぐそばにある「日常的なリスク」へと変貌しています。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
ライフスタイルの変化への対応の難しさ
 マイホーム購入は、しばしば「終(つい)の棲家(すみか)」を手に入れることと同義で語られます。
マイホーム購入は、しばしば「終(つい)の棲家(すみか)」を手に入れることと同義で語られます。
しかし、持ち家という「動かせない資産」は流動性に対して柔軟に対応する足かせとなり、時として人生の選択肢そのものを狭めてしまう危険性をはらんでいます。
キャリアの流動化
かつての日本社会は、新卒で入社した会社に定年まで勤め上げる「終身雇用」が一般的でした。
そのため、会社の近くに家を建てれば、大きな生活の変化なく一生を過ごすことができました。
しかし、今は全く違います。
- 転職・キャリアアップの一般化:より良い条件ややりがいを求めて、数年単位で転職を繰り返すことはもはや珍しくありません。スキルアップのために、全く異なる業種へ挑戦することも増えています。
- 企業の統廃合と事業所の移転:会社の経営状況によっては、合併や買収、事業所の地方移転や海外移転などが突然行われる可能性があります。
- 働き方の多様化(リモートワーク):リモートワークが普及したことで、住む場所の自由度は増しました。しかし、逆に出社が義務付けられる方針転換があれば、通勤可能な場所への引っ越しを余儀なくされるケースも出てきます。
こうした状況で持ち家があるとどうなるでしょうか。
例えば、東京に家を買った後に、大阪本社への転勤を命じられたり、福岡のスタートアップ企業から魅力的なオファーを受けたりした場合、大きな決断を迫られます。
家を売るのか、貸すのか、それとも単身赴任を選ぶのか。
どの選択肢も簡単ではありません。
家族のカタチの変化
家を買う時、多くの人はその時点での家族構成を基準に間取りを考えます。
「子どもが2人生まれるから、子ども部屋は2つ用意しよう」「夫婦2人だから、コンパクトな2LDKで十分だ」。
しかし、家族のカタチは時間と共に必ず変化します。
- 子どもの成長と独立:小学生の頃はちょうど良かった子ども部屋も、子どもが成長して家を巣立てば、ただの「空き部屋」になります。使わない部屋のために、掃除の手間や固定資産税を払い続けることになります。
- 親との同居・介護:予期せぬ親の病気や高齢化により、同居や近居が必要になる場合があります。購入した家に親を引き取るスペースがなければ、家を売って住み替えるか、リフォームするかの選択を迫られます。バリアフリーに対応していない住宅では、大規模な改修が必要になることもあります。
- 自身の高齢化:若いうちは気にならなかった2階への階段の上り下りも、高齢になると大きな負担になります。平屋にしなかったことや、寝室を2階にしてしまったことを後悔する声は後を絶ちません。
ご近所トラブル
忘れてはならないのが、ご近所との人間関係です。
騒音、ゴミ出しのルール、ペット、子どもの声、町内会の付き合いなど、トラブルの火種は日常の至る所に潜んでいます。
賃貸であれば、どうしても合わない隣人がいれば「引っ越す」という最終手段があります。
しかし、持ち家の場合はそうはいきません。
何千万円ものローンを組んで手に入れた我が家から、簡単に出ていくことはできないのです。
周辺環境の変化
マイホームの価値は、美しい建物や最新の設備だけで決まるわけではありません。
むしろ、その価値の根幹を支えているのは、家が建つ「土地」とその周辺環境です。
利便性と資産価値
人口減少と高齢化は、特に地方都市や郊外の住宅地に「衰退」をもたらします。
- 商業施設の撤退と買い物難民化:「駅前にあったデパートが閉店」「近所で唯一のスーパーが撤退」。採算が合わなくなった商業施設は、容赦なくそのシャッターを下ろします。これにより、日々の買い物が困難になる「買い物難民」が生まれます。特に、高齢になり車の運転が難しくなった時、歩いて行ける店がないという状況は死活問題です。活気のあった商店街がゴーストタウン化し、地域の魅力は失われ、不動産としての価値も当然ながら下落します。
- 公共インフラの縮小と「陸の孤島」化:自治体の財政難は、住民サービスに直結します。利用者が減ったバス路線は、まず減便され、やがては廃止されます。最寄り駅は無人化され、図書館や公民館といった公共施設は統廃合の対象となります。子育て世帯にとって重要な小中学校の統廃合は、地域の活力を決定的に奪う出来事です。
再開発による環境悪化
一方で、「再開発計画があるから、この土地は将来有望だ」と考えるのも早計です。
一見するとポジティブな「発展」が、住人にとっては深刻な「住環境の悪化」をもたらすケースは少なくありません。
- 交通量の激増と環境悪化:近所に大型の商業施設や物流センターが建設されたり、新たな幹線道路が開通したりすると、その地域の交通量は爆発的に増加します。これまで静かだった生活道路が、大型トラックや乗用車の抜け道となり、一日中騒音や振動、排気ガスに悩まされることになるかもしれません。購入時には想像もしなかった環境の変化が、心の安らぎを奪うのです。
- 日照権・眺望の侵害という資産価値の毀損:最も直接的な被害が、隣接地への高層マンションの建設です。購入時に決め手となった南向きの明るいリビングが、壁一枚隔てたかのように一日中日陰になってしまったり、自慢だった窓からの美しい眺望がコンクリートの壁に塞がれてしまったりする可能性があります。日当たりや眺望は、不動産の資産価値を構成する重要な要素です。これが失われることは、すなわち資産価値が直接的に毀損されることを意味します。法的な規制はあっても、それを完全に防ぐことは困難です。
学区と自治体サービス
同じように見える住宅地でも、一本の道路を挟んだだけで、その未来が大きく変わってしまう境界線が存在します。
- 学区リスク:人気の公立学校の学区内にある物件は、子育て世帯からの需要が高く、不動産価値も高く維持される傾向があります。しかし、この「学区」は永遠ではありません。自治体の都合による児童数の調整などで、学区の線引きは数年おきに見直されることがあります。「人気の〇〇小学校に通わせるためにこの家を買ったのに、数年後に学区が変更になってしまった」という悲劇は、実際に起こり得るのです。
- 自治体リスク:隣り合う市や区でも、その財政力によって住民サービスには天と地ほどの差が生まれます。子育て支援の手厚さ、医療費の助成制度、ゴミ収集の頻度や分別方法、公園や道路の管理状況など、日々の暮らしの質を左右する要素は、すべて自治体の財政状況に依存しています。財政難の自治体にある家を買ってしまうと、将来的にサービスが低下していくリスクを抱え込むことになります。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
維持コストの負担増大

マイホームを手に入れた瞬間の喜びは、何物にも代えがたいものです。
しかし、その喜びと同時に、目には見えないもう一つの「ローン」の返済が始まります。
それが「維持コスト」です。
避けられない「税金」と「保険料」
家を所有すると、たとえ誰も住んでいなくても、法律によって支払いが義務付けられているコストが発生します。
- 固定資産税・都市計画税:毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課される地方税です。土地と建物の評価額に基づいて税額が算出され、おおよその目安として「評価額×1.4%(固定資産税)+評価額×0.3%(都市計画税)」がかかります。例えば、評価額が2,000万円の物件であれば、年間で約34万円、月に換算すると約2.8万円もの税金を、ローン返済とは別に支払い続けなければなりません。この評価額は3年ごとに見直され、地価の上昇などによって税額が上がる可能性も十分にあります。
- 火災保険料・地震保険料の高騰:前述の通り、近年の自然災害の激甚化により、損害保険料は値上がりの一途をたどっています。かつては長期契約で割安に加入できましたが、今では最長でも5年契約となり、更新のたびに保険料が上昇するリスクにさらされます。特に、水害リスクの高いエリアでは、水災補償を付けると保険料が跳ね上がります。住宅ローンを組む際には、火災保険への加入が必須条件となっているため、このコストから逃れることはできません。
これらの税金や保険料は、まさに「住むための家賃」のようなもの。
ローンの返済が終わった後も、生涯にわたって家計に重くのしかかり続けるのです。
10年ごとに訪れる数百万円の出費
新築の輝きも永遠ではありません。
建物は、雨風や紫外線にさらされ、時間と共に確実に劣化していきます。
その劣化を放置すれば、家の寿命を縮めるだけでなく、雨漏りなどの深刻な事態を引き起こしかねません。
そのため、計画的なメンテナンス、すなわち「大規模修繕」が不可欠となります。
築10年〜15年の目安
- 外壁塗装・屋根塗装:美観の維持だけでなく、防水性能を回復させるために必須。足場の設置費用も含め、100万円〜200万円が一般的な相場です。
- 給湯器の交換:寿命は約10年〜15年。突然お湯が出なくなる前に交換が必要で、20万円〜40万円程度の費用がかかります。
- シロアリ対策:木造住宅の場合、防蟻処理の保証期間は5年〜10年。再処理に15万円〜30万円が必要です。
築20年〜30年の目安
- 屋根の葺き替え・カバー工法:塗装だけでは対応できなくなった屋根材の本格的な修繕。200万円以上かかることも珍しくありません。
- 水回り設備の一新:キッチン、ユニットバス、トイレ、洗面台などの交換。すべてを一新すると、300万円を超える大規模なリフォームになります。
- 配管の更新:目に見えない部分ですが、給水管や排水管も経年で劣化・詰まりが生じます。
マンションの「管理費・修繕積立金」
一戸建てに比べて管理が楽だと思われがちなマンションですが、そこには特有のコストが待ち受けています。
それが、毎月徴収される「管理費」と「修繕積立金」です。
- 管理費:共用部分の清掃、エレベーターの保守点検、管理人の人件費などに充てられる費用です。
- 修繕積立金:12年〜15年周期で行われる外壁補修や屋上防水などの大規模修繕工事のために、全戸から計画的に資金を積み立てるものです。
問題なのは、これらの金額が将来に渡って同じではないということです。
- 人件費・物価高騰による値上げ:管理会社の人件費や清掃・点検にかかる費用が上がれば、管理費は値上げされます。
- 修繕積立金の不足問題:新築時に安く設定されていた修繕積立金が、いざ大規模修繕の時期になると、想定以上に工事費が高騰していて資金が足りない、というケースが多発しています。その結果、一時金として数十万円を徴収されたり、毎月の積立金が大幅に値上げされたりします。特に、築年数が古いマンションほど、このリスクは高まります。
住宅ローンの返済が終わってホッとしたのも束の間、高齢になって年金生活に入ってから、管理費や修繕積立金が2倍、3倍に値上がりし、支払いが困難になる…。
そんな未来も十分に考えられるのです。
このように、購入価格だけでは測れない「維持コスト」という名の重荷は、インフレという追い風を受けて、その重さを増し続けています。
この見えにくいコスト構造を理解せずして家を買うことは、ゴールの見えないマラソンに、重りを背負って飛び出すようなもの。
その過酷さが、「今、家を買うなんて信じられない」という声の、偽らざる本音なのです。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
まとめ
「今、家を買うなんて信じられない」。
この記事を通じて、その言葉の背景にある7つの深刻なリスクについて詳しく見てきました。
これらのリスクを並べてみると、確かに「今は家を買うべきではない」という結論に傾くのも無理はありません。
将来の不確実性がこれほど高まっている状況で、30年以上にわたる巨大な借金を背負う決断は、あまりにも無謀に映るかもしれません。
しかし、一方で「今すぐに家を買うべきだ」と主張する声があるのも事実です。
建築コストは今後さらに上昇し続け、「今日が一番安い日」である可能性。
若いうちにローンを組むことで、定年までに返済を終え、老後の安心を手に入れられるメリット。
そして何より、自分たちの理想を詰め込んだ、家族にとって最高の「城」で過ごす時間の価値は、何物にも代えがたいという考え方です。
結局のところ、住宅購入に「誰にとっても完璧な正解のタイミング」というものは存在しません。
ぜひ自分自身の価値観と照らし合わせながら、納得のいく決断をしてみてくださいね。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
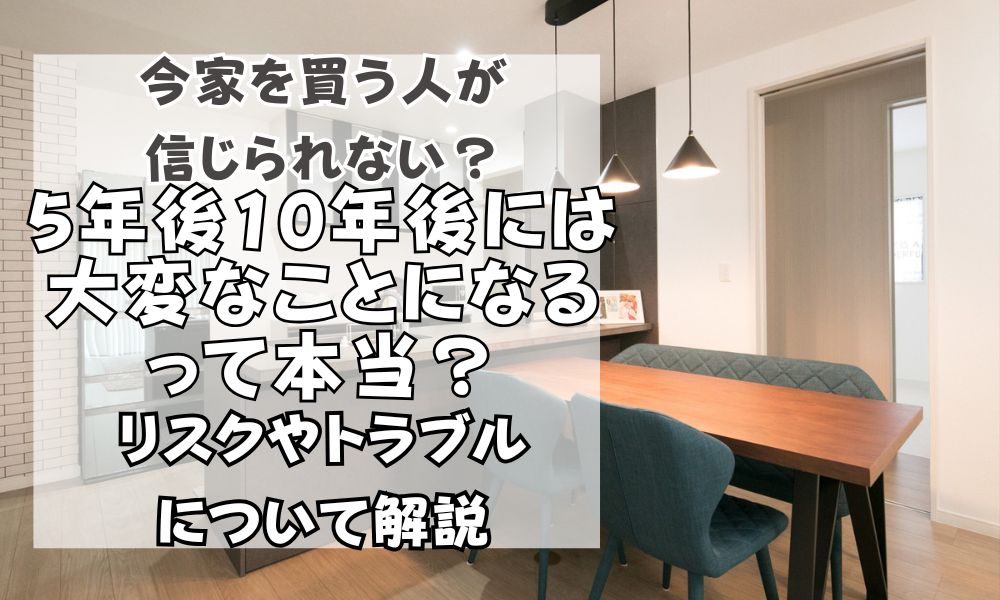
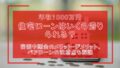

コメント