「年収900万円あれば住宅ローンは余裕で組めるはず!」
そう思っていませんか?
実は、年収が高くても借りすぎによる家計破綻は珍しくありません。
金融機関が提示する借入限度額8000万円台に惑わされず、本当に無理なく返済できる適正額を知ることが、マイホーム購入成功の鍵となります。
そこでこの記事では、年収900万円世帯が住宅ローンで失敗しないための借入額の目安から、具体的な返済シミュレーション、金利選択のポイントまで、専門家の視点も交えて解説していきます。
マイホームを購入するための大事なプロセスである住宅ローンについて不安や疑問がある人は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
本文に入る前に、「今の年収で本当に家づくりができるの・・・?」と感じている人に向けてぜひ利用してほしいサービスを紹介しておきます。
それが下記の2つの無料サービスです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。それぞれのハウスメーカーのカタログを比較しながら住宅ローン借入額の検討もできるのがポイント。ぜひ一度カタログを見ながら資金計画を練ってみることをおすすめします。 不動産のポータルサイトSUUMOが運営する注文住宅相談サービスです。全国各地のハウスメーカー・工務店とのネットワークも豊富。スーモカウンターの最大の特徴が、店舗またはオンラインでアドバイザー相談が可能なことです。資金計画や住宅ローンについてもアドバイスを受けられるので、「今の年収でいくら借り入れられるのか不安」「資金について何から始めたら良いのかわからない」と言う人はまずはスーモカウンターに相談することをおすすめします。 |
上記の2サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
後悔のない家づくりのために、上記のサービスを活用しながら、納得のいく住宅ローンと資金計画を進めてみてくださいね!
\家づくりでおすすめ!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
それでは本文に入っていきましょう!
年収900万円はいくらまで住宅ローンを借りられる?【借入限度額8000万円の現実】
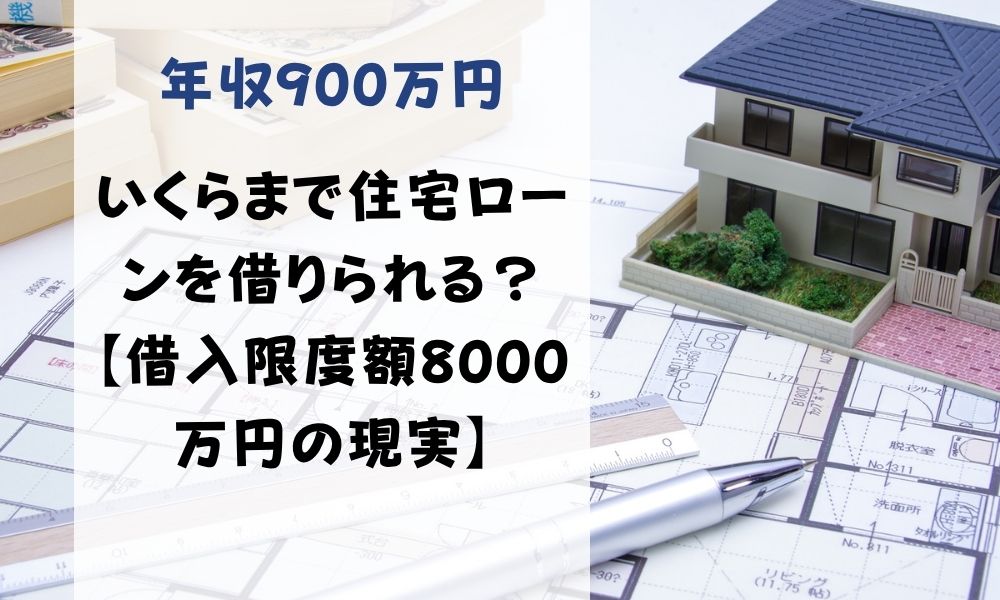
年収900万円は一般的に高所得者に分類されますが、住宅ローンにおいて「借りられる金額」と「無理なく返せる金額」は全く別物です。まずは金融機関の審査基準から、実際にいくらまで借りられるのかを正確に把握しましょう。
住宅ローン審査で見られる2つの基準
住宅ローンの審査では、主に以下の2つの基準で借入可能額が決まります。
1.返済負担率35%が上限の目安
返済負担率とは、年収に占める年間住宅ローン返済額の割合を指します。多くの金融機関では、この返済負担率の上限を35%に設定しており、年収900万円の場合、年間返済額の上限は315万円(月約26万円)となります。
ただし、この35%という数字は額面年収をベースにした計算であり、実際の手取り収入から考えると、かなり厳しい返済負担となることに注意が必要です。
2.年収倍率7~10倍まで借入可能
年収倍率とは、住宅購入価格が年収の何倍かを示す指標です。一般的に住宅ローンでは年収の7~10倍程度まで借入が可能とされており、年収が高いほど倍率も高くなる傾向があります。年収900万円の場合、この基準では6300万円から9000万円程度が借入可能額の目安となります。
年収900万円の借入限度額は約7500万~8000万円
上記の基準を踏まえ、具体的な借入限度額を算出してみましょう。
主要銀行の審査基準比較
返済負担率35%(月約26万円)で計算した場合の借入限度額は、金利や返済期間によって以下のように変わります。
- フラット35(金利1.84%、35年返済):約8,046万円
- 民間銀行(金利1.4%、35年返済):約8,700万円
- 民間銀行(金利1.69%、35年返済):約8,318万円
多くの金融機関で8000万円台の借入が理論上可能という結果になります。
世帯年収900万(単独・共働き別)での違い
同じ世帯年収900万円でも、一人で稼ぐ場合と夫婦合算の場合では手取り収入に差が生じます。
一般的に、夫婦共働きで合計900万円の方が、所得税や住民税の累進課税の影響で手取りが多くなる傾向があります。ただし、借入限度額の計算は額面年収ベースで行われるため、審査上の差はそれほど大きくありません。
借入限度額8000万円は現実的ではない理由
理論上は8000万円を超える借入が可能でも、この金額での借入は極めて危険です。
最大の理由は、借入限度額はあくまで「金融機関が貸せる上限」であり、「借主が無理なく返せる金額」ではないからです。返済負担率35%は手取り収入の約半分を住宅ローン返済に充てることを意味し、住宅維持費や将来の支出を考慮すると、生活が極めて困窮する可能性が高くなります。
また、金利上昇リスクや収入減少リスクを考慮すると、上限近くまで借りることは家計破綻への道筋を作ってしまう危険性があります。
年収900万円世帯の住宅ローン平均額と適正な借入額の目安
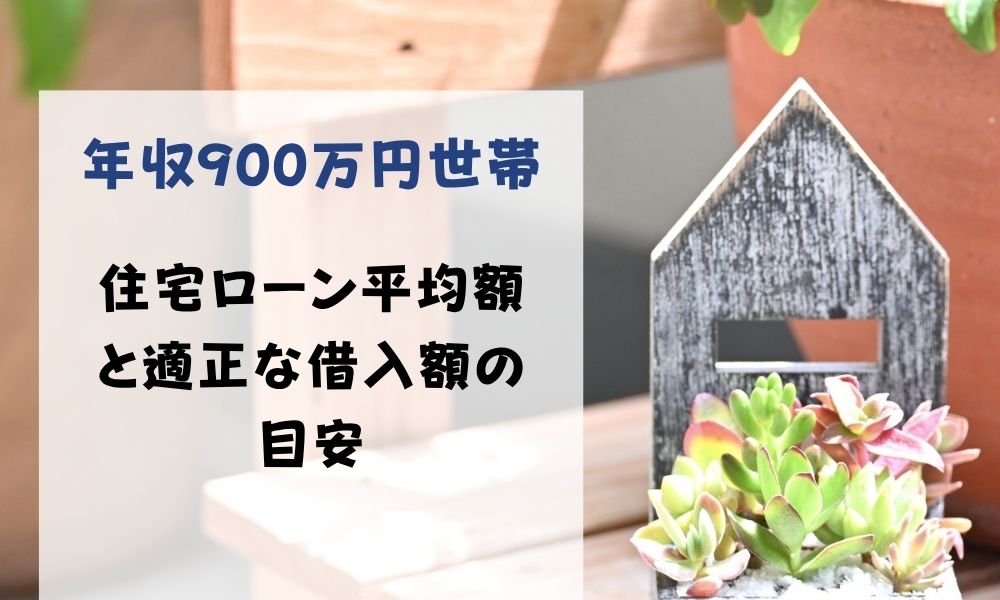
実際の年収900万円世帯は、借入限度額よりもはるかに慎重な借入を行っています。では、適正な借入額とはどのくらいなのでしょうか?統計データと専門家の見解から、現実的な借入額を探ってみましょう。
統計で見る年収900万円世帯の平均借入額
住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査」によると、2023年度の世帯年収900万円台の平均借入額は5,261万円でした。これは借入限度額8000万円台と比較すると、約3000万円も控えめな金額です。
実際の借入状況を詳しく見ると、年収900万円世帯の多くが借入限度額の6割程度に抑えていることがわかります。これは、住宅ローン以外の費用や将来のリスクを考慮した結果と考えられます。
注文住宅・建売・マンション別の傾向
令和2年度の住宅市場動向調査報告書では、三大都市圏において以下のような傾向が見られます。
- 新築マンション:平均世帯年収864万円、平均購入資金4,393万円、自己資金1,124万円
- 新築注文住宅:平均世帯年収761万円、平均購入資金4,486万円、自己資金989万円
これらのデータから、年収900万円世帯では5000万円前後の物件を購入し、1000万円程度の自己資金を投入するのが一般的なパターンであることがわかります。
適正な借入額は4000万~5000万円が現実的
多くの専門家が推奨する「無理のない返済額」から逆算すると、年収900万円世帯の適正借入額が見えてきます。
返済負担率20~25%で計算した適正額
理想的な住宅ローン返済負担率は、手取り年収の20~25%とされています。年収900万円の手取り年収は約650~672万円(月収約54~56万円)が目安となります。
手取り月収の20~25%にあたる月々の返済額は約10.8~14万円です。この返済額で借入可能な金額を金利別で計算すると、以下のようになります。
- 金利0.4%、35年返済、月11万円:約4,400万円
- 金利0.625%、35年返済、月14万円:約5,280万円
- 金利1.54%、35年返済、月13.5万円:約4,381万円
手取り収入ベースでの安全な借入額
これらの計算結果と年収倍率5~6倍という目安を総合すると、年収900万円世帯にとって無理のない借入額は4000万円台後半から5000万円台前半が適正範囲と言えるでしょう。
実際に、住宅金融支援機構のデータによる平均借入額5,261万円も、この適正範囲内に収まっています。
なぜ適正額と借入限度額にこれほど差があるのか
借入限度額8000万円台と適正額4000~5000万円台の間に3000万円もの差が生じる理由は、計算の前提条件にあります。
金融機関の審査基準は額面年収ベースの返済負担率35%で計算されるのに対し、実際に無理なく生活できるレベルは手取り年収ベースの返済負担率20~25%で計算されるためです。
また、借入限度額の計算には以下の要素が考慮されていません。
- 住宅維持費(固定資産税、保険料、修繕費など)
- 将来の教育費や介護費用
- 病気や失業などのリスクへの備え
- 金利上昇リスク
これらの現実的な要素を考慮すると、借入限度額での借入は極めて危険であることがわかります。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
借入額別返済シミュレーション|4000万・5000万・6000万円で比較

具体的な返済イメージを掴むために、異なる借入額での返済シミュレーションを比較してみましょう。金利や返済期間の設定により結果は変動しますが、ここでは一般的な条件で計算します。
借入4000万円の場合(安全圏)
借入額4000万円は、年収900万円世帯にとって最も安全性の高い借入レベルです。
月々返済額と年収に占める割合
主な返済パターンは以下の通りです。
- 金利1.5%、35年返済:月約12.3万円
- 金利1.84%、35年返済:月約13万円
- 金利1.84%、30年返済:月約14.5万円
年収900万円の手取り月収約54~56万円に対し、月13万円の返済は手取り月収の約23~24%にあたります。これは理想的な返済負担率20~25%の範囲内に収まります。
家計への影響度
この返済レベルであれば、住宅ローン返済後も月40万円以上の収入が手元に残ります。総務省の家計調査によると、年収900万円世帯の平均支出(住居費除く)は月30万円程度のため、十分な余裕を持って生活できる計算になります。
また、教育費の積立や老後資金の準備、急な出費への対応も無理なく行えるレベルと言えるでしょう。
借入5000万円の場合(適正上限)
借入額5000万円は、年収900万円世帯の平均借入額に近く、適正な借入額の上限付近に位置します。
返済額と生活費のバランス
金利1.5%、35年返済の場合、月々の返済額は約15.4万円となります。手取り月収約56万円に対する返済負担率は約27.5%で、理想的な25%をやや上回りますが、工夫次第で管理可能な範囲です。
返済後の手取り収入は月約40.6万円となり、生活費30万円を差し引いても月10万円程度の余裕があります。
将来リスクへの備え
この借入レベルでは、以下の点により注意深い家計管理が必要になります。
- 教育費や介護費用などの将来支出への計画的な備え
- 病気や失業といった収入減少リスクへの対策
- 金利上昇時の返済額増加への準備
共働き世帯の場合は、どちらか一方の収入が減少しても返済を継続できるかの検証も重要です。
借入6000万円の場合(やや高リスク)
借入額6000万円は、年収900万円世帯にとって適正額を大きく超える高リスクな借入です。
家計圧迫のリスクと対策
金利1.5%、35年返済の場合、月々の返済額は約18.4万円となります。手取り月収約56万円に対する返済負担率は約33%に達し、家計を大きく圧迫する水準です。
返済後の手取り収入は月約37.6万円となり、生活費30万円を差し引くと月7.6万円程度しか余裕がありません。住宅維持費(月3~4万円)を考慮すると、実質的な自由度は極めて低くなります。
どんな世帯なら可能か
この借入レベルが可能なのは、以下のような限定的な条件を満たす世帯のみです。
- 将来的に大幅な収入増加が確実に見込める
- 潤沢な貯蓄があり、頭金や繰上返済で借入額を実質的に減らせる
- 夫婦共働きで、どちらかの収入だけで返済できる水準まで抑えている
- 住宅維持費や将来の支出を極限まで切り詰められる
一般的には推奨できない借入レベルと言えるでしょう。
住宅ローン以外の費用で見落としがちな年間100万円の出費
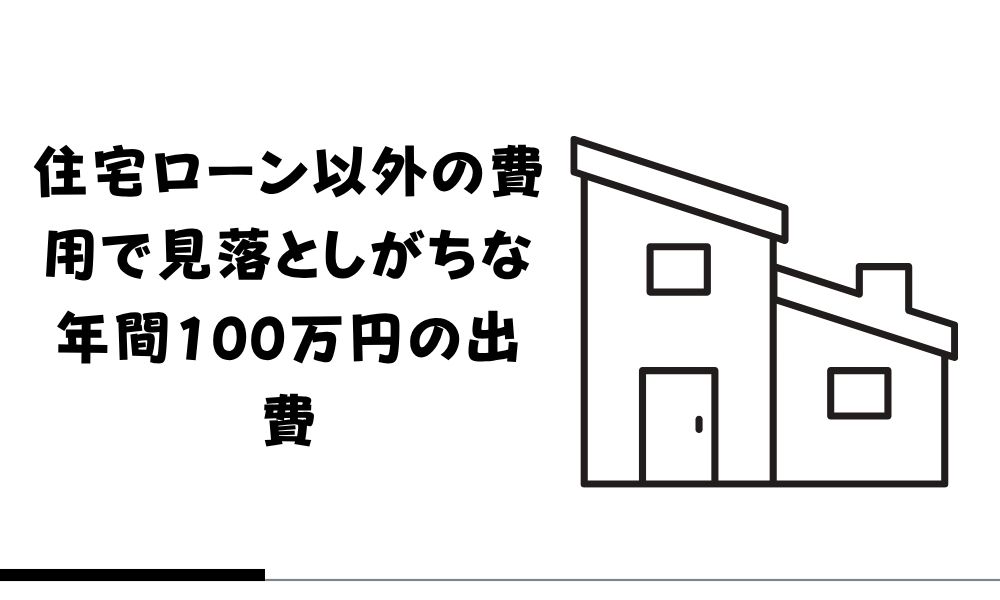
住宅購入には、物件価格と住宅ローン返済以外にも多額の費用がかかります。これらを見落とすと家計計画が大きく狂うため、事前の把握が不可欠です。
住宅購入時の諸費用(物件価格の7~10%)
住宅購入時には、物件価格とは別に「諸費用」と呼ばれる様々な費用が発生します。
主な諸費用には以下があります。
【税金関係】
- 印紙税:売買契約書や住宅ローン契約書に貼付
- 登録免許税:所有権移転登記や抵当権設定登記の際に必要
- 不動産取得税:物件取得後に都道府県から課税
【住宅ローン関係】
- 事務手数料:借入額の2.2%程度(定率型)または3~5万円程度(定額型)
- 保証料:借入額や期間により数十万円~数百万円
- 団体信用生命保険料:金利に含まれる場合が多い
【その他】
- 火災保険料・地震保険料:10年分一括払いで数十万円
- 司法書士報酬:登記手続き代行費用として10~20万円程度
- 仲介手数料:中古物件の場合、物件価格の3%+6万円+消費税
これらの諸費用は通常現金で支払うため、頭金とは別に物件価格の7~10%程度の現金を準備する必要があります。5000万円の物件であれば350~500万円の諸費用を見込んでおきましょう。
住宅の年間維持費50~100万円の内訳
住宅購入後も、継続的に発生する維持費があります。
【税金(固定資産税・都市計画税)】
毎年1月1日時点の所有者に課税される税金です。
- 固定資産税:固定資産税評価額の1.4%(標準税率)
- 都市計画税:固定資産税評価額の0.3%(上限税率、市街化区域のみ)
新築住宅には軽減措置がありますが、それでも年間10~20万円程度の負担となります。
【保険料・管理費・修繕費】
住宅の種類により異なる維持費が発生します。
マンションの場合
- 管理費:月1~2万円程度
- 修繕積立金:月1~3万円程度(築年数とともに増額)
- 駐車場代:月5千円~2万円程度
- 火災保険料:年3~5万円程度
戸建ての場合
- 火災保険料:年3~5万円程度
- 地震保険料:年1~3万円程度
- 修繕費の積立:年10~30万円程度(外壁・屋根・設備の更新費用)
年収900万円世帯の理想的な住宅費の割合
住宅ローン返済額と住宅維持費を合わせた「総住居費」の管理が重要です。
理想的には、手取り収入に対して総住居費が30%以下に収まることが望ましいとされています。年収900万円(手取り約650~672万円)の場合、月16~17万円程度が総住居費の上限目安となります。
住宅ローン返済額を月13万円とした場合、維持費として月3~4万円まで許容できる計算になります。これは前述の維持費相場とほぼ一致するため、借入額4000万円程度であれば無理のない家計運営が可能と言えるでしょう。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
世帯年収900万円|最適な住宅ローンの組み方

同じ世帯年収900万円でも、一人で稼ぐ場合と夫婦合算で稼ぐ場合では、住宅ローンの組み方や注意点が大きく異なります。それぞれの働き方に応じた最適な戦略を検討しましょう。
単独で年収900万円の場合の借入方法
一人で年収900万円を稼いでいる場合、収入の安定性が高い反面、収入源が一つに集中するリスクがあります。特徴を見てみましょう。
単独高収入の場合の特徴とメリット
- 金融機関からの評価が高く、希望する条件での借入が比較的容易
- 収入が安定している場合、長期的な返済計画が立てやすい
- 住宅ローン控除を一人でフル活用できる可能性が高い
ただし、病気や失業などにより収入がゼロになるリスクがあるため、以下の点により注意が必要です。
- 無理のない返済額(手取りの20~25%)を厳守する
- 万が一の備えとして、生活費の6ヶ月分以上の貯蓄を維持する
- 団体信用生命保険の特約(三大疾病保障など)を検討する
住宅ローン控除の最大活用法
年収900万円の場合、住宅ローン控除の恩恵を最大限受けられる可能性があります。2024年入居分の場合、新築住宅で年間最大35万円(認定住宅は最大45.5万円)の控除が13年間受けられるため、総額で455万円~591.5万円の減税効果が期待できます。
ただし、控除額には所得税・住民税額による上限があるため、具体的な控除額は税理士等に相談することをお勧めします。
夫婦合算で世帯年収900万円の場合の借入方法
夫婦の収入を合算して世帯年収900万円とする場合、住宅ローンの組み方の選択肢が広がります。
主な選択肢は以下の3つです。
ペアローン
- 夫婦それぞれが債務者となり、お互いが連帯保証人になる
- 夫婦両方が住宅ローン控除を受けられる
- 団信もそれぞれ加入するため、どちらかに万が一があっても相手の債務は残る
収入合算(連帯債務型)
- 夫婦の一方が主債務者、もう一方が連帯債務者となる
- フラット35では夫婦両方が住宅ローン控除を受けられる
- 団信は主債務者のみ加入が一般的
収入合算(連帯保証型)
- 夫婦の一方が主債務者、もう一方が連帯保証人となる
- 住宅ローン控除は主債務者のみ
- 団信は主債務者のみ加入
産休・育休・転職リスクへの備え
共働き世帯最大のリスクは、収入の変動です。特に注意すべきは、出産・育児による一時的な収入減少で、産休・育休期間中は収入が大幅に減少するケースが多く見られます。
また、転職による収入変動も重要なリスク要因で、転職先での年収が必ずしも現在と同水準になるとは限りません。さらに、配偶者の病気や失業といった予期せぬ事態により、一方の収入が突然途絶える可能性もあります。
これらのリスクに備えるため、理想的には片方の収入だけで住宅ローンを無理なく返済できる金額に借入額を抑えることが推奨されます。
共働き世帯が陥りやすい借りすぎの罠
夫婦合算で世帯年収が高いと、金融機関からより高額な借入が可能になります。しかし、「現在の高い世帯収入を前提とした借入」は以下のリスクを伴います。
よくある失敗パターン
- 夫婦合わせた年収900万円を前提に6000万円以上借入
- 妻の産休・育休で世帯年収が一時的に600万円台に減少
- 月18万円超の返済が家計を圧迫し、生活が困窮
安全な借入戦略
- 主たる稼ぎ手の収入(例:年収600万円)をベースに借入額を決定
- 配偶者の収入(例:年収300万円)は頭金や繰上返済資金として活用
- 手取り収入の20~25%以内の返済負担率を維持
この戦略により、収入変動があっても安定した返済が可能になります。
年収900万円で失敗しない住宅ローン返済計画【5つの鉄則】
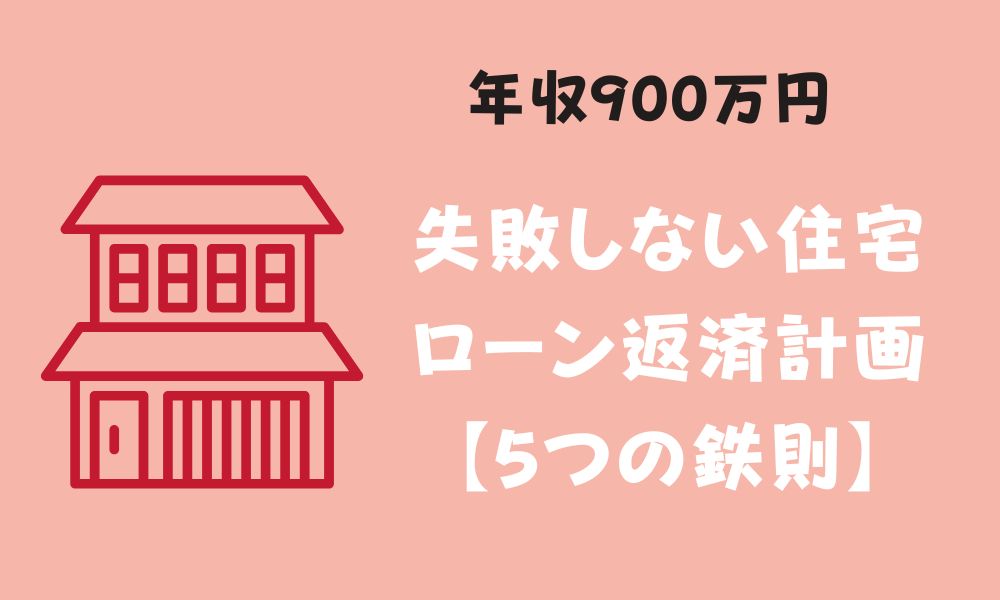
年収900万円という高い年収でも、住宅ローンで失敗するケースは珍しくありません。長期にわたる返済を成功させるための5つの鉄則を紹介します。
- 月々返済額は手取りの25%以内に設定
- 定年までに完済できる返済期間を選ぶ
- 頭金は最低でも物件価格の20%を用意
- 教育費・老後資金も並行して貯蓄
- 金利上昇時の返済額増加に備える
それぞれ見ていきましょう。
①月々返済額は手取りの25%以内に設定
最も重要な原則は、月々の住宅ローン返済額を手取り月収の25%以内に抑えることです。
年収900万円の手取り月収約54~56万円の場合、月々の返済額は13.5~14万円以内が目安となります。この範囲であれば、住宅ローン返済と並行して以下も無理なく行えます。
- 日常の生活費の支払い
- 教育費や老後資金の積立
- 急な出費への対応
- 趣味や娯楽への支出
25%を超える返済は、短期的には可能でも、長期的には家計を圧迫し、生活の質を著しく低下させるリスクがあります。
②定年までに完済できる返済期間を選ぶ
住宅ローンの返済期間設定では、定年退職時期を重要な基準とすべきです。
一般的に、60~65歳で退職した場合、収入は年金中心となり現役時代の3~5割程度に減少します。この収入減少を考慮すると、原則として定年までに完済できる返済期間を選ぶことが安全です。
年齢別の推奨返済期間
- 30歳:30~35年(60~65歳完済)
- 35歳:25~30年(60~65歳完済)
- 40歳:20~25年(60~65歳完済)
ただし、十分な退職金や年金が見込める場合は、この限りではありません。
③頭金は最低でも物件価格の20%を用意
頭金の投入には複数のメリットがあります。
金銭的メリット
- 借入額が減ることで総返済額(特に利息分)を大幅に削減
- 金融機関によっては頭金比率に応じた金利優遇
- 毎月の返済額軽減による家計負担の軽減
リスク軽減効果
- 借入額が少ないほど金利上昇の影響を受けにくい
- 収入減少時の家計圧迫を軽減
- 物件価格下落時の資産価値割れリスクを軽減
理想的な頭金は物件価格の20~30%です。5000万円の物件であれば1000~1500万円の頭金を用意できると、借入額を3500~4000万円に抑えることができ、非常に安全な返済計画となります。
ただし、頭金として全財産を投入するのは危険です。諸費用分と併せて、最低でも生活費6ヶ月分程度の現金は手元に残しておきましょう。
④教育費・老後資金も並行して貯蓄
住宅ローン返済に追われて将来への備えがおろそかになることは避けなければなりません。お子さんがいる家庭は子供の教育費、自分たちの老後資金も必要です。
教育費の目安
- 幼稚園~高校(すべて公立):約540万円
- 幼稚園~高校(すべて私立):約1,830万円
- 大学(国立4年):約240万円
- 大学(私立文系4年):約400万円
- 大学(私立理系4年):約550万円
子ども一人あたり1000~2000万円の教育費を18年間で準備する必要があるため、月5~10万円程度の積立が必要になります。
老後資金の目安
- 夫婦二人の老後資金:2000~3000万円程度
- 65歳までに準備が必要
これらの将来費用も考慮した上で、住宅ローンの返済額を決定することが重要です。
⑤金利上昇時の返済額増加に備える
特に変動金利を選択する場合、将来の金利上昇リスクへの備えが不可欠です。
金利上昇の影響度
借入額5000万円&35年返済の場合、
- 金利1.0%:月約14.1万円
- 金利2.0%:月約16.5万円(月2.4万円増)
- 金利3.0%:月約19.2万円(月5.1万円増)
わずか1~2%の金利上昇でも、月々の返済額は数万円単位で増加します。
対策方法
- 繰上返済用資金の計画的な積立
- 金利上昇を見越した家計の余裕度確保
- 固定金利期間選択型やミックスローンの検討
- 借入額を保守的に設定することでリスク自体を軽減
変動金利を選択する場合は、金利が2~3%上昇しても返済を継続できる家計余力を確保しておくことが重要です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
変動金利vs固定金利|年収900万円世帯はどちらを選ぶべき?
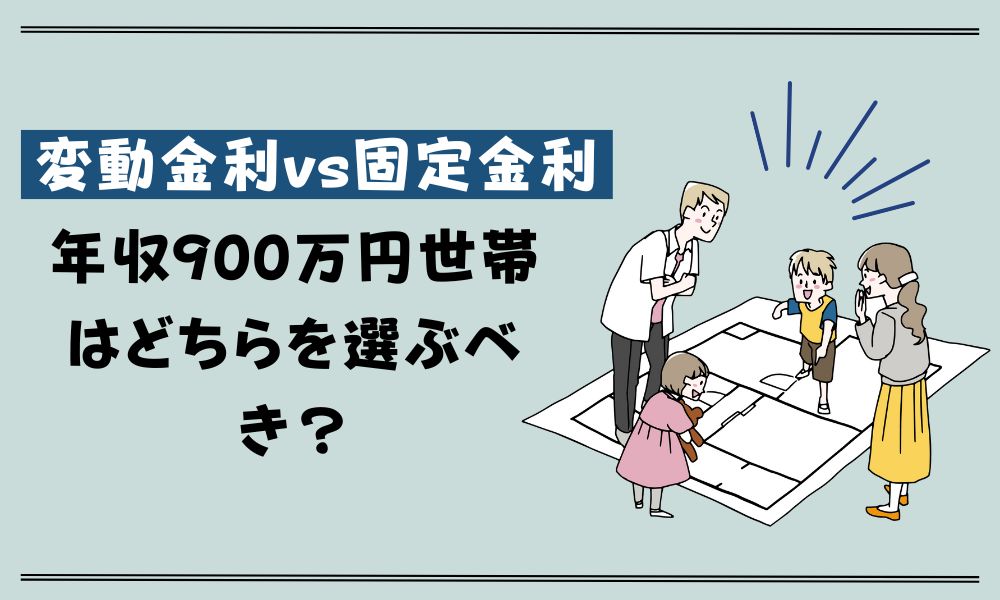
住宅ローンの金利タイプ選択は、総返済額を大きく左右する重要な決定です。年収900万円世帯の場合、どのような基準で金利タイプを選択すべきでしょうか。
変動金利のメリット・デメリット
変動金利型は市場金利の変動に応じて半年ごとに金利が見直されるタイプで、現在多くの借入者に選ばれています。
低金利のメリットと上昇リスク
変動金利の最大のメリットは、固定金利と比較して低金利で借入できることです。2025年現在、多くの金融機関で年0.3~0.7%程度の変動金利が提供されており、固定金利との差は1%以上になることも珍しくありません。
借入額5000万円、35年返済の場合の金利差による影響
- 変動金利0.5%:月約12.9万円、総返済額約5,420万円
- 固定金利1.5%:月約15.4万円、総返済額約6,460万円
- 差額:月約2.5万円、総返済額約1,040万円
この差額は年収900万円世帯にとっても非常に大きな金額です。
しかし、変動金利には金利上昇リスクが常に付きまといます。過去30年間は低金利が続いていますが、将来的には金利が上昇する可能性も否定できず、その場合は返済額が大幅に増加します。
5年ルール・125%ルールの落とし穴
しかし、多くの変動金利型住宅ローンには急激な金利上昇による影響を最小限に抑えるため、以下の仕組みがあります。
5年ルール
- 金利が変動しても5年間は毎月の返済額が変わらない
- 金利上昇時は返済額に占める利息の割合が増加し、元金の減少が遅くなる
125%ルール
- 5年後の返済額見直し時も、新しい返済額は従来の125%が上限
- 急激な返済額増加を抑制する効果がある
これらのルールは借入者保護の側面がある一方で、以下の落とし穴もあるため注意が必要です。
- 返済額が変わらない期間中、元金の減少が想定より遅れる
- 125%を超える利息は「未払利息」として繰り延べられ、将来負担となる
- すべての金融機関でこれらのルールが適用されるわけではない
固定金利のメリット・デメリット
固定金利型は借入期間中(または一定期間)金利が変わらないタイプです。
安定性と金利コストのバランス
固定金利の最大のメリットは返済額の確定性です。
- 借入時に将来の返済額が確定するため、長期的な家計計画が立てやすい
- 金利上昇リスクを完全に回避できる
- 教育費や老後資金の準備計画を正確に立てられる
年収900万円世帯のような計画的な家計管理を行う世帯にとって、この予測可能性は大きな価値があります。
一方で、固定金利のデメリットは金利コストの高さです。
- 一般的に変動金利より0.5~1.5%程度高い金利設定
- 市場金利が低下しても、その恩恵を受けられない
- 総返済額が変動金利より多くなる可能性が高い
年収900万円世帯におすすめの金利選択
年収900万円世帯の金利選択は、借入額とリスク許容度によって判断すべきでしょう。
借入額別の推奨金利タイプ
借入額別におすすめの金利をまとめてみました。
借入額4000万円以下(保守的な借入)
- 家計に余裕があるため、金利上昇時の返済額増加に対応可能
- 低金利のメリットを享受できる変動金利がおすすめ
- ただし、金利上昇時の対策(繰上返済資金の準備など)は必須
借入額5000万円前後(適正な借入)
- 金利上昇時の影響を慎重に検討する必要がある
- リスク許容度により変動金利・固定金利どちらも選択肢
- 10年固定など中期固定金利も有効な選択肢
借入額6000万円以上(高額な借入)
- 金利上昇時の家計への影響が深刻
- 返済額の安定性を重視し、固定金利を推奨
- 家計の安全性を最優先すべき借入レベル
ミックスローンという選択肢
変動金利と固定金利の中間的な選択肢として、ミックスローンという選択肢もあります。
- 借入額を2つに分け、一方を変動金利、もう一方を固定金利で借入
- 金利変動リスクを分散しつつ、低金利のメリットも享受
- 例:5000万円を変動3000万円+固定2000万円に分割
ミックスローンは手続きが複雑になるデメリットがありますが、リスクとリターンのバランスを取りたい年収900万円世帯には有効な選択肢です。
住宅ローン審査を通すコツと銀行選びのポイント
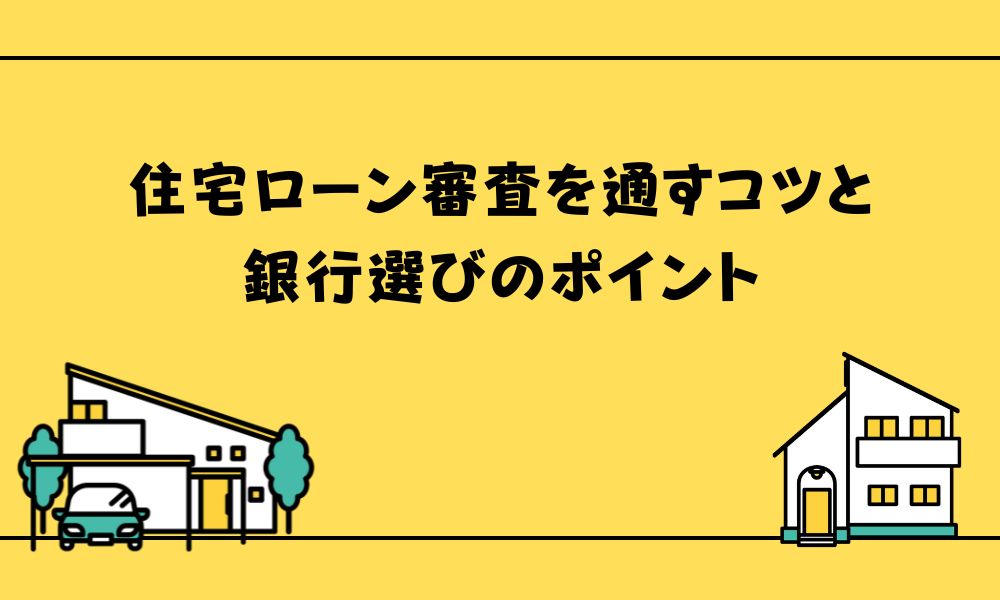
年収900万円という高収入でも、住宅ローン審査で思わぬ落とし穴にはまることがあります。審査を確実に通過し、最適な条件で借入するためのポイントを解説します。
年収900万円でも審査に落ちるケース
高年収でも以下の要因により審査に落ちる可能性があります。
1.他の借入・クレジット履歴の影響
年収900万円でも、既存の借入が多い場合は要注意です。特に下記のような借入には気を付けましょう。
- 自動車ローン:月3~5万円の返済でも年間36~60万円の負担
- カードローン・キャッシング:金利が高く、返済能力への懸念材料
- 教育ローン:長期間の返済が続く場合は影響大
- クレジットカードのリボ払い:残高が多い場合は審査に悪影響
これらの年間返済額が合計で年収の10%を超える場合、住宅ローンの借入可能額が大幅に減額される可能性があります。
2.信用情報の問題
未払いなどの信用情報は金額の大小に関わらず、審査に大きな影響を与えます。
- クレジットカードの支払遅延(直近2年以内)
- 携帯電話料金の滞納(特に端末代金の分割払い)
- 公共料金の口座振替不能による滞納履歴
心当たりがある場合は、あらかじめ自分の信用情報を確認しておきましょう。
3.勤続年数・雇用形態の重要性
年収900万円でも以下の場合は審査が厳しくなる場合があります。
勤続年数が短い場合
- 転職直後(勤続1年未満):収入の安定性に疑問視される
- 勤続1~3年:金融機関により対応が分かれる
- 勤続3年以上:一般的に問題なし
雇用形態による影響
- 正社員:最も有利
- 契約社員:期間の定めがない場合は比較的有利
- 個人事業主・自営業:収入の安定性で厳しく審査される
- 会社役員:業績変動リスクで慎重に審査される
複数銀行での事前審査が重要な理由
住宅ローンは金融機関により条件が大きく異なるため、複数での比較検討が必須です。
金融機関で比較すべき条件
主要な比較項目は以下の通りです。
金利関連
- 基準金利と優遇金利の幅
- 変動金利と固定金利の水準
- 金利優遇の条件(給与振込、カード作成など)
手数料関連
- 融資手数料:定率型(借入額の2.2%)vs定額型(3~5万円)
- 保証料:一括前払い vs 金利上乗せ
- 繰上返済手数料:無料 vs 有料
商品・サービス
- 団体信用生命保険の内容(三大疾病、八大疾病保障等)
- 諸費用の借入可否
- 窓口相談の可否
ネット銀行vs地方銀行vs都市銀行
金融機関それぞれ自体にも特徴があります。それぞれの特徴を理解して選択しましょう。
ネット銀行
- メリット:金利が低い、手続きがオンライン完結
- デメリット:対面相談ができない、審査が機械的
- 向いている人:手続きに慣れている、金利を最優先する
都市銀行・地方銀行
- メリット:対面相談可能、地域密着型サービス
- デメリット:金利がやや高い、手続きに時間がかかる
- 向いている人:相談しながら進めたい、地元志向
年収900万円世帯の場合、金利の差による影響が大きいため、まずはネット銀行を中心に比較し、必要に応じて対面相談可能な銀行も検討するのが効率的です。
審査を有利にする事前準備
住宅ローン審査をスムーズに進めるための準備項目を整理しました。
書類関連の準備
- 源泉徴収票(直近3年分)
- 住民税決定通知書
- 勤務先の概要(従業員数、設立年等)
- 他の借入に関する返済予定表
- 購入予定物件の資料
信用情報の事前確認: CIC、JICC、KSCなどの信用情報機関で自身の信用情報を事前確認し、問題がある場合は対策を講じておきましょう。
既存借入の整理: 可能であれば住宅ローン申込前に以下を実行しておきましょう。
- カードローンの完済
- 自動車ローンの一括返済(資金に余裕がある場合)
- クレジットカードの枚数整理
これらの準備により、審査通過率の向上と、より良い条件での借入が期待できます。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
住宅ローンで後悔しないための注意点
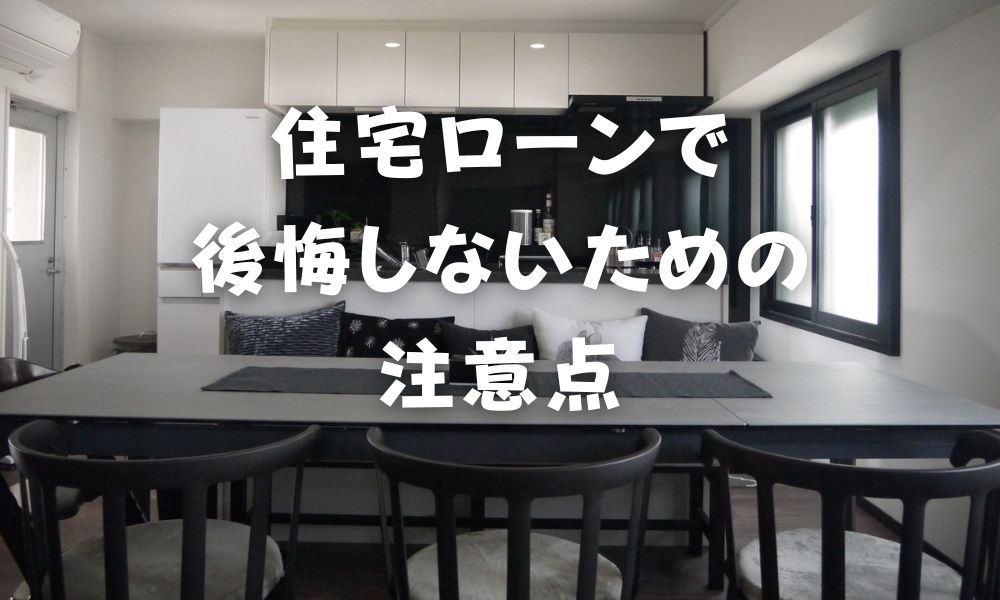
住宅ローンは人生最大の借入であり、契約後の変更は困難です。契約前の最終チェックで後悔のない選択をしましょう。
住宅ローンを組む前の最終確認事項2つ
契約前に必ず確認すべき重要なポイントを整理します。
1.家計の見直しと将来設計
住宅ローン契約前に、改めて家計全体を見直しましょう。
現在の家計バランス確認
- 手取り収入に対する住宅ローン返済額の割合(25%以下が理想)
- 住宅維持費を含めた総住居費の割合(30%以下が理想)
- 生活費の内訳と節約可能な項目の洗い出し
将来のライフイベント確認
- 子どもの進学予定と必要な教育費
- 親の介護が必要になる時期と費用
- 夫婦の退職時期と退職後の収入見込み
- 住宅のリフォーム時期と費用
年収900万円世帯の場合、総務省家計調査によると以下が平均的な支出構造です。
- 食費:月約9万円
- 光熱水道費:月約2.5万円
- 通信費:月約1.8万円
- 教育費:月約3.5万円(子どもがいる場合)
- 保険料:月約4万円
これらの固定費を把握した上で、住宅ローン返済額を加えても無理のない家計になるかを確認しましょう。
2.万が一のリスクヘッジ
住宅ローンは長期間の借入のため、様々なリスクに備えた保障の検討が重要です。
団体信用生命保険の選択
- 一般団信:死亡・高度障害時にローン残高がゼロ
- 三大疾病保障:がん・急性心筋梗塞・脳卒中でもローン残高がゼロ
- 八大疾病保障:上記に加え、高血圧症・糖尿病等でも保障
- 全疾病保障:すべての病気・ケガで長期就業不能時に保障
年収900万円世帯の場合、収入が高い分、収入減少時の家計への影響も大きくなります。月数百円~数千円の保険料上乗せで手厚い保障を受けられるため、積極的な検討をお勧めします。
緊急時の資金確保
- 生活費6ヶ月分以上の預貯金確保
- 親族からの緊急時借入の可能性
- 勤務先の福利厚生制度(住宅資金貸付等)の確認
専門家に相談すべきケース
以下の状況に該当する場合は、専門家への相談を強く推奨します。
【専門家相談が必要なケース】
- 転職予定があり、収入変動が見込まれる
- 個人事業主・自営業で収入が不安定
- 希望借入額が年収の7倍を超える
- 既存の借入が多い
- 夫婦の収入バランスが大きく偏っている
- 親からの資金援助を検討している
- 投資用不動産との併用を考えている
ファイナンシャルプランナー(FP)は家計全般の専門家として、以下のサービスを提供してくれます。ぜひ、有効に活用してみましょう。
- 個別の家計状況に応じた適正借入額の算出
- 複数の住宅ローン商品の客観的比較
- 住宅購入と並行した資産形成プランの提案
- 税制優遇制度(住宅ローン控除等)の最適活用法
- 将来のライフイベントを考慮した長期資金計画
【相談時に準備する資料】
FP相談を有効活用するため、以下の資料を事前に準備しましょう。
収入関連
- 源泉徴収票(夫婦分)
- 確定申告書(個人事業主の場合)
- 給与明細(直近3ヶ月分)
支出関連
- 家計簿(直近6ヶ月分)
- クレジットカード明細
- 保険証券一式
資産関連
- 預貯金残高(全口座)
- 有価証券残高
- 退職金見込額
負債関連
- 既存借入の返済予定表
- クレジットカードのリボ残高
購入予定物件情報
- 物件概要資料
- 見積書
- 諸費用の概算
これらの資料を整理して相談することで、より具体的で実行可能なアドバイスを受けることができます。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
まとめ
この記事では、年収900万円世帯の住宅ローンについて、借入限度額から適正額、具体的な返済計画まで解説してきました。
重要なのは「借りられる金額」ではなく「無理なく返せる金額」を基準に計画を立てることです。
4000万円台後半から5000万円台前半という適正な借入額を守り、手取り収入の25%以内という返済負担率を維持することで、住宅ローンと上手に付き合いながら、豊かな生活を実現できるでしょう。
ぜひこの記事も参考にしながら、理想の家づくりを進めてみてくださいね!

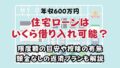

コメント