「年収700万円で住宅ローンはいくらまで借りられるの?」
「4000万円や6000万円の借入は現実的?」
そんな疑問を持っている人もいるのではないでしょうか?
実は、注意点として「借りられる額」と「返せる額」はまったくの別物です。無理のない返済計画を立てるためには、適正な借入額を見極めることが何より重要となってきます。
そこでこの記事では、年収700万円世帯の住宅ローン事情を分析し、借りすぎリスクを避けながら理想の住まいを手に入れるための方法を紹介します。
これから住宅ローンを検討している人は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
本文に入る前に、「今の年収で本当に家づくりができるの・・・?」と感じている人に向けてぜひ利用してほしいサービスを紹介しておきます。
それが下記の2つの無料サービスです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。それぞれのハウスメーカーのカタログを比較しながら住宅ローン借入額の検討もできるのがポイント。ぜひ一度カタログを見ながら資金計画を練ってみることをおすすめします。 不動産のポータルサイトSUUMOが運営する注文住宅相談サービスです。全国各地のハウスメーカー・工務店とのネットワークも豊富。スーモカウンターの最大の特徴が、店舗またはオンラインでアドバイザー相談が可能なことです。資金計画や住宅ローンについてもアドバイスを受けられるので、「今の年収でいくら借り入れられるのか不安」「資金について何から始めたら良いのかわからない」と言う人はまずはスーモカウンターに相談することをおすすめします。 |
上記の2サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
後悔のない家づくりのために、上記のサービスを活用しながら、納得のいく住宅ローンと資金計画を進めてみてくださいね!
\家づくりでおすすめ!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
それでは本文に入っていきましょう!
年収700万円で家を買う前に知っておくべきこと
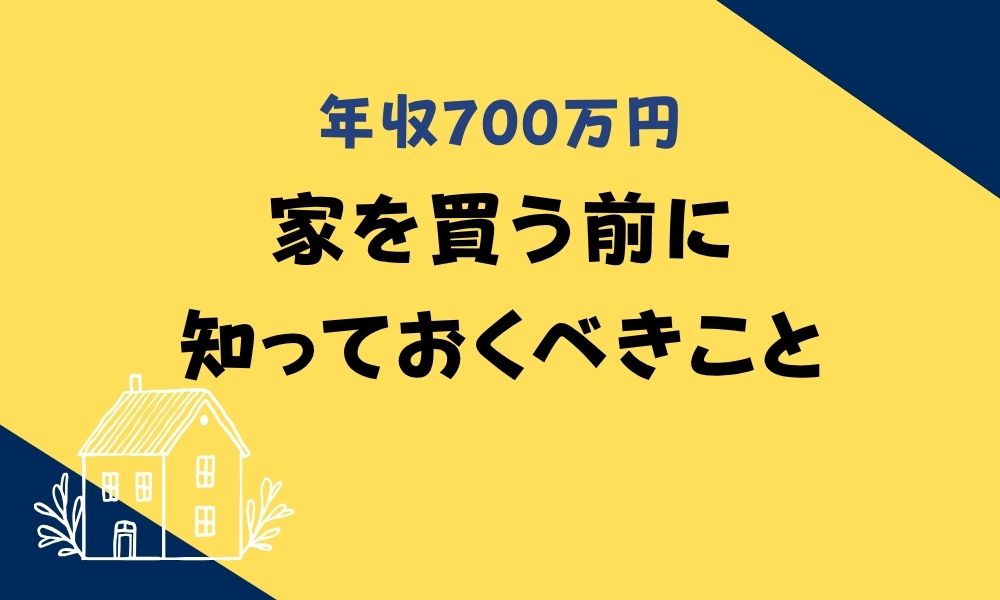
年収700万円という収入水準は、住宅購入において比較的有利な立場にあります。しかし、だからといって安易に高額な住宅ローンを組んでしまうと将来的に家計が圧迫される可能性があります。
住宅ローンを検討する際に最も重要なのは、「借りられる上限額」と「無理なく返せる適正額」は全く別物だということです。
借りられる上限額と適正額の違い
- 借りられる上限額:金融機関の審査基準による最大借入可能額(年収700万円なら5000万円超も可能)
- 適正額:実際の生活を考慮した安全な借入額(年収700万円なら3200万円~4000万円)
年収700万円の住宅ローン借入上限額|いくらまで借りられる?

年収700万円の方が住宅ローンを申し込んだ場合、金融機関からはどの程度の金額まで借入が可能なのでしょうか。まずは制度上の上限額について理解しておきましょう。
金融機関の審査基準による最大借入可能額
金融機関が住宅ローンの審査で重視する指標の一つが「返済負担率」です。これは年収に占める年間返済額の割合を示すもので、多くの金融機関では30%から35%を上限としています。
年収700万円の借入可能額シミュレーション
- 返済負担率35%の場合:年間返済額245万円(月額約20.4万円)
- 35年返済・金利1.0%で逆算:借入可能額約5500万円
- 年収倍率7~8倍で計算:4900万円~5600万円
また、年収倍率という観点からも借入上限を考えることができます。一般的に金融機関では年収の7倍から8倍程度までの借入を認めることが多く、年収700万円の場合は4900万円から5600万円程度が目安となります。
上限額の注意点
しかし、これらの金額はあくまでも「制度上借りられる上限額」であり、実際に借りることが賢明かどうかは別問題です。上限額近くを借りてしまうと、以下のリスクが生じます。
- 月々の返済が家計を大きく圧迫
- 生活の質の低下
- 将来への備えができない
- 急な出費への対応力低下
現実的な借入額の考え方
適正な借入額を考える際には、額面年収ではなく実際の手取り収入をベースに計算することが重要です。
年収700万円の手取り収入目安
- 手取り年収:530万円~550万円程度
- 手取り月収:44万円~46万円程度
住宅ローンの返済に充てられる理想的な金額は、手取り収入の20%から25%程度とされています。これは家計の健全性を保ちながら、教育費や老後資金などの将来への備えも並行して行うための目安です。
適正な月々返済額の計算
- 手取り月収45万円×20% = 9万円
- 手取り月収45万円×25% = 11.25万円
- 推奨返済額:月々9万円~12万円程度
この返済額を35年返済・金利1.0%で逆算すると、借入額は約3200万円から4300万円程度が適正範囲ということになります。
年収700万円で4000万・6000万円は適正?借入額別の返済シミュレーション

具体的な借入額として検討されることが多い4000万円と6000万円について、実際の返済負担と家計への影響を詳しく見てみましょう。
借入4000万円の場合の家計への影響
借入額4000万円を35年返済・金利1.0%で借りた場合の具体的な数字を見てみましょう。
借入4000万円の返済条件
- 月々返済額:約11.2万円
- 年間返済額:約134万円
- 総返済額:約3,940万円
- 利息負担:約940万円
年収700万円(手取り約540万円)の家計にとって、この返済負担はどの程度になるでしょうか。
家計への影響分析
- 返済負担率:約25%(手取り月収45万円に対して)
- 返済後の手取り収入:約34万円
- 家計の余裕度:★★☆(適正範囲の上限)
この水準は一般的に「適正範囲の上限」とされる水準です。返済後の手取り収入は約34万円となり、生活費や貯蓄に回せる金額としては決して余裕があるとは言えませんが、やりくり次第では十分に生活できる水準といえます。
ただし、4000万円の借入には以下の注意点があります。
注意すべきポイント
- 子どもの教育費負担との重複リスク
- 急な出費への対応力の低下
- ボーナス返済併用時のボーナスカットリスク
- 収入減少時の家計圧迫リスク
借入6000万円の場合のリスク分析
一方、借入額6000万円の場合はどうでしょうか。同じ条件で計算した結果が以下です。
借入6000万円の返済条件
- 月々返済額:約16.9万円
- 年間返済額:約203万円
- 総返済額:約5,910万円
- 利息負担:約1,910万円
家計への深刻な影響
- 返済負担率:約37%(手取り月収45万円に対して)
- 返済後の手取り収入:約28万円
- 家計の余裕度:★☆☆(危険水域)
6000万円の借入には以下のような深刻なリスクがあります。
6000万円借入の主要リスク
- 家計の硬直化
- 住宅ローンが家計支出の大部分を占める
- 他の支出を大幅削減が必要
- 生活の質の著しい低下
- 収入減少への対応力不足
- 病気・転職・経済情勢変化時の脆弱性
- 返済継続困難のリスク
- 将来への備え不足
- 子どもの教育費準備困難
- 老後資金積立不可能
- 長期的家計安定性の欠如
- 重い利息負担
- 利息負担約1,910万円(4000万円借入の約2倍)
- 家計への負担が非常に重い
適正借入額の結論
これらのシミュレーション結果を踏まえると、年収700万円の方にとって適正な借入額は以下の通りです。
年収700万円の適正借入額
- 安全重視:3,200万円程度(返済負担率20%)
- 標準的:3,500万円程度(返済負担率22.5%)
- 積極的:4,000万円程度(返済負担率25%)
- 危険水域:6,000万円(返済負担率37%)→ 避けるべき
6000万円の借入は、年収700万円の家計にとっては明らかに過大であり、家計破綻のリスクを大幅に高める危険な選択といえます。
適正借入額設定のメリット
- 住宅ローン返済と生活の質の両立
- 子どもの教育費準備との並行実行
- 老後資金積立の継続
- 急な出費への対応力確保
- 長期的な家計安定性の維持
住宅は人生最大の買い物ですが、その支払いのために生活の質を大幅に落としたり、将来への備えを犠牲にしたりしては本末転倒です。適正な借入額を設定することで、本当の意味で豊かな住生活を実現できます。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
子ども2人世帯の住宅ローン|教育費との両立は可能?
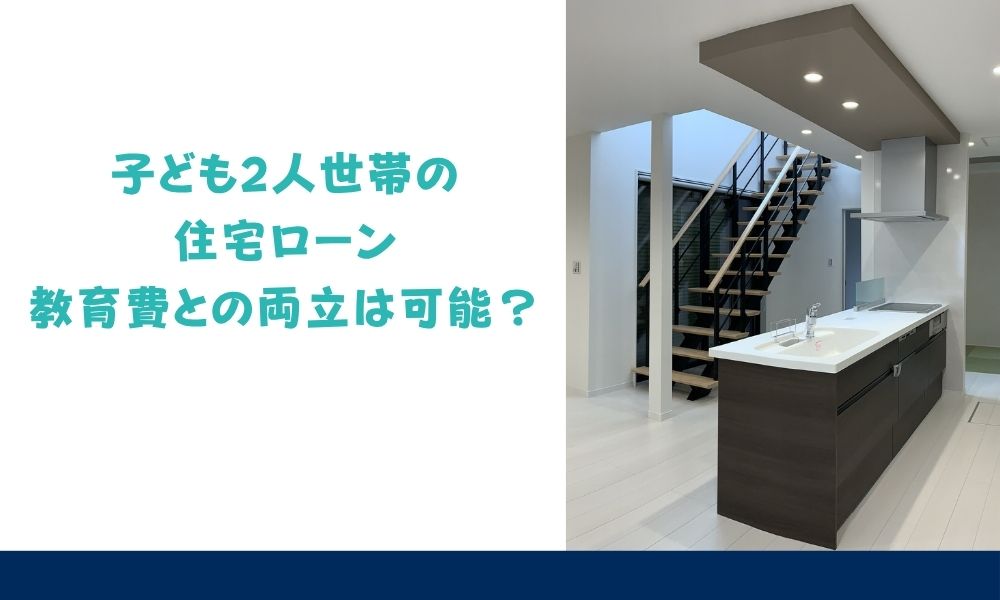
子育て世帯にとって住宅ローンを検討する際には、教育費との両立が大きな課題となります。特に子ども2人の世帯では、教育費の負担が家計に与える影響を十分に考慮した借入額の設定が必要です。
子育て世帯の特別な注意点
子ども2人を育てる場合の教育費負担は決して軽くありません。まず、教育費の全体像を把握しておきましょう。
子ども1人あたりの教育費(文部科学省調査より)
- 幼稚園~高校(すべて公立):約540万円
- 幼稚園~高校(すべて私立):約1,830万円
- 大学4年間(国公立):約250万円
- 大学4年間(私立文系):約400万円
- 大学4年間(私立理系):約550万円
子ども1人の総教育費目安
- 公立中心コース:800万円~1,000万円
- 私立中心コース:2,000万円~2,500万円
子ども2人の場合、これらの費用が2倍になるため、家計への影響は非常に大きなものとなります。
子育て世帯特有のリスク要因
- 育児休業による収入減少
- 時短勤務による給与カット
- 第2子以降の育休期間延長
- 想定外の教育費増加(習い事・塾費用等)
住宅ローンの返済期間は通常20年から35年と長期にわたるため、この期間中に子どもの教育費負担が重なることは避けられません。住宅ローンと教育費の両方を無理なく支払うためには、借入額を慎重に設定する必要があります。
子ども2人世帯の適正借入額
子ども2人の教育費を考慮した場合、住宅ローンの適正借入額はより保守的に設定する必要があります。
教育費を考慮した月々負担の配分
- 住宅ローン返済:8万円~10万円
- 教育費積立(子ども2人分):4万円
- その他生活費・貯蓄:31万円~33万円
- 合計固定支出:12万円~14万円
この配分で35年返済・金利1.0%の条件で逆算すると、借入額は約2900万円から3600万円程度となります。
子ども2人世帯の推奨借入額
- 安全重視:2,800万円程度(月々返済約7.9万円)
- 標準的:3,200万円程度(月々返済約9.0万円)
- 上限:3,600万円程度(月々返済約10.1万円)
年収700万円の世帯であっても、子ども2人の教育費を考慮すると、3000万円程度の借入に抑えることが現実的な選択といえます。
教育資金準備の重要性
- 子ども1人あたり月々2万円の積立推奨
- 学資保険・積立投資信託の活用
- 早期開始による月々負担の軽減
- 計画的な準備で教育費不足を回避
共働き夫婦の収入合算・ペアローン活用法
共働き世帯の場合、夫婦それぞれの収入を合算して住宅ローンを組むことで、借入可能額を増やすことができます。しかし、子育て世帯の場合は、どちらか一方の収入減少リスクを十分に考慮する必要があります。
収入合算を行う場合、どちらかの収入のうち算入する割合は50%程度に抑えることが安全です。例えば、夫の年収が700万円、妻の年収が400万円の場合、妻の収入は200万円程度で計算し、合算年収を900万円として借入額を算定するという考え方です。
ペアローンを利用する場合も同様の注意が必要です。ペアローンは夫婦それぞれが債務者となるため、住宅ローン控除を2人分受けられるというメリットがありますが、どちらかの収入が減少した場合でも返済義務は残ります。
頭金なしでも大丈夫?年収700万円のフルローン戦略
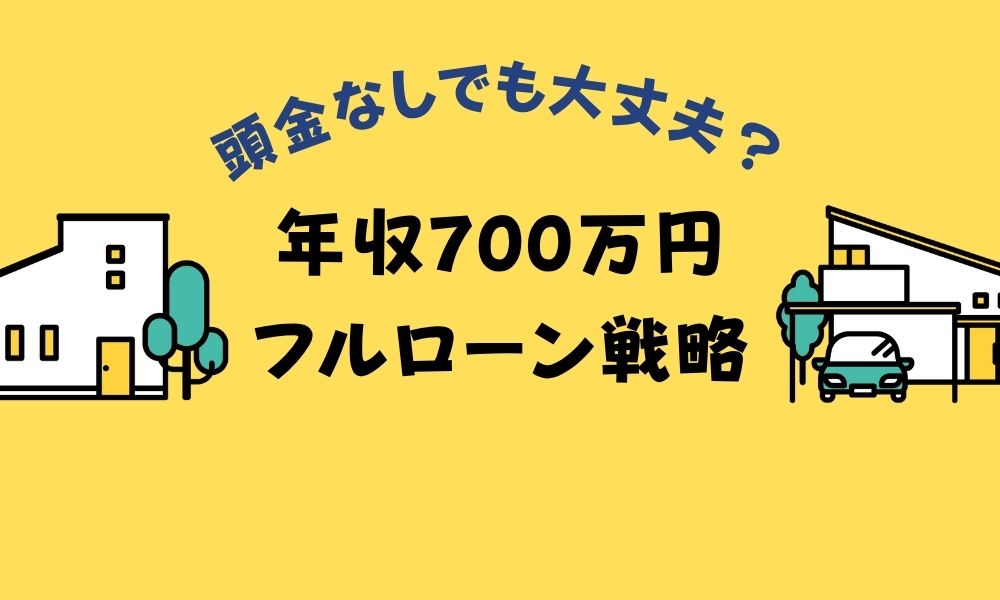
近年、頭金なしで住宅を購入する「フルローン」を選択する人が増えています。年収700万円の方にとって、頭金なしでの住宅購入は現実的な選択肢なのでしょうか。
頭金なし(フルローン)のメリット・デメリット
フルローンの最大のメリットは、手元資金を温存できることです。頭金として数百万円から1000万円程度の資金を投入せずに済むため、緊急時の備えや他の投資機会に資金を回すことができます。特に若い世帯の場合、手元資金が限られているため、フルローンによって早期の住宅購入が実現できるというメリットがあります。
また、現在の低金利環境下では、住宅ローンの金利よりも高い利回りで資金運用できる可能性もあります。例えば、住宅ローンの金利が1.0%程度であれば、株式投資や投資信託で3%から5%程度の利回りを期待できる場合、頭金を投入せずに運用に回した方が有利になる可能性があります。
一方で、フルローンにはデメリットもあります。最も大きなデメリットは、月々の返済額が増加することです。頭金を500万円入れた場合と比較すると、月々の返済額は1.5万円程度増加し、総返済額も数百万円増加することになります。
また、物件価格の下落リスクも考慮する必要があります。頭金なしで購入した場合、購入直後に物件価格が下落すると、ローン残高が物件価値を上回る「オーバーローン」状態になる可能性があります。
金融機関によっては、フルローンの場合に金利が高く設定されることもあります。また、審査が厳しくなる傾向もあるため、年収や勤続年数などの条件をより厳格にチェックされる可能性があります。
頭金なしの場合の借入可能額
年収700万円の方が頭金なしで住宅を購入する場合、借入額は物件価格と等しくなります。前述の適正借入額3200万円から4000万円という基準を適用すると、購入可能な物件価格も同程度ということになります。
ただし、住宅購入には物件価格以外にも諸費用がかかります。新築物件の場合は物件価格の3%から7%程度、中古物件の場合は6%から10%程度の諸費用が必要になります。4000万円の物件を購入する場合、諸費用だけで120万円から400万円程度が必要になります。
これらの諸費用も含めてローンを組む「諸費用ローン」を利用する場合、総借入額はさらに増加します。諸費用ローンは住宅ローンよりも金利が高く設定されることが多いため、可能であれば諸費用分は現金で準備することが望ましいでしょう。
頭金なしで安全に借入できる金額は、諸費用を含めても3500万円程度が上限と考えるべきです。これは物件価格で3200万円から3300万円程度に相当します。
頭金ありvsなしの総合比較
具体的な比較をしてみましょう。物件価格4000万円の場合、頭金200万円を入れた場合と頭金なしの場合を比較してみます。
頭金200万円の場合、借入額は3800万円となり、35年返済・金利1.0%で月々の返済額は約10.7万円です。一方、頭金なしの場合は借入額4000万円で月々返済額は約11.2万円となり、差額は約5000円です。
総返済額では、頭金ありの場合が約3770万円(頭金含めて3970万円)、頭金なしの場合が約3940万円となり、頭金なしの方が約170万円多くなります。
しかし、頭金として投入予定だった200万円を年利3%で35年間運用した場合、最終的な資産額は約560万円になります。この場合、フルローンを選択した方が実質的に有利になる計算です。
ただし、投資にはリスクが伴うため、確実性を重視するなら頭金を入れた方が安全といえます。また、月々の返済負担を軽減したい場合も、頭金を入れることで家計の余裕を確保できます。
どちらを選ぶかは、個々の家計状況やリスク許容度、投資に対する考え方によって判断すべきです。重要なのは、どちらを選択しても無理なく返済できる借入額に設定することです。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
金利・返済期間・商品選択で変わる月々返済額
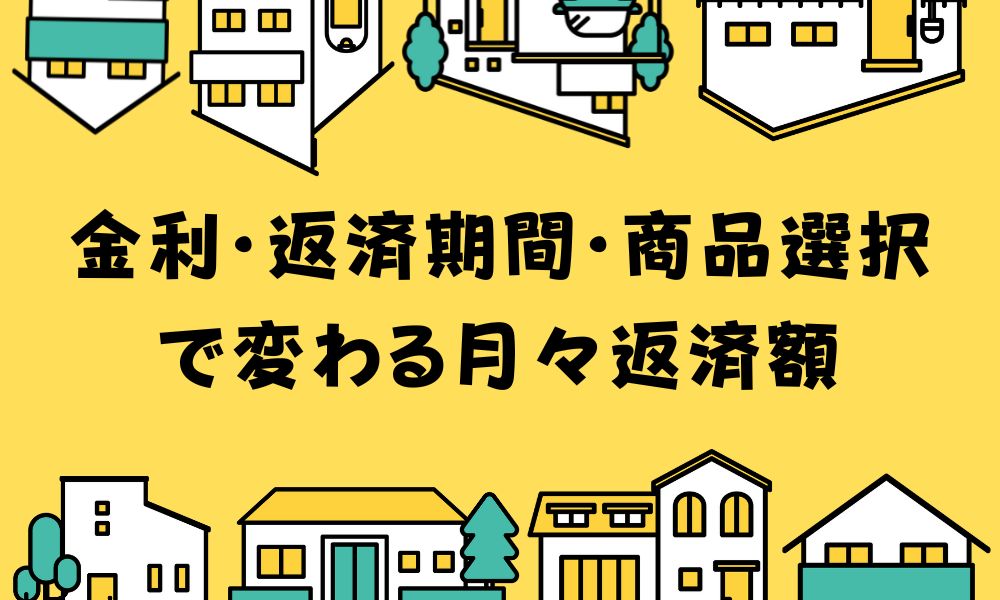
住宅ローンの月々返済額は、金利タイプや返済期間、選択する商品によって大きく変わります。年収700万円の方が最適な選択をするためのポイントを詳しく解説します。
金利タイプ別の返済額と総支払額
住宅ローンの金利タイプは大きく変動金利と固定金利に分かれます。2025年現在、変動金利は0.3%から0.7%程度、全期間固定金利は1.3%から1.8%程度で推移しています。
借入額4000万円、返済期間35年の場合を例に比較してみましょう。
【変動金利0.5%の場合】
- 月々返済額:約10.4万円
- 総返済額:約4370万円
【全期間固定金利1.5%の場合】
- 月々返済額:約12.2万円
- 総返済額:約5130万円
結果、月々で約1.8万円、総額で約760万円の差が生じます。
変動金利の最大のメリットは、現在の低金利の恩恵を受けられることです。金利が低い間は返済額も少なく、家計への負担を軽減できます。また、金利が下がった場合には、さらに返済額が減少するメリットもあります。
しかし、変動金利には金利上昇リスクがあります。金利が上昇した場合、返済額も増加し、家計を圧迫する可能性があります。特に借入額が大きい場合、金利上昇の影響も大きくなります。
固定金利のメリットは、返済額が変わらないため、将来の家計管理がしやすいことです。金利上昇リスクを回避できるため、安心して返済計画を立てることができます。デメリットは、変動金利と比較して金利が高く、返済額も多くなることです。
金利タイプの選択は、金利動向の予測やリスク許容度によって判断すべきです。金利上昇リスクを取れる場合は変動金利、安定性を重視する場合は固定金利を選択するのが基本的な考え方です。
返済期間の選択ポイント
住宅ローンの返済期間は、月々の返済額と総返済額のバランスを考慮して決定する必要があります。一般的に選択されることが多いのは30年、35年、40年です。
借入額4000万円、金利1.0%の場合の比較をしてみましょう。
【返済期間30年の場合】
- 月々返済額:約12.9万円
- 総返済額:約4640万円
【返済期間35年の場合】
- 月々返済額:11.2万円
- 総返済額:約3940万円
【返済期間40年の場合】
- 月々返済額:10.1万円
- 総返済額:約4840万円
返済期間を長くすると月々の返済額は少なくなりますが、総返済額は増加します。また、完済時の年齢も考慮する必要があります。35歳で借入を開始した場合、30年返済なら65歳、35年返済なら70歳、40年返済なら75歳で完済となります。
定年退職後も返済が続く場合は、退職金や年金収入での返済計画を立てる必要があります。一般的には、定年退職時には住宅ローンを完済しているか、残債が退職金の範囲内に収まっていることが望ましいとされます。
年収700万円の方の場合、月々12万円程度の返済であれば家計に与える影響は許容範囲内といえます。したがって、30年返済を選択して総返済額を抑えることも検討に値します。ただし、子育て期間中は教育費負担も重なるため、月々の返済額を抑えたい場合は35年返済を選択し、余裕ができた時点で繰上返済を行うという戦略も有効です。
おすすめ住宅ローン商品
年収700万円の方におすすめの住宅ローン商品を、金融機関のタイプ別に紹介します。
- ネット銀行系の住宅ローンは、金利の低さが最大の魅力です。店舗コストを抑えることで、競争力のある金利を提供しています。変動金利では0.3%台から0.5%台、固定金利でも1.3%台から1.5%台という低金利商品があります。ただし、ネット銀行では対面での相談機会が限られるため、住宅ローンの知識がある程度ある方や、自分で情報収集できる方に適しています。また、審査基準が比較的厳しく、年収や勤続年数などの条件をクリアする必要があります。
- 都市銀行の住宅ローンは、金利面ではネット銀行に劣りますが、全国に店舗があり、対面でのサポートが充実しています。住宅ローンが初めての方や、複雑な案件を抱えている方には適しているでしょう。
- 地方銀行や信用金庫では、地域密着型のサービスが特徴です。地元の不動産情報に詳しく、物件選びから資金計画まで総合的なサポートを受けることができます。金利面では都市銀行と同程度ですが、地域によっては優遇金利などの特典がある場合もあります。
- 疾病保障付きの団体信用生命保険(団信)も重要な選択ポイントです。一般的な団信では死亡・高度障害時にローン残債が免除されますが、3大疾病保障や8大疾病保障付きの商品では、がんや脳卒中などの疾病時にも保障が受けられます。
年収700万円という安定した収入がある方の場合、多くの金融機関で優遇金利の対象となる可能性があります。複数の金融機関で仮審査を受けて、金利や条件を比較検討することが重要です。
勤務先によっては、提携ローンや社内融資制度がある場合もあります。これらの制度は一般的な住宅ローンよりも有利な条件で借入できることが多いため、まずは勤務先の制度を確認することをおすすめします。
住宅ローンで失敗しないための注意点とリスク対策

住宅ローンは長期間にわたる大きな借入であるため、様々なリスクが存在します。年収700万円の方が安心して住宅ローンを組むための注意点と対策を、ここでは解説します。
よくある失敗パターンと対策
住宅ローンで最も多い失敗パターンは、「年収の何倍まで大丈夫」という単純な基準で借入額を決定してしまうことです。年収700万円の場合、「年収の7倍まで借りられる」として4900万円の借入を検討する方がいますが、これは非常に危険な考え方です。
年収倍率だけで判断すると、実際の家計状況や将来のライフプランが考慮されません。子どもの教育費、親の介護費用、自身の老後資金など、住宅ローン以外にも必要な支出は多数あります。これらを無視して高額な借入を行うと、将来的に家計が行き詰まる可能性があります。
もう一つの典型的な失敗は、ボーナス返済に過度に依存することです。月々の返済額を抑えるためにボーナス返済を多く設定すると、ボーナスがカットされた場合や転職によってボーナス制度がない会社に移った場合に、返済が困難になります。
ボーナス返済を利用する場合でも、年間返済額の30%以下に抑えることが安全です。年収700万円の方でも、ボーナスに頼らず月々の給与だけで返済できる金額に設定することが重要です。
変動金利を選択した場合の金利上昇リスクも見逃せません。現在の低金利環境がいつまで続くかは予測困難であり、金利が上昇した場合の家計への影響を事前に検討しておく必要があります。変動金利で借入する場合は、金利が2%から3%上昇しても返済を続けられるかどうかをシミュレーションしておくべきです。
返済が困難になった時の対処法
どれだけ慎重に計画を立てても、病気や失業、収入減少などにより返済が困難になる可能性はゼロではありません。そうした状況に陥った場合の対処法を知っておくことが重要です。
最も重要なのは、返済が困難になりそうだと感じた時点で、できるだけ早く金融機関に相談することです。延滞が始まってから相談するのではなく、延滞する前の段階で相談することで、より多くの選択肢を検討することができます。
金融機関では、返済条件変更(リスケジュール)という制度を用意しています。これは月々の返済額を一時的に減額したり、返済期間を延長したりすることで、返済負担を軽減する制度です。ただし、総返済額は増加することが多く、あくまでも一時的な措置として考えるべきです。
返済条件変更を行った場合でも返済が困難な場合は、任意売却という選択肢があります。これは金融機関の合意のもとで住宅を売却し、売却代金で住宅ローンの一部または全部を返済する方法です。競売と比較して高値で売却できる可能性が高く、残債の圧縮効果が期待できます。
住宅ローン以外にも借入がある場合は、それらの整理も重要です。消費者金融やクレジットカードのリボ払いなど、高金利の借入がある場合は、住宅ローンよりも優先して返済することで、全体的な利息負担を軽減できます。
住宅ローン以外の住居コスト
住宅を購入すると、住宅ローンの返済以外にも様々な費用が継続的に発生します。これらの費用も含めて月々の住居費として考え、家計計画に組み込んでおく必要があります。
【固定資産税・都市計画税】:固定資産税と都市計画税は、毎年確実に発生する税金です。税額は物件の評価額によって決まりますが、4000万円程度の住宅の場合、年間15万円から20万円程度が目安となります。月割りにすると1.3万円から1.7万円程度の負担となります。
【管理費・修繕積立金】:マンションを購入した場合は、管理費と修繕積立金が毎月発生します。管理費は月々1万円から3万円程度、修繕積立金は月々1万円から2万円程度が一般的です。これらの費用は住宅ローンとは別に支払う必要があり、一般的に値上がりする傾向があります。
【火災保険料】:火災保険料も必要な費用です。木造住宅の場合、年間3万円から5万円程度、マンションの場合は年間1万円から3万円程度が目安となります。地震保険に加入する場合は、さらに年間2万円から5万円程度が必要です。
【メンテナンス費】:戸建て住宅の場合は、外壁塗装や屋根の修繕などのメンテナンス費用も考慮する必要があります。これらの費用は一度に数十万円から数百万円かかることもあるため、計画的に積立を行っておくことが重要です。月々2万円から3万円程度の積立を行うことが目安となります。
これらの費用を合計すると、住宅ローンの返済額に加えて月々3万円から8万円程度の追加負担が発生することになります。年収700万円で住宅ローンの返済額を11万円に設定した場合、住居費の総額は14万円から19万円程度となり、手取り収入の30%から40%を占めることになります。
2025年の住宅ローン控除と税制メリット活用法
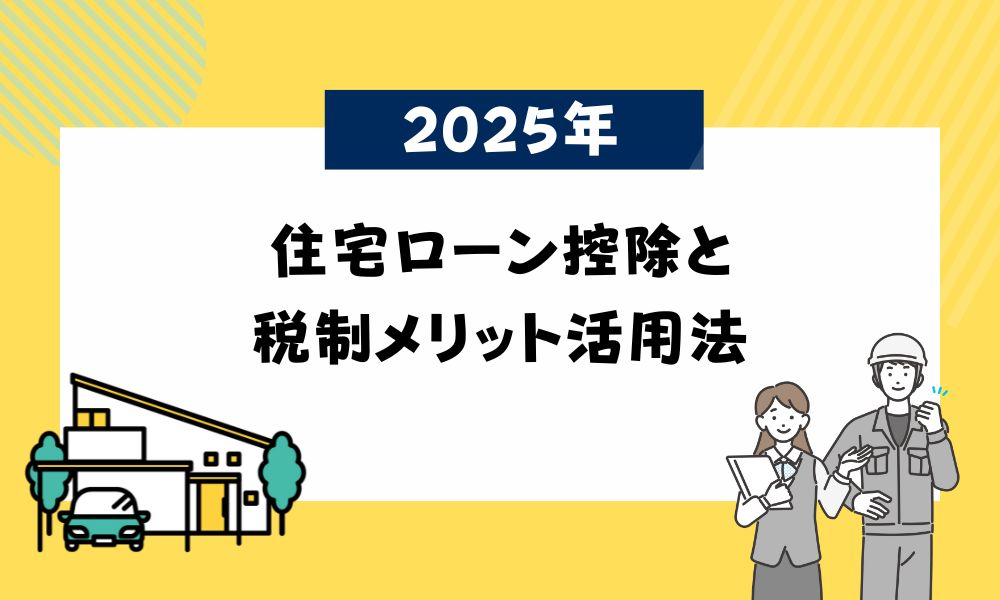
住宅購入時には、住宅ローン控除をはじめとする税制優遇措置を活用することで、実質的な負担を軽減することができます。年収700万円の方が受けられるメリットについて詳しく解説します。
住宅ローン控除の仕組みと控除額
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税から控除する制度です。控除期間は新築住宅で13年間、中古住宅で10年間となっています。ただし、控除額には年間の上限があり、住宅の性能や取得時期によって異なります。
年収700万円の方の場合、所得税額は年間30万円から40万円程度となることが一般的です。住民税からの控除上限は年間9.75万円となっているため、合計で年間40万円から50万円程度の控除を受けることが可能です。
借入額4000万円の場合、1年目の控除額は28万円(4000万円×0.7%)となります。年収700万円の方であれば、この控除額を満額活用できる可能性が高く、13年間で総額約300万円程度の控除を受けることができるでしょう。
ただし、住宅ローン控除は所得税からの控除であるため、所得税額が少ない場合は控除しきれない場合があります。また、控除期間中に繰上返済を行ってローン残高が減少すると、控除額も連動して減少します。
住宅ローン控除の恩恵を最大限に活用するためには、控除期間中は積極的な繰上返済を控え、余剰資金は他の投資に回すという戦略も考えられます。住宅ローンの金利が1%程度であれば、住宅ローン控除により実質金利は0.3%程度となるため、それ以上の利回りで運用できる投資があれば、繰上返済よりも有利になる可能性があります。
贈与税非課税措置の活用
親からの住宅取得資金の贈与を受ける場合は、贈与税の非課税措置を活用することができます。令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅で1000万円、その他の住宅で500万円まで非課税で贈与を受けることができます。
住宅取得資金贈与の非課税枠(2025年現在)
- 省エネ等住宅:1,000万円まで非課税
- その他の住宅:500万円まで非課税
- 適用期間:令和6年1月1日~令和8年12月31日
年収700万円の方の場合、親からの資金援助により頭金を確保したり、借入額を圧縮したりすることで、より安全な住宅購入が可能になります。ただし、贈与税の非課税措置を受けるためには、一定の要件を満たす必要があり、適切な手続きを行うことが重要です。
贈与税非課税措置の注意点
- 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告が必要
- 申告期限を過ぎると制度を利用できない
- 省エネ等住宅の要件は年々厳しくなっている
- 直系尊属(父母・祖父母)からの贈与のみが対象
住宅取得等資金贈与の特例を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、同年12月31日までに居住を開始する必要があります。また、贈与税の申告も必要となるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
年収700万円の住宅購入成功事例と失敗事例

実際の事例を通じて、年収700万円の方の住宅購入における成功と失敗のポイントを具体的に見てみましょう。
成功事例
まずは成功事例を見てみましょう。
Aさん夫婦(夫30歳・会社員、妻28歳・パート、子ども1歳)のケース
夫の年収700万円で新築マンションを購入しました。物件価格は3500万円で、頭金300万円を用意し、借入額3200万円で35年返済を選択しました。
月々の返済額は約9万円で、手取り月収45万円に対する返済負担率は20%となっています。妻のパート収入月8万円と合わせた世帯手取り収入は53万円で、住宅ローンを除いても44万円の生活費を確保できています。
Aさん夫婦の成功ポイントは、借入額を抑えたことです。金融機関からは4500万円程度の借入も可能でしたが、将来の教育費や妻の収入減少リスクを考慮して、夫の収入だけでも無理なく返済できる金額に設定しました。
また、変動金利を選択しましたが、金利が2%上昇しても返済を続けられることを事前にシミュレーションで確認しています。余裕資金は子どもの教育費として月々3万円、老後資金として月々2万円を積立投資に回しており、バランスの取れた家計管理を実現しています。
Bさん夫婦(夫26歳・会社員、妻25歳・会社員、子どもなし)のケース
夫の年収700万円、妻の年収400万円の共働き世帯です。新築一戸建て4200万円を頭金200万円、借入額4000万円で購入しました。
ペアローンを活用し、夫3000万円、妻1000万円の借入で、それぞれが住宅ローン控除を受けています。世帯の月々返済額は約11万円で、世帯手取り収入85万円に対する返済負担率は13%と余裕のある設定となっています。
Bさん夫婦の成功ポイントは、将来のライフプラン変化を見据えた借入配分です。妻の借入額を少なめに設定することで、出産・育児による収入減少時でも、夫の収入だけで返済を続けられるよう配慮しています。
失敗・後悔事例
次に失敗してしまったケースを見てみます。
Cさん夫婦(夫35歳・会社員、妻33歳・パート、子ども2人)のケース
夫の年収700万円で5500万円の新築マンションを購入しました。頭金500万円、借入額5000万円で35年返済を選択し、月々の返済額は約14万円となっています。
購入当初は妻もフルタイムで働いており、世帯年収1000万円を超えていたため返済に余裕がありました。しかし、第2子の出産を機に妻が退職し、世帯収入が大幅に減少しました。夫の手取り月収45万円に対して返済額14万円は重い負担となり、生活費を切り詰めても貯蓄ができない状況に陥っています。
さらに、子どもの習い事や塾代などの教育費が想定以上にかかり、家計は常に赤字状態です。住宅ローンの返済を優先するため、老後資金の積立は全くできておらず、将来への不安が増大しています。
Cさん夫婦の失敗ポイントは、世帯収入の最大値で借入額を設定したことです。妻の収入減少リスクを軽視し、夫の収入だけでは返済困難な金額を借りてしまいました。
事例から学ぶ成功のポイント
これらの事例から、年収700万円で住宅購入を成功させるためのポイントが見えてきます。
最も重要なのは、適正な借入額の設定です。金融機関の借入可能額や世帯収入の最大値ではなく、最もリスクの高い状況でも返済を続けられる金額に設定することが重要です。共働き世帯の場合は、片方の収入がなくなっても返済できる金額に抑えることが安全です。
ライフプランとの整合性確認も欠かせません。子どもの教育費、親の介護費用、老後資金など、住宅ローン以外の将来支出も考慮して借入額を決定する必要があります。特に子育て世帯の場合は、教育費負担のピーク時期と住宅ローン返済時期の重複を考慮することが重要です。
余裕を持った返済計画の重要性も事例から明らかです。返済負担率は手取り収入の20%から25%程度に抑え、金利上昇や収入減少などのリスクに対応できる余裕を確保しておくことが長期的な安定につながります。
年収700万円で後悔しない住宅ローンの組み方
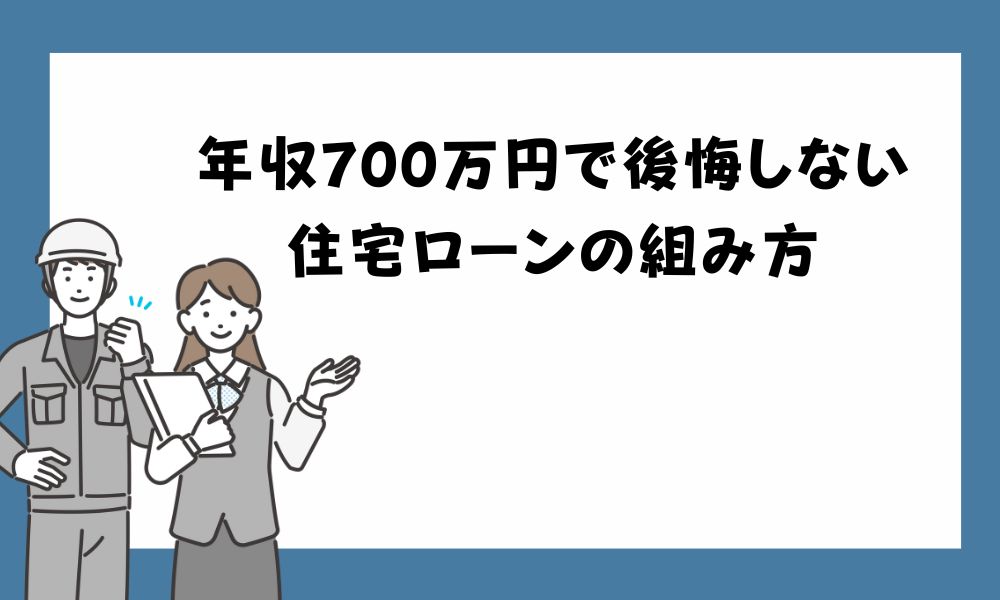
年収700万円での住宅ローンについて、様々な角度から詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントを改めて整理しておきましょう。
最重要ポイント
年収700万円の方にとって適正な借入額は、3200万円から4000万円程度が現実的な範囲です。子ども2人の世帯の場合は、教育費負担を考慮して3000万円以下に抑えることを強く推奨します。6000万円といった高額借入は、年収700万円の家計にとってはリスクが高すぎる選択といえます。
月々の返済額は、手取り収入の20%から25%以内、具体的には12万円から15万円程度に収めることが重要です。これにより、住宅ローンの返済と並行して、教育費の準備や老後資金の積立も無理なく行うことができます。
頭金なしでの住宅購入も可能ですが、その場合は借入額をより慎重に設定する必要があります。諸費用を含めても総借入額3500万円程度が安全な上限といえるでしょう。頭金を用意できる場合は、月々の返済負担軽減や総返済額の圧縮効果を得ることができます。
住宅ローン成功への5ステップ
住宅ローンを成功させるためには、以下の5つのステップを着実に実行することが重要です。
- 手取り収入の正確な把握と返済可能額の算出:額面年収ではなく実際の手取り収入をベースに、現実的な返済可能額を計算しましょう。
- ライフプランに応じた借入額の決定:将来の教育費、親の介護費用、老後資金などを考慮し、長期的に無理のない借入額を設定します。
- 金利タイプと返済期間の選択:リスク許容度や金利動向予測に基づいて、変動金利と固定金利のどちらを選択するかを決定し、返済期間も家計状況に応じて設定します。
- 複数金融機関での比較検討:金利だけでなく、団信の保障内容、手数料、サービス内容なども総合的に比較し、最適な商品を選択します。
- 契約前の最終チェック:返済額、総返済額、諸費用などを改めて確認し、本当に無理のない計画となっているかを最終確認します。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
まとめ
年収700万円でのマイホーム購入は、適切な計画を立てることで十分に実現可能な目標です。
重要なのは「借りられる額」ではなく「無理なく返せる適正額」を見極めること。
3200万円から4000万円程度の借入に抑え、手取り収入の20~25%以内で返済計画を組むことで、住宅ローンの返済が現実的なものになります。
子育て世帯であっても、教育費との並行準備は可能です。また、頭金なしでの購入や、住宅ローン控除・贈与税非課税措置などの税制優遇も活用できます。
ぜひこの記事も参考に、理想の返済計画を立ててみてくださいね!
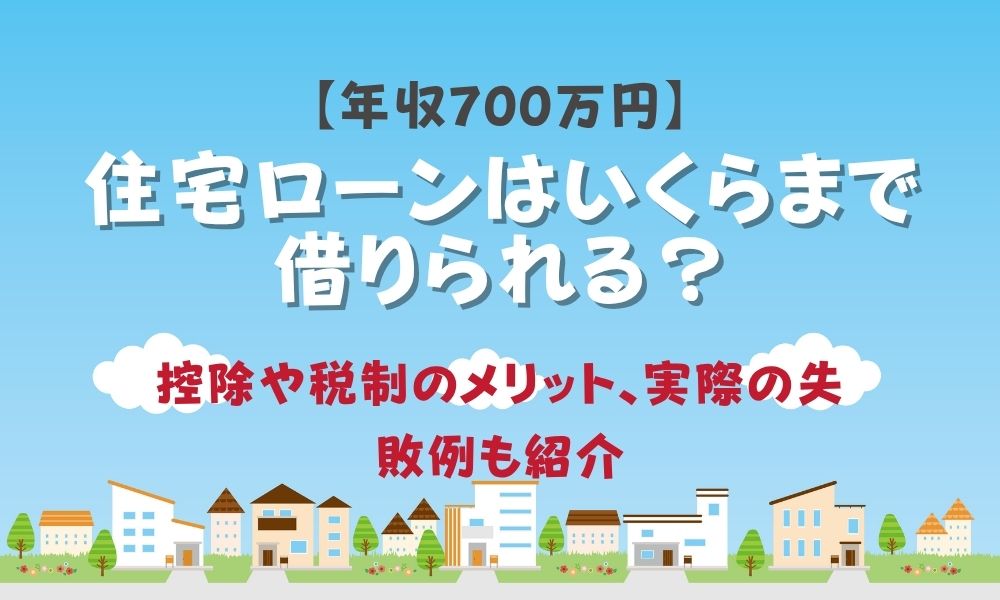
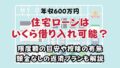

コメント