「年収がだいたい600万円くらいだけど、4000万円や5000万円の物件は買えるの?」
「頭金なしでも大丈夫?」
「共働きで子どもが2人いる場合の借り入れ適正額はいくらくらい?」
そんな疑問を持っている人は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、年収600万の方は金融機関の審査基準では4000万円どころか5000万円を超える借入も可能です。しかし、「借りられる」ことと「無理なく返せる」ことは全く別の話なので注意が必要です。
年収600万円の方が住宅ローンで失敗する最大の要因は、金融機関が提示する借入可能額をそのまま鵜呑みにしてしまうことと言っても過言ではないでしょう。金融機関は貸し倒れリスクを避けるため、あなたの返済能力を厳格に審査しますが、それでもなお「ギリギリ返せる金額」で貸付上限を設定しています。一方で、あなたが本当に必要なのは「余裕を持って返せる金額」での借入です。
この記事では、年収600万円世帯の住宅ローンについて、借入可能額から無理なく返せる適正額まで、具体的なシミュレーションと実例を交えて解説していきます。
ぜひ、最後まで読んでみてくださいね!
本文に入る前に、「今の年収で本当に家づくりができるの・・・?」と感じている人に向けてぜひ利用してほしいサービスを紹介しておきます。
それが下記の2つの無料サービスです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。それぞれのハウスメーカーのカタログを比較しながら住宅ローン借入額の検討もできるのがポイント。ぜひ一度カタログを見ながら資金計画を練ってみることをおすすめします。 不動産のポータルサイトSUUMOが運営する注文住宅相談サービスです。全国各地のハウスメーカー・工務店とのネットワークも豊富。スーモカウンターの最大の特徴が、店舗またはオンラインでアドバイザー相談が可能なことです。資金計画や住宅ローンについてもアドバイスを受けられるので、「今の年収でいくら借り入れられるのか不安」「資金について何から始めたら良いのかわからない」と言う人はまずはスーモカウンターに相談することをおすすめします。 |
上記の2サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
後悔のない家づくりのために、上記のサービスを活用しながら、納得のいく住宅ローンと資金計画を進めてみてくださいね!
\家づくりでおすすめ!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
それでは本文に入っていきましょう!
年収600万円の住宅ローン「借入可能額」と「無理なく返せる額」

年収600万円の方の住宅ローン借入について、まず押さえておくべき点は「借入可能額」と「適正借入額」の違いです。この差を理解せずに住宅ローンを組んでしまうと、後々の生活で苦労することになります。
金融機関の審査で借りられる上限額|最大5,200万円〜6,000万円
金融機関の住宅ローン審査では、一般的に年収に対する返済負担率が35%以下であることが条件となります。年収600万円の場合、年間返済額は210万円まで、月々では17.5万円までの返済が理論上可能とされます。
現在の住宅ローン金利(変動金利0.4%程度、35年返済)で計算すると、月々17.5万円の返済で借りられる金額は約5,200万円です。固定金利でも1.5%程度であれば、約4,800万円程度の借入が可能となります。
ただし、これらの金額はあくまで「金融機関が貸してくれる上限」であり、実際にこの金額を借りることが賢明かどうかは別問題です。年収600万円の手取り額は約470万円程度(月約39万円)ですから、月々17.5万円の返済は手取り収入の45%を占めることになります。
専門家が推奨する「無理なく返せる額」|3,000万円〜3,500万円
ファイナンシャルプランナーや住宅ローンの専門家が推奨する安全な返済負担率は、手取り収入の20〜25%程度です。年収600万円(手取り約470万円)の場合、月々の返済額は8万円〜10万円程度が理想的とされています。
この返済額で借りられる住宅ローンの金額を計算すると、月々8万円の返済で約2,700万円、月々10万円の返済で約3,400万円となります(変動金利0.4%、35年返済の場合)。つまり、年収600万円の方が無理なく返せる住宅ローンの適正額は、3,000万円〜3,500万円程度が目安となります。
この金額であれば、住宅ローンの返済以外にも教育費や老後資金の準備、急な出費への対応も可能となり、ゆとりある生活を維持できます。
年収600万円で4000万円借りるリスクとは?
年収600万円で4000万円の住宅ローンを組んだ場合、月々の返済額は約12.5万円(変動金利0.4%、35年返済)となります。これは手取り収入約39万円の32%に相当し、一般的に「ややきつい」とされる水準です。
4000万円借入の主なリスクは以下の通りです。
まず、住宅ローン以外の住居費用(固定資産税、火災保険、管理費など)を含めると、住居費全体で月15万円程度となり、家計を圧迫する可能性があります。また、子どもの教育費がかさむ時期や、夫婦のどちらかが転職・減収した場合の家計への影響が深刻になります。
さらに、変動金利を選択した場合、金利が1%上昇すると月々の返済額が約1.5万円増加し、家計への負担がさらに重くなります。貯蓄や投資に回せる資金も限られるため、将来の資産形成にも支障をきたす可能性があります。
年収600万円で5000万円は危険?
年収600万円で5000万円の住宅ローンを組んだ場合、月々の返済額は約15.6万円(変動金利0.4%、35年返済)となります。これは手取り収入の40%に相当し、住宅ローン以外の生活費や教育費を考慮すると、極めて厳しい家計状況となります。
5000万円借入の場合、住宅ローン以外の住居費用も含めると月18万円程度の住居費となり、手取り収入の約46%を占めることになります。この水準では、子どもの習い事や家族旅行などの「ゆとり費用」はほとんど確保できず、急な出費や収入減に対応できない危険性があります。
また、金利上昇リスクも深刻で、変動金利が1%上昇すると月々の返済額は約2万円増加し、17.6万円となります。これは手取り収入の45%超に相当し、家計破綻のリスクが高まります。
年収600万円で5000万円の借入は、よほど特殊な事情がない限り避けるべきでしょう。
【ケース別シミュレーション】年収600万円の住宅ローン返済プラン

年収600万円の方が住宅ローンを検討する際、具体的な返済プランをシミュレーションすることで、各借入額の現実的な負担感を把握できます。
ここでは、代表的な借入額での返済プランを詳しく見ていきましょう。
ローン借入額3,000万円の場合
借入額3,000万円は、年収600万円の方にとって最も安全性の高い借入額といえます。
変動金利0.4%、35年返済の場合、月々の返済額は約9.4万円となります。これは手取り収入約39万円の24%に相当します。
これは理想的な返済負担率の範囲内です。
3,000万円借入の場合、住宅ローン以外の住居費用(固定資産税年15万円、火災保険年3万円など)を含めても、月々の住居費は約11万円程度に収まります。これにより、教育費月3万円、食費月8万円、その他生活費月10万円を確保しても、月7万円程度の余裕資金を確保できます。
この余裕資金は、子どもの教育費積立、老後資金の準備、急な出費への対応など、様々な用途に活用できます。
また、繰上返済により総支払利息を減らすことも可能で、長期的な家計の安定性が確保されます。
ローン借入額4000万円の場合
借入額4000万円の場合、月々の返済額は約12.5万円(変動金利0.4%、35年返済)となります。手取り収入に占める割合は32%で、一般的に「やや負担が重い」とされる水準です。
4000万円借入で注意すべき点は、家計の余裕度が大幅に減少することです。住宅ローン以外の住居費用を含めると月々の住居費は約15万円となり、残りの生活費は24万円程度となります。子ども2人の教育費や食費、その他の生活費を考慮すると、貯蓄に回せる金額は月2〜3万円程度と限られてしまいます。
また、金利上昇リスクへの対応力も低下します。変動金利が1%上昇すると月々の返済額は約1.5万円増加し、家計はかなり厳しい状況となります。4000万円の借入を検討する場合は、以下の条件を満たすことが重要です。
- 夫婦共働きで安定した収入の確保
- 教育費の事前準備
- 金利上昇への備え
- 十分な緊急時資金の確保
ローン借入額5000万円の場合
借入額5000万円の場合、月々の返済額は約15.6万円(変動金利0.4%、35年返済)となり、手取り収入の40%を占めます。
これは住宅ローンの返済だけで家計の4割を占めることを意味し、非常にリスクの高い借入といえます。
5000万円借入の最大の問題は、家計の柔軟性が極めて低くなることです。住宅ローン以外の住居費用を含めると月々の住居費は約18万円となり、残りの生活費は21万円程度しか確保できません。子ども2人の教育費、食費、その他の必要経費を差し引くと、貯蓄や投資に回せる金額はほとんどありません。
さらに深刻なのは、リスクへの対応がほとんどできないことです。
以下のようなリスクがあり、家計に深刻な影響を与えてしまいます。
- 夫婦のどちらかが病気やリストラで収入減少した場合の即座の家計破綻
- 子どもの教育費がかさむ時期の塾代や受験費用の捻出困難
- 金利1%上昇で月々約2万円の負担増による家計行き詰まり
- 貯蓄や投資資金の不足による将来の資産形成への支障
頭金なしフルローンと頭金ありの返済額比較
ここでは頭金の有無による返済額の違いを、4000万円の物件購入を例に比較してみましょう。
頭金なしでフルローン4000万円を借りる場合と、頭金500万円を用意して3500万円を借りる場合では、月々の返済額に大きな差が生じます。
頭金なしの場合、月々の返済額は約12.5万円ですが、頭金500万円ありの場合は約10.9万円となり、月々1.6万円の差が生まれます。35年間では総額約670万円の差となり、頭金500万円を上回る効果があります。
ただし、頭金を用意することで手持ち資金が減少し、急な出費への対応力が低下するデメリットもあります。また、住宅ローン控除も借入額に応じて減少します。頭金を用意するかどうかは、家計の余裕度、金利水準、税制優遇措置などを総合的に検討して決定することが重要です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
世帯年収600万円・共働き夫婦の住宅ローンの戦略

共働きで世帯年収600万円の夫婦にとって、住宅ローンは単独で借りるか、夫婦で協力して借りるかによって大きく条件が変わります。
ここからは共働き夫婦ならではのメリットを活かした住宅ローン戦略を解説していきます。
単独ローン vs ペアローン vs 収入合算
共働き夫婦の住宅ローンには、主に3つの選択肢があります。
- 単独ローン:まず単独ローンは、夫婦のどちらか一方の名義で借りる最も一般的な方法です。審査が簡単で手続きも比較的簡素ですが、借入可能額は一人分の年収に基づいて決まります。
- ペアローン:ペアローンは、夫婦それぞれが別々の住宅ローンを組む方法です。例えば、夫が年収400万円で2500万円、妻が年収200万円で1000万円をそれぞれ借りるといった形になります。借入可能額を増やせる上、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるメリットがあります。
- 収入合算:収入合算は、夫婦の収入を合わせて一つの住宅ローンを組む方法です。借入可能額を大きく増やすことができますが、主債務者以外は住宅ローン控除を受けられないデメリットがあります。また、連帯保証人となる配偶者にも返済義務が生じます。
世帯年収600万円の共働き夫婦の場合、税制面でのメリットを最大化できるペアローンが最も有利なケースが多いといえます。
共働き夫婦が借入額を増やす3つの方法
共働き夫婦が借入額を増やしたい場合、いくつかの効果的な方法があります。
- ペアローン:最も基本的なのがペアローンの活用で、夫婦それぞれの年収に基づいて借入を行うことで単独ローンよりも大幅に借入額を増やすことができます。
- 夫婦の年収バランス:夫婦の年収バランスを調整することも重要です。片方の年収が極端に低い場合、その分の借入可能額が制限されてしまいます。可能であれば、妻の勤務時間を増やしたり、夫の収入アップを図ったりして、バランスの良い年収配分を目指すといいでしょう。
- 他の借金を完済しておく:カーローンや教育ローンなどの他の借入がある場合、その分だけ住宅ローンの借入可能額が減少します。住宅ローンの金利は他のローンよりも低いことが多いため、可能な限り他の借入を整理してから住宅ローンを申し込むことが賢明です。
産休・育休や時短勤務を考慮した借入額の決め方
共働き夫婦で特に注意が必要なのが、産休・育休や子育てのための時短勤務による収入減少リスクです。出産・育児により収入が一時的に大幅に減少することを前提とした資金計画を立てる必要があります。
安全な借入額を決める際は、例えば夫の収入のみで返済可能な金額を基本とし、妻の収入は余裕資金として考えるなどの工夫が重要です。例えば、夫年収450万円、妻年収150万円の夫婦の場合、夫の年収450万円ベースで借入額を検討し、2500万円〜3000万円程度を上限とするのが賢明でしょう。
また、育児手当や児童手当などの公的支援も考慮に入れて、育休期間中の家計収支をシミュレーションしておくことが大切です。職場復帰後も、時短勤務により収入が減少する可能性があるため、長期的な視点での資金計画が必要です。
共働き世帯の住宅ローン控除活用の方法
共働き夫婦がペアローンを組む場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができ、大きな税制メリットを享受できます。住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税・住民税から控除される制度で、最大13年間適用されます。
例えば、夫が2500万円、妻が1000万円のペアローンを組んだ場合、1年目はそれぞれ17.5万円と7万円、合計24.5万円の控除を受けることができます。これは単独で3500万円借りた場合と同じ控除額ですが、ペアローンの場合は夫婦それぞれの所得税・住民税の範囲内で控除を受けられるため、より確実に控除枠を活用できます。
ただし、住宅ローン控除を最大限活用するためには、夫婦それぞれに十分な所得税・住民税が発生していることが前提となります。妻の収入が少ない場合は、控除しきれない部分が生じる可能性があるため、事前に税理士やファイナンシャルプランナーに相談することをお勧めします。
子ども2人家庭の住宅ローンと教育費の両立

子ども2人を持つ家庭にとって、住宅ローンの計画で最も重要なのが教育費との両立です。住宅ローンの返済期間中には、子どもの教育費が大きくかさむ時期が必ず訪れるため、この点を十分に考慮した借入額の設定が必要です。
子ども2人の大学までの教育費はいくら?
子ども2人の教育費を計算する際は、幼稚園から大学卒業までの総額で考える必要があります。
文部科学省の調査によると、すべて公立の場合でも一人当たり約800万円、私立大学に進学した場合は約1,200万円程度が必要とされています。
つまり、子ども2人の場合、すべて公立コースでも約1,600万円、私立大学進学を考慮すると約2,400万円の教育費が必要という計算なります。
さらに、塾や習い事などの費用を加えると、実際の支出はこれらの金額を上回ることが多いのが現実です。
特に注意すべきは、大学進学時期の教育費集中です。子どもが2歳差の場合、上の子が大学1年生の時に下の子が高校3年生となり、2年間は大学費用と大学受験費用が重複します。
この時期には年間200万円以上の教育費が発生する可能性があるため、事前の資金準備が不可欠です。
【教育費ピーク時】家計圧迫を避ける借入額の上限
教育費がピークを迎える時期の家計圧迫を避けるためには、住宅ローンの借入額を慎重に設定する必要があります。年収600万円で子ども2人の家庭の場合、教育費ピーク時に年間200万円程度の教育費支出を想定し、その時期でも無理なく返済を続けられる住宅ローン額を逆算することが重要です。
具体的には、教育費ピーク時の可処分所得(手取り収入から教育費を差し引いた金額)の20〜25%以内に住宅ローンの返済額を収めることが理想的です。年収600万円(手取り470万円)で年間教育費200万円を支出する場合、残りは270万円となり、住宅ローンの年間返済額は54万円〜68万円(月4.5万円〜5.7万円)が上限となります。
この返済額で借りられる住宅ローン額は、約1,500万円〜1,900万円程度(変動金利0.4%、35年返済)となり、通常時の適正借入額3,000万円〜3,500万円よりもかなり少なくなります。このことからも、子ども2人の家庭では、教育費を十分に考慮した保守的な借入額の設定が必要であることがわかります。
もちろん、年収がこの先上がっていく可能性も当然あるでしょうが、反対に昇進による交際費などの出費増、残業代がつかない、ボーナスカット、などの可能性もあるため、現時点での年収をベースに考えると最も安心と言えるでしょう。
子育て世帯におすすめの住宅ローン返済方法
子育て世帯の住宅ローン返済戦略では、教育費の支出パターンに合わせた柔軟な返済計画が重要です。最も効果的なのは、教育費負担の軽い時期に繰上返済を積極的に行い、教育費のかさむ時期の返済負担を軽減する方法です。
具体的には、子どもが小学生の間は比較的教育費が少ないため、この時期に年間50万円〜100万円程度の繰上返済を行います。これにより、子どもが中学・高校生になる頃には住宅ローンの残高を大幅に減らし、月々の返済額を軽減できます。
また、ボーナス払いの活用も子育て世帯には有効です。ただし、ボーナス払いの割合は総返済額の20%以下に抑え、ボーナスが減額されても対応できる範囲に留めることが重要です。教育費の支出が増える時期には、ボーナス払いの一時停止や減額ができる金融機関を選ぶことも検討しましょう。
学資保険と住宅ローン繰上返済はどちらが優先?
子育て世帯が直面する典型的な悩みが、余裕資金を学資保険の積立に回すか、住宅ローンの繰上返済に充てるかという選択です。
この判断は、住宅ローンの金利と学資保険の予定利率を比較しながら行うと良いでしょう。
現在の住宅ローン金利が0.4%〜1.5%程度である一方、学資保険の予定利率は0.25%〜0.5%程度と低く設定されています。
純粋に利回りで比較すると、住宅ローンの繰上返済の方が有利なケースが多いといえます。
ただし、学資保険には確実な教育資金の準備というメリットがあります。繰上返済により住宅ローンの負担は軽減されますが、教育費が必要な時期に必要な資金が確保されているとは限りません。一方、学資保険は子どもの進学時期に合わせて確実に資金を受け取ることができます。
理想的なバランスとしては、教育費の基礎部分(大学4年間の学費など)は学資保険で確実に準備し、余裕資金については住宅ローンの繰上返済に充てるという方法がおすすめです。
この方法により、教育資金の確保と住宅ローン負担の軽減を両立できます。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
頭金なし住宅ローンのメリット・デメリット

近年、頭金なしで住宅ローンを組む方が増えています。
年収600万円の方にとって、頭金なし住宅ローンは選択肢の一つとして十分に検討する価値がありますが、メリットとデメリットを十分に理解した上で判断することが重要です。
頭金なしで住宅ローンを組むメリット・デメリット
頭金なし住宅ローンの最大のメリットは、手持ち資金を温存できることです。例えば、4000万円の物件を購入する際、従来であれば400万円〜800万円程度の頭金が必要でしたが、頭金なしであればこの資金を他の用途に活用できます。
具体的なメリットとしては、住宅購入後の家具・家電購入費用の確保、引越し費用や諸手続き費用への対応、さらには緊急時資金の維持などが挙げられます。また、住宅ローン控除の対象額が大きくなるため、税制面でのメリットも受けることができます。
一方で、デメリットも存在します。最も大きいのは総支払額の増加で、頭金500万円を用意した場合と比較すると、35年間で約600万円〜700万円程度の差が生じます。また、物件価格の全額を借り入れるため、金利上昇リスクの影響をより大きく受けることになります。
さらに、頭金なしの場合は金融機関の審査がより厳格になる傾向があり、金利優遇幅が小さくなったり保証料が高くなったりする可能性もあります。
頭金なしの場合の金利・諸費用への影響
頭金なしで住宅ローンを組む場合、金利面での影響を理解しておくことが重要です。多くの金融機関では、融資率(物件価格に対する借入額の割合)が高くなるほど、適用金利が高くなる傾向があります。
例えば、『物件価格の80%以下の借入では金利0.4%、90%を超える借入では0.5%、100%の借入では0.6%』といった具合に段階的に金利が上昇することがあります。頭金なしで100%融資を受ける場合、通常よりも0.1%〜0.3%程度高い金利が適用される可能性があります。
諸費用面では、保証料や事務手数料が高くなるケースがあります。保証料は借入額に比例して増加するため、頭金なしで借入額が大きくなれば、その分保証料も増加します。また、一部の金融機関では、高融資率の場合に追加の保証料を設定していることもあります。
これらの追加コストを考慮すると、頭金なしの場合の実質的な負担増は、単純な利息計算よりも大きくなる可能性があります。事前に複数の金融機関で条件を比較し、総合的な負担を検討することが重要です。
頭金なしでも審査に通りやすくする方法
頭金なしで住宅ローンの審査に通りやすくするためには、他の面で信用力を高めることが重要です。最も効果的なのは、安定した勤務先と勤続年数の確保です。大企業や公務員、医師・弁護士などであれば、頭金なしでも比較的審査に通りやすくなります。
年収600万円の方が頭金なしで審査を有利に進めるためのポイントは以下の通りです。
- 他の借入の事前完済:カーローンやカードローンがあると借入可能額が減少するため可能な限り整理する。
- 安定した勤務先と勤続年数:大企業・公務員・士業であれば審査で有利になる。
- 健康状態の良好さ:団信加入が条件のため、健康診断結果が重要。
- 配偶者収入の活用:共働き夫婦なら世帯年収での審査を検討する。
喫煙者の場合は、可能であれば禁煙してから審査に臨むことをお勧めします。
頭金なし vs 頭金200万円 vs 頭金500万円の総支払額を比較
4000万円の物件購入を例に、頭金の有無による総支払額の違いを比較してみましょう。
- 頭金なしでフルローン4000万円を借りる場合:5年間の総支払額は約4,320万円(変動金利0.4%)。
- 頭金200万円を用意して3800万円を借りる場合:35年間の総支払額は約4,104万円となり、頭金200万円と合わせると総額4,304万円。頭金なしと比較すると約16万円の節約となります。
- 頭金500万円を用意して3500万円を借りる場合:35年間の総支払額は約3,780万円となり、頭金500万円と合わせると総額4,280万円。頭金なしと比較すると約40万円の節約となります。
この比較から分かることは、頭金を多く用意するほど総支払額は減少しますが、その効果は頭金額ほど大きくないということです。頭金500万円を用意しても節約額は40万円程度に留まるため、手持ち資金の流動性を重視する場合は、頭金なしという選択も十分に合理的といえます。
ただし、これらの計算は金利が変動しないことを前提としているため、金利上昇リスクを考慮すると、頭金ありの方が安全性は高くなります。
年収600万円に最適な住宅ローン選択

年収600万円の方が住宅ローンを選ぶ際は、金利だけでなく様々な要素を総合的に判断することが重要です。
変動金利 vs 固定金利
年収600万円の方にとって、変動金利と固定金利のどちらを選ぶかは重要な判断となります。
変動金利の最大のメリットは、現在の低金利水準(0.4%程度)を活用できることです。3000万円を35年で借りる場合、変動金利0.4%なら月々約9.4万円の返済ですが、固定金利1.5%なら約11.6万円となり、月々2.2万円の差が生じます。
しかし、変動金利には金利上昇リスクが伴います。年収600万円で3000万円を借りている場合、金利が1%上昇すると月々の返済額は約1.3万円増加します。手取り月収39万円に対して1.3万円の増加は約3.3%に相当し、家計への影響は決して小さくありません。
年収600万円の方に推奨されるのは、借入額3000万円以下で十分な貯蓄がある場合は変動金利、借入額3500万円以上または貯蓄に余裕がない場合は固定金利という選択です。
また、金利上昇に備えて、変動金利を選ぶ場合は月々の返済額の10%程度を金利上昇対策として別途積み立てておくことをおすすめします。
借入期間【35年 vs 30年】総支払額と月々負担の違い
借入期間の選択も、年収600万円の方にとって重要な判断ポイントです。3000万円を変動金利0.4%で借りる場合、35年返済なら月々約9.4万円、30年返済なら約10.8万円となり、月々1.4万円の差が生じます。
総支払額で比較すると、35年返済では約3,320万円、30年返済では約3,290万円となり、30年返済の方が約30万円少なくなります。ただし、この差額以上に重要なのは、月々の家計負担と資金の流動性です。
年収600万円の方の場合、月々1.4万円の差は手取り収入の約3.6%に相当します。この差額を貯蓄や投資に回すことができれば、30年間で500万円以上の資産を形成することも可能です。特に子育て世帯の場合、教育費の支出が重なる時期には月々の負担軽減が重要となるため、35年返済を選択し、余裕がある時期に繰上返済を行うという方法が有効です。
ただし、定年退職時の年齢を考慮することも重要です。35歳で35年ローンを組むと完済時は70歳となるため、退職後の返済計画も含めて検討する必要があります。
金融機関選びのポイント(ネット銀行・都市銀行・地銀)
年収600万円の方が金融機関を選ぶ際は、金利だけでなくサービス内容や審査基準も総合的に比較することが重要です。
ネット銀行は一般的に最も低い金利を提供していますが、審査が厳格で手続きがオンライン中心となります。ネット銀行のメリットとしては、変動金利0.3%〜0.4%、固定金利1.3%〜1.5%程度の低金利が挙げられます。また、保証料が無料の場合が多く、初期費用を抑えることができます。一方で、対面相談ができないため、住宅ローンに不慣れな方には不安に感じられる場合があります。
都市銀行は金利面ではネット銀行に劣りますが、全国展開していることによる安心感と充実したサポート体制が魅力です。変動金利0.5%〜0.7%程度で、固定金利は1.5%〜1.8%程度が一般的です。転勤の多い年収600万円のサラリーマンの方には、全国どこでも同じサービスを受けられるメリットがあります。
地方銀行は地域密着型のサービスが特徴で、地元企業に勤める年収600万円の方には審査面で有利に働く場合があります。金利は都市銀行と同程度ですが、地域の不動産情報に詳しく、物件選びの相談なども可能です。
審査に通りやすくする事前準備と注意点
年収600万円の方が住宅ローン審査をスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。
- まず、信用情報の確認を行いましょう。過去のクレジットカードやローンの延滞履歴は審査に大きく影響するため、CICやJICC等の信用情報機関で自分の信用情報を確認しておくことをお勧めします。
- 次に、必要書類の準備を行います。年収600万円のサラリーマンの場合、源泉徴収票(直近3年分)、住民票、印鑑証明書、物件に関する書類などが必要となります。自営業の場合は、確定申告書(直近3年分)と納税証明書も必要です。
- 勤続年数も審査の重要な要素です。一般的に3年以上の勤続年数が望ましいとされていますが、転職したばかりの場合は前職との関連性や年収アップの経緯を説明できるよう準備しておきましょう。年収600万円でも勤続年数が短い場合は、審査が厳しくなる可能性があります。
健康状態の管理も重要です。団体信用生命保険への加入が必要なため、健康診断で異常値が見つかった場合は改善に努め、必要に応じて再検査を受けることをお勧めします。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
【実例紹介】年収600万円世帯の住宅ローン成功・失敗事例

ここからは実際に年収600万円で住宅ローンを組んだ人の事例をみながら、成功と失敗のポイントを学んでいきましょう。
【成功事例】借入額3,200万円で無理なく返済中の4人家族
Aさん一家は、夫35歳(年収600万円)、妻33歳(パート年収100万円)、子ども2人(7歳、4歳)の4人家族です。3年前に3,800万円の新築戸建を購入し、頭金600万円を用意して3,200万円の住宅ローンを組みました。変動金利0.45%、35年返済で月々の返済額は約10万円です。
Aさんの成功ポイントは、借入額を年収の約5.3倍に抑えたことです。手取り月収約40万円に対して住宅ローン返済10万円は25%に相当し、理想的な返済負担率を維持しています。住宅ローン以外の住居費(固定資産税、火災保険など)を含めても月12万円程度で、家計に十分な余裕があります。
この余裕により、子どもの習い事費用月3万円、学資保険月2万円、家族の貯蓄月5万円を確保できています。また、金利上昇に備えて月1万円を金利上昇対策資金として積み立てており、万が一の事態にも対応できる準備をしています。
【失敗事例】借入額4,800万円で生活が苦しくなったケース
Bさんは夫38歳(年収620万円)、妻36歳(専業主婦)、子ども1人(5歳)の3人家族で、2年前に5,000万円の新築マンションを購入しました。頭金200万円で4,800万円の住宅ローンを組み、変動金利0.5%、35年返済で月々の返済額は約15万円となっています。
Bさんの失敗は、借入額を年収の約7.7倍まで増やしてしまったことです。
手取り月収約41万円に対して住宅ローン返済15万円は37%を占め、住宅ローン以外の住居費を含めると月18万円程度となり、家計を大きく圧迫しています。
現在の家計状況は、食費月8万円、光熱費月2万円、通信費月2万円、子どもの費用月3万円、その他生活費月5万円で、貯蓄はほとんどできない状態です。子どもの習い事を諦めたり、家族旅行も控えたりしており、生活には余裕がないと言えるでしょう。
さらに深刻なのは、変動金利の上昇リスクです。金利が1%上昇すると月々の返済額は約2万円増加し、月17万円となります。この場合、家計は完全に破綻してしまう可能性があります。
【共働き成功事例】ペアローンで4,000万円を無理なく返済
Cさん夫婦は、夫32歳(年収400万円)、妻30歳(年収250万円)の共働き夫婦で、子どもはまだいません。昨年、4,200万円の中古マンションをリノベーションして購入し、頭金200万円、ペアローンで4,000万円を借り入れました。
ペアローンの内訳は、夫が2,500万円(月々約7.8万円)、妻が1,500万円(月々約4.7万円)で、合計月12.5万円の返済です。世帯手取り月収約45万円に対して28%の返済負担率となり、適正な範囲内に収まっています。
ペアローンの最大のメリットは、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられることです。夫は年17.5万円、妻は年10.5万円、合計年28万円の控除を受けており、実質的な金利負担が大幅に軽減されています。
また、妻の育休時のリスクにも備えており、夫の収入のみでも生活できるよう家計を設計しています。現在は月8万円の貯蓄ができており、将来の教育費や住宅ローンの繰上返済に充てる予定です。
【頭金なし成功事例】フルローン3,500万円の活用法
Dさんは夫29歳(年収580万円)、妻27歳(年収150万円)の共働き夫婦で、1年前に3,500万円の新築戸建を頭金なしのフルローンで購入しました。本来なら頭金500万円程度を用意できる貯蓄がありましたが、あえて頭金なしを選択しました。
Dさんの戦略は、頭金として使う予定だった500万円を投資信託で運用することです。住宅ローンの金利0.4%に対して、投資信託の期待リターンを年3%〜5%程度と見込み、金利差による利益を狙っています。
月々の住宅ローン返済は約11万円で、世帯手取り月収約48万円の23%に相当します。頭金なしでも適正な返済負担率を維持できているのは、借入額を年収の約6倍に抑えたことが要因です。
頭金なしのデメリットである金利上昇リスクには、変動金利を選択しつつ、金利上昇時の対策として月2万円を別途積み立てています。また、住宅ローン控除により年約25万円の控除を受けており、実質的な金利負担は大幅に軽減されています。
住宅ローン返済で失敗しないための注意点とリスク対策

年収600万円で住宅ローンを組む際は、様々なリスクを想定した対策を行うことが重要です。事前にリスクを把握し適切な対策を立てることで、安心して住宅ローンを返済し続けることができます。
転職・収入減少リスクへの対策
年収600万円のサラリーマンにとって、転職や収入減少は現実的なリスクです。特に現在の雇用環境では、終身雇用制度の崩壊により転職が一般的となっており、転職時の収入変動に備えることが重要です。
転職リスクへの最も効果的な対策は、住宅ローンの借入額を保守的に設定することです。年収600万円の方の場合、転職により年収が450万円〜500万円程度に減少する可能性を考慮し、減収後でも無理なく返済できる金額での借入を心がけましょう。
具体的には、現在の年収ではなく、転職後の想定年収をベースに借入額を決定する方法が推奨されます。
年収600万円の方が年収500万円に減収することを想定すると、適正借入額は2,500万円〜3,000万円程度となります。
また、転職活動期間中の収入減少に備えて、生活費の6ヶ月〜1年分に相当する緊急時資金を確保しておくことも重要です。年収600万円の方の場合、200万円〜300万円程度の緊急時資金があると安心です。
金利上昇リスクと対策
変動金利で住宅ローンを組んだ場合、金利上昇リスクは避けて通れない問題です。
年収600万円で3,000万円を変動金利0.4%で借りている場合、金利が1%上昇すると月々の返済額は約1.3万円増加します。
金利上昇リスクへの対策として最も効果的なのは、金利上昇分に対応できる資金の積立です。月々の返済額の10%〜15%程度を金利上昇対策資金として別途積み立てることで、金利が1%〜2%上昇しても対応できる準備ができます。
3,000万円借入の場合、月々1万円〜1.5万円を金利上昇対策として積み立てれば、5年間で60万円〜90万円の資金が蓄積されます。この資金があれば、金利上昇時に繰上返済を行い、月々の返済額の増加を抑制することができます。
また、金利が上昇した際には固定金利への借り換えも検討しましょう。ただし、借り換えには手数料がかかるため、金利差と手数料を比較した上で判断することが重要です。一般的に、金利差が1%以上あり、残存期間が10年以上ある場合は借り換えのメリットが大きくなります。
住宅ローン以外の住居費用も考慮する
住宅ローンの返済額だけに注目していると、実際の住居費負担を見誤ってしまいます。
年収600万円の方が住宅を購入する際は、住宅ローン以外の住居費用も含めた総合的な資金計画を立てることが重要です。
戸建住宅の場合、住宅ローン以外に以下の費用が必要となります。
- 固定資産税:年10万円〜20万円
- 火災保険・地震保険:年3万円〜8万円
- 修繕費:年20万円〜30万円
これらを月割りすると、月3万円〜5万円程度の追加負担となります。
マンションの場合は、以下の費用が発生します。
- 管理費:月1万円〜3万円
- 修繕積立金:月1万円〜2万円
- 固定資産税:年8万円〜15万円
- 保険料:年2万円〜5万円
月割りでは月3万円〜6万円程度の追加負担となります。
年収600万円で3,000万円を借り入れ、月々の返済額が9.4万円の場合、住宅ローン以外の住居費用を含めると月12万円〜15万円程度の住居費となります。この総額を考慮した上で、家計に無理のない借入額を決定することが重要です。
緊急時の資金確保と繰上返済のバランス
住宅ローンを返済しながら家計を安定させるためには、緊急の資金確保と繰上返済のバランスを適切に保つことが重要です。年収600万円の方の場合、緊急時資金として生活費の6ヶ月分程度、約200万円〜250万円を確保することが推奨されています。
緊急時の資金を確保した上で、それでも資金に余裕がある場合に、繰上返済を検討しましょう。繰上返済には期間短縮型と返済額軽減型の2種類がありますが、年収600万円の方には返済額軽減型がおすすめです。月々の返済負担を軽減することで、教育費や老後資金の準備により多くの資金を充てることができます。
繰上返済のタイミングとしては、金利の低い現在の環境では急いで行う必要はありません。子どもの教育費がかさむ前の時期や、ボーナス時期などに余裕資金がある場合に実施すれば十分です。年間50万円〜100万円程度の繰上返済でも、長期的には大きな効果が期待できます。
ただし、住宅ローン控除を受けている期間中は、繰上返済により控除額が減少する可能性があります。住宅ローン控除の控除率0.7%と住宅ローン金利を比較し、金利の方が高い場合に繰上返済を実施することが有効です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
よくある質問と専門家からのアドバイス

年収600万円で住宅ローンを検討している方から寄せられる代表的な質問と、専門家からのアドバイスをまとめました。
これらの質問は多くの方が抱く疑問でもあるため、ぜひ参考にしてみてください。
Q. 5000万円借りたい場合の現実的な対策は?
年収600万円で5000万円の借入を希望する場合、現実的には非常に困難であり、仮に借りられたとしても返済リスクが極めて高くなります。5000万円を借りる場合の月々返済額は約15.6万円となり、手取り収入の40%を占めることになります。
どうしても5000万円の物件を購入したい場合の対策として、まず十分な頭金の準備が必要です。1000万円〜1500万円の頭金を用意し、借入額を3500万円〜4000万円程度に抑えることで、返済負担を軽減できます。
また、共働きでペアローンを組むことで借入可能額を増やす方法もあります。夫年収400万円、妻年収200万円の場合、それぞれ2500万円と1500万円を借り入れることで、合計4000万円の借入が可能となります。ただし、この場合でも夫婦両方に安定した収入が必要で、子育てを検討している場合には妻の産休時のリスクも考慮する必要があります。
最も現実的な選択肢は、物件価格を見直すことです。年収600万円の場合、無理なく購入できる物件価格は3500万円〜4000万円程度が適正です。立地や物件タイプを見直すことで、予算内で満足できる物件を見つけることができるでしょう。
Q. 共働きが前提の住宅ローンは危険?
共働きを前提とした住宅ローンには確かにリスクがありますが、適切な対策を講じることでリスクを軽減できます。最大のリスクは、妻の出産の際や、夫婦で育休を取る際の収入減少、また夫婦のどちらかの転職・失業による収入変動です。
共働き前提の住宅ローンを安全に組むためのポイントは、どちらかの収入のみでも返済可能な金額を基本とすることです。例えば、夫年収400万円、妻年収200万円の夫婦の場合、夫の年収400万円をベースに借入額を決定し、2500万円〜3000万円程度を上限とします。妻の収入は繰上返済や教育費の準備に充てると考えましょう。
また、妻の産休時の収入減少に備えて、育児手当や児童手当も含めた収支シミュレーションを行うことが重要です。産休中は給与の67%(最初の6ヶ月)から50%(それ以降)程度の育児休業給付金が支給されるため、この金額も考慮して家計計画を立てましょう。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
まとめ
年収600万円での住宅ローンは、適切な知識と計画があれば安心して組むことができます。
重要なのは「借りられる額」ではなく「無理なく返せる額」で判断することです。
適正借入額3000万円〜3500万円を目安にすれば、教育費や老後資金の準備も両立でき、ゆとりある生活を維持できます。共働き夫婦はペアローンで選択肢が広がり、頭金なしでも計画的に進めることができれば問題ありません。
金利選択や金融機関選びも含め、この記事の知識を活用すれば、きっと理想のマイホームを手に入れることができるでしょう。
この記事も参考にしながら、年収600万円という安定収入を活かし、ぜひ家族の幸せな未来への第一歩を踏み出してくださいね。
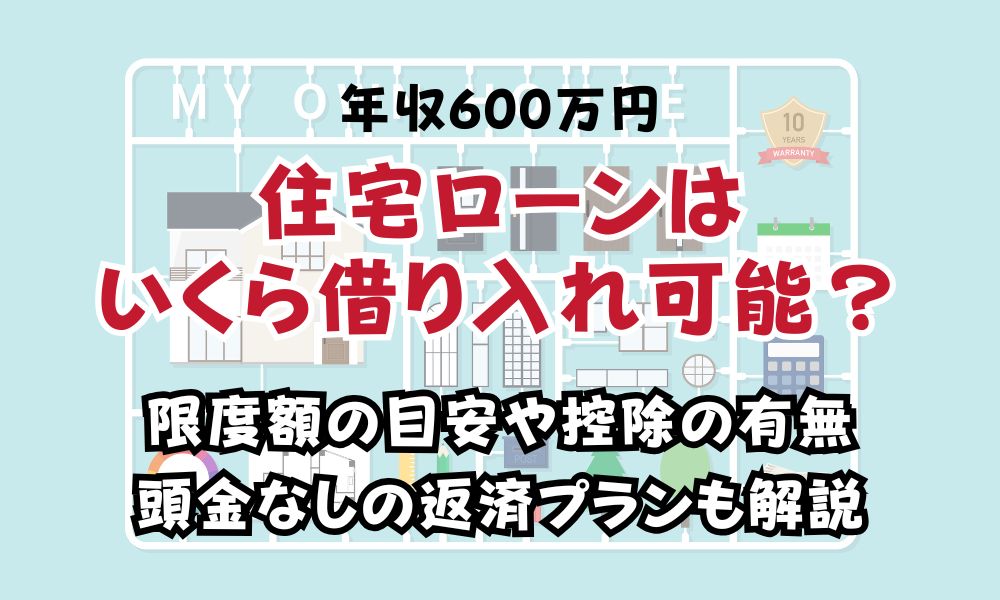
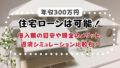
コメント