「年収400万円で住宅ローンはいくらまで借りられるの?」
「3500万円や4000万円は現実的?」
「頭金なしでも大丈夫?」
マイホーム購入を検討している年収400万円の方なら、誰もが抱く疑問ではないでしょうか。
実際に金融機関からは「4000万円まで借りられます」と言われても、実際に無理なく返済できるかは別問題なので不安になってしまいますよね。
そこでこの記事では、年収400万円の方が知っておくべきローンの金額を、具体的なシミュレーションも交えながら解説します。
ぜひ最後まで読んで参考にしてみてくださいね。
本文に入る前に、「今の年収で本当に家づくりができるの・・・?」と感じている人に向けてぜひ利用してほしいサービスを紹介しておきます。
それが下記の2つの無料サービスです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。それぞれのハウスメーカーのカタログを比較しながら住宅ローン借入額の検討もできるのがポイント。ぜひ一度カタログを見ながら資金計画を練ってみることをおすすめします。 不動産のポータルサイトSUUMOが運営する注文住宅相談サービスです。全国各地のハウスメーカー・工務店とのネットワークも豊富。スーモカウンターの最大の特徴が、店舗またはオンラインでアドバイザー相談が可能なことです。資金計画や住宅ローンについてもアドバイスを受けられるので、「今の年収でいくら借り入れられるのか不安」「資金について何から始めたら良いのかわからない」と言う人はまずはスーモカウンターに相談することをおすすめします。 |
上記の2サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
後悔のない家づくりのために、上記のサービスを活用しながら、納得のいく住宅ローンと資金計画を進めてみてくださいね!
\家づくりでおすすめ!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
それでは本文に入っていきましょう!
【結論】年収400万円で住宅ローンはいくらまで借りられる?
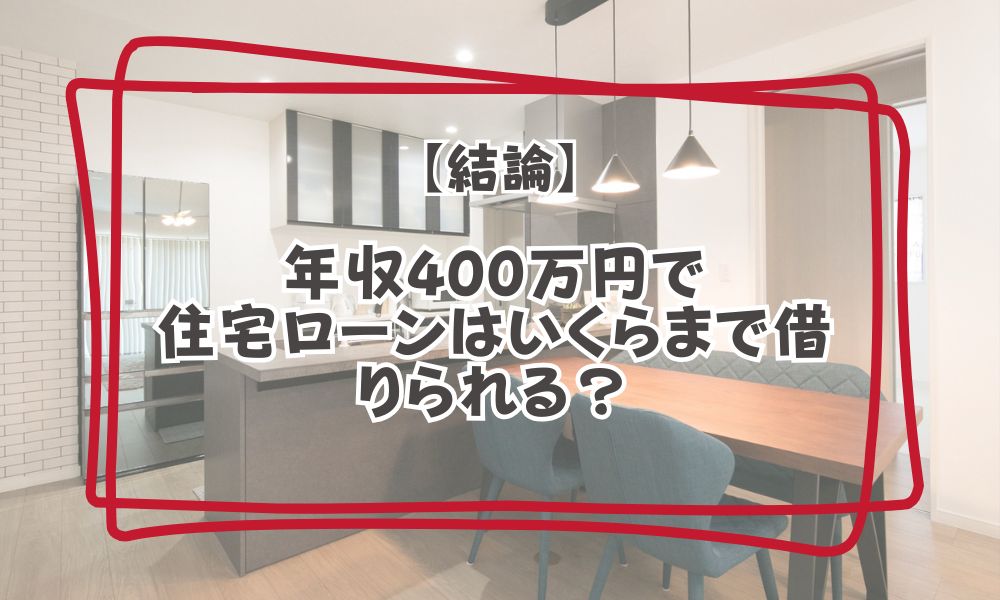
年収400万円で住宅ローンを検討している方に、まず結論をお伝えします。
金融機関の審査基準と実際に無理なく返済できる金額には、大きな差があることを理解しておきましょう。
借入可能額の上限は最大4000万円
年収400万円の場合、年収倍率10倍で計算すると最大4000万円まで借入可能です。多くの金融機関では、年収400万円以上であれば返済負担率35%以内という基準を設けており、理論上は4000万円程度の融資を受けることができます。
4000万円借入の計算根拠
- 年間返済可能額:400万円 × 35% = 140万円
- 月間返済可能額:140万円 ÷ 12ヶ月 = 約11.7万円
- 借入可能額:月11.7万円で35年返済 = 約4000万円
ただし、これは金融機関の「貸せる上限」であり、借り手にとっての「返せる上限」とは大きく異なります。
現実的な上限は3500万円(条件付き)
4000万円の借入は月々の返済額が手取り収入の45%を占めるため現実的ではありません。返済負担率30%程度に抑えた3500万円が、審査に通りやすく、かつギリギリ返済可能な上限と考えられます。
3500万円借入時の条件
- 月々返済額:約10.2万円
- 返済負担率:約30%
- 手取り収入に対する負担:約39%
しかし、これでも相当な家計管理能力と将来への備えが必要です。食費、光熱費、教育費、貯蓄などを手取り残額15.8万円で賄う必要があり、余裕のない生活を強いられる可能性があります。
無理なく返せる額は2200万円
家計に余裕を持ち、将来のライフイベントに備えるなら、借入額は2200万円以下に抑えることを強く推奨します。
2200万円借入時のメリット
- 月々返済額:約6.4万円
- 手取り収入に対する負担:25%
- 生活費として確保:約19.6万円
- 貯蓄・緊急時資金:十分な余裕
年収400万円は、給与所得者の平均年収460万円に近い標準的な収入層です。
住宅金融支援機構の調査でも、年収400万円台の住宅ローン利用者が最も多いことが分かっており、決してマイホーム購入が不可能な年収ではありません。重要なのは「借りられる額」ではなく「返せる額」で判断することです。
年収400万円で4000万円・3500万円借りた場合の返済シミュレーション
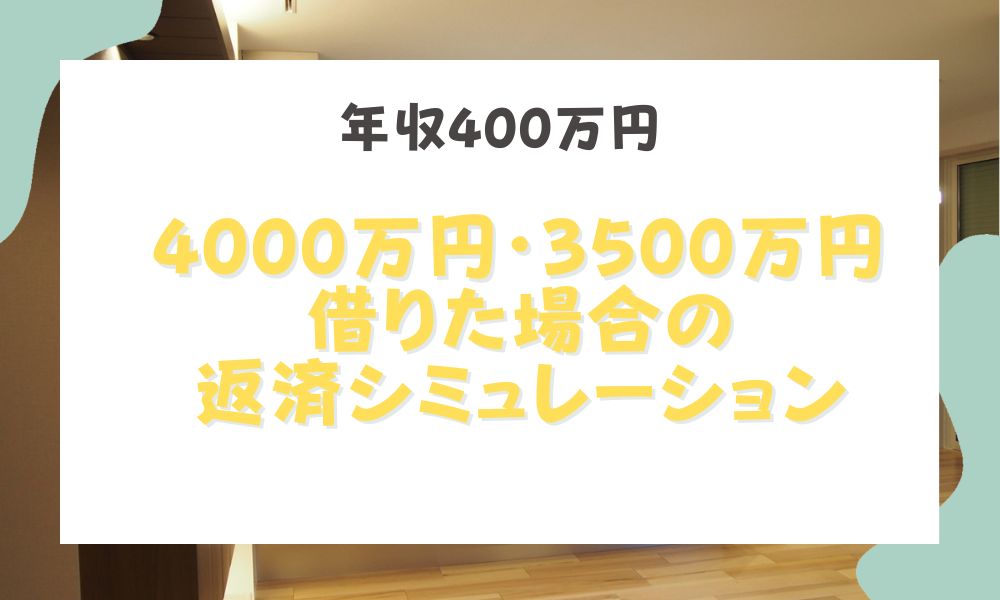
実際に年収400万円で高額な住宅ローンを組んだ場合、月々の返済額や家計への影響を具体的に検証してみましょう。
借入可能額の上限「4000万円」は家計破綻リスクが大きい
4000万円を35年返済・金利1.5%・元利均等返済で借入した場合の詳細な返済シミュレーションを見てみましょう。
4000万円借入時の返済詳細
- 月々返済額:約11.7万円
- 年間返済額:約140万円
- 総返済額:約4910万円(利息約910万円)
- 手取り26万円に対する負担率:45%
年収400万円の手取り額は、社会保険料や税金を差し引くと約320万円(月約26万円)です。ここから11.7万円を住宅ローン返済に充てると、残りは14.3万円しかありません。
残り14.3万円での生活費内訳
- 食費:6万円(切り詰めても最低限)
- 光熱費:2万円
- 通信費:1.5万円
- 保険料:1.5万円
- 日用品・被服費:1万円
- 交通費:1万円
- 残額:1.3万円(教育費・貯蓄・予備費)
この状況では、子供の教育費、車の維持費、家電の買い替え、病気・けがなどの急な出費に対応できません。また、住宅購入後に発生する固定資産税(年間15万円程度)も考慮されていないため、実質的に家計が破綻する可能性が高くなります。
現実的な上限「3500万円」でも要注意
3500万円借入の場合、月々返済額は約10.2万円、返済負担率は約30%となります。一見すると4000万円より余裕がありそうですが、依然として厳しい状況です。
3500万円借入時の家計シミュレーション
- 月々返済額:約10.2万円
- 手取り残額:約15.8万円
- 返済負担率:30%(金融機関審査はクリア)
- 手取りベース負担率:39%(危険水域)
手取り26万円から10.2万円を差し引いた15.8万円で、一般的な4人家族が生活することを考えてみましょう。
必要最低限の生活費(月額)
- 食費:6万円
- 光熱費:2万円
- 通信費:1.5万円
- 保険料:1.5万円
- 教育費・習い事:2万円
- 日用品・被服費:1.5万円
- 交通費・ガソリン代:1万円
- 合計:15.5万円
この計算では、貯蓄はわずか3000円しかできません。さらに、住宅購入後に発生する年間固定費を月割りで考慮すると以下のようになります。
住宅関連の追加年間費用
- 固定資産税:15万円
- 火災・地震保険:3万円
- 住宅修繕積立:10万円
- 合計:28万円(月割り約2.3万円)
これらを考慮すると、実質的に毎月2万円程度の赤字となり、ボーナスや貯蓄の取り崩しで補填する必要があります。
金利上昇リスクも考慮が必要
変動金利で借りた場合、金利上昇によりさらに返済額が増加する可能性があります。現在の低金利環境がいつまで続くかは不透明で、将来的な金利上昇を想定した返済計画が重要です。
金利上昇時の返済額変化(35年返済)
- 現在金利0.5% → 2.0%上昇時の影響
- 4000万円借入:月10.3万円 → 13.2万円(+2.9万円)
- 3500万円借入:月9.0万円 → 11.5万円(+2.5万円)
- 2800万円借入:月7.2万円 → 9.2万円(+2.0万円)
4000万円借入で金利が2.0%まで上昇すると、月々返済額が13.2万円となり、手取り26万円の51%を占めます。これでは生活が成り立たず、家計が完全に破綻してしまいます。3500万円借入でも11.5万円(手取りの44%)となり、非常に厳しい状況に追い込まれます。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
年収400万円で「無理なく返せる額」はいくら?
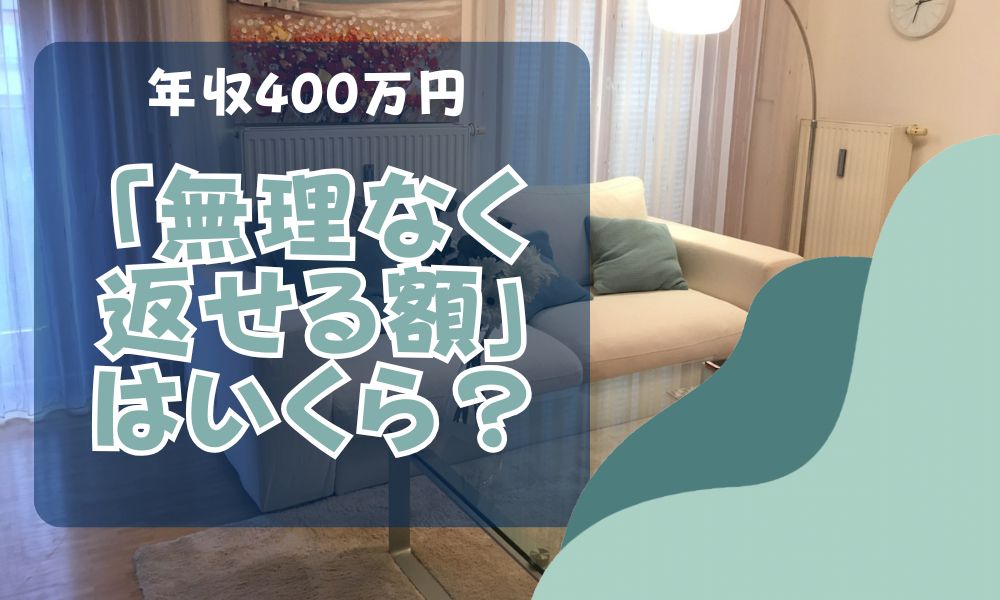
「借りられる額」と「返せる額」は全く違います。
年収400万円で本当に無理なく返済できる借入額を、詳細な家計分析とともに算出してみましょう。
理想的な返済負担率は手取りの20~25%
住宅ローンの返済負担率について、金融機関の審査基準(年収に対して30~35%)と、実際に無理なく返済できる水準は大きく異なります。
年収ベース vs 手取りベースの返済負担率
- 金融機関基準:年収の30~35%
- 安全な基準:手取りの20~25%
- 年収400万円の手取り:約320万円(月約26万円)
- 安全な返済額:月5.2万円~6.5万円
この差が生まれる理由は、金融機関が「返済不能にならない最低限の基準」で審査するのに対し、借り手は「ゆとりある生活を維持できる基準」で考える必要があるためです。
安全な借入額の計算
- 月々返済額6.5万円 × 35年返済 × 金利1.5% = 約2200万円
- 月々返済額5.2万円 × 35年返済 × 金利1.5% = 約1750万円
つまり、年収400万円で無理なく返済できる借入額は1750万円~2200万円の範囲となります。
生活費から逆算した現実的な家計
年収400万円の4人家族(夫婦+子供2人)を想定した、リアルな家計シミュレーションを行ってみましょう。
年収400万円世帯の詳細な家計内訳(月額)
固定費
- 食費:5.5万円(外食費含む)
- 光熱費:1.8万円(電気・ガス・水道)
- 通信費:1.2万円(携帯・インターネット)
- 保険料:1.5万円(生命・医療・自動車)
- 教育費:2万円(保育園・習い事・塾)
変動費
- 日用品・被服費:1.5万円
- 交通費・ガソリン代:1万円
- 医療費・理美容費:0.5万円
- 交際費・娯楽費:1万円
貯蓄・予備費
- 貯蓄:2万円(年24万円)
- 予備費・その他:1.5万円
生活費合計:18.5万円
手取り26万円から生活費18.5万円を差し引くと、住居費に充てられるのは7.5万円となります。ただし、住居費には住宅ローン返済以外の費用も含まれます。
住居費に含まれるその他の支出(月額換算)
- 固定資産税:1.2万円(年15万円÷12)
- 火災・地震保険料:0.3万円(年3.5万円÷12)
- 住宅維持修繕費:0.8万円(年10万円÷12)
- その他住居費合計:2.3万円
したがって、純粋な住宅ローン返済に充てられるのは約5.2万円(7.5万円-2.3万円)となります。
将来の支出増加も考慮が必要
住宅ローンは最長35年という長期にわたる返済のため、将来のライフステージの変化による支出増加も考慮する必要があります。
ライフステージ別の支出増加要因
子育て期(現在~15年後)
- 子供の成長に伴う食費増加:月1万円~2万円
- 教育費の段階的増加:小学生3万円、中学生5万円、高校生8万円、大学生15万円
- 習い事・部活動費:月2万円~3万円
中年期(15年後~30年後)
- 住宅の大規模修繕:15年ごとに200万円~500万円
- 親の介護費用:月5万円~15万円
- 子供の結婚資金援助:1人300万円~500万円
老後期(30年後~)
- 年金減少による収入ダウン
- 医療・介護費の増加
- 住宅のバリアフリー化費用
これらの将来支出に備えるため、現在の家計に十分な余裕を持たせておくことが重要です。特に子供が大学生になる時期は、教育費が月15万円程度必要になるため、住宅ローン返済額は極力抑えておく必要があります。
推奨借入額:2200万円以下
以上の分析から、年収400万円で無理なく返済できる借入額は2200万円以下、月々の返済額は6.5万円以下に抑えることを強く推奨します。
この水準であれば、将来の支出増加にも対応でき、計画的な繰り上げ返済による総返済額削減も可能となります。
年収400万円で「頭金なし」でも住宅ローンは組める?

頭金なしでの住宅購入は可能ですが、メリットとデメリットを十分理解した上で判断する必要があります。年収400万円における頭金なし購入の現実と戦略を詳しく解説します。
頭金なしのフルローンは可能だが制約あり
現在、多くの金融機関で物件価格の100%を融資するフルローン(頭金なし)が可能です。ただし、完全に資金ゼロでの購入はできません。
頭金なし購入で必要な自己資金
- 登記費用:30万円~50万円
- 融資手数料:50万円~80万円(借入額の1~2%)
- 火災保険料:20万円~30万円(数年分前払い)
- 引越し費用:20万円~40万円
- 家具・家電購入費:100万円~200万円
- 合計:220万円~400万円
3000万円の物件を頭金なしで購入する場合でも、最低220万円程度の自己資金が必要です。さらに、購入後しばらくは生活費の3~6ヶ月分(80万円~160万円)を緊急資金として確保しておく必要があります。
頭金なし購入の制約と注意点
- 借入額が最大となり、月々返済額が高くなる
- 審査が厳しくなる傾向(自己資金力の評価が低い)
- 金利優遇を受けにくい場合がある
- 諸費用ローンを併用する場合、さらに返済負担が増加
- オーバーローン状態のリスク(売却時に残債が残る)
年収400万円で頭金なしの場合、安全に購入できる物件価格は2200万円程度が限界です。これ以上の物件を頭金なしで購入すると、月々の返済額が手取り収入の25%を超えてしまい、家計が圧迫される可能性が高くなります。
頭金を用意するメリットと効果
頭金を用意することで得られるメリットは、単純な借入額の減少だけではありません。住宅購入全体における戦略的な効果があります。
頭金を用意する7つのメリット
- 借入額減少による月々返済額の軽減
- 審査通過率の向上(自己資金力のアピール)
- 金利優遇の可能性(フラット35S、銀行の優遇金利)
- 総返済額の減少(利息軽減効果)
- 住宅ローン控除との最適バランス
- オーバーローンリスクの回避
- 心理的安心感(借金額の減少)
具体的な頭金効果(3500万円物件の場合)を比較してみましょう。
頭金なし↓
- 借入3500万円
- 月々返済約10.2万円
- 総返済額約4300万円
- 手取りに対する負担39%
頭金700万円↓
- 借入2800万円
- 月々返済約8.2万円
- 総返済額約3440万円
- 手取りに対する負担32%
したがって、頭金700万円のメリットは下記になります。
- 月々返済額:2万円軽減
- 総返済額:860万円軽減
- 負担率改善:39% → 32%
この2万円の差は家計にとって非常に大きく、教育費や貯蓄、急な出費への対応に充てることができます。
頭金準備の判断基準と戦略
年収400万円の場合、頭金を準備すべきか、頭金なしで早期購入すべきかの判断基準を明確にしておくことが重要です。
頭金準備をおすすめするケース
現在の住環境に大きな問題がない場合
- 現在の家賃が6万円以下
- 子供の学校区に問題がない
- 通勤時間に大きな不満がない
- 近隣トラブルがない
ライフプランに余裕がある場合
- 子供の教育費が本格的にかかるまで5年以上ある
- 夫婦ともに30歳以下で貯蓄期間を確保できる
- 昇給・昇格による年収アップが期待できる
- 親からの援助が期待できる
頭金なしを検討するケース
現在の住環境に問題がある場合
- 現在の家賃が9万円以上で住居費負担が重い
- 子供の学校区を変更したい
- 通勤時間が片道1時間以上
- 近隣トラブルや住環境の悪化
早期購入のメリットが大きい場合
- 子供の小学校入学前に住環境を整えたい
- 金利上昇前に固定金利で借りたい
- 物件価格上昇前に購入したい
- 夫婦ともに35歳以上で住宅ローン完済年齢を考慮する必要
年収400万円での頭金を準備する方法
- 目標金額:物件価格の20%(例:2500万円物件なら500万円)
- 準備期間:3年~5年
- 月々積立額:8万円~14万円
- 積立方法:定期預金、財形貯蓄、つみたてNISA
この積立額は年収400万円の手取りに対して30~50%を占めるため、相当な節約と家計管理が必要です。一方、頭金なしで購入する場合は、購入後の返済額を抑えるため、物件価格を2200万円以下に限定することが重要です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
年収400万円で3500万円・4000万円を借りるための条件と対策

年収400万円で高額な住宅ローンを組むには、単独での借入では限界があります。具体的な対策と条件を詳しく解説します。
夫婦の収入を合算して借入可能額を増やす
配偶者の収入を活用する方法として、収入合算とペアローンの2つの選択肢があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを理解して選択することが重要です。
収入合算の仕組みとメリット
収入合算は、主たる債務者の年収に配偶者の年収を加算して審査を受ける方法です。
合算できる収入の範囲
- 配偶者の収入:全額または50%(金融機関により異なる)
- 親族の収入:同居の親・子の収入(条件あり)
- 合算者の条件:安定した収入、連帯保証人または連帯債務者になること
具体的な効果例
- 夫年収400万円 + 妻年収200万円(全額合算)= 世帯年収600万円
- 借入可能額:600万円 × 6~7倍 = 3600万円~4200万円
- 無理なく返せる額:世帯手取り約38万円 × 25% = 月9.5万円
この場合、3500万円の借入でも月々約10.2万円の返済となり、世帯手取りに対して27%の負担率となります。単独年収400万円では厳しい借入額も、夫婦合算であれば現実的になります。
ペアローンの特徴とメリット
ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを組む方法で、収入合算とは異なる特徴があります。
ペアローンの仕組み
- 夫婦それぞれが債務者となる
- 物件の持分も夫婦それぞれが持つ
- 互いに連帯保証人となる
- それぞれが住宅ローン控除を受けられる
ペアローン活用例
- 夫:年収400万円で2000万円借入
- 妻:年収200万円で1000万円借入
- 合計:3000万円借入
- 住宅ローン控除:夫婦それぞれが受けられるため最大70万円
収入合算 vs ペアローン比較
| 項目 | 収入合算 | ペアローン |
|---|---|---|
| 契約数 | 1つ | 2つ |
| 債務者 | 主債務者のみ | 夫婦両方 |
| 住宅ローン控除 | 主債務者のみ | 夫婦両方 |
| 団信 | 主債務者のみ | 夫婦両方 |
| 手数料 | 1契約分 | 2契約分 |
返済負担率を下げる事前準備
年収400万円付近では、わずかな年収の違いや他の借入状況が借入可能額に大きく影響します。
年収400万円のボーダーライン効果
多くの金融機関で年収400万円を境に返済負担率の上限が変わります。
フラット35の返済負担率基準
- 年収400万円未満:30%以内
- 年収400万円以上:35%以内
この5%の差が借入可能額に与える影響
- 年収399万円:借入可能額約2700万円
- 年収400万円:借入可能額約3330万円
- 差額:約630万円
年収399万円の方が400万円になるだけで、630万円も多く借りることができます。昇給のタイミングで住宅ローンを申し込むことで、より有利な条件での借入が可能になります。
他の借入完済の重要性と効果
返済負担率はすべての借入の年間返済額で計算されるため、住宅ローン以外の借入がある場合は大幅に借入可能額が減少します。
年収400万円で他の借入がある場合の影響
他の借入なし
- 住宅ローンに充てられる年間返済額:140万円
- 借入可能額:約3330万円
カーローン月3万円(年36万円)がある場合
- 住宅ローンに充てられる年間返済額:104万円
- 借入可能額:約2500万円
- 減額:約830万円
完済すべき借入の優先順位
- 消費者金融・クレジットカードリボ(金利15~18%)
- カードローン(金利10~15%)
- クレジットカード分割払い(金利12~15%)
- 自動車ローン(金利2~5%)
- 奨学金(金利0~2%)
金利の高い借入から優先的に完済することで、住宅ローンの借入可能額を最大化できます。
金融機関選びと審査対策
年収400万円で高額借入を目指す場合、金融機関の特徴を理解して戦略的に選択することが重要です。
フラット35の活用メリット
フラット35は住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利の住宅ローンで、年収400万円の方にとって以下のメリットがあります。
フラット35の特徴
- 最低年収の制限なし
- 雇用形態の制約が少ない(派遣・契約社員も利用可能)
- 年収400万円以上で返済負担率35%以内
- 団体信用生命保険への加入は任意
- 物件の技術基準をクリアすれば金利優遇あり
年収400万円ぴったりの方や、雇用形態に不安がある方にとって、フラット35は最も利用しやすい住宅ローンの一つです。
民間金融機関の特徴と選び方
民間金融機関は商品の種類が豊富で、金利や条件が多様です。年収400万円での高額借入を目指す場合の選び方のポイントを整理します。
金融機関別の特徴
都市銀行
- 金利水準:やや高め(0.5~1.0%)
- 審査:厳格、年収や勤続年数の要件が厳しい
- 優遇制度:給与振込、資産運用など総合取引での優遇
- 適用対象:安定した大企業勤務者、高年収者
地方銀行・信用金庫
- 金利水準:中程度(0.6~1.2%)
- 審査:地域密着型、柔軟な対応
- 優遇制度:地元企業勤務、地域貢献での優遇
- 適用対象:地域在住・在勤者、中小企業勤務者
ネット銀行
- 金利水準:低め(0.3~0.8%)
- 審査:システム化、客観的基準重視
- 優遇制度:手数料体系がシンプル、疾病保障充実
- 適用対象:ネット活用に抵抗がない、手続きの簡素化重視
複数行での事前審査の重要性
年収400万円で3500万円以上の借入を目指す場合、以下の観点で複数の金融機関を比較検討することが重要です。
事前審査で比較すべきポイント
- 借入可能額の上限:同じ年収でも金融機関により200万円~500万円の差
- 金利水準と優遇条件:店頭金利からの優遇幅
- 審査の厳格さ:承認確率、減額の可能性
- 手数料体系:融資手数料、繰上返済手数料、保証料
- 疾病保障等の付帯サービス:がん保障、全疾病保障
事前審査は通常無料で、信用情報への影響も限定的です。年収400万円で高額借入を検討する場合は、必ず3~5行で条件を比較し、最も有利な条件を見つけることが成功の鍵となります。
年収400万円に適した物件価格と購入の方法
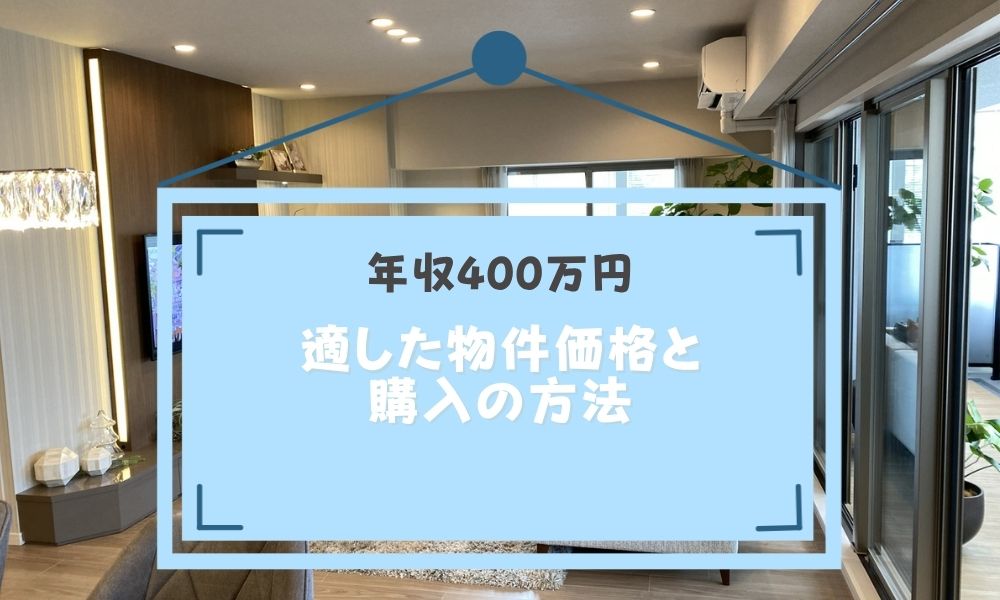
年収400万円での住宅購入を成功させるには、借入額に応じた現実的な物件選択が重要です。地域別の価格動向も含めて、最適な購入の仕方を検討しましょう。
借入額別の物件選択戦略
年収400万円での借入可能額に応じて、どのような物件が購入できるかを具体的に見てみましょう。
2200万円借入(安全圏)での物件選択
この水準は最も安全で、将来的なリスクが少ない借入額です。
物件選択の枠組み
- 頭金300万円 + 借入2200万円 = 物件価格2500万円
- 月々返済額:約6.4万円(手取り収入の25%)
- 対象物件:中古マンション、中古戸建て中心
- 購入後の家計:十分な余裕、繰り上げ返済も可能
2500万円物件で購入できる住宅例
- 中古マンション:3LDK、築10~15年、最寄り駅徒歩10分以内
- 中古戸建て:3~4LDK、築15~20年、土地面積100㎡以上
- 新築戸建て:地方都市の郊外、2~3LDK、土地面積80㎡程度
この価格帯では新築物件の選択肢は限られますが、中古物件であれば十分に良質な住宅を購入できます。特に地方都市では築10年以内の中古戸建ても視野に入ります。
2800万円借入(やや背伸び)での物件選択
この水準は家計管理をしっかり行えば対応可能な借入額です。
物件選択の枠組み
- 頭金400万円 + 借入2800万円 = 物件価格3200万円
- 月々返済額:約8.2万円(手取り収入の32%)
- 対象物件:新築戸建て、築浅中古住宅
- 購入後の家計:やや厳しいが管理可能
3200万円物件で購入できる住宅例
- 新築戸建て:地方都市、3~4LDK、土地面積120㎡程度
- 築浅中古戸建て:首都圏郊外、3~4LDK、築5年以内
- 新築マンション:地方都市、3LDK、駅徒歩5分以内
この価格帯になると、地方都市では新築戸建ての選択肢も出てきます。ただし、月々8万円超の返済は家計に与える影響が大きく、将来の教育費増加時期には注意が必要です。
3500万円借入(要夫婦合算)での物件選択
この水準は夫婦合算が前提となる借入額です。
物件選択の枠組み
- 頭金500万円 + 借入3500万円 = 物件価格4000万円
- 世帯年収600万円想定(夫400万円+妻200万円)
- 月々返済額:約10.2万円(世帯手取りの27%)
- 対象物件:新築戸建て、新築マンション
4000万円物件で購入できる住宅例
- 新築戸建て:首都圏郊外、4LDK、土地面積100㎡以上
- 新築マンション:地方中核都市、3~4LDK、駅徒歩3分以内
- 注文住宅:地方都市、希望に合わせた設計
夫婦合算であれば、この価格帯の新築住宅も現実的な選択肢となります。ただし、配偶者の収入が将来も安定して続くことが前提条件となります。
新築vs中古の現実的な選択
年収400万円での住宅購入では、物件種別による価格差を理解して選択することが重要です。
中古マンションの魅力と注意点
住宅金融支援機構の調査によると、中古マンションの平均購入価格は約2500万円です。年収400万円の借入可能額にぴったりマッチする価格帯といえます。
中古マンションのメリット
- 立地条件が良い物件を選べる:駅近、都心部でも予算内
- 修繕積立金で大規模修繕に備えられる:個別負担なし
- 管理体制が整っている:管理会社による維持管理
- 資産価値の下落が比較的緩やか:立地重視の価値
中古マンションの注意点
- 管理費・修繕積立金の継続負担:月2万円~4万円
- 修繕積立金の値上がりリスク:築年数とともに増加
- 管理組合の運営状況:購入前の確認が必要
- 専有部分のリフォーム制約:管理規約による制限
中古戸建ての検討ポイント
中古戸建ての平均購入価格は約2400万円で、年収400万円に適した価格帯です。
中古戸建てのメリット
- 土地資産を持てる:建物が古くなっても土地価値は残る
- 管理費・修繕積立金がかからない:月々の固定費削減
- リフォームで自分好みにカスタマイズ可能:間取り変更も自由
- 駐車場代が不要:車を持つ家庭には大きなメリット
中古戸建ての注意点
- 建物の劣化状況の把握:構造、設備の詳細チェック必要
- 修繕費の自己負担:屋根、外壁、設備更新すべて自費
- セキュリティ面での不安:マンションに比べて劣る
- 売却時の流動性:マンションより売りにくい場合がある
新築住宅への憧れと現実
新築戸建ての平均価格は約3400万円、新築マンションは約4600万円となっており、年収400万円単独では厳しい価格帯です。
新築を希望する場合の現実的な選択肢
- 夫婦合算での借入:世帯年収600万円以上が前提
- 頭金を大幅に用意:1000万円以上で借入額を圧縮
- 建売住宅や郊外立地での妥協:立地・仕様のグレードダウン
- 建物面積や設備のグレードダウン:コストカットで予算内に
新築のメリット
- 最新の設備・性能:省エネ、耐震、バリアフリー
- 当面の修繕不要:10年程度は大きな修繕なし
- 住宅ローン控除の優遇:借入限度額が高い
- 心理的満足感:誰も住んでいない新しい家
新築のデメリット
- 価格が高い:中古の1.3~1.5倍程度
- 立地制約:予算内では郊外になりがち
- 購入後の価値下落:新築プレミアム分の下落
地域別の購入可能性
住宅価格は地域によって大きく異なります。年収400万円での購入可能性を地域別に詳しく検証してみましょう。
首都圏での現実的な選択
首都圏の住宅価格は全国平均を大きく上回っており、年収400万円での新築購入は困難です。
首都圏の住宅価格相場
- 新築戸建て:4000万円~6000万円
- 新築マンション:5000万円~8000万円
- 中古戸建て:3000万円~4500万円
- 中古マンション:3000万円~5000万円
年収400万円での現実的な選択肢は限定され、中古マンションなら築15年以上で最寄り駅徒歩15分以上の物件、中古戸建てなら築20年以上で都心から1時間以上の立地が中心となります。夫婦合算により世帯年収600万円以上を確保できれば、新築住宅購入も視野に入りますが、立地や広さでの妥協が必要です。
関西圏での購入可能性
関西圏は首都圏より価格が抑えられており、年収400万円でもやや選択肢が広がります。
関西圏の住宅価格相場
- 新築戸建て:3000万円~4500万円
- 新築マンション:3500万円~5500万円
- 中古戸建て:2000万円~3500万円
- 中古マンション:2000万円~3500万円
年収400万円での現実的な選択肢として、中古住宅全般で築10年程度まで視野に入り、郊外立地なら夫婦合算により新築戸建ても可能です。地方部では新築マンションも単独借入で検討できる価格帯となっています。
地方中核都市での新築住宅購入
地方中核都市では、年収400万円でも新築住宅購入の可能性が高まります。
地方中核都市の住宅価格相場
- 新築戸建て:2500万円~3500万円
- 新築マンション:2800万円~4000万円
- 中古戸建て:1500万円~2500万円
- 中古マンション:1800万円~2800万円
年収400万円での現実的な選択肢として、頭金準備または夫婦合算により新築戸建ても十分可能で、中古住宅なら築浅物件も選択できます。立地にこだわらなければ新築マンションも単独借入で購入可能です。
地方都市・郊外エリアでの理想的な住宅購入
地方都市では年収400万円でも十分に新築住宅を購入できます。
地方都市の住宅価格相場
- 新築戸建て:2000万円~3000万円
- 新築マンション:2000万円~3000万円
- 中古戸建て:1000万円~2000万円
年収400万円なら単独借入でも新築住宅購入が現実的であり、注文住宅によるこだわりの家づくりも予算内で可能です。中古住宅なら築浅の優良物件を低価格で購入でき、住宅ローン以外の生活費も抑えられるため、最も無理のない住宅購入が可能です。ただし、将来的な転勤や転職の可能性、物件の資産価値、売却時の流動性なども考慮して選択することが重要です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
金利タイプ別の借入戦略といくらまで借りるべきか

住宅ローンの金利タイプによって、年収400万円で安全に借りられる金額は大きく変わります。それぞれの特徴とリスクを詳しく理解し、適切な借入額を設定しましょう。
変動金利選択時は2800万円以下が安全
変動金利は現在の住宅ローンの主流で、利用者の約7割が選択しています。低金利の魅力がある一方、金利上昇リスクを考慮した借入額設定が重要です。
変動金利の仕組みと現在水準
変動金利は半年ごとに金利を見直し、5年ごとに返済額を見直す仕組みになっています。また、返済額の上昇は前回の1.25倍までに制限されています(125%ルール)。2025年現在、主要銀行の変動金利は0.3%~0.7%程度の歴史的な低水準で推移していますが、将来的な金利上昇の可能性は常にあります。
日本銀行の金融政策変更、海外金利の上昇、インフレ率の上昇などが金利上昇の要因となり得ます。変動金利で年収400万円の場合、金利上昇を考慮した安全な借入額は2800万円以下とすることをおすすめします。
金利水準別の返済額シミュレーション(35年返済)
現在金利0.5%の場合
- 2800万円借入:月々約7.2万円(手取りの28%)
- 3500万円借入:月々約9.0万円(手取りの35%)
- 4000万円借入:月々約10.3万円(手取りの40%)
金利が1.5%に上昇した場合
- 2800万円借入:月々約8.6万円(手取りの33%)
- 3500万円借入:月々約10.7万円(手取りの41%)
- 4000万円借入:月々約12.2万円(手取りの47%)
金利が2.5%に上昇した場合
- 2800万円借入:月々約10.0万円(手取りの38%)
- 3500万円借入:月々約12.5万円(手取りの48%)
- 4000万円借入:月々約14.3万円(手取りの55%)
2800万円以下の借入であれば、金利が2.5%まで上昇しても月々返済額は10万円に留まり、手取り収入の38%以内に収まります。一方、3500万円や4000万円の借入では、金利上昇時に家計が破綻する可能性が高くなります。
5年ルール・125%ルールの落とし穴
変動金利の5年ルールや125%ルールは、金利上昇の影響を先送りするだけで根本的な解決にはなりません。未払い利息の発生により元本が増加し、返済期間の延長や総返済額の増加、完済時の一括返済リスクなどの問題が生じる可能性があります。年収400万円で高額借入を行う場合、これらのリスクは致命的になる可能性があります。
固定金利なら3500万円程度が上限
フラット35などの全期間固定金利は、返済額が変わらないため長期的な返済計画を立てやすいメリットがあります。
固定金利の特徴と現在水準
借入時の金利が完済まで継続し、毎月の返済額が変わらないため将来の家計管理がしやすく、計画性を重視する方に適しています。2025年現在、フラット35の金利は1.5%~1.8%程度で推移しています。この金利は市場金利に連動して決まり、申込み時点ではなく融資実行時の金利が適用されます。
フラット35(金利1.6%・35年返済)での返済額
- 3000万円借入:月々約9.1万円(手取りの35%)
- 3500万円借入:月々約10.6万円(手取りの41%)
- 4000万円借入:月々約12.1万円(手取りの47%)
固定金利でも年収400万円で3500万円を超える借入は家計負担が重く、4000万円の借入は現実的ではありません。3500万円が実質的な上限と考えるべきです。
固定金利のメリット・デメリット
固定金利のメリット
- 返済計画が立てやすい:35年間返済額が変わらない
- 金利上昇リスクがない:インフレや金利上昇局面で有利
- 家計管理がしやすい:毎月の支出が一定
- 将来の教育費等の準備がしやすい:収支計画が明確
固定金利のデメリット
- 変動金利より金利が高い:当初の返済負担が重い
- 金利低下の恩恵を受けられない:金利下降局面では不利
- 繰り上げ返済のメリットが限定的:低金利時代では効果薄
借入額に応じた金利タイプの選択
借入額の大きさによって、最適な金利タイプは変わってきます。年収400万円での借入額別に最適な選択を検証してみましょう。
2200万円以下の借入の場合
この金額レベルであれば、変動金利・固定金利どちらを選んでも大きなリスクはありません。
変動金利0.5%の場合
- 月々返済額:約5.7万円(手取りの22%)
- 金利2.0%上昇時:約6.8万円(手取りの26%)
固定金利1.6%の場合
- 月々返済額:約6.7万円(手取りの26%)
- 35年間変動なし
どちらも手取り収入の30%以内に収まり、金利上昇があっても対応可能な範囲です。この場合の選択基準は、金利重視・リスク許容度が高ければ変動金利、安心感重視・計画性重視なら固定金利、将来の金利動向予測で上昇予想なら固定、横ばい予想なら変動となります。
2800万円~3000万円の借入の場合
この価格帯では金利タイプの選択が重要になります。
変動金利0.5%の場合
- 月々返済額:約7.2万円~7.7万円(手取りの28~30%)
- 金利2.0%上昇時:約8.6万円~9.2万円(手取りの33~35%)
固定金利1.6%の場合
- 月々返済額:約8.5万円~9.1万円(手取りの33~35%)
この水準では、変動金利なら当初の家計負担は軽いですが金利上昇リスクを考慮する必要があり、固定金利は安心ですが月々の負担が重くなります。選択の判断基準として、家計に余裕があれば変動金利で当初負担軽減、リスクを避けたいなら固定金利で安定性確保、繰り上げ返済計画があれば変動金利で利息軽減効果大となります。
3500万円以上の借入の場合
この金額になると、金利タイプに関わらずリスクが高くなります。
変動金利0.5%の場合
- 月々返済額:約9.0万円(手取りの35%)
- 金利2.0%上昇時:約10.7万円(手取りの41%)
固定金利1.6%の場合
- 月々返済額:約10.6万円(手取りの41%)
どちらを選んでも手取り収入に対する負担率が高く、変動金利では金利上昇時の家計破綻リスク、固定金利では高い返済負担による生活圧迫リスクがあります。
年収400万円での金利タイプ選択指針
借入額別の推奨金利タイプ
- 2200万円以下:リスク許容度に応じてどちらでも可
- 2800万円~3000万円:リスク許容度と家計状況で判断
- 3500万円以上:固定金利推奨(返済計画の安定性重視)
年収400万円で高額借入を行う場合、変動金利の金利上昇リスクは致命的になる可能性があるため、固定金利での安定した返済計画を立てることを強く推奨します。ただし、固定金利でも借入額が多すぎると家計が圧迫されるため、借入額自体を抑えることが最も重要です。
住宅ローン返済中のリスクと対策

年収400万円で住宅ローンを組んだ後に想定されるリスクと、それに対する具体的な対策について詳しく解説します。特に高額借入を行った場合のリスクは深刻で、事前の対策が重要です。
年収400万円で高額借入時の将来リスク
年収400万円で3000万円を超える住宅ローンを組んだ場合、ライフステージの変化に伴って様々なリスクに直面する可能性があります。
教育費ピーク時の家計圧迫
子供の成長に伴い、教育費は段階的に増加していきます。
小学生時期は公立で年間約35万円、私立で約160万円が必要で、学習塾や習い事を加えると年間50万円~100万円の負担となります。中学生時期は公立で約50万円、私立で約140万円に加え、学習塾費が年間80万円~150万円必要です。高校生時期は公立で約50万円、私立で約100万円ですが、予備校や塾費用が年間100万円~200万円と高額になります。
最も負担が重いのは大学生時期で、国立大学でも年間55万円、私立大学文系で年間120万円~150万円、理系で年間150万円~200万円が必要です。下宿する場合は生活費として年間100万円~150万円が追加で必要となります。年収400万円で3500万円借入(月々10.2万円返済)している家庭では、子供が大学生になると教育費だけで月15万円~25万円が必要となり、手取り26万円から住宅ローン返済を差し引いた残りでは明らかに不足します。
住宅維持費の継続的負担
住宅購入後は、住宅ローン返済以外にも継続的な費用が発生します。固定資産税は評価額の1.4%で戸建てなら年間15万円~25万円、都市計画税も対象地域では追加で必要です。火災保険料は年間2万円~4万円、地震保険料は年間1万円~3万円が必要で、戸建ての場合は外壁塗装(10年ごとに100万円~200万円)、屋根修繕(15年ごとに50万円~100万円)、設備更新費用も計画的に準備する必要があります。
マンションの場合は管理費月1万円~2万円、修繕積立金月1万円~3万円が継続的に必要です。これらの費用を年間で合計すると、戸建てで30万円~50万円、マンションで40万円~70万円の追加負担となり、月換算では2.5万円~6万円の支出増加です。
定年時のローン残高リスク
年収400万円で高額借入を行った場合、定年時のローン残高が大きくなるリスクも深刻です。
35歳で3500万円を借入した場合、定年(60歳)時の残高は約1800万円、65歳時でも約1300万円が残り、退職金での完済は困難です。4000万円借入の場合はさらに深刻で、定年時残高が約2000万円を超える可能性があります。理想的な定年時ローン残高は1000万円以下とされており、年収400万円で高額借入を行う場合は計画的な繰り上げ返済が必要不可欠です。
返済困難時の対処法
想定外の事態で住宅ローンの返済が困難になった場合の対処法を知っておくことで、早期に適切な対応を取ることができます。
繰り上げ返済による負担軽減
家計に余裕がある時期に繰り上げ返済を行うことで、将来の返済負担を軽減できます。繰り上げ返済には期間短縮型と返済額軽減型があり、期間短縮型では返済期間を短くして総返済額を大幅削減でき、返済額軽減型では毎月の返済額を下げて家計負担を軽減できます。
年収400万円で3000万円借入の場合、100万円の繰り上げ返済により期間短縮型では約2年短縮・利息軽減約160万円、返済額軽減型では月々返済額約3000円減となります。繰り上げ返済は早期に行うほど効果が大きく、ボーナスや昇給分を計画的に充てることで大幅な負担軽減が可能です。
借り換えによる金利負担軽減
金利環境の変化や借入当初より信用力が向上した場合、より有利な条件の住宅ローンに借り換えることで返済負担を軽減できます。借り換えのメリットが出る目安は金利差0.5%以上、残高1000万円以上、残期間10年以上とされていますが、借り換えには手数料(50万円~80万円程度)がかかるため、総合的な損益計算が必要です。
条件変更による一時的な負担軽減
返済が困難になった場合、金融機関に条件変更を相談することもできます。返済期間の延長により月々返済額を軽減したり、一定期間の元本据え置きで利息のみ返済したり、ボーナス返済を取りやめることが可能な場合があります。ただし、条件変更を行うと信用情報に記録が残り、将来の借入に影響する可能性があります。
他の対策では解決できない場合の最終手段として、住宅を売却して住み替えを行う選択肢もありますが、住宅ローン残高が売却価格を上回る場合は差額の準備が必要で、売却費用も考慮する必要があります。年収400万円で高額借入を行った場合、将来的に売却を余儀なくされるリスクも考慮して、資産価値の下落しにくい物件を選ぶことが重要です。
無理のない返済を続けるための工夫
年収400万円で住宅ローンを組んだ後、長期間にわたって安定した返済を続けるための具体的な工夫を実践することが重要です。
住宅ローン控除の最大活用
住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高の0.7%(上限35万円)が所得税・住民税から控除される制度ですが、年収400万円の場合は所得税額約5万円~8万円、住民税額約15万円~20万円で、控除可能額は合計20万円~28万円程度となります。住宅ローン残高が3000万円を超えても控除額は頭打ちになる可能性があるため、高額借入のメリットは限定的です。
ボーナス払いのリスクと対策
ボーナス払いを併用すると月々の返済額を抑えられますが、ボーナスカットや減額のリスク、転職時の制度変更リスク、年2回の大きな支出による家計管理の困難などの問題があります。年収400万円の場合、ボーナスに依存しない安定した返済計画を立てることを強く推奨します。
定期的な家計見直しと繰り上げ返済計画
住宅ローンは長期間にわたる返済のため、年1回の家計見直しにより収入の変化(昇給・転職等)、支出の変化(教育費・医療費等)、金利環境の変化、繰り上げ返済の検討を行うことが重要です。年収400万円で2500万円借入の場合、年間50万円の繰り上げ返済を10年間続けることで、返済期間を約8年短縮し、利息負担を約300万円軽減できます。
緊急時の資金確保
住宅ローン返済中は、緊急時に備えた資金確保も重要です。最低限として生活費6ヶ月分(年収400万円なら160万円程度)、理想的には生活費1年分(年収400万円なら320万円程度)を緊急資金として確保しておく必要があります。年収400万円で高額借入を行う場合、頭金を多く入れすぎて緊急資金が不足しないよう注意が必要で、頭金と緊急資金のバランスを考慮した資金計画を立てることが重要です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
年収400万円の住宅ローン実例とよくある質問

ここでは実際の事例を通じて年収400万円での住宅ローン利用パターンを確認していきましょう。
成功事例と失敗事例
年収400万円での住宅ローン利用について、実際の事例をもとに成功パターンと注意すべきパターンを紹介します。
堅実な借入で安定した生活を維持している事例
年収400万円の35歳会社員が2200万円を借入し、中古マンション2500万円(頭金300万円)を購入しました。月々返済額は6.4万円で手取りの25%に抑え、住宅購入後も安定した家計を維持できています。子供の教育費や車の買い替えなどの大きな支出にも対応でき、10年間で300万円の繰り上げ返済も実施し、返済期間を5年短縮して利息負担を150万円軽減しました。
この事例では、無理のない借入額に抑えたことで、長期的な安定性を確保できています。
夫婦合算で理想の住宅を購入した事例
夫年収400万円、妻年収200万円(世帯年収600万円)でペアローン3200万円を組み、新築戸建て3800万円(頭金600万円)を購入しました。月々返済額は夫7万円+妻3.5万円の計10.5万円で世帯手取りの28%となり、それぞれが住宅ローン控除を受けられるため税制上のメリットも大きく、安定した返済を続けています。
夫婦合算により、単独では困難な新築住宅購入を実現した成功例です。
借入額が多く家計が圧迫された事例
年収400万円の30歳会社員が3500万円を借入し、新築戸建て3500万円を頭金なしで購入しました。月々返済額は10.2万円で手取りの39%を占め、当初は「家賃と変わらない」と考えていましたが、固定資産税、住宅維持費、子供の教育費増加により家計が圧迫されました。5年後には貯蓄がほぼゼロになり、車の買い替えもできない状況となり、現在は返済期間延長を検討しています。
金利上昇で返済困難に陥った事例
年収400万円の28歳会社員が4000万円を変動金利で借入し、新築マンション4000万円を頭金なしで購入したケースでは、当初月々返済額は10.3万円(金利0.5%)でしたが、金利上昇により13.2万円(金利2.0%)まで増加し、手取り26万円に対して51%を占めるようになりました。これでは生活が成り立たず、現在は売却を検討していますが、購入価格を下回る可能性が高く、数百万円の持ち出しが必要な状況です。
よくある質問とその回答
年収400万円での住宅ローンについて、特に多く寄せられる質問を見ていきましよう。
Q. 月々10万円の返済は無謀?
年収400万円の手取り26万円に対して10万円の返済(38%)は危険水域です。食費、光熱費、教育費、貯蓄を16万円で賄う必要があり、家計が破綻するリスクが高くなります。さらに固定資産税等の住宅関連費用を考慮すると、実質的に家計収支が赤字になる可能性があります。
Q. 年収が下がった場合の対処法は?
まず金融機関に相談し、返済期間の延長や条件変更を検討します。それでも困難な場合は、借り換えや最終的には売却も視野に入れる必要があります。年収が10%以上下がった場合は、早急に家計の見直しと金融機関への相談を行うことが重要です。
Q. 転職直後でも借りられる?
一般的に勤続1年以上が条件ですが、フラット35なら転職直後でも借入可能な場合があります。ただし、前職と同業種で年収アップの転職であることが望ましいです。転職による年収変化や雇用の安定性について、金融機関に十分な説明ができるよう準備が必要です。
Q. ボーナス払い併用のメリット・デメリットは?
メリットは月々返済額の軽減ですが、ボーナスカットリスクがあります。年収400万円の場合、ボーナスに依存しない安定した返済計画を推奨します。ボーナス払いを利用する場合は、ボーナス分を別途貯蓄しておき、万一の時に対応できるよう備えることが重要です。
Q. 審査に落ちる主な原因は?
他の借入が多い、勤続年数が短い、個人信用情報に問題がある、返済負担率が基準を超えているなどが主な原因です。事前に信用情報を確認し、他の借入を整理することが重要です。年収400万円の場合、カーローン等があるだけで大幅に借入可能額が減少するため、住宅ローン申込前の借入整理は必須です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
まとめ
この記事では、年収400万円での住宅ローンについて詳しく解説してきました。最も重要なのは「借りられる額」ではなく「返せる額」で判断することです。
金融機関が提示する借入可能額上限は4000万円となる場合もありますが、現実的ではありません。現実的な上限は3500万円で、夫婦合算や大幅な頭金が必要です。無理なく返せる額は2200万円で、手取り収入の25%以内に抑えることで安定した生活を維持できます。
ぜひこの記事も参考にしながら、理想的なローンの金額を見極めてみてくださいね!
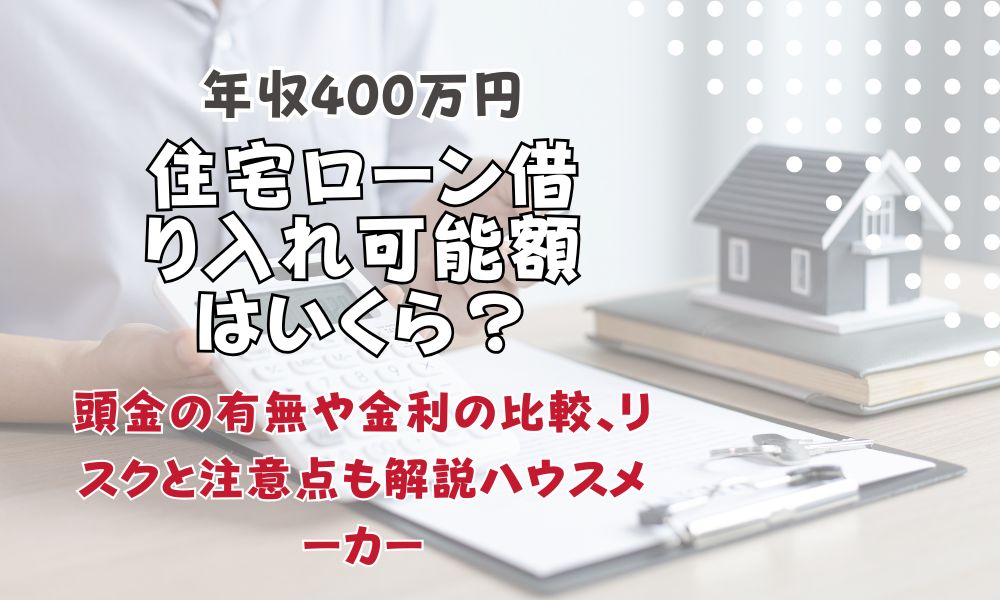
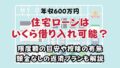

コメント