スウェーデンハウスは坪単価100万円を超える高価格帯でありながら、多くの人から選ばれ続けています。
その理由として、温かみのある北欧デザイン、冬の厳しい寒さや夏の蒸し暑さを忘れさせるほどの圧倒的な断熱・気密性能、そして愛着を持って住み継いでいくことを前提としたサスティナブルな家づくりが挙げられます。
しかし、その一方で、高額な建築費用や、木製サッシのメンテナンスなど、契約前に必ず知っておくべき現実も存在します。
憧れだけで選んで後悔しないために、その特性を正しく理解することが不可欠です。
そこでこの記事では、スウェーデンハウスの価格の理由から、「感動レベル」と言われている快適性、そして契約後に後悔しないための具体的なチェックポイントまで解説していきます。
ぜひ最後まで参考にしてみてくださいね!
本文に入る前に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えしておきます。
家づくりで一番大切なこと、それは「気になっているハウスメーカーを徹底的に比較検討すること」です。
よくある失敗パターンとして、住宅展示場に行って営業マンの巧みなトークに流されその場で契約をしてしまうというケースがあります。実際に、「もしもしっかりと比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
だからこそ、きちんとした比較検討をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
ではどのように比較検討すればいいのでしょうか。
その方法は、「ハウスメーカーのカタログをとりあえず集めてしまうこと」なんです!

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、全ての会社に連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのようにカタログを集めていいのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしい無料で利用できるサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記のサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。 |
LIFULL HOME'Sのカタログ請求は完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
後悔のない家づくりのために、1社でも多くの会社を比較検討してみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫
家づくりで後悔しないために、このサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
スウェーデンハウスとは

スウェーデンハウスは、単に北欧「風」のデザインを取り入れた住宅ではなく、スウェーデン本国の厳しい自然環境と豊かな住文化の中で育まれた「本物の木の家」を日本で提供する、輸入住宅専門のハウスメーカーです。
スウェーデンの家づくり
スウェーデンハウスの家づくりを理解する上で欠かせないのが、その背景にあるスウェーデンの気候と文化です。
北欧の冬は長く、日照時間も短いため、人々は家の中で過ごす時間を非常に大切にします。
家族や友人と暖炉を囲み、温かい光の中で語らう時間を「MYSIGT(ミーシグ)」(心地よい、の意)と呼ぶなど、家は単なる生活の箱ではなく、人生を豊かにするための最も重要な場所として位置づけられています。
このような文化が、快適で居心地の良い空間を追求する家づくりの原点となっています。
北欧デザイン
スウェーデンハウスの外観を特徴づける大きな三角屋根は、デザイン的な美しさだけでなく、積雪地域では雪が自然に滑り落ちやすく、雪下ろしの負担を軽減するという機能的な役割も果たします。
温かみのある木製サッシは、高い断熱性能を発揮すると同時に、年月を経るごとに味わいを増し、家の表情を豊かにしていきます。
内装に目を向ければ、床や壁、天井にふんだんに使われるパイン材などの自然素材が、心地よい木の香りとぬくもりで住む人を優しく包み込みます。
また、冬の日差しを最大限に室内に取り込むための窓の配置計画など、自然の恵みを巧みに活かす設計思想も北欧デザインならではの特徴です。
高品質な部材と徹底した品質管理
美しいデザインを支えているのが、見えない部分への徹底したこだわりです。
家の骨格となる構造材には、スウェーデン北部で産出される樹齢80年前後の「オウシュウアカマツ」が使われています。
厳しい寒さの中でゆっくりと時間をかけて育った木は、年輪の目が細かく詰まっており、高い強度と耐久性を誇ります。
これらの高品質な木材は、スウェーデンの自社工場で高精度に加工され、壁となる木質パネルや木製サッシ3層ガラス窓といった主要なパーツがユニットとして生産されます。
これを日本に輸送し、現場で組み立てることで、職人の技術力や天候に左右されることのない、均一で極めて高い品質の住まいを実現しているのです。
50年間のサポート
スウェーデンハウスが提供する価値は、建物そのものだけではありません。
業界でも類を見ない50年間無料の定期検診システム「HUSドクトル50」は、家を建てた後も長期にわたってオーナーに寄り添い続けるという、メーカーとしての強い意志の表れです。
定期的に専門家が住まいの健康状態をチェックすることで、問題の早期発見につながり、適切な時期のメンテナンスを可能にします。
これは結果的に、将来的な大規模修繕のリスクやコストを抑制することにも繋がります。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
スウェーデンハウスのメリット

スウェーデンハウスが多くの人々から高い評価と信頼を得ている背景には、数々のメリットが存在します。
1. 高気密・高断熱性能
スウェーデンハウスの最大の強みであり、多くのオーナーが「住んでみて最も感動した」と口を揃えるのが、極寒の地で培われた圧倒的な高気密・高断熱性能です。
これは、夏の蒸し暑さや冬の厳しい寒さが存在する日本において、一年を通して心身ともに健康で快適な暮らしを実現するための根幹となる性能です。
3つの技術
スウェーデンハウスの快適さは、主に3つの要素によって実現されています。
- 木製サッシ3層ガラス窓: 家の断熱性能を左右する最大の弱点である「窓」に、徹底的にこだわっています。熱伝導率がアルミの約1700分の1という木材をサッシに採用。 さらに、厚さ4mmのガラスを3枚重ね、その間に乾燥空気を封入した2つの中空層を設けることで、壁とほぼ同等の断熱性能を発揮します。これにより、窓辺のヒンヤリ感や、夏の強烈な日差しによる室温上昇を劇的に抑制します。
- 隙間なく充填される分厚い断熱材: 天井には300mm、壁には120mm、そして床には一般的なハウスメーカーの3倍以上にもなる200mm(北海道エリアは220mm)という分厚い高性能グラスウール断熱材を、隙間なく施工します。 家全体を高性能な断熱材でまるごと包み込むことで、外気の影響をほとんど受けない安定した室内環境を創り出します。
- 徹底した気密施工: どれだけ高性能な断熱材を使っても、家に隙間があれば熱は逃げてしまいます。スウェーデンハウスでは、壁や床の継ぎ目にグラスウールを挟み込み、さらにその上から防湿・気密フィルムを丁寧に貼ることで、徹底的に隙間をなくす施工を行っています。
性能を「実測値」で保証
スウェーデンハウスは、1999年という早い段階から、一棟一棟すべての家で断熱性能(Q値・UA値)の計算と気密性能(C値)の測定を行い、その数値を「性能報告書」としてオーナーに提出する「全棟高性能保証表示システム CQ+24」を実施しています。
特に、家の隙間の総量を表すC値は、実測しなければ本当の性能はわかりません。
これを全棟で実施し、平均C値0.64㎠/㎡という業界トップクラスの数値を叩き出している事実は、性能に対する自信と誠実さの証です。
高性能で豊かな暮らし
性能は、私たちの暮らしに具体的で豊かなメリットをもたらします。
- 温度のバリアフリー: 冬場でもリビングと廊下、脱衣所の温度差がほとんどなく、ヒートショックのリスクを大幅に軽減します。家中どこにいても快適なため、活動範囲が広がり、家族のコミュニケーションも自然と増えるでしょう。
- 光熱費の大幅な削減: 「魔法瓶」のような家は、冷暖房の効率が非常に高く、一度快適な温度になるとそれを長時間維持できます。そのため、月々の光熱費を大幅に削減することが可能となり、長期的に見れば経済的なメリットも非常に大きくなります。
- 健康的な空気環境: 高気密と聞くと息苦しいイメージがあるかもしれませんが、計画的な換気が可能な「24時間熱交換型換気システム」を組み合わせることで、常に新鮮な空気を保ちます。また、室内外の温度差に起因する結露の発生をほぼゼロに抑えるため、アレルギーの原因となるカビやダニの繁殖を防ぎ、クリーンで健康的な住環境を実現します。
- 卓越した遮音性: 高気密な家は、音の侵入も防ぎます。外の車の音や雨音が気にならない静かな室内は、読書や音楽鑑賞に集中したい時や、安らかな眠りを求める上で大きな価値となります。
2. 優れた耐震性
地震大国である日本において、家の耐震性は家族の命と財産を守るための最重要項目です。
スウェーデンは地震が少ない国ですが、スウェーデンハウスは日本の建築基準を遥かに超える、極めて高い耐震性を誇ります。
- 強固な「モノボックス®構造」:スウェーデンハウスの耐震性の秘密は、独自の「モノボックス®構造」にあります。 これは、壁・床・屋根の6つの面を一体化させた、強固な箱型の構造です。地震のエネルギーが加わった際、柱や筋交いといった「線」で支える在来工法とは異なり、建物全体の「面」で揺れを吸収・分散させます。これにより、力が特定の部分に集中するのを防ぎ、ねじれや変形を最小限に抑えることができるのです。この構造は、もともと何トンもの雪が積もるスウェーデンの厳しい自然環境に耐えるために開発されたものであり、その強固さが日本の地震対策にも効果を発揮します。
- 最高ランク「耐震等級3」に標準で対応:住宅性能表示制度における最高ランクである「耐震等級3」にも、全プランで対応可能です。 これは、消防署や警察署など、災害時の拠点となる建物に求められるレベルと同じ耐震性であり、大切な家族が安心して暮らし続けるための、大きな安心材料となります。
3. 時代を超えて愛される北欧デザイン性
性能面だけでなく、見る人の心を惹きつける温かく普遍的なデザインも、スウェーデンハウスの大きな魅力です。
- 街並みに映える、象徴的な外観:大きな三角屋根、温かみのある木製バルコニー、そして多彩なカラーバリエーションの外壁が織りなす外観は、まるで絵本の世界から抜け出してきたかのよう。 周囲の家とは一線を画すその佇まいは、我が家への愛着を深め、日々の暮らしに彩りを与えてくれます。
- 五感で感じる、自然素材の心地よさ:一歩家に入ると、パイン材などの無垢材をふんだんに使用した、明るく心地よい空間が広がります。 無垢材の床は素足に心地よく、木の香りはリラックス効果をもたらします。また、木には湿度を調整する性質があるため、室内の空気を快適に保つ効果も期待できます。白を基調とした内壁は、どんなインテリアとも調和し、空間をより広く明るく見せてくれます。
- 家族と共に歴史を刻む「経年美化」という価値:本物の木材は、年月を経るごとに色合いが深みを増し、美しい飴色へと変化していきます。 これは「劣化」ではなく、味わいが増す「経年美化」と呼ぶべきものです。子供たちがつけた小さな傷や日々の暮らしの跡さえも、家族の歴史を刻む大切な思い出となり、家への愛着をより一層深いものにしてくれるでしょう。
4. 50年間の無料検診
家は建てて終わりではなく、そこからが本当の付き合いの始まりです。
スウェーデンハウスは、「世代を超えて住み継ぐ」という理念を具現化するために、業界でも類を見ない手厚い長期アフターサービスを提供しています。
- 業界の常識を覆す「HUSドクトル50」:引き渡し後、50年間にわたって無料で定期検診を実施する「HUSドクトル50」は、スウェーデンハウスの大きな特徴の一つです。 引き渡し後10年間は定期的に、その後も50年目まで5年ごとに専門のスタッフが訪問し、住まいの健康状態を隅々までチェックしてくれます。 これにより、問題の早期発見・早期対応が可能となり、家の資産価値を長期にわたって維持することができます。
- オーナーとの絆を深めるサポート体制:構造躯体は初期保証10年、最長で20年の保証が付いています。また、オーナー専用のウェブサイト「グッダー」では、メンテナンス情報の提供や各種相談ができるだけでなく、オーナー同士が交流できる場も設けられています。ライフスタイルの変化に対応するためのリフォーム体制も整っており、まさに一生涯のパートナーとして、大切な住まいを見守り続けてくれる安心感があります。
スウェーデンハウスのデメリット・後悔ポイント
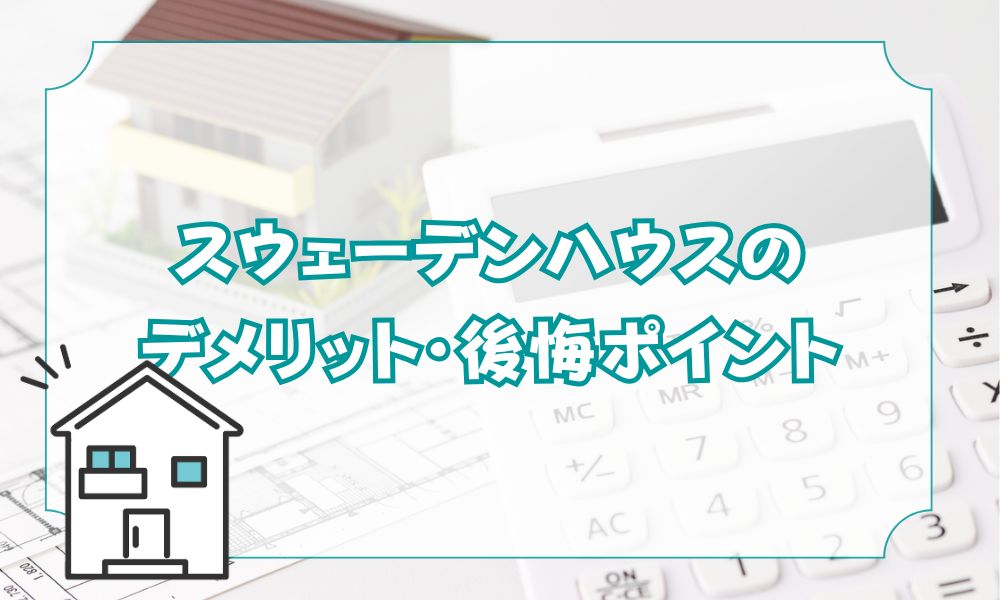
多くの魅力と卓越した性能を誇るスウェーデンハウスですが、その独自性ゆえに、契約後に「こんなはずではなかった」と感じる、いわば「後悔ポイント」も存在します。
これらは決して欠陥ではなく、スウェーデンハウスの特性や家づくりの思想から来るものです。
事前にこれらの点を深く理解し、ご自身のライフスタイル、価値観、そして予算と照らし合わせて慎重に検討することが、後悔のない家づくりを実現するための鍵となります。
1. 「建築費用の高さ」という現実
スウェーデンハウスを検討する上で、誰もが最初に直面するのが価格の問題です。
高品質な住まいであることは理解できても、その初期投資の大きさは、決して軽視できないデメリットと言えるでしょう。
- 坪単価だけではない、総額で考える必要性:スウェーデンハウスの坪単価は大手ハウスメーカーの中でもトップクラスですが、注意すべきは坪単価に含まれない費用です。 契約前には敷地調査や地盤調査、設計依頼料として7万円、さらに契約時には100万円の契約金が必要となります。 これらに加え、オプション費用、外構工事費、登記費用、火災保険料などの諸経費を合わせると、最終的な総額は想定よりも大きく膨らむ可能性があります。 北欧デザインの雰囲気を高めるためのウッドデッキや、こだわりの造作家具、照明器具などを追加していくと、オプション費用だけで数百万円に達することも珍しくありません。
- 高価格を形成する、妥協なき品質へのコスト:この価格は、単なるブランド料ではありません。スウェーデンから高品質な木材や木製サッシを輸入するための輸送費や関税、全棟で実施される気密測定などの品質管理コスト、そして一棟一棟を丁寧に作り上げるための人件費など、高い性能と品質を維持するための必然的なコストが積み重なった結果です。 言い換えれば、その価格は「安心と快適さへの対価」とも言えますが、限られた予算の中で家づくりを考える場合、この価格の高さが大きな障壁となることは紛れもない事実です。
2. メンテナンスの手間と費用
スウェーデンハウスは「建てて終わり」の工業製品ではなく、住まい手が愛情を注ぎながら共に時を重ねていく「パートナー」のような存在です。
- 最大の課題でもある「木製サッシ」のメンテナンス:スウェーデンハウスの顔とも言える木製サッシは、その美しい外観と高い断熱性能を維持するために、紫外線や雨風から木部を保護する定期的な塗装が不可欠です。 メーカーは2〜3年に1回のメンテナンスを推奨しており、これを怠ると塗膜が剥がれ、木が水分を吸って変色したり、最悪の場合は腐食して断熱性能の低下や開閉不良につながる恐れがあります。
- 北欧文化に起因する網戸の仕様と修理の問題:虫が少なく乾燥した気候の北欧では、そもそも網戸を使用する習慣がありません。そのため、スウェーデンハウスでは網戸が標準仕様ではなくオプション扱いであり、設置する場合も窓の内側に取り付けられるタイプが主流です。 これにより、「窓を開けてから網戸を閉めるため、その間に虫が入ってくる」「網戸を開けないと窓の開閉ができない」といった使い勝手の悪さを指摘する声があります。 また、輸入住宅であるため、サッシの部品や設備の修理が必要になった際、国内に在庫がなくスウェーデンから取り寄せるケースがあります。その場合、修理完了までに数週間から数ヶ月という長い時間を要する可能性も考慮しておく必要があります。
3. 「間取りの自由度」の制約
卓越した耐震性を誇る「モノボックス構造」は、スウェーデンハウスの大きなメリットですが、その構造上の特性が、間取り設計における一定の制約につながるという側面も持ち合わせています。
- 「壁」で支える構造ゆえの限界:木質パネル工法は、柱や梁ではなく「壁(耐力壁)」で建物を支える構造です。そのため、構造上どうしても取り除くことができない壁が存在し、その配置には厳格なルールがあります。これにより、近年流行しているような「柱のない30畳以上の広大なLDK」や「壁一面をガラス張りにする大開口」といった、極端に開放感を重視する間取りの実現は難しい場合があります。 間取りの自由度を最優先に考えるのであれば、在来工法や鉄骨造のハウスメーカーの方が希望を叶えやすいかもしれません。
- 窓や建具の規格とモジュールの違い:窓はスウェーデンから輸入されるオリジナルの規格品であるため、日本のハウスメーカーのようにミリ単位でサイズを調整したり、特殊な形状の窓を自由に取り入れたりすることは困難です。 これにより、窓の位置や大きさが希望通りにならない可能性があります。また、窓のサイズが特殊なため、市販のカーテンではサイズが合わず、オーダーメイドになることが多い点も、コストアップの要因となります。 さらに、スウェーデンハウスが採用する1,200mmのメーターモジュールは、一般的な910mmの尺モジュールに比べて空間にゆとりが生まれる一方、設計の細かな調整がしにくいと感じる場合もあります。
4. 「アフターフォロー」への一部不満
スウェーデンハウスは総じて顧客満足度が高いことで知られていますが、その一方で、アフターフォローの対応について、担当者や支店によって質にばらつきがあるという声が聞かれるのも事実です。
- 担当者による対応の差:ネット上の口コミは、個人の主観的な意見であり、特に悪い評判の方が目立ちやすい傾向があるため、全てを鵜呑みにするのは危険です。その上で、「定期点検の連絡が予定より遅れた」「不具合の相談をした際のレスポンスが遅い」「担当者の知識や経験に差がある」といった指摘が一部で見られます。これはあくまでネット上の数ある私見のうちの一つですが、家づくりは人対人の側面が大きいため、信頼できる担当者との出会いが満足度を大きく左右すると言えるでしょう。 契約を急がせる、質問に対して曖昧な返事をするなど、少しでも不安を感じるようであれば、担当者の変更を申し出るか、他の支店やモデルハウスを訪れてみることも一つの方法です。
5. 工期の長さ
家の主要な部材をスウェーデンの工場から船便で輸送するため、スウェーデンハウスの工期は国内生産のハウスメーカーと比較して長くなる傾向があります。
- 着工から完成まで1年以上かかる可能性も:部材の生産スケジュール、船便の運航状況、天候、そして港での通関手続きなど、国内の家づくりでは考慮する必要のない多くの不確定要素が絡んできます。 そのため、契約から引き渡しまで最低でも1年程度、場合によってはそれ以上の期間を見込んでおく必要があります。 工期が延びれば、その分だけ現在の住まいの家賃負担が増えることになります。また、お子様の入学や転勤といった、ライフイベントのタイミングに新居の完成を合わせたい場合には、かなり早い段階から計画的に動き出し、余裕を持ったスケジュールを組むことが不可欠です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
スウェーデンハウスの住宅商品・プラン

スウェーデンハウスは、画一的な住宅を提供するのではなく、魅力的な住宅商品ラインナップを用意しています。
コンセプト商品
フルオーダーに近い自由な設計思想のもと、特定のテーマやライフスタイルを深く追求するために用意された商品群です。
スウェーデンハウスが長年培ってきた設計ノウハウとデザイン性が凝縮されており、唯一無二の住まいを実現したい方に最適です。
- ヒュースプレミエ ゴーデン (HUS PREMIER GÅRDEN) :スウェーデンハウスのフラッグシップモデルであり、デザイン性、住宅性能、そして素材のすべてにおいてトップクラスを誇る最高級ラインです。スウェーデン語で「邸宅」を意味する「ゴーデン」の名を冠し、参考坪単価は85万円以上が目安となります。最大の特徴は、室内と屋外を緩やかにつなぐ半屋外空間「コンバーチブルガーデン」の設計が可能な点です。これは、床材を室内と連続させ、大きな開口部を設けることで、リビングの延長線上にあるもう一つの部屋として庭を活用する設計思想です。季節の良い日には窓を開け放ち、内と外が一体化した開放的な大空間でパーティーを開いたり、雨の日でも軒下で読書を楽しんだりと、日本の住宅にはない自然との豊かな関わり方を提案します。本物志向で、ステイタスと唯一無二の空間価値を求める方にふさわしいプランです。
- レイディアンス (RADIANCE) :隣家が密集しがちな都市部の敷地において、「最大限の採光」と「プライバシーの確保」という相反する課題を解決するために生まれた都市型住宅です。参考坪単価は82万〜100万円/坪。このプランでは、周囲の視線を気にすることなく光を取り入れるための設計工夫が随所に凝らされています。例えば、高い位置に設けたハイサイドライト(高窓)から安定した北側の光を取り入れたり、建物で囲まれた中庭(パティオ)を設けてプライベートな屋外空間を創出したりと、都市の制約を逆手に取った巧みな空間構成が魅力です。さらに、スウェーデンハウスオリジナルの制震壁パネルが標準装備されており、3階建てにも対応可能。都市の利便性を享受しながらも、静かで明るく、そして安全な暮らしを求める方に最適なソリューションです。
- ビヨルク (BJÖRK) :スウェーデン語で「白樺」を意味する名を冠した、人気の平屋建てプランです。参考坪単価は80万円以上が目安。ワンフロアで生活が完結するため、階段の上り下りがなく、将来を見据えたバリアフリー設計にしやすいのが特徴です。しかし、ビヨルクの魅力はそれだけではありません。勾配天井を活かした縦に広がる開放的なリビング空間や、すべての部屋から庭の緑を身近に感じられる設計など、平屋ならではの豊かさを最大限に引き出します。家族が常に同じフロアにいるためコミュニケーションが取りやすく、子育て世代にも、夫婦二人の穏やかな暮らしを求めるシニア世代にもフィットします。
- ミューク (MJUK) / ボーラヴォーラ (BÅLAVÅLA) :ミュークは「自分たちの暮らしを愛でる」をコンセプトに、スウェーデンの価値観である「Lagom(ラーゴム)=多すぎず、少なすぎず、ちょうど良い)」の精神を住まいに反映させます。本当に好きなもの、必要なものだけを時間をかけて揃えていく、丁寧な暮らしを求める方に寄り添うプランです。一方、ボーラヴォーラは、趣味や好きなことを満喫するための空間づくりに重点を置いています。例えば、愛車を眺められるビルトインガレージ、気兼ねなく音を出せる防音仕様の音楽室、創作活動に没頭できるアトリエなど、住まいを人生を謳歌するための「基地」として捉える方に最適です。
2. セミオーダー商品
スウェーデンハウスの基本性能やデザイン性はそのままに、あらかじめ用意された豊富な間取りや仕様のバリエーションから選んでいくことで、コストを抑え、家づくりのプロセスをシンプルにした商品群です。
- ヘンマ ベスト! (Hemma Bäst!) :スウェーデン語で「我が家が一番!」を意味するこのプランは、その名の通り多くのファミリーに支持されています。人気の理由は、プロが設計した暮らしやすい数百種類もの間取りプランと、多彩な外観・内観のカラースタイルから、パズルを組み合わせるように自分たちの好みに合わせてセレクトできる点にあります。設計を規格化することで、部材の大量発注や生産効率の向上を図り、フルオーダーに比べて建築費用を抑えることを可能にしています。スウェーデンハウスに憧れるけれど価格面で迷っている、という20〜30代の子育て世代にとって、夢を現実にするための最適な選択肢となるでしょう。
- レットナード (LÄTTNAD) / サキタテ (SAKITATE) :レットナードは、平屋の暮らしを手軽に実現する規格住宅です。屋根付きのアウトドアリビング「ルフトデッキ」が特徴で、BBQやガーデニング、休日のブランチなど、気軽にアウトドア気分を楽しめる豊かな暮らしを提案します。一方、サキタテは「20代からのスウェーデンハウス」をコンセプトに、基本性能を維持しながら仕様をシンプルに絞ることで、さらに手の届きやすい価格を実現したエントリーモデルです。テレワークに対応した書斎スペース付きのプランなど、現代の若い世代のニーズに応える20タイプのベーシックプランからカスタマイズ可能です。
3. 高性能ZEH住宅
- ヒュースエコゼロ (HUS ECO ZERO):ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、断熱性能の向上と省エネ設備の導入により消費エネルギーを減らし、太陽光発電などでエネルギーを創ることで、年間のエネルギー収支を実質ゼロ以下にすることを目指す住宅です。スウェーデンハウスは、標準仕様のままでZEHの基準をクリアできるほど断熱・気密性能が極めて高いため、他社のように断熱性能を上げるための追加オプション費用がほとんどかかりません。多くの場合、太陽光発電システムを搭載するだけで、国がより高く評価する「ZEH+」の基準さえも満たすことが可能です。これは、屋根の形状を太陽光パネルの設置効率に最適化させる必要性が低く、デザインの自由度を損なわずに高性能なZEH住宅を実現できるという大きなメリットにも繋がります。快適で健康的、かつ光熱費を抑えられ、環境にも貢献できる。まさに未来基準のスマートな暮らしを、標準仕様の延長線上で実現できるのが「ヒュースエコゼロ」です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
スウェーデンハウスで後悔しないためのポイント
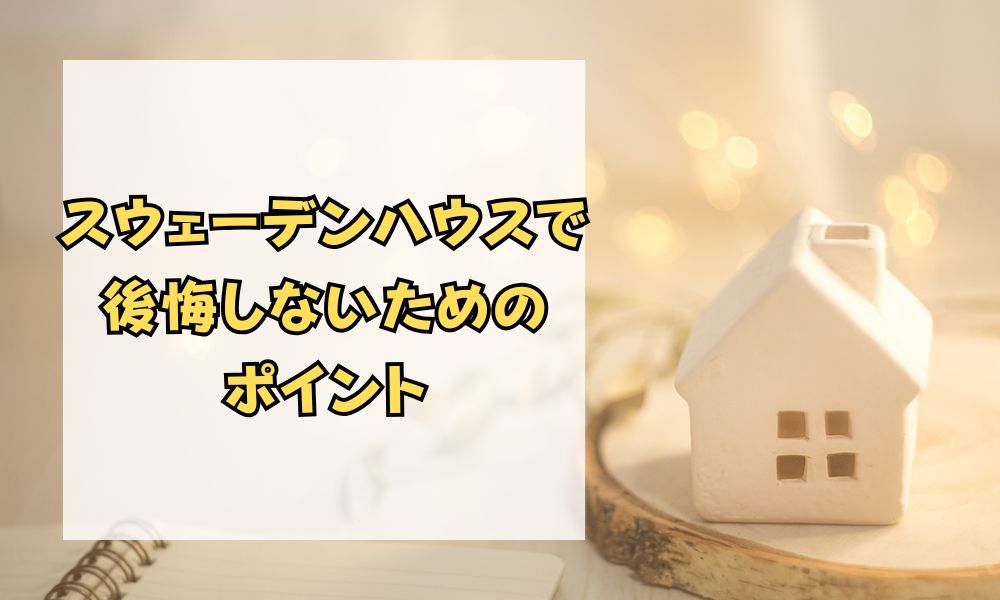
スウェーデンハウスで理想の家づくりを成功させるためには契約前の準備段階が極めて重要になります。
ここでは、後悔を避けるために不可欠な具体的な4つのステップを解説します。
情報収集を徹底
カタログやウェブサイトに並ぶ美しい写真や「C値」「UA値」といった性能数値だけでは、スウェーデンハウスの本当の価値は理解できません。
「宿泊体験」で確かめる
スウェーデンハウスが提供しているモデルハウスへの「宿泊体験」は、絶対に活用すべき絶好の機会です。
短時間の見学ではわからない、リアルな住み心地を検証しましょう。
- 温熱環境: 一晩過ごし、朝起きた時の室温をチェックします。冬であれば、暖房を切って寝た翌朝でも寒さを感じないか。夏であれば、夜中にエアコンが切れても寝苦しくないか。リビング、寝室、廊下、洗面所など、家中の温度差がほとんどない「温度のバリアフリー」を肌で感じてください。
- 遮音性: 大通り沿いのモデルハウスであれば、夜間の車の走行音がどれくらい聞こえるかを確認します。雨の日に当たれば、屋根や窓に当たる雨音が気にならないかも重要なチェックポイントです。驚くほどの静けさは、日々の暮らしの質を大きく向上させます。
- 空気環境: 24時間換気システムが作動している状態での空気の質や、就寝時の作動音の大きさを確認します。また、高気密住宅で気になる「乾燥」の度合いも体感できます。冬場であれば、喉の渇き具合や肌の乾燥感をチェックし、加湿器の必要性を判断する材料にしましょう。
- 窓の性能: 冬の朝、窓ガラスやサッシフレームに結露が発生していないかを確認してください。結露がないことは、家の健康と住む人の健康を守る上で非常に重要です。
オーナーの生の声
実際に暮らしているオーナーの話ほど、信頼できる情報源はありません。
公式サイトで紹介されている入居者宅見学会に参加したり、もし身近にオーナーがいれば話を聞いたりする機会を積極的に設けましょう。
その際は、メリットだけでなく、「実際に住んでみて感じたデメリット」や「こうすれば良かったという点」、「メンテナンスの実際の手間や頻度」など、少し踏み込んだ質問をすることが重要です。
オーナーのブログやSNSも参考になりますが、個人の主観が強いため、複数の情報を比較検討する視点を忘れないようにしましょう。
お金を洗い出す資金計画
スウェーデンハウスは初期費用が高額であるため、目先の建物価格だけで判断するのは非常に危険です。
建築費用はもちろん、入居後のランニングコストや将来のメンテナンス費用まで含めた、生涯にわたる「トータルコスト」を把握し、無理のない資金計画を立てることが不可欠です。
「総額」に含まれる費用の内訳を理解する
見積もりを取る際は、建物本体価格以外に何が含まれているのかを徹底的に確認しましょう。
一般的に、総額には以下の費用が含まれます。
- 建物本体工事費: 家そのものを建てる費用。
- 付帯工事費: 給排水・ガス・電気の引き込み工事、地盤改良工事(必要な場合)、駐車場やフェンスなどの外構工事費。
- 諸費用: 登記費用、住宅ローン手数料、火災保険料・地震保険料、印紙税、不動産取得税など。
- オプション費用: こだわりを実現するための追加費用。
これらをすべて含んだ「総費用」を早い段階で把握し、自己資金と住宅ローンでどう賄うかを計画します。
将来のランニングコストまでシミュレーションする
家計への負担は、住宅ローンの返済だけではありません。
- メンテナンス費用: 木製サッシの塗装費用(数年ごとに約20万円〜)や、24時間換気システムのフィルター交換費用などを具体的にリストアップし、長期修繕計画として積み立てていく必要があります。
- 税金: 毎年かかる固定資産税・都市計画税。
- 光熱費: スウェーデンハウスは光熱費を大幅に削減できますが、オール電化にするかガスを併用するかなど、エネルギー計画によって変動します。
これらのランニングコストを月々のローン返済額と合わせてシミュレーションし、将来の教育費や老後資金の計画と両立できるかを確認することが、安心して暮らし続けるための絶対条件です。
ライフスタイルに合った間取り
スウェーデンハウスの木質パネル工法は、高い耐震性と気密性を実現する一方で、間取りに一定の制約が伴います。
この特性を理解した上で、現在の暮らしだけでなく、10年後、20年後、さらにはその先の家族の未来まで見据えた、柔軟で飽きのこない間取りを検討することが重要です。
- 設計士に「暮らし方」を具体的に伝える:設計士との打ち合わせでは、単に「広いリビングが欲しい」といった要望を伝えるだけでなく、家族の「暮らし方」を具体的に共有しましょう。「休日は家族で何をして過ごすことが多いか」「友人を招いてホームパーティーを開く頻度は?」「夫婦それぞれの趣味は何か」「現在の住まいで不便に感じている動線は?」など、日々の生活の様子を細かく伝えることで、設計士は家族に本当にフィットするプランを提案しやすくなります。
- 将来の変化に対応できる「可変性」のある間取り:子供の成長や独立、親との同居など、家族構成は時間と共に変化します。例えば、子供が小さいうちは広い一部屋として使い、将来は壁で仕切って二部屋にできるようにしておく。あるいは、将来的に車椅子での生活も想定し、廊下やトイレの幅を広く確保しておくなど、ライフステージの変化に柔軟に対応できる「可変性」を間取りに持たせることが、長く快適に住み続けるための秘訣です。収納計画も同様に、現在の持ち物だけでなく、将来増えるであろう物量を見越して、適材適所に十分な量を確保しましょう。
担当者を見極める
家づくりは、ハウスメーカー選びであると同時に、「担当者選び」でもあります。
何千万円という大きな買い物を成功に導くためには、信頼できる営業担当者や設計士との出会いが不可欠です。
- 信頼できる担当者の見極め方:良い担当者は、自社のメリットをアピールするだけでなく、デメリットやリスクについても正直に説明してくれます。こちらの質問に対して曖昧な返事をせず、根拠を持って的確に回答できるか。契約を急がせることなく、こちらのペースに合わせてくれるか。そして何より、こちらの家族の幸せを真剣に考えてくれるか。複数の担当者と話をする中で、知識、誠実さ、そして人間的な相性を見極めましょう。
- 「相見積もり」で価値を客観的に判断する:スウェーデンハウスに心を決めている場合でも、必ず他のハウスメーカー(特に高気密・高断熱を強みとするメーカー)からも相見積もりを取り、プランを比較検討することをおすすめします。 これは単なる価格比較のためだけではありません。他社の提案を見ることで、スウェーデンハウスの強みや弱みがより客観的に浮き彫りになり、「なぜ自分たちはスウェーデンハウスを選びたいのか」という価値観を再確認することができます。また、他社の優れた点をスウェーデンハウスのプランに取り入れられるか相談するきっかけにもなります。最終的に、すべての疑問や不安が解消され、心から納得できるまで、決して契約書にサインしてはいけません。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
まとめ
ここまで、スウェーデンハウスの住宅性能、時代を超えて愛される北欧デザイン、そして価格やメンテナンスといった現実的な側面まで解説してきました。
しかし、注意しないと後悔につながるポイントがあるのも事実です。
契約をして後悔しないために、ぜひこの記事も参考に、しっかりとした情報収集を行ってみてくださいね。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
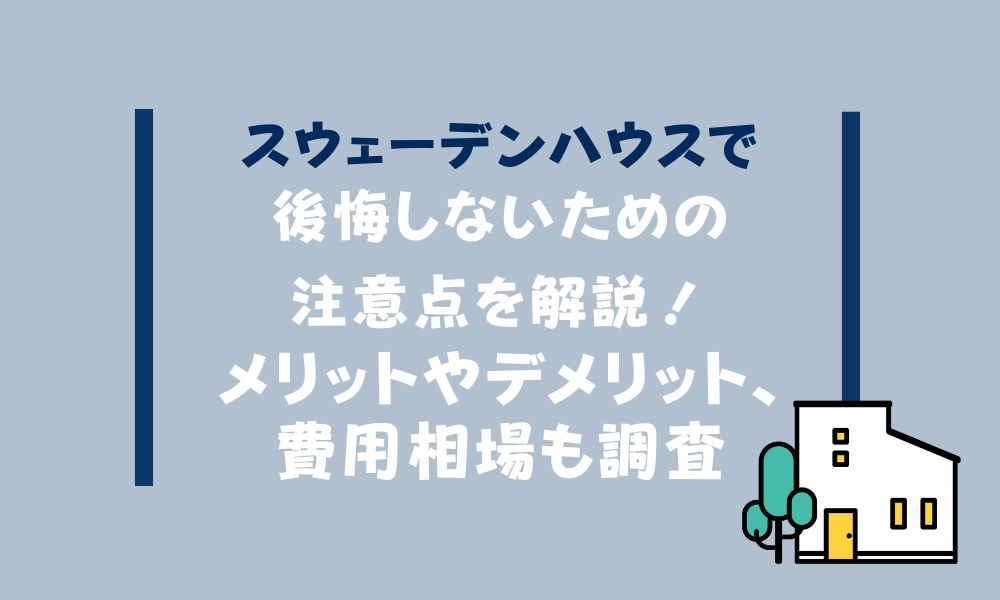

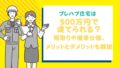
コメント