「日本ハウスHD やばい」
マイホームを検討する中で、こんな言葉を目にして、不安な気持ちになっていませんか?
日本ハウスHDは大手ハウスメーカーでありながら、なぜネット上ではネガティブな評判が目立つのでしょうか。
この記事では、国産檜へのこだわりや業界トップクラスの住宅性能といった「良い意味でやばい」と言われる圧倒的な強みから、価格の高さ、担当者の対応のばらつき、過去のトラブルといった具体的なデメリットまで、網羅的に解説します。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
本文に入る前に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えしておきます。
家づくりで一番大切なこと、それは「気になっているハウスメーカーを徹底的に比較検討すること」です。
よくある失敗パターンとして、住宅展示場に行って営業マンの巧みなトークに流されその場で契約をしてしまうというケースがあります。実際に、「もしもしっかりと比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
だからこそ、きちんとした比較検討をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
ではどのように比較検討すればいいのでしょうか。
その方法は、「ハウスメーカーのカタログをとりあえず集めてしまうこと」なんです!

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、全ての会社に連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのようにカタログを集めていいのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしい無料で利用できるサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記のサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。 |
LIFULL HOME'Sのカタログ請求は完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
後悔のない家づくりのために、1社でも多くの会社を比較検討してみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫
家づくりで後悔しないために、このサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
日本ハウスHDとは

株式会社日本ハウスホールディングスは、半世紀以上にわたり日本の住まいづくりをリードしてきたハウスメーカーです
創業以来、事業エリアを東日本から全国へと拡大していく中で、2015年5月、「株式会社日本ハウスホールディングス」へと社名を変更しました。
これまでの木造注文住宅事業を中核としながら、リフォーム事業、不動産事業、さらには海外事業までをも見据えた、総合住生活提案企業へと進化していくという強い決意が込められています。
現在では、東京証券取引所の最上位市場であるプライム市場に上場しており、これは厳しい審査基準をクリアした企業であることの証と言えるでしょう。
日本ハウスHDの家づくりの基本理念
日本ハウスHDの家づくりは、「環境に優しい脱炭素社会の住宅づくり」という明確なモットーに基づいています。
- 「日本の森林を守る『檜品質』」:外国産の安価な木材に頼るのではなく、積極的に国産材、特に日本の誇る銘木「檜」を使用すること。これは、日本の林業を活性化させ、適切に管理された森林を次世代に引き継ぐという社会的責任を果たすことにも繋がります。木材の地産地消は、輸送にかかるエネルギーを削減し、CO2排出量の抑制にも貢献します。一本一本の木材の生産地が明確な「トレーサビリティ」を確保することで、品質への責任と安心を提供しています。
- 「エネルギー自給自足を目指す『ゼロエネ品質』」:これは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準をクリアする、極めて高い省エネ性能を追求することを意味します。太陽光発電システムなどでエネルギーを「創り」、高い断熱性・気密性でエネルギー消費を「抑え」、高効率な設備でエネルギーを「賢く使う」。これにより、光熱費を大幅に削減できるだけでなく、災害時にも電気が使えるという安心感をもたらします。エネルギー問題や地球温暖化が深刻化する現代において、未来を見据えた家づくりのスタンダードです。
- 「安心安全な『快適品質』」:家族が末永く、心身ともに健康で快適に暮らせるための品質です。地震大国日本で命を守るための高い「耐震性」、世代を超えて住み継がれる「耐久性」はもちろんのこと、シックハウス症候群の原因となる化学物質を極力排除し、檜の持つ自然の力で空気を清浄に保つといった「健康配慮」も含まれます。さらに、メーターモジュールの採用によるゆとりある空間設計や、将来を見据えたバリアフリー対応など、日々の暮らしやすさを追求する快適性も重要な要素です。
国産檜への徹底したこだわり
日本ハウスHDを語る上で、絶対に欠かすことのできないのが「国産檜」へのこだわりです。
なぜ檜なのか
世界最古の木造建築物である法隆寺が、1300年以上もの時を経てなおその姿を保ち続けているのは、主材に檜が使われているからです。
檜は伐採されてから約200年間は強度が増し続け、その後1000年かけてゆっくりと元の強度に戻っていくという、他の木材にはない驚異的な特性を持っています。
この「木の王様」とも称される檜を、家の骨格となる土台や柱に贅沢に使用することで、日本ハウスHDは世代を超えて受け継がれるほどの高い耐久性を持つ住まいを実現しているのです。
檜の科学的効能
- 心安らぐ香り(リラックス効果):檜特有の爽やかな香りの正体は、「フィトンチッド」という成分です。この香りには、人間の自律神経を安定させ、心拍数を下げ、ストレスを軽減するリラックス効果があることが分かっています。檜の家に住むことは、まるで森林浴をしているかのように、日々の疲れを癒してくれることでしょう。
- 見えない敵から守る(抗菌・防虫効果):フィトンチッドには、カビや細菌の増殖を抑える抗菌作用や、ダニを防ぐ効果もあります。さらに、シロアリが嫌う成分を含んでいるため、木造住宅の天敵であるシロアリ被害のリスクを大幅に低減させます。
- 天然のエアコン(調湿効果):檜の無垢材は「呼吸」をしています。室内の湿度が高い時には湿気を吸収し、乾燥している時には水分を放出することで、室内を常に快適な湿度に保とうとします。この天然の調湿機能により、ジメジメした梅雨の時期でも過ごしやすく、冬の過乾燥や結露の発生を抑制する効果が期待できます。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
日本ハウスHDのリアルな評判・口コミ

ハウスメーカー選びにおいて、実際に家を建てた人の「生の声」は、参考となります。
ここでは、インターネット上やSNSで見られる日本ハウスHDの評判・口コミを、「良い点」と「悪い点」の両面から深掘りしていきます。
良い評判・口コミ
日本ハウスHDのオーナーからは、総じて満足度の高い声が多く聞かれます。
その理由は、カタログのスペックだけでは測れない「本質的な価値」にあるようです。
最も多く見られる良い口コミは、やはり「檜の香り」と「木の温もり」に関するものです。
「家に帰ると檜の良い香りがして、一日の疲れが癒される」「子供がアレルギー持ちだったが、この家に住んでから調子が良い気がする」といった声がありました。
また「東日本大震災を経験したが、家はびくともしなかった」「近所の家は揺れがひどかったのに、うちはほとんど揺れを感じず、安心して過ごせた」といった、災害時の安心感に関する口コミも非常に多く見られます。
悪い評判・口コミ|「やばい」は本当?
一方で、インターネット上にはネガティブな評判も存在します。
「見積もりを取ったら、ローコストメーカーの倍近くになった」「標準仕様は良いものだが、その分、基本価格が高い」といった費用面での不満は、最も多く見られる悪い口コミです。
また、「営業担当の連絡が遅く、話が進まなかった」「設計担当の提案力が乏しく、希望がうまく伝わらなかった」など、担当者の質に対する不満の声も散見されます。
日本ハウスHDの坪単価と総額費用
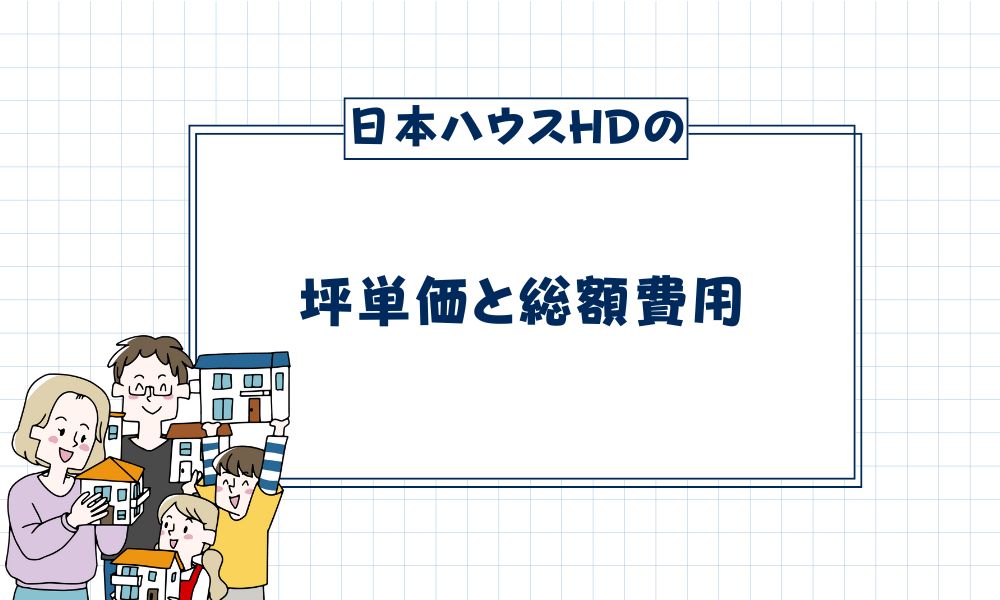
家づくりにおいて、最も気になるのが「お金」の話です。
ここでは、日本ハウスHDの坪単価の実態から、最終的に支払うことになる「総額費用」のシミュレーション、そして賢くコストを抑えるための具体的なテクニックまで解説します。
坪単価の「カラクリ」とリアルな価格帯
ハウスメーカーのウェブサイトやカタログでよく目にする「坪単価」という言葉。
しかし、この数字だけで単純に比較するのは非常に危険です。まずは、坪単価の正しい知識を身につけましょう。
多くのハウスメーカーが広告などで提示している坪単価は、「建物本体工事費」を「延床面積(坪)」で割ったものです。
しかし、家を建てるためには、この他に「付帯工事費」や「諸費用」が必ずかかります。
つまり、「坪単価 × 坪数」が、そのまま家の値段にはならないということを絶対に覚えておいてください。
さらに、坪単価は以下の要因で大きく変動するため、注意が必要です。
- 家の大きさと坪単価の関係:一般的に、延床面積が小さい家ほど坪単価は割高になります。なぜなら、キッチンやバス・トイレといったコストのかかる設備は、家の大小にかかわらず必要であり、面積が小さいとその費用負担の割合が大きくなるためです。
- 家の形状と仕様:正方形に近いシンプルな「総二階建て」が最もコスト効率が良いとされ、凹凸の多い複雑な形状の家や、平屋は坪単価が上がる傾向にあります。当然、導入する設備のグレードやオプションの数によっても価格は大きく変わります。
これらの前提を踏まえた上で、日本ハウスHDの坪単価は、おおよそ50万円~100万円が目安となります。
より具体的には、主力商品である「極」「輝」「雅」シリーズで坪70万円~90万円前後、そして最高級のフラッグシップモデル「館」シリーズでは坪100万円を超えるケースもあります。
「総額」で考える家づくり費用
賢い資金計画のためには、坪単価ではなく、最終的にいくら支払う必要があるのかという「総額費用」で考えることが不可欠です。
注文住宅の総額は、大きく分けて以下の3つの費用で構成されます(土地代は別途)。
- ① 建物本体工事費(総額の約70%):家の構造や内外装、設備など、建物そのものを作るための費用。
- ② 付帯工事費(総額の約20%):建物本体以外にかかる工事費用。
- ③ 諸費用(総額の約10%):工事以外の手続きや税金などにかかる費用。
これらの付帯工事費・諸費用(仮に建物本体価格の30%と想定)を加味した、よりリアルな総額費用のシミュレーションは以下の通りです。
| 延床面積 | 坪単価の例 | 建物本体価格(目安) | 総額費用(目安) |
| 25坪 | 66.5万円 | 約1,663万円 | 約2,162万円~ |
| 30坪 | 68万円(輝・雅など) | 約2,040万円 | 約2,652万円~ |
| 30坪 | 88.2万円(極など) | 約2,646万円 | 約3,441万円~ |
| 35坪 | 68万円(輝・雅など) | 約2,380万円 | 約3,094万円~ |
| 40坪 | 88.2万円(極など) | 約3,528万円 | 約4,589万円~ |
| 平屋 (26.7坪) | 91.3万円 | 約2,438万円 | 約3,170万円~ |
※平屋の坪単価が高くなるのは、2階建てと同じ延床面積でも、建物の土台となる「基礎」と「屋根」の面積が大きくなるため、材料費や工事費が割高になるためです。
建築費用を賢く抑えるためのテクニック
高品質な日本ハウスHDの家を、少しでも予算内で理想に近づけるための具体的なコストダウン術をご紹介します。
- 「標準仕様」を最大限に活用する:日本ハウスHDは標準仕様のグレードが高いのが魅力です。契約前に「どこまでが標準仕様に含まれるのか」を徹底的に確認し、オプションの追加を最小限に抑えることがコストダウンの基本です。
- 「凸凹」を減らし「総二階」を目指す:家の形は、できるだけ正方形に近い「総二階建て(1階と2階がほぼ同じ形)」にすると、外壁の面積や屋根の形状がシンプルになり、材料費と工事費を抑えられます。
- 本当に必要な「広さ」を見極める:むやみに廊下を作らず、リビング階段やウォークスルークローゼットを採用するなど、デッドスペースをなくす工夫で床面積を数坪減らすだけで、100万円以上のコスト削減に繋がります。
- 建具(ドア)と窓の数を最適化する:室内のドア1枚で数万円、窓1つでもサイズや性能によって10万円以上の差が出ます。収納はオープンクローゼットにしたり、風の通り道を考えて窓を効果的に配置したりすることで、数を減らしながら快適性を保つことが可能です。
- 水回りは1箇所に集約する:キッチン、洗面、浴室、トイレといった水回り設備をできるだけ近い場所にまとめることで、給排水の配管が短くなり、工事費と材料費を数十万円単位で節約できます。
- 外構工事は「分離発注」も視野に入れる:ハウスメーカーに一括で依頼せず、外構専門の業者に直接依頼する「分離発注」という方法があります。中間マージンがなくなるため、同じ内容でも2~3割安くなる可能性があります。ただし、自分で業者を探し、打ち合わせをする手間がかかる点と、住宅ローンに含められない場合がある点には注意が必要です。
- 照明やカーテンは「施主支給」を検討:照明器具やカーテンレール、タオルハンガーなどを自分で購入し、取り付けだけを依頼する「施主支給」が可能か確認しましょう。インターネットなどで安く購入できれば、コストを抑えられます。ただし、保証の対象外になる場合があるため、事前に担当者とよく相談することが重要です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
日本ハウスHDの住宅性能と特徴

日本ハウスHDの住宅が多くの人々から高く評価される理由は、単に「良い木材を使っている」というだけではありません。
「国産檜」へのこだわり
日本ハウスHDの家づくり哲学の根幹をなすのが、日本の誇る銘木「国産檜」への徹底したこだわりです。
なぜ「外国産」ではなく「国産」なのか、なぜ「檜」なのか。
そこには明確な理由があります。
木材は、育った環境の気候風土に最も適応する性質を持っています。
高温多湿で四季の変化が激しい日本で育った国産檜は、まさに日本の家づくりに最適な木材なのです。
その中でも、家の骨格となる柱や土台には、一般的な3.5寸(10.5cm)角よりも一回り太い4寸(12cm)角の檜無垢材を標準採用。
断面積で約1.3倍にもなるこの太い柱が、構造的な強度と安定感を格段に高めています。
さらに、檜が持つ科学的に証明された効能は、住む人に計り知れない恩恵をもたらします。
リラックス効果をもたらす香りの成分「フィトンチッド」は、ダニの繁殖を抑え、カビや細菌にも強い抗菌作用を発揮します。
また、無垢材ならではの優れた調湿性能は、室内がジメジメする時期には湿気を吸収し、乾燥する冬には水分を放出することで、一年中快適な湿度環境を保ちます。
これは、結露の抑制やアレルギー症状の緩和にも繋がる、まさに「天然の空気清浄機付きエアコン」と言える機能です。
断熱・気密性能
「夏涼しく、冬暖かい家」を実現するために不可欠なのが、断熱性と気密性です。
日本ハウスHDの住宅は、国の省エネ基準をはるかに超える、業界でも最高水準の性能を誇ります。
その性能を示す数値として、断熱性を示すUA値は0.25W/m2K(「館」「極」シリーズ)、気密性を示すC値は0.5㎠/㎡以下を公表しています。
UA値は数値が小さいほど熱が逃げにくく、国のZEH基準である0.6よりも遥かに高性能です。
C値は家の隙間の量を示し、数値が小さいほど隙間がなく計画的な換気が可能になります。
C値0.5という数値は、家全体で名刺の半分程度の隙間しかないことを意味し、極めて高い施工精度がなければ実現できません。
この高性能を支える技術が、壁の中に断熱材を充填する「充填断熱」と、家全体を外側から断熱材で覆う「外張断熱」を組み合わせた「付加断熱工法」です。
内と外から二重で家を魔法瓶のように包み込むことで、熱の出入りを徹底的にシャットアウトします。
さらに、家の中で最も熱が逃げやすい「窓」には、アルミサッシの約4倍の断熱性能を持つYKK AP製の高性能トリプルガラス樹脂サッシ(APW430)を標準採用。
これらの技術の組み合わせにより、厳しい基準である「Heat20 G2レベル」や「ZEHプラス基準」をクリアし、最小限のエネルギーで家中どこにいても快適な温度環境と、驚くほどの光熱費削減を両立させているのです。
新木造ストロング工法
地震大国・日本において、家族の命を守る耐震性能は最優先事項です。
日本ハウスHDは、消防署など防災の拠点となる建物と同レベルの「耐震等級3」を全棟で標準仕様としています。
その強固な構造を実現するのが、伝統的な木造軸組工法に最新技術を融合させた独自の「新木造ストロング工法」です。
4寸角の檜柱で組まれた骨格の外周に、地震や台風の水平力を面で受け止める「構造用合板」を隙間なく張り巡らせます。
これにより、家全体が一体化した強固な箱のような「モノコック構造」となり、地震の揺れによる建物のねじれを防ぎます。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
日本ハウスHDの保証とアフターサービス

家は、建てて引き渡されたら終わり、ではありません。
むしろ、そこからが数十年にわたる本当の付き合いの始まりです。
ここでは、日本ハウスHDが提供する「長期的な安心」の仕組みを、「保証」「点検」「トラブル対応」という3つの観点から深く掘り下げていきます。
最長60年間の長期保証プログラム
日本ハウスHDは、国の法律で定められた10年間の瑕疵担保責任期間を大きく超える、最長60年間の長期保証プログラムを提供しています。
これは、同社が自社の住宅の耐久性に絶対的な自信を持っていることの表れです。
しかし、「最長60年」という言葉だけを鵜呑みにせず、その仕組みと条件を正しく理解することが重要です。
この保証プログラムは、大きく分けて2つの期間で構成されています。
- 初期保証(10年間):引き渡しから最初の10年間は、構造耐力上主要な部分(柱や基礎など)と、雨水の浸入を防止する部分(屋根や外壁など)に重大な欠陥が見つかった場合、無償で修理・交換が保証されます。これは法律で定められた義務であり、どのハウスメーカーでも提供している基本的な保証です。
- 保証延長(10年ごと、最長60年まで):10年目の定期点検の際に、日本ハウスHDが指定する「有償メンテナンス工事」を実施することで、保証期間をさらに10年間延長することができます。これを繰り返すことで、最長60年まで保証を継続させることが可能です。
定期点検と「ホームドクターシステム」
保証制度が「万が一の時の保険」だとすれば、定期点検は「病気を未然に防ぐ健康診断」です。
日本ハウスHDでは、この定期点検を「ホームドクターシステム」と名付け、非常に手厚いサポート体制を構築しています。
このシステムの最大の特徴は、単なる機械的な点検で終わらない点にあります。
引き渡し後、5年目までは年に2回、6年目から10年目までは年に1回という頻度で、「感謝訪問」という名の定期訪問が実施されます。
これは、家の状態をチェックするだけでなく、住み心地に変わりはないか、何か困っていることはないかなど、オーナーとのコミュニケーションを通じて、暮らし全体を見守ることを目的としています。
まさに、家族の健康を常に気にかけてくれる「かかりつけのお医者さん」のような存在がいる安心感。
これがホームドクターシステムのメリットです。
万が一のトラブル発生時に本当に頼れるのか?
どんなに定期点検をしていても、「給湯器が壊れた」「トイレの水が止まらない」といった急なトラブルは起こり得ます。
そんな緊急時に頼りになるのが、24時間365日対応のコールセンターです。
休日や深夜を問わず、いつでも専門のオペレーターにつながるという安心感は非常に大きいものです。
日本ハウスHDで後悔しないためのデメリット

日本ハウスHDは数多くの魅力を持つ優れたハウスメーカーですが、その一方で、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔する可能性がゼロではありません。
しかし、事前に注意すべき点(デメリット)を正しく理解し、賢い対策を講じることで、これらのリスクは十分に回避できます。
価格の幅が広くプラン次第で高額になる可能性
「日本ハウスHDは高い」という評判は、最もよく聞かれるデメリットの一つです。
その理由は、①高品質な国産檜を構造材にまで使用していること、②トリプルガラスサッシなど高性能な設備が標準であること、③下請けに丸投げしない直営工事体制を維持していること、といった品質へのこだわりにあります。
そのため、ローコストメーカーと同じ感覚で見積もりを取ると、その金額に驚くかもしれません。
特に危険なのが、豪華なモデルハウスを見て「あれもいいな、これもいいな」とオプションを追加していくうちに、当初の予算を大幅に超過してしまう「予算オーバー」の罠です。
例えば、キッチンをハイグレードなものに変更(+50万円)、床材を無垢材に(+40万円)、造作のテレビボードを追加(+30万円)…といった小さな積み重ねが、気づけば数百万円の追加費用になっているケースは少なくありません。
営業担当者の知識・対応のばらつき
「担当者ガチャ」という言葉があるように、営業担当者の質にばらつきがあるのは、全国展開する大手ハウスメーカーの宿命とも言えます。
経験豊富で知識も深く、親身になってくれる素晴らしい担当者もいれば、残念ながら知識不足でレスポンスが遅い担当者に当たってしまう可能性も否定できません。
家づくりは担当者と二人三脚で進める長い道のりです。
信頼できないパートナーとでは、満足のいく家づくりは望めません。
アフターサービスへの不満・対応の遅さ
24時間対応のコールセンターや手厚い定期点検制度がある一方で、「連絡しても対応が遅い」という不満の声が一部で見られます。
これは、支店の人員体制や、修理を担当する協力業者のスケジュール、災害時などのトラブル集中といった複合的な要因によって引き起こされます。
特に緊急性の低いと判断された案件は、後回しにされてしまうケースがあるようです。
間取り・仕様の自由度と制約
日本ハウスHDは「完全自由設計」を謳っていますが、工法上の制約は存在します。
伝統的な「木造軸組工法」は、耐震性を確保するために一定の間隔で柱や「耐力壁」と呼ばれる壁が必要になります。
そのため、鉄骨造のハウスメーカーが得意とするような、「柱が一本もない30畳以上の大空間リビング」や「壁一面の大開口サッシ」といった設計には限界があります。
また、「メーターモジュール」は空間にゆとりをもたらす一方、30坪以下のコンパクトな家では、廊下やトイレが少し広くなる分、居室が狭くなるといった影響が出る可能性も考慮が必要です。
檜の床は傷つきやすい特性
無垢材である檜の床は、肌触りが良く調湿性に優れるなど多くのメリットがありますが、複合フローリングに比べて柔らかいという特性があります。
子供がおもちゃを落としたり、ペットが爪で引っ掻いたり、重い家具を引きずったりすると、比較的簡単に傷やへこみがついてしまいます。
この傷を「家族の歴史が刻まれた味わい」と捉えられるか、「気になる欠点」と捉えるかで、満足度が大きく変わってきます。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
後悔しない家づくりのための7つのステップ
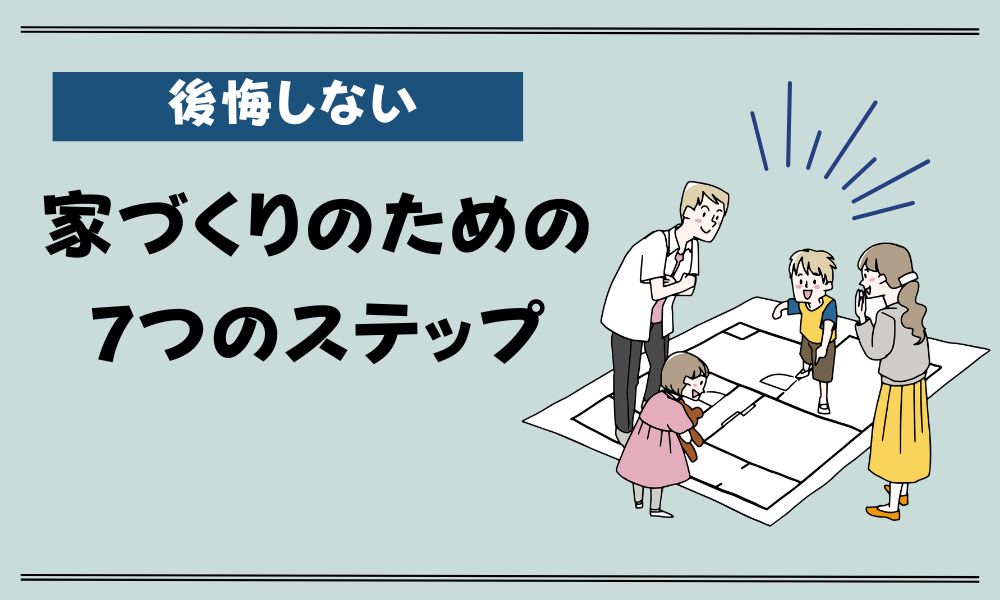
家づくりは、多くの人にとって一生に一度の大きなプロジェクトです。
ここでは、理想のマイホームを実現し、「建てて本当に良かった」と心から思えるための、具体的で実践的な7つのステップを解説します。
ステップ1:情報収集
家づくりは情報戦です。
知識の差が、数百万、時には一千万円以上の価値の差を生むこともあります。
まずは焦らず、じっくりと情報を集めることから始めましょう。
「日本ハウスHDが良いと聞いたから」と最初から一社に絞ってしまうのは、最も危険な選択です。
必ず最低でも3社、できれば5社程度のハウスメーカーや工務店を比較検討してください。
ステップ2:資金計画
家づくりで最も後悔しやすいのが、お金の問題です。
無理なローン計画は、その後の暮らしを圧迫し、幸せなはずのマイホームが苦しみの種になりかねません。
「坪単価」で予算を考えるのは絶対にやめましょう。
必ず、「建物本体工事費」+「付帯工事費」+「諸費用」+「土地代」を合わせた「総額」で考える癖をつけてください。
特に、総額の20〜30%を占める「付帯工事費」と「諸費用」は見落としがちです。
最低でも以下の費用は予算に組み込んでおきましょう。
- 付帯工事費の例:地盤改良工事(30〜200万円以上)、外構工事(100〜300万円以上)、給排水・ガス工事(80〜150万円)
- 諸費用の例:登記費用(30〜50万円)、住宅ローン手数料、火災・地震保険料(数十万円〜)、印紙代
ステップ3:要望整理
「こんな家に住みたい」という漠然としたイメージを、設計担当者に正確に伝えることは、プロでも至難の業です。
ミスマッチを防ぐためには、自分たちの要望をできるだけ具体的にしておく必要があります。
InstagramやPinterest、住宅雑誌などで見つけた「いいな」と思う家の写真(外観、リビング、キッチンなど)を、どんどんスクラップしていきましょう。
ノートに貼ったり、スマホのフォルダにまとめたりするだけで構いません。
これを見せるだけで、あなたの好みのテイストや雰囲気が、言葉で説明するよりも遥かに正確に担当者に伝わります。
ステップ4:契約
一度工事請負契約書にサインをしてしまうと、その後の仕様変更には高額な追加料金がかかったり、変更自体ができなかったりします。
契約は、すべての内容に100%納得してから行う、まさに「最後の砦」です。
契約前には、膨大な量の書類に目を通すことになります。
以下のポイントは最低限チェックしましょう。
- 見積書:「一式」という曖昧な項目はないか?すべての項目にメーカー名、型番、単価、数量が明記されているか?
- 契約書:工事請負契約書だけでなく、小さな文字で書かれた「約款」も必ず熟読してください。特に、工期が遅れた場合の対応や、契約解除に関する条項は重要です。
- 図面:間取りだけでなく、コンセントやスイッチの位置と数、窓の高さや開き方、収納内部の棚の仕様など、実際の生活をシミュレーションしながら隅々まで確認しましょう。
ステップ5:施工
契約後はハウスメーカーに丸投げではありません。
施主が積極的に現場に関わることで、施工品質は確実に向上します。
専門知識は不要です。週末に散歩がてら、以下の3つのポイントをチェックしましょう。
- 整理整頓:現場が綺麗に片付いているか。現場の美しさは、仕事の丁寧さに比例します。
- 図面との整合性:図面を持参し、窓の位置やコンセントの場所が合っているかなどを確認します。もし間違いがあっても、早い段階なら修正が容易です。
- 職人さんとのコミュニケーション:「いつもありがとうございます」と缶コーヒーを差し入れするだけでも、職人さんのモチベーションは大きく変わります。「自分の家」を建ててもらっているという意識が芽生え、より丁寧な仕事に繋がります。
ステップ6:引き渡し
ついにマイホームが完成しても、喜びのあまりチェックが甘くなってはいけません。
引き渡し前の「施主検査(内覧会)」が、不具合を無償で直してもらえる最後のチャンスです。
図面、メジャー、水平器、マスキングテープなどを持参し、家族や友人と一緒に、床や壁の傷や汚れ、建具の開閉具合、設備の動作確認などを徹底的にチェックします。
気になる箇所を見つけたら、遠慮なくマスキングテープを貼り、写真に撮って記録しましょう。
この時点での指摘は、施主の正当な権利です。
ステップ7:入居後
引き渡しを受けたら、いよいよ新しい生活のスタートです。
家の価値を長く保つために、最後の仕上げを行いましょう。
確認申請書や保証書、各種設備の取扱説明書など、引き渡された膨大な書類をファイルにまとめて一元管理しましょう。
定期点検の記録や小さな修繕の履歴も一緒に保管しておくことで、将来のリフォームや売却時に非常に役立つ「住まいの履歴書」になります。
アフターサービスを賢く活用し、大切な我が家を長く、大切に育てていきましょう。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
まとめ
ここまで、様々な角度から日本ハウスHDを徹底検証してきましたが、最終的な結論として、「日本ハウスHDは、決して“やばい”ハウスメーカーではない」ということです。
むしろ、国産檜を贅沢に使い、最高クラスの耐震性・断熱性を標準で実現する優れた企業であると言えるでしょう。
この記事で少しでも日本ハウスHDに興味を持ったら、ぜひ一度問い合わせてみてくださいね。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
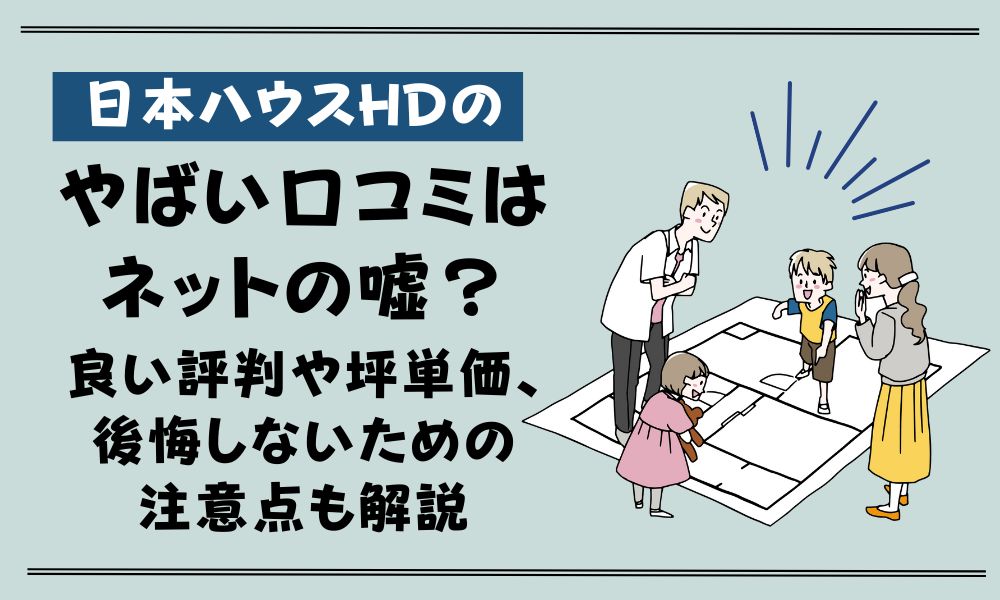


コメント