「いいだのいい家」で知られる飯田産業の住宅を検討しているけれど、インターネットで目にする「恥ずかしい」「安っぽい」といったネガティブな評判が気になり、決断に踏み切れないでいませんか?
人生で最も大きな買い物であるマイホームだからこそ、後悔だけは絶対にしたくないですよね。
そこでこの記事は、飯田産業の企業概要から、「恥ずかしい」という評判が生まれる背景、坪単価からは想像できない「耐震等級3」という強み(メリット)から、契約前に必ず知っておくべきオプション仕様や断熱性といった弱み(デメリット)まで解説していきますよ。
ぜひ最後まで参考にしてみてくださいね!
本文に入る前に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えしておきます。
家づくりで一番大切なこと、それは「気になっているハウスメーカーを徹底的に比較検討すること」です。
よくある失敗パターンとして、住宅展示場に行って営業マンの巧みなトークに流されその場で契約をしてしまうというケースがあります。実際に、「もしもしっかりと比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
だからこそ、きちんとした比較検討をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
ではどのように比較検討すればいいのでしょうか。
その方法は、「ハウスメーカーのカタログをとりあえず集めてしまうこと」なんです!

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、全ての会社に連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのようにカタログを集めていいのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしい無料で利用できるサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記のサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。 |
LIFULL HOME'Sのカタログ請求は完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
後悔のない家づくりのために、1社でも多くの会社を比較検討してみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫
家づくりで後悔しないために、このサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
飯田産業の概要と「恥ずかしい」という評判の理由

「いいだのいい家」という親しみやすいキャッチフレーズで知られる飯田産業は、日本の住宅市場、特にローコスト住宅分野において圧倒的な存在感を放つハウスメーカーです。
しかし、その圧倒的な知名度と供給数ゆえに、インターネット上では「飯田産業 恥ずかしい」といったネガティブな評判が散見されるのも事実です。
「恥ずかしい」という評判が生まれる背景
- 外観デザインの画一性からくる「安っぽい」という印象:飯田産業の住宅は、コストを抑え、効率的に建築するために、外観デザインがある程度規格化されています。 例えば、シンプルな形状の屋根や、標準的なサイディング(外壁材)が多く採用されます。分譲地では似たようなデザインの家が建ち並ぶことも多く、これが一部で「個性がなく安っぽい」という印象に繋がることがあります。 しかし、これは無駄を徹底的に省き、購入者の負担を軽減するための合理的な企業努力の結果とも言えます。
- 「安い家=質が低い」という根強い先入観:日本の住宅市場には、依然として「価格が高いものほど高品質である」という価値観が根強く残っています。そのため、飯田産業が実現している「低価格」が、そのまま「品質が低いのではないか」という先入観に結びついてしまうことがあります。 特に、建売住宅に対して「安かろう悪かろう」という古いイメージを持つ層からは、厳しい目が向けられがちです。
- 所有者自身の心理的な要因と周囲との比較:住宅は人生で最も大きな買い物の一つであり、ステータスシンボルと捉える人も少なくありません。 そのため、SNSなどで見るデザイン性の高い注文住宅や、高価格帯のハウスメーカーで建てた知人の家などと比較し、引け目を感じてしまうケースがあります。 「飯田産業=安い家」というブランドイメージが広く浸透しているからこそ、他人の評価を過剰に気にしてしまい、「恥ずかしい」という感情が芽生えてしまうのです。
飯田産業の強み・メリット

飯田産業の住宅が多くの人々に選ばれる理由は、単に「価格が安い」という一点だけではありません。
ここでは、飯田産業が持つ強み(メリット)を深掘りしていきます。
圧倒的な低価格
飯田産業の最大の魅力は、坪単価35万円~60万円程度という、他の大手ハウスメーカーでは実現が難しい価格設定です。
この驚異的な低価格は、決して品質を犠牲にして生まれるものではなく、明確で合理的な理由に基づいています。
- スケールメリットを最大限に活かしたコスト削減:飯田産業が属する飯田グループホールディングスは、年間で数万棟もの住宅を供給する日本最大のパワービルダーです。 この圧倒的なスケールを活かし、木材や住宅設備(キッチン、バス、トイレなど)をメーカーから直接、大量に一括仕入れしています。これにより、一棟あたりの材料費を劇的に抑えることが可能になります。さらに、木材の加工を自社工場で行う「プレカットシステム」を導入し、品質の均一化と現場での作業効率向上を両立。過剰なテレビCMや豪華な住宅展示場への出展を控えるなど、広告宣伝費を最小限に抑え、その分を住宅価格に還元しているのも、低価格を実現する大きな要因です。
- 予算が立てやすい「コミコミ価格」の絶大な安心感:家づくりにおいて多くの人が不安に感じるのが、契約後に次々と発生する追加費用です。飯田産業では、この不安を解消するため、初期の見積もり段階で総額に近い金額がわかる「コミコミ価格」を採用しています。一般的に別途費用となりがちな、地盤調査費、建築確認申請費、屋外の給排水工事費といった諸費用や付帯工事費の多くが本体価格に含まれています。これにより、「最初の見積もりから最終金額が大きく跳ね上がってしまった」という事態を避けやすく、購入者は安心して資金計画を立てることができます。
最高等級の耐震性能
ローコスト住宅と聞くと、安全性に不安を感じる方もいるかもしれません。
しかし、飯田産業はこの点を最も重視しており、価格以上の安心性能を提供しています。
- 全棟「耐震等級3」が標準仕様という揺るぎない安心:飯田産業の住宅は、3階建ての一部を除き、住宅性能表示制度における最高等級である「耐震等級3」を標準仕様としています。 これは、建築基準法で定められた耐震基準の1.5倍の強度を持つことを意味し、大規模な地震が発生した際に人命を守る避難所となる、消防署や警察署といった防災拠点と同等のレベルです。 地震大国である日本において、この性能が標準で備わっていることは、何物にも代えがたい大きなメリットと言えるでしょう。
- 独自の「I.D.S.工法」が支える強固な構造体:この高い耐震性を実現しているのが、飯田産業独自の「I.D.S.工法(木造軸組-パネル工法)」です。 これは、日本の伝統的な「木造軸組工法」の設計自由度の高さを活かしつつ、壁に構造用合板を張り付けて「面」で建物を支える「パネル工法」の強さを組み合わせたハイブリッドな工法です。地震の揺れを柱や梁といった「点」で受け止めるのではなく、壁全体という「面」で受け止め、力を効率的に分散させることで、建物のねじれや倒壊を防ぎます。
- 見えない部分へのこだわりが光るオリジナル金物「TロックⅡ」:さらに、基礎と建物を強固に連結するために、一般的な「ホールダウン金物」の約2倍の強度を持つオリジナル金物「TロックⅡ」を採用しています。 このように、完成後には見えなくなってしまう構造部分にまで徹底的にこだわる姿勢が、飯田産業の住宅の信頼性を支えています。
ライフステージの変化に対応する設計思想
飯田産業の家は、建てて終わりではありません。
家族の成長や変化に寄り添い、長く快適に住み続けられる工夫が凝らされています。
- 耐震性を維持しつつ、間取りの自由度を確保:前述のI.D.S.工法は、耐力壁の配置に関する制約が比較的少ないため、耐震性を確保しながらも、柱や壁の少ない開放的なリビング空間など、自由度の高い間取り設計が可能です。
- 長く住み続けるための「SI住宅」という先進的な考え方:飯田産業は、構造躯体(スケルトン)と内装・設備(インフィル)を分離して考える「スケルトン・インフィル(SI)住宅」に対応しています。 これは、建物の骨格さえしっかりしていれば、内装や設備は後から自由に変更できるという考え方です。例えば、子供の成長に合わせて部屋を間仕切りしたり、独立後に壁を取り払って広い趣味の部屋にしたりと、大規模なリフォーム工事をすることなく、ライフステージの変化に合わせた間取りの変更が容易になります。これは、住宅の資産価値を長期的に維持する上でも非常に有効な考え方です。
スピーディーな入居
- 最短49日!工期短縮がもたらす経済的メリット:徹底した規格化と効率的な生産システムにより、飯田産業では最短49日という短い工期での建築が可能です。 工期が短いことは、現場の人件費を抑え、住宅価格に反映されるだけでなく、施主にとっても現在の住まいの家賃負担や仮住まいの期間を短縮できるという直接的な経済的メリットに繋がります。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
飯田産業の弱み・デメリット
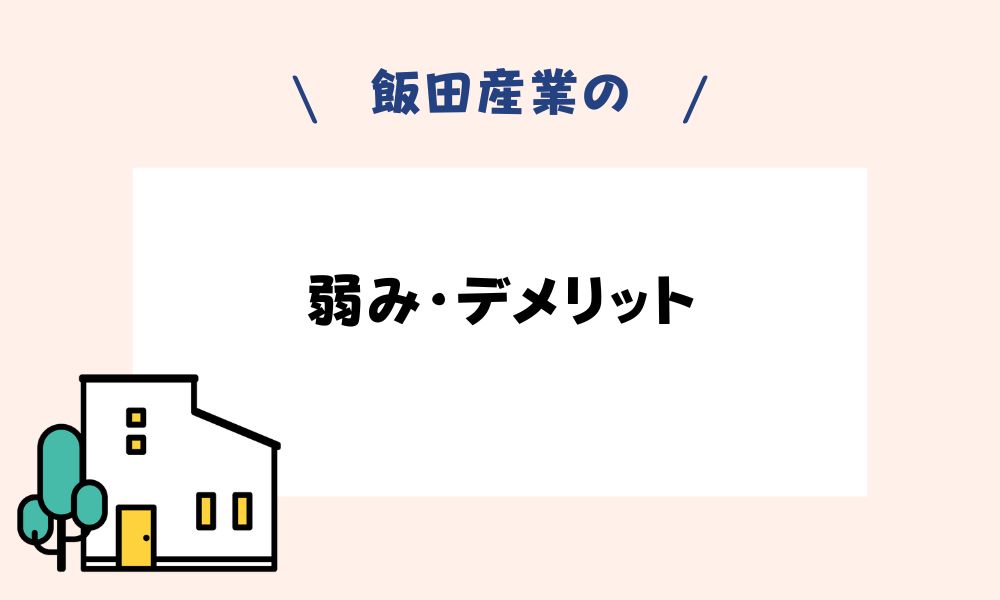
多くの強みを持つ飯田産業の住宅ですが、その魅力的な価格を実現するため、いくつかの点がデメリットになっていることも事実です。
標準仕様は「必要最低限」
飯田産業の驚異的な低価格は、建物の本体価格に含まれる仕様を「生活に最低限必要なもの」に絞り込むことで実現されています。
これは、購入者が自分のライフスタイルや予算に合わせて必要なものを自由に選択できるというメリットがある一方、注意すべき点も多く含んでいます。
- 意外な項目と追加費用:多くの人が「当然ついているもの」と思いがちな設備の多くが、オプション扱いとなっています。具体的には、網戸、カーテンレール、照明器具、テレビアンテナといった生活必需品から、食洗機、浴室換気乾燥機、カップボード(食器棚)、クローゼット内のハンガーパイプや枕棚に至るまで、多岐にわたります。これらのオプションを一般的なレベルで追加していくだけで、総額は数十万円から、場合によっては100万円以上になることも珍しくありません。最初の見積もり金額だけを見て資金計画を立てると、最終的に予算を大幅にオーバーしてしまう可能性があるため、契約前に「何が標準で、何がオプションなのか」を詳細なリストで徹底的に確認することが不可欠です。
- 標準仕様のグレードとデザインの制約:コストを最適化するため、標準仕様で選べる建具(ドアなど)、フローリング、壁紙、住宅設備(キッチン、バス、洗面台など)は、グレードやデザインの選択肢が限られています。機能的には十分なものが揃っていますが、デザイン性や質感において高級感を求める方には、やや物足りなく感じられるかもしれません。例えば、フローリングは複合フローリングが基本で、無垢材のような質感は得られにくいでしょう。内装のオリジナリティやデザインに強いこだわりがある場合は、オプションでのグレードアップや、入居後にDIYやリフォームで自分好みに変えていくことを視野に入れる必要があります。
断熱性・気密性への懸念と快適性
飯田産業の住宅は、2022年3月まで最高等級であった「断熱等性能等級4」を取得しており、国が定める最低限の基準はクリアしています。
しかし、より高いレベルの快適性を求める際には、注意が必要です。
- 公表されていない性能数値(UA値・C値):近年、住宅の省エネ性能を示す客観的な指標として、UA値(外皮平均熱貫流率:熱の逃げやすさ)やC値(相当隙間面積:家の隙間の多さ)を重視する傾向が強まっています。しかし、飯田産業はこれらの数値を公式には公表していません。これは、数値を競うような高性能住宅とは目指す方向性が異なり、あくまでコストと性能のバランスを重視しているためと考えられます。数値を基準にハウスメーカーを比較検討したい方にとっては、判断材料が少ないと感じるでしょう。
担当者や職人の「質」のバラつき
年間数万棟という膨大な数を供給する大企業だからこそ、関わる人間の数も非常に多くなり、残念ながら対応の質にバラつきが生じてしまう可能性があります。
- 営業担当者とのミスマッチ:口コミでは「連絡が遅い」「質問に対する知識が不十分」「契約を急かされる」といった営業担当者への不満の声が見られます。特に飯田産業の場合、販売窓口がグループ会社や地域の不動産仲介業者であることも多く、その担当者が必ずしも飯田産業の家の仕様や工法に精通しているとは限りません。家づくりは担当者との二人三脚で進めるため、信頼関係を築けないと感じた場合は、担当者の変更を申し出る勇気も必要です。
施工エリアが限定的であること
飯田グループ全体としては全国をカバーしていますが、「飯田産業」という会社単体で見ると、施工エリアは東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、宮城県、静岡県、愛知県、大阪府、沖縄県などに限られています。
検討している土地が施工エリアに入っているか、まずは公式サイトで確認することが第一歩となります。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
飯田産業がおすすめな人・おすすめできない人
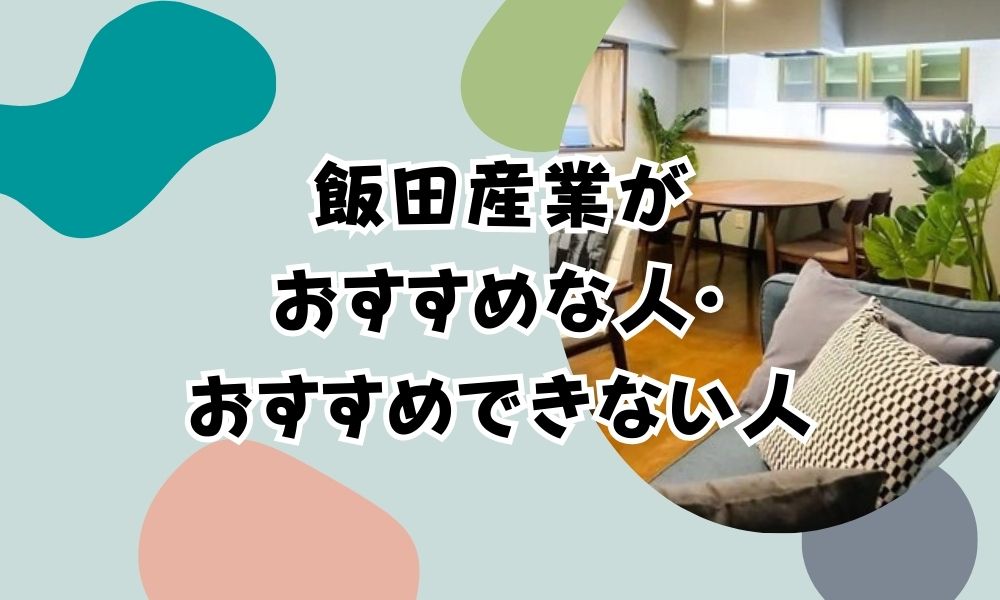
これまで見てきた飯田産業の強みと弱みを踏まえると、その住宅がどのような価値観やライフプランを持つ人に適しているかが明確になります。
飯田産業がおすすめな人
飯田産業の住宅は、特定のニーズを持つ人にとって、他のハウスメーカーにはない絶大な価値を提供します。
以下のような考え方や状況に当てはまる方には、非常に満足度の高い選択となるでしょう。
コストを最優先し賢くマイホームを手に入れたい「現実派・合理派」
何よりもまず、住宅取得にかかる総費用を抑えたいと考えている方にとって、飯田産業は最適な選択肢の一つです。
建物価格を1,000万円台~2,000万円台に抑えることで、住宅ローンの負担を大幅に軽減できます。
これにより、教育費や老後の資金、家族旅行や趣味といった「暮らしを豊かにするためのお金」に余裕が生まれます。
家はあくまで快適に暮らすための「器」と捉え、住宅ローンに縛られることなく、人生の他の楽しみも大切にしたいという合理的な考え方を持つ人に、飯田産業のコストパフォーマンスは強く響くはずです。
見た目の華やかさより「安心・安全」という本質を重視する人
家の価値は、デザインや設備の豪華さだけでは決まりません。
日々の暮らしを根底から支える「安全性能」を何よりも重視する堅実な方にも、飯田産業はおすすめです。
ローコストでありながら、国の定める最高等級である「耐震等級3」を標準仕様としている点は、飯田産業の最大の誠意とも言えます。
消防署や警察署といった防災拠点と同レベルの耐震性が、標準価格で手に入るという事実は、見えない部分の安心を重視する人にとって、何物にも代えがたい魅力となるでしょう。
建物そのものよりも「立地・周辺環境」を最優先したい人
「家は建て替えられても、土地は動かせない」という言葉があるように、住環境を家づくりの最優先事項と考える方にとって、飯田産業は強力なパートナーとなり得ます。
パワービルダーとしての圧倒的な情報網と開発力を活かし、飯田産業は好立地の土地を数多く保有しています。
一般的な注文住宅では予算的に手が届かないような人気のエリアでも、土地と建物がセットになった飯田産業の分譲住宅なら、現実的な価格で理想の立地を手に入れられる可能性が広がります。
飯田産業がおすすめできない人

一方で、家づくりに特定のこだわりや価値観を持つ方にとっては、飯田産業の家がミスマッチとなる可能性もあります。
以下に当てはまる場合は、他の選択肢も視野に入れて慎重に検討することをおすすめします。
デザイン性を徹底的に追求したい人
家に対して、住む機能だけでなく、自らの個性やセンスを表現する「作品」としての価値を求める方には、物足りなさを感じるかもしれません。
飯田産業のビジネスモデルは、仕様を規格化することでコストを抑え、多くの人に提供することにあります。
そのため、デザインの自由度や選択肢は、フルオーダーの注文住宅を専門とするハウスメーカーや設計事務所に比べて大きく制限されます。
細部にまでこだわりを反映させたい場合、その希望は叶えられない可能性が高いでしょう。
「最高水準の快適性」を初期投資で手に入れたい人
断熱性や気密性をはじめとする住宅性能について、現行の最高水準を求める方には、標準仕様では満足できない可能性があります。
飯田産業は国の基準(断熱等性能等級4)はクリアしていますが、高気密・高断熱を専門に謳う一条工務店やスウェーデンハウスのようなトップクラスの性能を標準で備えているわけではありません。
オプションで断熱性能を強化することも可能ですが、その費用を追加すると、飯田産業の最大のメリットである「価格の安さ」が薄れ、結果的に他の高性能住宅メーカーと変わらない価格帯になることも考えられます。
家づくりそのものの「プロセスや特別感」を重視する人
性能や価格だけでなく、家づくりの打ち合わせや、自分たちだけの家を創り上げていく「体験」そのものに価値を感じる方には、飯田産業の効率的なスタイルが合わないかもしれません。
特に建売住宅の場合、すでに完成品を購入するという形に近くなります。
注文住宅であっても、効率化のために仕様の選択肢はある程度パッケージ化されており、フルオーダーのような無限の自由度はありません。
スピーディーで効率的な反面、じっくりと時間をかけた家づくりを求める方にとっては、あっさりとしすぎていると感じる可能性があります。
予算に十分な余裕があり多角的な選択が可能な人
住宅にかけられる予算に制約がなく、あらゆる選択肢の中からベストなものを選びたいという方にとっては、あえて飯田産業を選ぶ理由は少ないかもしれません。
予算が潤沢であれば、デザイン性、最高レベルの住宅性能、独自技術、手厚い長期保証、高いブランドイメージと資産価値など、価格に見合った付加価値を提供するハイブランドのハウスメーカーを検討できます。
コストパフォーマンスという制約から解放されている場合、より多くの夢や希望を叶えられる選択肢が他にあると言えるでしょう。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
後悔しないための5つのチェックポイント

飯田産業で理想のマイホームを実現し、後悔を避けるためには、契約という大きな決断を下す前に、いくつかの重要なポイントを自分自身の目で確認し、深く理解しておく必要があります。
情報収集は「広く、深く、多角的に」行う
家づくりにおける最初の、そして最も重要なステップが情報収集です。
一つの情報源、特に企業の公式情報だけを鵜呑みにするのではなく、様々な角度から情報を集め、客観的な視点を養うことが後悔を避けるための鍵となります。
自分の目で「現場・現物」を徹底的に確認する
図面やカタログだけでは決してわからない、空間のスケール感や品質は、必ず自分の五感で確かめる必要があります。
面倒くさがらずに現場へ足を運ぶことが、将来の安心に直結します。
必要なオプションを明確にし、「本当の総額」を把握する
飯田産業の魅力的な価格は、標準仕様をシンプルにすることで成り立っています。
そのため、契約前にオプションの全体像と、それにかかる費用を正確に把握することが、予算オーバーを防ぐための最重要課題です。
他のハウスメーカーと「同じ土俵」で比較検討する
飯田産業が自分たちにとって本当にベストな選択なのかを確信するためには、必ず他の会社と比較検討するプロセスが不可欠です。
情報収集の段階で興味を持った2~3社に絞り込み、相見積もりを取りましょう。
比較対象としては、同じパワービルダー系の会社や、価格帯の近いローコスト系の注文住宅メーカー、地域に根差した工務店などが考えられます。
将来のライフプランと「お金の流れ」を見据えて計画する
家は、建てて終わりではありません。
そこから何十年と続く暮らしと、それに伴うお金の流れまで見据えて計画を立てることが、長期的な満足に繋がります。
「今」の暮らしやすさだけでなく、10年後、20年後の家族の変化を想像してみましょう。
子供の成長と独立、親との同居の可能性、自分たちの老後など、ライフステージの変化に対応できる間取りになっているか、将来リフォームしやすい構造(SI住宅など)になっているか、という視点を持つことが大切です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
まとめ
ここまで、飯田産業の概要から評判の真相、具体的なメリット・デメリット、そして後悔しないためのチェックポイントまで解説してきました。
飯田産業の住宅は、「圧倒的なコストパフォーマンス」と「耐震等級3という安心性能」を両立させている一方で、その価格を実現するために「標準仕様がシンプル」で「オプションが多い」という側面も持ち合わせています。
最終的な決断を下す前に、この記事で紹介した後悔しないための5つのチェックポイントをぜひ実践してください。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
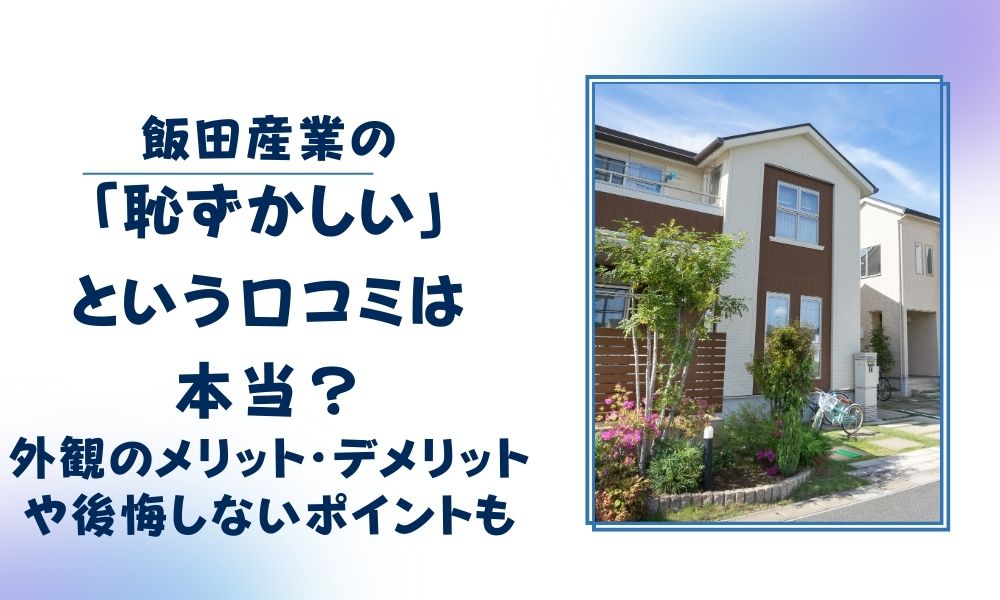
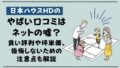
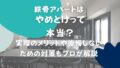
コメント