「マイホームは欲しいけれど、予算には限りがある…」
そんな悩みを抱える方にとって、1,000万円台から建てられるローコスト住宅は非常に魅力的な選択肢です。
しかし同時に、「安かろう悪かろうなのでは?」「すぐに壊れたり、夏は暑く冬は寒かったりするのでは?」といった不安や、「ローコスト住宅はやばい」というインターネット上のネガティブな評判に、一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ローコスト住宅がなぜ「やばい」と言われてしまうのか、その具体的な理由を一つひとつ解説していきます。
ぜひ最後まで参考にしてみてください。
本文に入る前に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えしておきます。
家づくりで一番大切なこと、それは「気になっているハウスメーカーを徹底的に比較検討すること」です。
よくある失敗パターンとして、住宅展示場に行って営業マンの巧みなトークに流されその場で契約をしてしまうというケースがあります。実際に、「もしもしっかりと比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
だからこそ、きちんとした比較検討をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
ではどのように比較検討すればいいのでしょうか。
その方法は、「ハウスメーカーのカタログをとりあえず集めてしまうこと」なんです!

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、全ての会社に連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのようにカタログを集めていいのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしい無料で利用できるサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」や「プロのアドバイザーに実際に相談できるサービス」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記の2つのサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。 不動産のポータルサイトSUUMOが運営する注文住宅相談サービスです。全国各地のハウスメーカー・工務店とのネットワークも豊富。スーモカウンターの最大の特徴が、店舗またはオンラインでアドバイザー相談が可能なことです。住宅の専門家に相談ができるので、住宅メーカー選びのみならず、家づくりの初歩的な質問から始めることが可能です。「何から始めたら良いのかわからない」と言う人はまずはスーモカウンターに相談することがおすすめです。 |
上記の2サイトはどれも完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
後悔のない家づくりのために、上記のサービスを活用しながら、1社でも多くの会社を比較検討してみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫

【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
家づくりで後悔しないために、これらのサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
ローコスト住宅が「やばい」と言われる主な理由
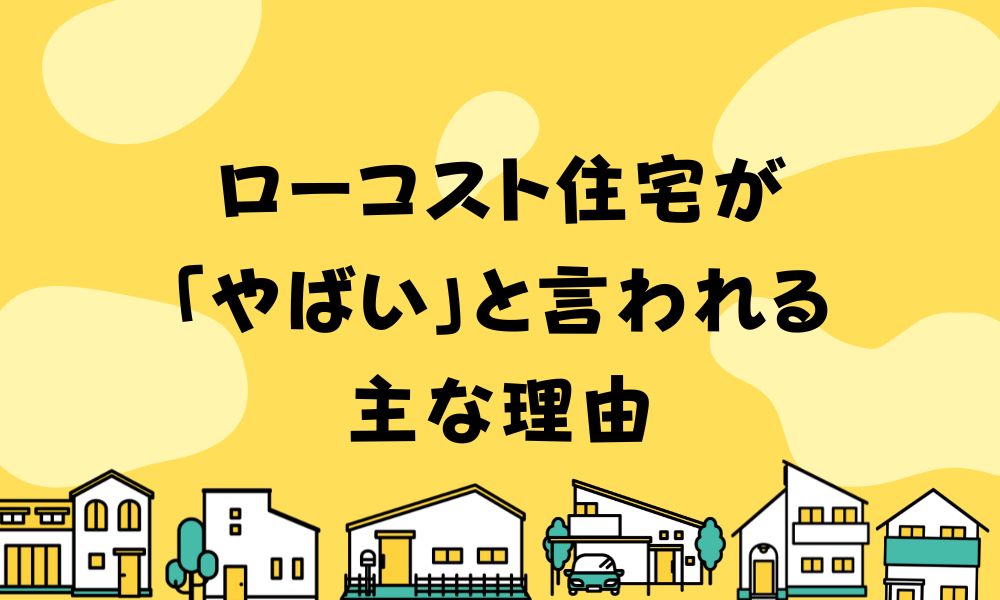
ローコスト住宅の購入を検討する際、多くの人が抱く「本当にこの価格で大丈夫なのだろうか」という漠然とした不安の背景には、価格の安さと引き換えに品質や性能面で妥協せざるを得ないのではないか、という懸念があります。
ここでは、ローコスト住宅が「やばい」と言われてしまう具体的な理由を解説していきます。
住宅としての寿命が短くなる可能性
住宅の耐久性は、使用される建材のグレードに大きく左右されます。
ローコスト住宅では、建築コストを抑えるために、日本の建築基準法で定められた最低限の基準を満たすレベルの建材が採用されるケースがあります。
例えば、構造材に安価な集成材が使われることがありますが、これは木材を接着剤で貼り合わせたもので、接着剤の経年劣化によって強度が低下する懸念が指摘されることがあります。
また、外壁や屋根材なども含め、雨風や紫外線に対する耐久性が比較的低い材料が使われると、一般的な住宅に比べて劣化の進行が早まり、結果的に住宅全体の寿命が短くなる可能性があります。
耐久性の低さは、地震や台風といった自然災害時における被害のリスクを高める一因にもなり得ます。
気密性・断熱性が低い
快適な住環境を維持する上で、住宅の気密性と断熱性は非常に重要な要素です。
ローコスト住宅では、コスト削減のために断熱材のグレードが低かったり、窓にアルミサッシが採用されたりすることがあります。
これにより、住宅全体の気密性や断熱性が低くなりがちで、外気の影響を受けやすくなります。
その結果、「夏は二階が蒸し風呂のように暑く、冬は足元から冷気が伝わってきて寒い」といった状況に陥りやすくなります。
冷暖房設備の効きも悪くなるため、快適な室温を保とうとすると電気代などの光熱費が高額になってしまうリスクも考えられます。
さらに、気密性の低さは壁の内部結露を引き起こし、カビやダニの発生原因となるなど、健康面への影響も懸念されます。
間取り・デザイン・設備の自由度が低い
ローコスト住宅が安価な価格を実現できる大きな理由の一つに「規格化」があります。
間取りやデザイン、キッチンやお風呂といった住宅設備の仕様をあらかじめパッケージ化し、選択肢を絞ることで、設計コストや打ち合わせにかかる人件費を削減しています。
そのため、凹凸の少ないシンプルな四角形の総二階建ての家が多く、個性的なデザインや複雑な間取りを実現することは難しくなります。
「ここに収納が欲しい」「書斎スペースを作りたい」といった細かな要望に応えるには、規格外のオプション扱いとなり、追加費用が発生することがほとんどです。
一般的な注文住宅のように、ライフスタイルに合わせて細部までこだわりを反映させたい方にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。
将来的なメンテナンス費用が高額になる懸念
初期費用である建築コストを抑えられても、長期的な視点で見るとメンテナンス費用がかさみ、結果的に高くついてしまうケースがあります。
これは、コストを抑えるために採用された建材や設備の耐久性が低いことに起因します。
例えば、ローコスト住宅でよく使用される外壁材「窯業系サイディング」は、定期的な目地のコーキング打ち替えや塗装の塗り替えが必要です。
これを怠ると、ひび割れから雨水が浸入し、建物の構造自体を傷める原因にもなりかねません。
屋根材や給湯器などの設備も同様で、グレードの低いものは交換サイクルが早まる傾向があります。
購入時の安さだけでなく、将来発生しうるメンテナンスコストまで含めたトータルコストで判断することが重要です。
オプション追加で総額が跳ね上がるケース
広告などで目にする「1,000万円台で建つ家」といった魅力的な価格は、あくまで最低限の設備や仕様がパッケージされた「本体価格」であることがほとんどです。
より快適な暮らしやデザイン性を求めてオプションを追加していくと、当初の想定を大幅に超える金額になることは珍しくありません。
断熱性能の向上、食洗機付きのキッチンへの変更、床材や壁紙のグレードアップ、コンセントの増設など、一つひとつの追加費用は少額でも、積み重なると大きな金額になります。
最終的な見積もりを見て、「これなら普通のハウスメーカーと変わらないのでは?」と感じることもあり、ローコスト住宅ならではの価格メリットが薄れてしまう可能性があります。
施工品質やアフターサービスへの不安
インターネット上の口コミでは、施工品質やアフターサービスに関する不安の声が見受けられます。
これは、限られた予算と人員で多くの現場を管理しなければならない状況から、職人の技術力にばらつきが出たり、現場監督のチェックが行き届きにくくなったりするリスクがあるためです。
もちろん、これはローコスト住宅に限った話ではありませんが、ネットの口コミは悪い評判の方が目立ちやすい傾向があるため、一部でそうした意見が見られるのも事実です。
また、アフターサービスに関しても、保証期間が法律で定められた最低限の10年のみであったり、定期点検の内容が簡素であったりする場合があります。
家は建てて終わりではないため、長期にわたるサポート体制が手厚いかどうかは、安心して暮らすための重要なポイントになります。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
なぜローコスト住宅は安価に建てられるのか

ローコスト住宅の圧倒的な低価格は、「品質を犠牲にしているのでは?」という疑念を抱かせることがあります。
しかし、その安さの背景には、手抜き工事のような不正行為ではなく、住宅建築のあらゆる工程を見直し、徹底的なコストカットを追求する企業の合理的な努力があります。
間取りやデザインの「規格化」で設計コストを削減
ローコスト住宅の価格を支える最大の柱が「規格化」です。
これは、あらかじめ用意された複数の間取りパターンやデザイン、仕様の中から顧客が選択する方式を指します。
ゼロから自由に設計する注文住宅とは異なり、設計にかかる時間と手間を大幅に削減できます。
これにより、設計士との複雑な打ち合わせ回数が減り、人件費を圧縮することが可能です。
また、規格化された住宅は、凹凸の少ないシンプルな形状が多いため、使用する建材のロスが少なく、施工も効率的に進められます。
この設計段階での効率化が、コストダウンと工期の短縮に直結しているのです。
建材・設備の大量一括仕入れによるスケールメリット
住宅を建てるためには、木材や断熱材、外壁材といった建材から、キッチン、バス、トイレなどの住宅設備まで、多種多様な資材が必要です。
ローコスト住宅メーカーは、使用する建材や設備の種類をあらかじめ限定し、特定のメーカーから大量に一括で仕入れることで、一つあたりの仕入れ単価を下げています。
これは「スケールメリット」と呼ばれるもので、大量購入を約束する代わりに、卸売価格を交渉しやすくする仕組みです。
施工の効率化による人件費と工期の圧縮
規格化された住宅は、建築プロセスもマニュアル化しやすく、現場での作業をスムーズに進めることができます。
例えば、構造材を工場であらかじめカットしておく「プレカット工法」などを採用することで、現場での加工作業を最小限に抑え、職人の技術力による品質のばらつきを防ぎながら、効率的に工事を進めることが可能です。
施工が効率化されることで、現場で働く作業員の労働時間が短縮され、人件費を抑えることができます。
結果として、契約から完成までの工期も2〜3ヶ月程度と、一般的な注文住宅に比べて大幅に短縮されます。
これは、建築コストを抑えるだけでなく、施主にとっても仮住まいの家賃負担を軽減できるというメリットに繋がります。
広告宣伝費の抑制で建築費用に還元
大手ハウスメーカーは、ブランドイメージ向上のためにテレビCMを放映したり、豪華な仕様のモデルハウスを総合住宅展示場に出展したりと、莫大な広告宣伝費を投じています。
これらの費用は、当然ながら最終的に住宅価格に上乗せされることになります。
一方、多くのローコスト住宅メーカーは、こうした大規模な広告展開を控え、インターネット広告やSNS、紹介キャンペーン、地域密着型の見学会などを中心に集客活動を行っています。
広告宣伝費を必要最低限に抑えることで、その分を建築費用に還元し、顧客に低価格で提供することを可能にしているのです。
ローコスト住宅の意外なメリット

ローコスト住宅は、価格の安さから性能面や品質面でのデメリットが注目されがちですが、その価格設定だからこそ得られる数多くのメリットも存在します。
コストパフォーマンスで家計にゆとりができる
ローコスト住宅最大のメリットは、何と言っても建築費用を大幅に抑えられる点にあります。
一般的な注文住宅と比較して数百万から一千万円以上の価格差が生まれることも珍しくなく、この差額が家計に与える影響は非常に大きいと言えるでしょう。
まず、住宅ローンの借入額を減らすことができるため、月々の返済負担が軽くなります。
これにより、日々の生活に経済的な余裕が生まれ、精神的な安心感にも繋がります。
手元に残った予算や浮いた資金は、新生活を彩る家具や最新の家電の購入費用に充てたり、庭や駐車場といった外構工事を充実させたりすることも可能です。
さらに、子どもの教育資金や家族旅行、趣味など、住宅以外のことにお金を回す選択肢も広がります。
将来を見据えて貯蓄や資産形成に力を入れることもできるため、特に若い世代や子育て中のファミリーにとって、マイホーム取得のハードルを下げ、豊かなライフプランを実現するための強力な後押しとなります。
スピーディーな入居が可能な短い工期
設計や施工プロセスが効率化されているローコスト住宅は、契約から完成までの工期が非常に短いことも大きなメリットです。
一般的な注文住宅では、設計の打ち合わせから完成まで1年近くかかることもありますが、ローコスト住宅の場合、半年程度で入居できるケースも少なくありません。
例えば、お子様の小学校入学や転勤のタイミングなど、「この時期までに新居へ移りたい」という明確なスケジュールがある方にとっては、非常に魅力的です。
工期が短いということは、仮住まいの期間も短縮できることを意味します。
アパートなどの家賃や駐車場代といった、仮住まいにかかる余計な費用を最小限に抑えられる点も、経済的なメリットと言えるでしょう。
また、仕様がある程度決まっているため、打ち合わせの回数や時間も少なく済み、仕事や育児で忙しい方々の負担を軽減することにも繋がります。
ライフステージの変化に柔軟に対応
高額な費用をかけて建てた家は「一生に一度の買い物」として、長く住み続けることが前提となりがちです。
しかし、ローコスト住宅は初期投資が少ないため、将来のライフステージの変化に対して柔軟な選択肢を持ちやすいというメリットがあります。
例えば、子どもたちが独立して夫婦二人だけの生活になった際に、よりコンパクトで暮らしやすい平屋に建て替える、といった決断がしやすくなります。
また、年齢を重ねて階段の上り下りが負担になった場合でも、大規模なバリアフリーリフォームや、思い切って住み替えるという選択のハードルが心理的にも経済的にも低くなります。
住宅ローンの返済が比較的早く完了すれば、その後の人生設計の自由度も大きく向上します。
「家に縛られる」のではなく、「暮らしに合わせて住まいを変えていく」という身軽な考え方を実現しやすいのも、ローコスト住宅ならではの魅力です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
ローコスト住宅に住んでみた人の口コミ・評判
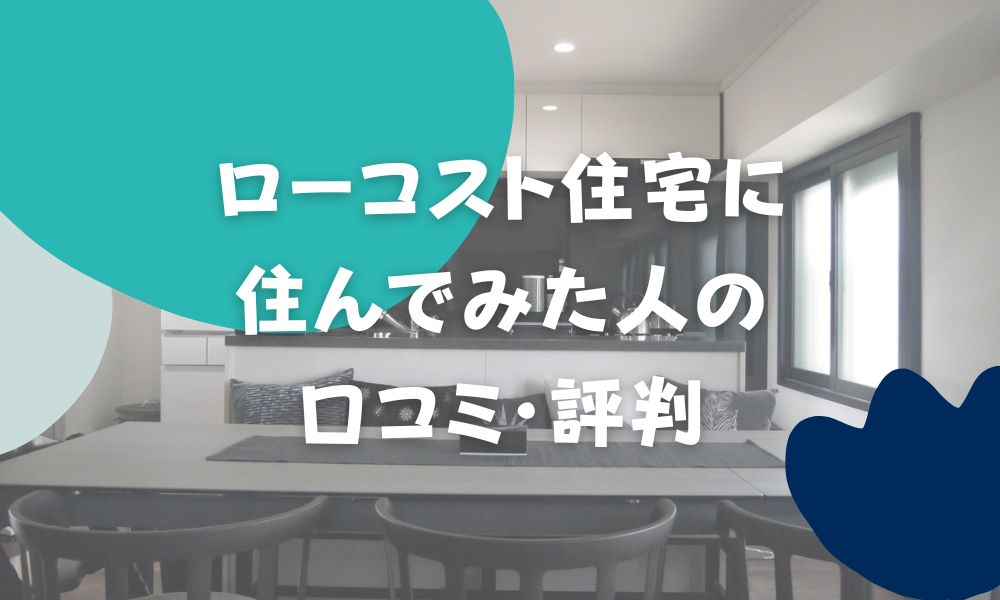
ローコスト住宅を検討する上で参考になるのが、実際に住んでいる人々の口コミです。
価格の安さというメリットの裏で、どのような現実に直面する可能性があるのか、また、どのような点に満足しているのか紹介します。
「やばい」と感じたネガティブな口コミ・評判
価格の安さと引き換えに、住み始めてから後悔や不満を感じたという声も一部で見られます。
具体的にどのような点が挙げられているのか見ていきましょう。
想定外のメンテナンス費用に悩む声
初期費用を抑えられたものの、将来的なメンテナンスコストまで考慮していなかったという後悔の声が聞かれます。
「築10年で外壁の塗り替えを考えたら150万円以上の見積もりになった」「10年点検で目地のシーリングにひび割れが見つかり、補修が必要になった」など、住み続けるための維持費が想定以上にかかるケースがあるようです。
「安っぽい」外観や内装への不満
コストを抑えた建材や内装材が使われることで、見た目のチープさが気になってしまうという意見もあります。
「フローリングやドアがアパートのようで、友人を招くのが少し恥ずかしい」「外壁材が薄い感じで、高圧洗浄をかけるのが怖い」といった声や、「壁紙の貼り方が雑で、1年ほどで継ぎ目が浮いてきた」など、施工の仕上げの粗さを指摘する口コミも見受けられました。
断熱性・遮音性の低さに関する不満
生活の快適さに直結する性能面での不満は、特に切実な問題として挙げられます。
「冬の寒さが厳しく、リビングのエアコンをつけっぱなしでも部屋が暖まらず、光熱費が毎月3万円を超えてしまった」「2階で子どもが歩く音が1階のリビングに筒抜けで、テレビの音も聞こえづらい」といった、断熱性や遮音性の低さに起因するストレスを訴える声があります。
また、「冬場は窓の結露がひどく、毎朝拭くのが大変」という悩みも聞かれます。
営業担当者や施工の質に関する問題
家そのものだけでなく、ハウスメーカーの担当者の対応や施工管理に問題があったというケースも報告されています。
「契約後は担当者と連絡が取りづらくなった」「キッチンのデザインや外壁の色など、発注ミスが何度もあった」といったコミュニケーション不足によるトラブルや、「予定より完成が半年も遅れた」という工期の遅延に関する不満も見られます。
施工に関しても、「サッシが数か所ズレていて補修が必要だった」など、品質管理への不安を感じさせる声が挙がっています。
ポジティブな口コミ・評判
一方で、デメリットを理解した上で賢く選択し、価格以上の価値を感じて満足度の高い生活を送っている人々も数多くいます。
経済的な安心感と預貯金の確保
やはり最大のメリットとして、経済的な負担の軽さを挙げる声が圧倒的に多いです。
「50坪近い広さの家を2,000万円台という価格で建てられ、コストパフォーマンスに非常に満足している」「建築費用を抑えられた分、預貯金をしっかり残すことができ、安心して新生活をスタートできた」など、住宅ローンに追われることなく、ゆとりのある生活を実現できた喜びが語られています。
思ったよりも快適に過ごせているという声
「ローコスト住宅は寒い・暑いと聞いて不安だったが、実際に住んでみると全く気にならない」という、性能面に満足している声も少なくありません。
「樹脂サッシのおかげか、冬でも結露がなく快適」「吹き付け断熱が標準仕様で、夏も冬もエアコン一台で十分過ごせる」など、ハウスメーカーを選べば、標準仕様でも高い性能を確保できるという意見が見られます。
こだわりの箇所に予算を集中できた事例
全てをハイグレードにするのではなく、予算配分を工夫することで理想の住まいを実現したという声も多くあります。
「ローコスト住宅にしたことで浮いたお金を、こだわりのキッチンや広い庭づくりに回せた」「耐震性能と断熱性能だけはオプションでグレードを上げ、老後も安心して暮らせる家にした」など、自分たちの価値観に合わせてお金をかける場所を選択できる点をメリットと感じているようです。
「広い収納スペースやロフトを付けられた」といった、間取りの工夫に満足する声も聞かれます。
アフターフォローが充実していた事例
「安いからアフターサービスは期待していなかったが、定期点検もしっかり来てくれるし、気になった部分も無料で直してくれた」といった、引き渡し後のサポート体制に満足している口コミも見られます。
アイフルホームやフジ住宅、マッケンジーハウスといった具体的な企業名を挙げて、「点検体制やアフターフォローがしっかりしている」と評価する声もあり、企業努力によって安心を提供している会社も多いことがうかがえます。
後悔しないためのローコスト住宅選びのポイント

ローコスト住宅で後悔しないためには、広告に表示されている価格の安さだけに目を奪われるのではなく、多角的な視点からハウスメーカーや住宅の仕様を慎重に検討することが重要です。
総額や各項目にかかる費用を徹底確認する
ハウスメーカーが提示する「坪単価」や「建物本体価格」は、あくまで家を建てるための基本的な費用です。
実際に住める状態にするためには、それ以外にも様々な費用が発生します。
広告の価格表示に惑わされず、付帯工事費(給排水・ガス工事など)、外構工事費、地盤改良費、各種税金、登記費用といった諸費用をすべて含んだ「総額」で資金計画を立て、比較検討することが不可欠です。
また、標準仕様でどこまでカバーされているのか、希望する設備や内装に変更する場合のオプション費用はいくらかかるのか、事前に詳細な見積もりを取り、内容を明確にしておきましょう。
さらに、将来的な外壁塗装や設備交換など、メンテナンスにかかる費用の概算も確認しておくと、長期的な視点で安心して家づくりを進められます。
住宅の構造・性能をしっかり確認する
完成後は壁や床に隠れて見えなくなってしまう構造や性能の部分こそ、住まいの快適性や安全性を左右する重要な要素です。
以下の3つの性能については、必ず確認しましょう。
- 断熱性:断熱材の種類や厚み、窓の仕様などを確認し、住宅の断熱性能を示す「UA値」をチェックしましょう。2025年4月からはすべての新築住宅で断熱等級4が最低基準となりますが、より快適な暮らしと光熱費削減のためには、それを上回る性能(UA値0.6以下が目安)を目指すことをおすすめします。
- 気密性:住宅の隙間の少なさを示す「C値」も重要です。C値が小さいほど気密性が高く、冷暖房効率が良くなります。可能であれば、全棟で気密測定を実施しているかを確認し、C値1.0以下が一つの目安となります。
- 耐震性:地震への備えとして「耐震等級」は必ず確認すべき項目です。建築基準法で定められた最低限の基準が耐震等級1ですが、より高い安心を求めるなら、長期優良住宅の認定基準でもある耐震等級2、あるいは最高等級である耐震等級3に対応しているかを確認しましょう。
自身の希望と優先順位を明確にする
ローコスト住宅は、間取りやデザインの選択肢が限られていることが多いため、自分たちが家づくりにおいて何を最も重視するのか、優先順位を明確にしておくことが成功の鍵となります。
「絶対に譲れない条件」と「ある程度は妥協できる点」を家族で事前にしっかりと話し合いましょう。
例えば、「断熱性と耐震性は最優先」「収納はできるだけ多く」「デザインはシンプルで良い」など、優先順位がはっきりしていれば、限られた予算の中でも的を絞ってオプションを選択でき、満足度の高い住まいを実現しやすくなります。
ハウスメーカーの担当者を見極める
家づくりは、ハウスメーカーの担当者と二人三脚で進めていく長い道のりです。
そのため、担当者との相性や信頼関係は非常に重要です。
説明は丁寧で分かりやすいか、こちらの質問や要望に誠実に耳を傾けてくれるか、対応はスピーディーか、メリットだけでなくデメリットもきちんと伝えてくれるかなど、人柄や姿勢をしっかりと見極めましょう。
疑問や不安を気軽に相談でき、的確なアドバイスをくれる担当者であれば、家づくりのプロセスも安心して楽しむことができます。
モデルハウスだけでなく完成見学会へ参加する
豪華なオプションが満載のモデルハウスは、夢が広がる一方で、標準仕様のイメージとは乖離していることがほとんどです。
より現実的な家のイメージを掴むためには、実際に施主が建てた家を見学できる「完成見学会」や「オープンハウス」に積極的に足を運ぶことを強くおすすめします。
標準仕様に近いリアルな家のサイズ感や建材の質感、コンセントの位置などを自分の目で確認することで、自分たちの暮らしを具体的にイメージしやすくなります。
特に、夏や冬といった厳しい季節に見学すると、その家の断熱性や気密性を肌で体感できる良い機会になります。
複数社のハウスメーカーを比較検討する
気になるハウスメーカーが見つかっても、すぐに1社に絞り込むのは避けましょう。
必ず2〜3社以上の会社から同じような条件で見積もり(相見積もり)を取り、価格だけでなく、提案される間取り、標準仕様の内容、性能、保証制度などを総合的に比較することが大切です。
複数の会社と話すことで、各社の強みや弱みが見えてくるだけでなく、住宅に関する知識も深まり、価格の妥当性を判断する目も養われます。
保証・アフターサービスの充実度を確認する
家は建てて終わりではなく、むしろそこからが本当のスタートです。
引き渡し後の定期点検や保証制度がどうなっているかは、安心して長く住み続けるために非常に重要なポイントです。
構造躯体や雨漏りに関しては法律で最低10年間の保証が義務付けられていますが、それ以上の長期保証(30年〜60年など)や、独自の保証内容を提供している会社も多くあります。
保証期間の長さはもちろん、定期点検の頻度や内容、トラブル発生時の対応などを比較し、長期にわたって信頼できるパートナーを選びましょう。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
【アドバイザーと実際に話せる!】スーモカウンターで無料相談をしてみる⇒
まとめ
この記事では、ローコスト住宅が「やばい」と言われる理由から、その安さの仕組み、意外なメリット、そして後悔しないための選び方まで解説してきました。
ローコスト住宅には、確かに断熱性や遮音性、デザインの自由度、将来のメンテナンスコストといった面で懸念点があるのは事実です。
しかし、それらは価格を抑えるための合理的な仕組みの結果であり、決して「欠陥住宅」というわけではありません。
間取りの規格化や建材の大量仕入れといった企業努力によって、若い世代でもマイホームを持つ夢を叶えやすくしているという大きなメリットがあります。
ぜひこの記事の情報も参考に、自分に合った家づくりを進めてみてくださいね。
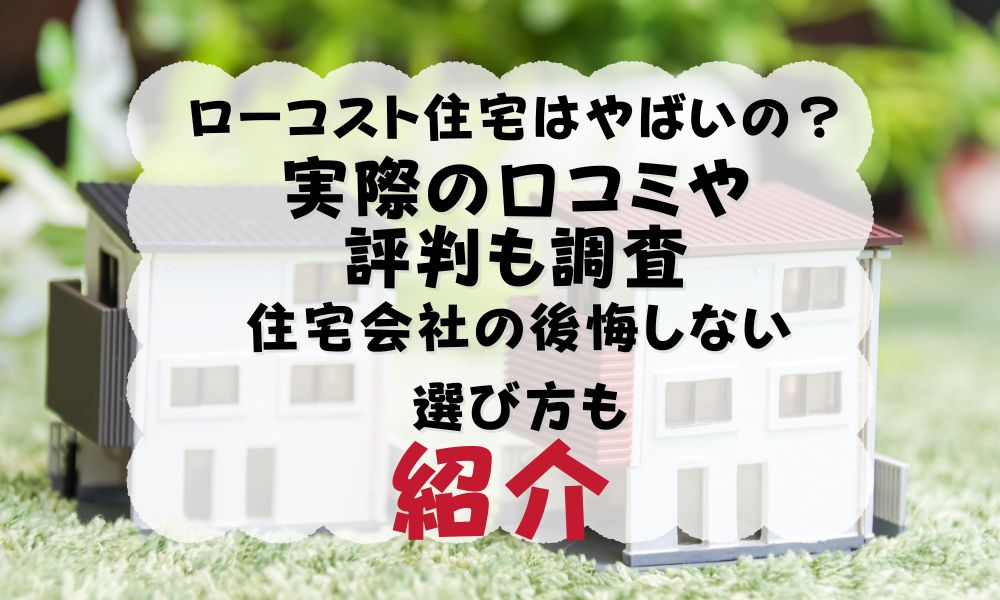


コメント