「鉄骨アパートはやめとけ」
「住んだら後悔する」
インターネットで賃貸物件を探していると、そんな言葉が目に飛び込んでくることはありませんか?
特に「軽量鉄骨造」のアパートは、防音性や断熱性の低さを理由に、ネガティブな評判が一人歩きしてしまっているのが現状です。
しかし、その情報を鵜呑みにして選択肢を最初から除外してしまうのは、非常にもったいないことかもしれません。
実は、鉄骨アパートには「木造を上回る高い耐震性」や「RC造よりも手頃な家賃」といった、暮らしの安心と経済的な余裕に直結する大きなメリットが数多く存在します。
そこでこの記事では、不動産のプロの視点から、「鉄骨アパートはやめとけ」と言われる理由を解説します。
なぜネガティブな評判が目立つのか、その具体的な理由と構造的な背景から、意外と知られていない隠れたメリットなどを網羅しました。
ぜひ最後まで参考にしてみてくださいね。
本文に入る前に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えしておきます。
家づくりで一番大切なこと、それは「気になっているハウスメーカーを徹底的に比較検討すること」です。
よくある失敗パターンとして、住宅展示場に行って営業マンの巧みなトークに流されその場で契約をしてしまうというケースがあります。実際に、「もしもしっかりと比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
だからこそ、きちんとした比較検討をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
ではどのように比較検討すればいいのでしょうか。
その方法は、「ハウスメーカーのカタログをとりあえず集めてしまうこと」なんです!

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、全ての会社に連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのようにカタログを集めていいのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしい無料で利用できるサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記のサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。 |
LIFULL HOME'Sのカタログ請求は完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
後悔のない家づくりのために、1社でも多くの会社を比較検討してみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫
家づくりで後悔しないために、このサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
「鉄骨アパートはやめとけ」と言われる背景
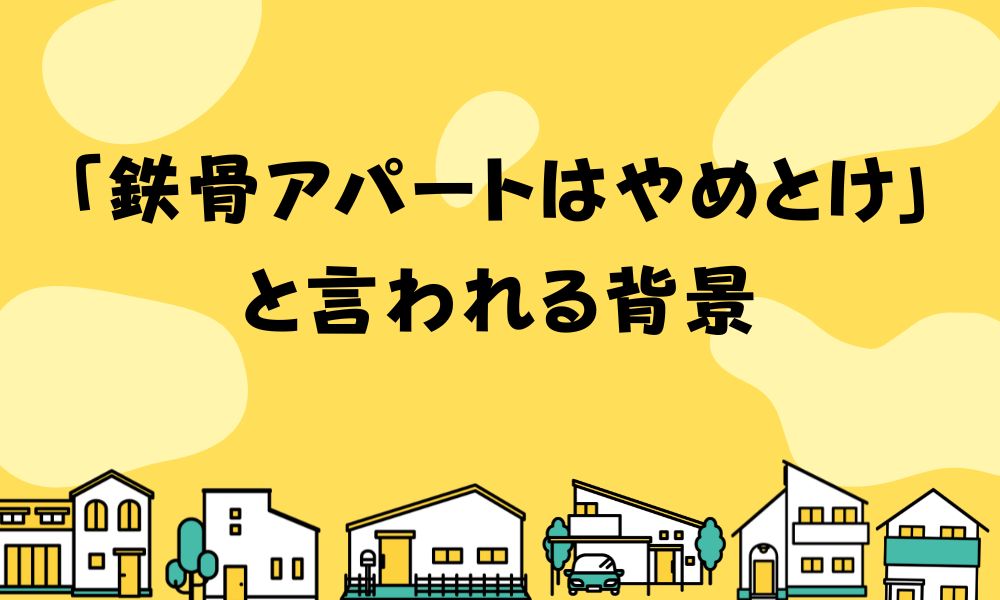
賃貸物件を探す際、間取りや立地、家賃といった条件と並んで「建物の構造」は非常に重要な要素です。
中でも、インターネットの検索窓に「鉄骨アパート」と入力すると、「やめとけ」「やばい」といったネガティブな言葉が並ぶことがあります。
これから新生活を始めようとする人にとって、このような評判は大きな不安材料となるでしょう。
なぜネガティブな評判が広まりやすいのか
「鉄骨アパート」と一括りにされがちですが、その多くは柱や梁に厚さ6mm未満の鋼材を使用する「軽量鉄骨造」を指します。
この構造は、工場で生産された部材を現場で組み立てるプレハブ工法が主流で、品質が安定し、木造より耐震性に優れるといったメリットがあります。
しかし、壁や床の基本的な構造は木造と大差ない場合が多く、特に防音性や断熱性において、より頑丈な鉄筋コンクリート造(RC造)などと比較すると性能が劣る傾向があるのは事実です。
インターネット、特にSNSや口コミサイトでは、こうしたデメリットに関する実体験が「隣人の生活音がうるさい」「夏は暑く冬は寒い」といった具体的な不満として投稿されやすく、共感を呼び拡散されやすい傾向があります。
満足している居住者の声よりも、強い不満を持った人の声の方が目立ちやすいため、実態以上にネガティブなイメージが先行してしまっている側面は否めません。
「鉄骨アパートはやめとけ」と言われる主な理由と実際の口コミ・評判
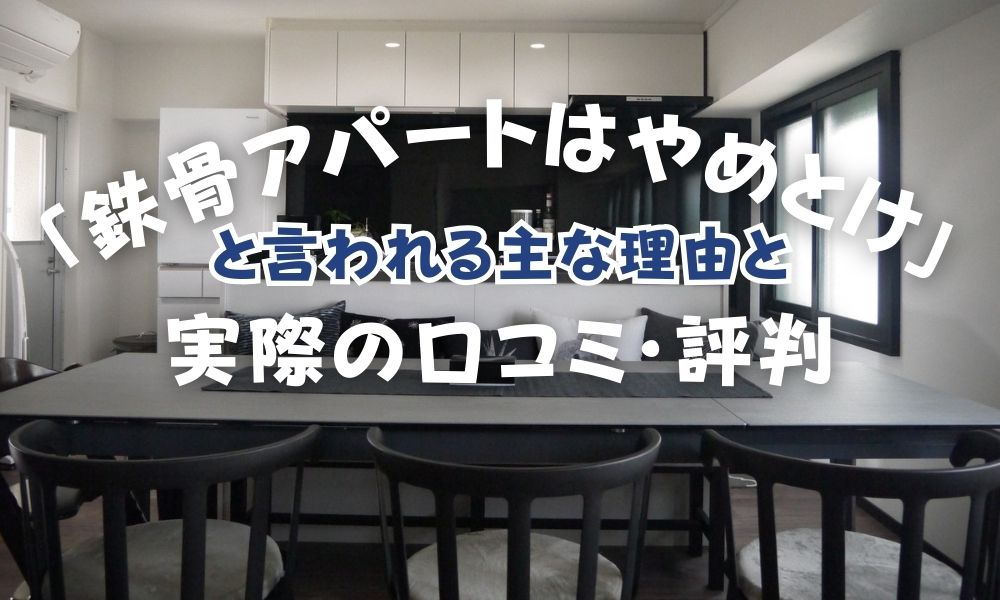
鉄骨アパート、特にアパートで主流の「軽量鉄骨造」が「やめとけ」「やばい」と言われるのには、いくつかの明確な理由が存在します。
防音性の低さによる騒音問題
軽量鉄骨造のアパートで、最も多くの人が不満を挙げるのが防音性の低さです。
「鉄骨」という言葉の響きから頑丈で音に強そうなイメージを持つかもしれませんが、実際には壁や床の構造が音の伝わりやすさに大きく影響します。
- なぜ鉄骨なのに音が響くのか?:建物の骨組みに鉄骨が使われていても、部屋を仕切る壁の内部は、木造アパートと同様に石膏ボードの間に空間(空気層)があるだけの構造が一般的です。 そのため、隣人の話し声やテレビの音といった「空気伝播音(空気を伝わって聞こえる音)」は、この壁を比較的容易に通り抜けてしまいます。日本建築学会が定める遮音等級では、木造がL-75程度、軽量鉄骨造がL-65程度とされ、RC造のL-50に比べると性能が低いことが示されています(L値は数値が小さいほど防音性が高い)。
- 振動を伝えやすい「太鼓現象」とは:さらに問題となるのが、上階の足音やドアの開閉音といった「固体伝播音(建物の構造を伝わって響く音)」です。鉄骨は木材に比べて振動を減衰させずに遠くまで伝える性質があります。 そのため、上階で発生した衝撃が鉄骨の梁を伝わり、天井や壁を太鼓の皮のように振動させて音を増幅させてしまう「太鼓現象」が起こりやすいのです。これが「ドゥンドゥン」という重低音や、建物全体が揺れるように感じる原因となります。
- 実際に聞こえる生活音のレベルとSNSでの後悔の声:SNS上では「隣の人のいびきやアラーム音で目が覚める」「掃除機をかける音や洗濯機の振動がはっきり伝わってくる」「上の階の人の歩くルートがわかるくらい足音が響く」といった切実な声が多数見られます。 もちろん、これらはあくまでネット上の数ある私見のうちの一つです。ネットの口コミは悪い評判の方が目立ちやすいので、一部そのような意見もあるという程度に捉えるべきですが、音に敏感な人にとっては深刻なストレスになり得ることは事実です。
断熱性・気密性の低さ
次に多く聞かれるのが、断熱性の低さに起因する「夏は暑く、冬は寒い」という問題です。
これも建物の構造が大きく関係しています。
- 外気の影響を直接受ける「ヒートブリッジ現象」:構造材である鉄は、木材に比べて約350倍も熱を伝えやすい性質を持っています。 外壁内部の鉄骨部分が、外の熱気や冷気を室内に直接伝えてしまう「ヒートブリッジ(熱橋)現象」が起こりやすいのです。これにより、外気温の影響をダイレクトに受け、特に外壁に面した部屋や最上階の角部屋では「夏は天然のサウナ状態」「冬はエアコンをつけても足元が冷える」といった状況になりがちです。
- エアコンが効きにくい?光熱費への影響:断熱性が低いと冷暖房の効率が悪くなり、快適な室温を保つためにエアコンを長時間フル稼働させる必要が出てきます。 その結果、「思っていたよりも光熱費が高額になった」という後悔の声につながる可能性があります。
- 気密性の高さが招く結露とカビのリスク:近年の住宅は気密性が高く作られていますが、断熱性が低いと室内外の温度差で壁内や窓に結露が発生しやすくなります。 鉄骨は湿気を通さないため、一度発生した湿気が逃げにくく、カビやダニの温床となったり、構造材である鉄骨自体の錆びにつながる恐れもあります。
火災時の強度低下
- 鉄は燃えないが「熱」に弱い:鉄骨自体は不燃材料ですが、意外にも火災時の「熱」には弱いという弱点があります。 鉄は540℃程度の熱に晒されると強度が急激に低下し始め、変形しやすくなります。 火災が続くと建物を支えきれなくなり、一気に倒壊に至る危険性が指摘されています。
- 木造は本当に火事に弱いのか?:「木造は燃えやすい」というイメージがありますが、ある程度の太さを持つ木材は、火に晒されると表面が炭化して内部への燃焼の進行を遅らせる性質があります。 一方、鉄骨は熱で強度が失われるため、耐火塗料や耐火材で鉄骨を覆う「耐火被覆」が非常に重要になります。
間取りの画一性とリフォームの制限
- 「プレハブ工法」がもたらすメリットとデメリット:軽量鉄骨造の多くは、工場で部材を生産し現場で組み立てる「プレハブ工法」で建てられます。 これにより工期が短縮でき、品質も安定しますが、一方で規格化された部材を使うため、どうしても似たような外観や間取りの物件が多くなります。
- 間取り変更を阻む「ブレース構造」の壁:軽量鉄骨造は、地震の揺れに耐えるために「ブレース」と呼ばれる筋交いが壁の中に入っていることが多くあります。このブレースが入った壁は建物の強度を保つ上で非常に重要であり、取り除くことができません。そのため、壁を壊して部屋を繋げるような大胆なリフォームは困難なケースが多いです。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
鉄骨アパートのメリット

「鉄骨アパートはやめとけ」という意見は、主に防音性や断熱性といったデメリットに焦点を当てたものですが、その一方で暮らしの安心感や経済的な負担を大きく左右する、数多くの優れたメリットも存在します。
木造を上回る耐震性の高さと地震への安心感
日本が地震大国である以上、住まいの耐震性は最も重視すべきポイントの一つです。
軽量鉄骨造は、この点で木造よりも優れた性能を発揮します。
- なぜ鉄骨は地震に強いのか?:鉄骨構造の最大の強みは、素材である鋼材が持つ「靭性(じんせい)」、つまり変形する能力と粘り強さにあります。 地震の大きなエネルギーを受けた際、木造が硬く耐えるのに対し、鉄骨はしなやかに揺れることで力を吸収し、建物全体へのダメージを逃がすことができます。 揺れは感じやすいものの、それは建物が倒壊を防ぐために正しく機能している証拠であり、ポキっと折れてしまうリスクが木造に比べて低いのです。
- 「新耐震基準」適合で得られる確かな安全性:1981年に導入された「新耐震基準」以降に建てられた物件は、震度6強から7程度の大規模な地震でも倒壊・崩壊しないことが基準となっています。 特に大手ハウスメーカーが施工した近年の物件では、さらに厳しい独自の基準を設けている場合も多く、暮らしの安心感は非常に高いと言えるでしょう。
- 建物が軽いことによるメリット:鉄骨造は、RC造(鉄筋コンクリート造)に比べて建物自体の重量が軽いため、地震の際に建物にかかるエネルギー(揺れの力)が小さくて済むという利点もあります。 この軽量性と柔軟性の組み合わせが、鉄骨造の高い耐震性を実現しているのです。
圧倒的なコストパフォーマンスと家賃の安さ
入居者にとって最も直接的なメリットは、経済的な負担の軽さでしょう。
鉄骨アパートは、その構造と建築方法から、優れたコストパフォーマンスを実現しています。
- なぜ家賃が安いのか?「プレハブ工法」の秘密:軽量鉄骨造の多くは、工場で部材を大量生産し、現場ではクレーンなどを使って組み立てる「プレハブ工法」で建てられます。 これにより、現場での作業が大幅に減り、工期が短縮されるため、人件費などの建築コストを大きく抑えることができます。 この削減されたコストが、最終的に毎月の家賃に反映されるのです。
- RC造に匹敵する安心感を、木造並みの家賃で:同じ立地や広さの物件で比較した場合、一般的に家賃は「木造≒軽量鉄骨造<重量鉄骨造<RC造」の順に高くなる傾向があります。 つまり、木造と同程度の家賃でありながら、より高い耐震性という安心感を得られる点が、軽量鉄骨造の最大の魅力と言えます。
- 法定耐用年数と実際の寿命:税法上の資産価値を示す法定耐用年数は、軽量鉄骨造の場合、鋼材の厚みによって19年〜34年と定められており、木造の22年と比較しても遜色ありません。 これはあくまで税務上の数字であり、適切なメンテナンスが行われていれば、実際の建物寿命はさらに長くなります。
工場生産による品質と施工の安定性
住んでから欠陥が見つかる、といったトラブルは絶対に避けたいものです。
その点において、軽量鉄骨造は非常に信頼性の高い構造と言えます。
- 職人の腕に左右されない安定した品質:プレハブ工法では、建物の重要なパーツが品質管理の行き届いた工場で、機械によって精密に製造されます。 そのため、現場の職人の技術力や天候によって品質がばらつくことが少なく、どの物件でも常に一定水準以上の性能が保証されています。 これは、当たり外れが少なく、欠陥住宅に当たるリスクを抑えられるという、住む側にとって大きな安心材料です。
- 大手ハウスメーカーによる技術革新:積水ハウスの「シャーメゾン」や大東建託の「DK SELECT」に代表されるように、大手ハウスメーカーが手がける軽量鉄骨アパートは数多く存在します。これらのメーカーは、長年の研究開発によって、弱点とされてきた防音性や断熱性を克服するための独自技術(高遮音床システムなど)を導入しており、「鉄骨アパート=音が響く」という従来のイメージを覆す高品質な物件も増えています。
駅近など好立地物件の多さ
- 土地活用ビジネスとしての優位性:建築コストが安く工期も短いため、土地のオーナーやデベロッパーにとっては、土地の仕入れから家賃収入を得るまでのサイクルが早く、投資効率の良いビジネスモデルとなります。 そのため、賃貸需要の高い駅の近くや商業施設の周辺など、利便性の高い場所に建てられるケースが多いのです。 通勤・通学の利便性を重視する人にとって、駅近で家賃が手頃な軽量鉄骨アパートは、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
軽量鉄骨造と他の構造の比較表

アパートやマンションの住み心地は、人間でいう「骨格」にあたる建物の構造によって大きく左右されます。
「鉄骨造」という言葉だけで判断するのではなく、木造やRC造といった他の構造との違いを正しく理解することが、後悔しない物件選びの絶対条件です。
ここでは、それぞれの構造が持つ個性と、住み心地にどう影響するのかを比較してみます。
構造別メリット・デメリット徹底比較表
| 構造 | 主な建物 | 家賃相場 | 耐震性(揺れ方) | 防音性(聞こえやすい音) | 断熱性(快適性) | 間取りの自由度 | こんな人におすすめ |
| 木造 | 2階建てアパート | 安い | △(揺れやすい) | ×(隣の話し声、テレビ音) | △(外気の影響を受けやすい) | ◎(デザイン豊富) | 家賃最優先の人、音に鈍感な人 |
| 軽量鉄骨造 | 2〜3階建てアパート | やや安い | ○(しなやかに揺れて力を逃がす) | △(上の足音、ドアの開閉音) | △(夏暑く冬寒い傾向) | △(画一的) | 家賃と耐震性のバランスを取りたい人 |
| 重量鉄骨造 | 3階建て以上マンション | やや高い | ◎(揺れにくい) | ○(話し声は聞こえにくい) | ○(比較的快適) | ○(広々空間が可能) | 開放感を求める人、性能も重視したい人 |
| RC造 | 中高層マンション | 高い | ◎(揺れをほとんど感じない) | ◎(非常に静か) | ◎(冷暖房効率が良い) | ×(壁の移動不可) | とにかく静けさを求める人、予算に余裕がある人 |
| SRC造 | タワーマンション | 非常に高い | ◎(最強) | ◎(最強) | ◎(最強) | ×(壁の移動不可) | 最高級の住環境を求める人 |
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
軽量鉄骨アパートの選び方と騒音・断熱対策
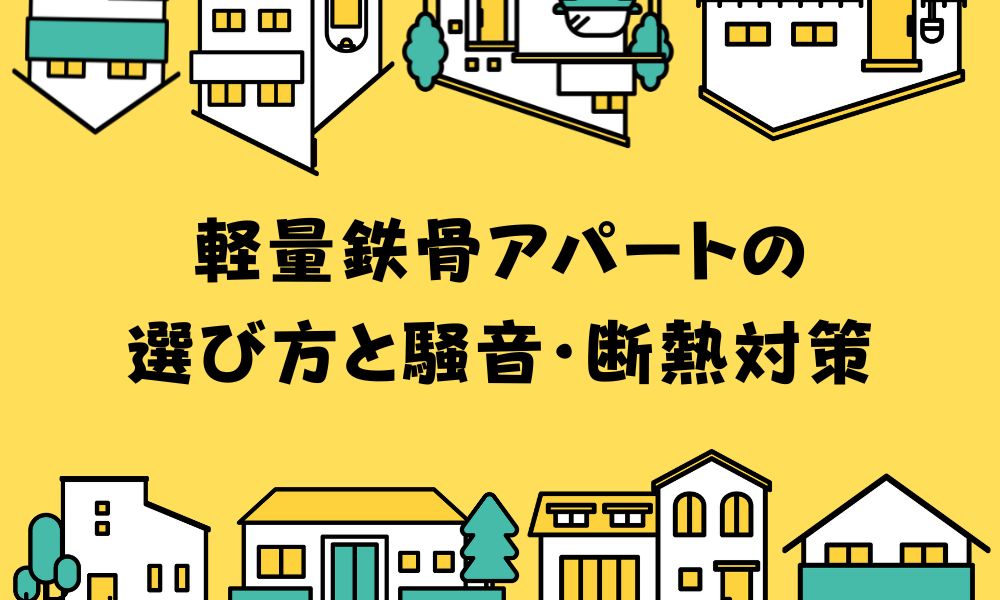
軽量鉄骨造のアパートが持つデメリットは、決して克服できないものではありません。
物件選びの段階で弱点となりうる箇所を的確に見抜き、入居後には適切な対策を講じることで、コストパフォーマンスに優れた快適な生活空間を創り出すことが可能です。
後悔しないための物件選びチェックポイント
内見は、物件のポテンシャルを最大限に見極める絶好の機会です。
間取りや日当たりだけでなく、以下のポイントを意識することで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。
① 築年数と「施工会社」で基本性能を予測する
「築浅が良い」というのは基本ですが、特に「築10年以内」の物件に注目しましょう。
近年の建築技術の進歩は目覚ましく、壁の内部に使用される断熱材や、床の衝撃音を軽減する建材の性能が格段に向上しています。
さらに重要なのが「どのハウスメーカーが建てたか」です。
例えば、積水ハウスの「シャイド55」や大東建託の「ノイズレスシステム」のように、大手ハウスメーカーは独自の高遮音床システムを開発・導入しており、従来の軽量鉄骨のイメージを覆す高い防音性を実現している場合があります。
気になる物件があれば、施工会社を調べてみる価値は十分にあります。
② 部屋の「位置」でリスクとリターンを知る
同じ建物内でも、部屋の位置によって住み心地は大きく変わります。
- 角部屋:隣接する部屋が一つ減るため、隣人の生活音のリスクは半減します。しかし、外気に接する壁面が多いため、断熱性が低い物件だと夏は暑く冬は寒くなりやすいというデメリットも考慮しましょう。
- 最上階:上階からの足音という、アパートで最も多い騒音トラブルから解放される最大のメリットがあります。一方で、屋根からの熱が直接伝わりやすく、夏場は室温が上がりやすい傾向があります。
- 1階:階下への足音を気にする必要がないため、小さなお子様がいるご家庭には大きなメリットです。ただし、防犯面の不安や、地面からの湿気、上階からの生活音が響きやすいといった点を考慮する必要があります。
③ 五感をフル活用する内見術
内見時には、以下の方法で建物の性能を体感的にチェックしましょう。
- 【聴覚】:不動産会社の担当者に許可を得て、部屋の中心で手を叩いてみましょう。音がすぐに消える(響かない)部屋は、吸音性が高く、ある程度の防音性が期待できます。また、窓を完全に閉めた状態と少し開けた状態で、外の音の聞こえ方がどれだけ違うかを確認するのも重要です。
- 【視覚】:窓ガラスを確認し、2枚のガラスで構成される「ペアガラス(二重窓)」になっているかチェックしましょう。これは断熱性・防音性の重要な指標です。また、壁紙の隅や窓のサッシ周りに、過去の結露によるシミやカビの痕跡がないかも見逃せません。
- 【触覚】:外気に面している壁を触ってみて、ひんやりと感じる場合は断熱材が不十分な可能性があります。
④ 不動産会社に聞くべき「質問リスト」
担当者への質問は、物件の隠れた情報を引き出す鍵です。遠慮せずに聞いてみましょう。
- 「この物件で、過去に騒音に関する問い合わせやトラブルはありましたか?」
- 「上下左右のお部屋には、どのような家族構成の方がお住まいですか?(例:日中不在の単身者、小さなお子様がいるご家族など)」
- 「施工会社はどちらですか?もしわかれば、壁や床にALCパネルなど、何か防音・断熱で工夫されている点はありますか?」
DIYでできる防音・断熱グレードアップ術
入居後に「思ったより音が響く」「少し寒い」と感じても、諦める必要はありません。
DIYで手軽にできる対策で、住まいの快適性は大きく向上します。
① 壁の対策
- 家具の配置を工夫する:隣室と接している壁側に、背の高い本棚や洋服ダンスを置くだけで、簡易的な防音壁になります。ポイントは、壁にぴったりつけず、数センチの空気層を設けること。この空気層が音を吸収し、効果を高めます。
- 吸音パネル・遮音シートを活用する:自分の出すテレビの音や話し声が気になる場合は、音を吸収する「吸音パネル」を壁に貼るのが効果的です。隣からの音を防ぎたい場合は、音を跳ね返す重い「遮音シート」を貼り、その上から吸音パネルを設置するとさらに効果が高まります。
② 床の対策
- 防音マット+カーペットの二重構造:床にまず防音・防振効果のあるマット(コルクマットやウレタン製マットなど)を敷き、その上に毛足の長い厚手のカーペットを敷くと、足音や物を落とした時の「ドスン」という重量衝撃音を大幅に軽減できます。
- 洗濯機・冷蔵庫には「防振マット」:モーター音や振動は意外と階下に響きます。家電の下に専用の防振ゴムマットを敷くことで、稼働音を抑えることができます。
③ 窓・ドアの対策
- 防音・遮光カーテンを選ぶ:窓は音と熱の最大の出入り口です。カーテンを選ぶ際は、生地が厚く、重量があり、ヒダの多いものを選びましょう。床に届くくらいの長さにすると、下からの音や冷気の侵入も防げます。
- 隙間テープで気密性をアップ:ドアや窓の隙間から漏れる音や風は、専用の「隙間テープ」を貼ることで簡単に防げます。これは防音だけでなく、冷暖房効率を上げる断熱対策としても非常に効果的です。
これらの対策は、一つひとつは小さな工夫ですが、組み合わせることで住まいの快適性を格段に向上させることができます。
物件の特性を理解し、賢く対策することで、軽量鉄骨アパートのメリットを最大限に享受しましょう。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
まとめ
ここまで、「鉄骨アパートはやめとけ」という言葉について、多角的に掘り下げてきました。
防音性や断熱性といった懸念点とその具体的な対策、そして、それらを上回る可能性もある耐震性、品質の安定性、コストパフォーマンスについても紹介しました。
ぜひこの記事も参考に鉄骨アパートのメリット・デメリットを比較しながら、自分に合ったアパートを見つけてみてくださいね!
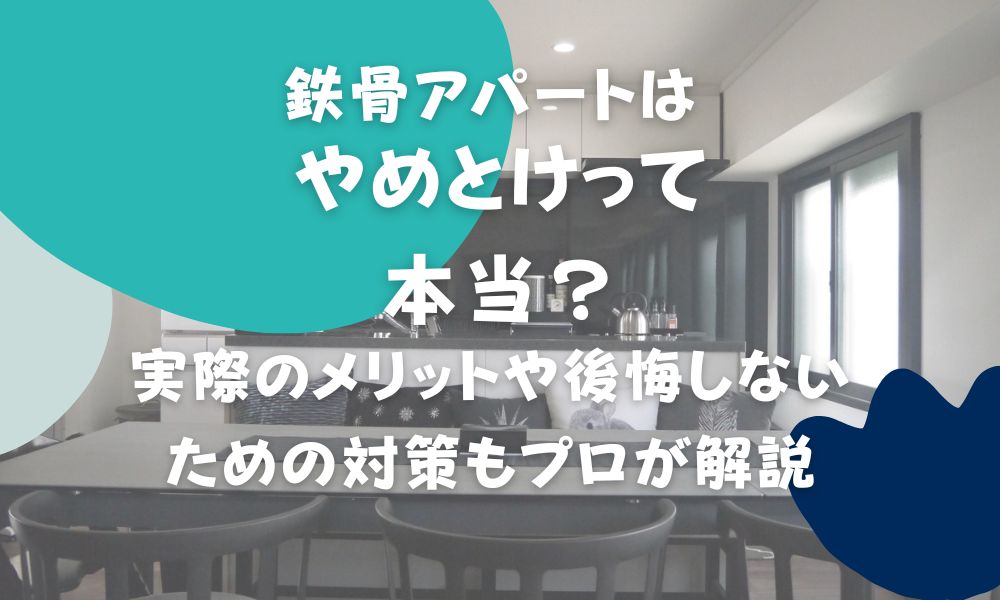


コメント