「もし、明日大地震が来ても、家族が絶対に安全だと確信できる家に住みたい」
「流行に左右されず、何十年も価値が色褪せない、資産となる家を建てたい」
「建てて終わりではなく、未来永劫にわたって安心して暮らせる保証が欲しい」
家づくりを考える多くの人がこのように思っているかもしれません。
そんなときに選択肢の一つとなるのが、旭化成ホームズが提供する「ヘーベルハウス」です。
そこでこの記事では、ヘーベルハウスのALCコンクリートと鉄骨構造の圧倒的な強みから、実際に建てたオーナーのリアルな評判・口コミ、そして後悔しないための具体的なポイントまで深掘りします。
ぜひ最後まで参考にしてみてくださいね。
本文に入る前に、後悔しない家づくりのための最も重要な情報をお伝えしておきます。
家づくりで一番大切なこと、それは「気になっているハウスメーカーを徹底的に比較検討すること」です。
よくある失敗パターンとして、住宅展示場に行って営業マンの巧みなトークに流されその場で契約をしてしまうというケースがあります。実際に、「もしもしっかりと比較検討していたら、同じ間取りの家でも300万円安かったのに・・・」と後悔する人が本当に多いんです。
だからこそ、きちんとした比較検討をせずにハウスメーカーを選ぶのは絶対にやめてください。
ではどのように比較検討すればいいのでしょうか。
その方法は、「ハウスメーカーのカタログをとりあえず集めてしまうこと」なんです!

そうは言っても、気になるハウスメーカーはたくさんあるし、全ての会社に連絡してカタログを取り寄せるなんて、時間と労力がかかりすぎるよ・・・
そう思う人も少なくありません。
そもそもどのようにカタログを集めていいのかわからないという人もいるでしょう。
そんなあなたにぜひ活用してほしい無料で利用できるサービスが、「ハウスメーカーのカタログ一括請求サービス」です!
これらのサービスを活用することで、何十倍もの手間を省くことができ、損をするリスクも最大限に減らすことができます。
中でも、不動産業界大手が運営をしている下記のサービスが特におすすめです。
|
東証プライム上場企業「LIFULL」が運営をしているカタログ一括請求サービスです。全国各地の優良住宅メーカーや工務店からカタログを取り寄せることが可能で、多くの家づくり初心者から支持を集めています。特にローコスト住宅に強いため、ローコスト住宅でマイホームを検討している若い世代や子育て世代に非常におすすめです。 |
LIFULL HOME'Sのカタログ請求は完全無料で利用できる上、日本を代表する大手企業が運営しているため、安心して利用することができます。
また、厳しい審査基準で問題のある企業を事前に弾いているため、悪質な住宅メーカーに依頼してしまうというリスクを避けることも可能です。
後悔のない家づくりのために、1社でも多くの会社を比較検討してみてくださいね!
\メーカー比較で数百万円得することも!/

【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる≫
家づくりで後悔しないために、このサービスをうまく活用しながら、ぜひあなたの理想を叶えてくれる住宅メーカーを見つけてみてください!
それでは本文に入っていきましょう!
ヘーベルハウスの特徴と強み

ヘーベルハウスの家づくりは、「ALL for LONGLIFE」というコンセプトを据えています。
ここではそんなヘーベルハウスの特徴や強みをみていきましょう。
ALCコンクリート・ヘーベルと鉄骨構造
ヘーベルハウスの品質と信頼性の象徴ともいえるのが、ALCコンクリート「ヘーベル」と、それを支える強靭な鉄骨構造の組み合わせです。
この独自の構造躯体が、地震や火災といった日本の住まいが直面する深刻なリスクに対し、圧倒的な防御力を発揮します。
- ①圧倒的な耐火性: ヘーベルは国土交通大臣認定の耐火構造部材であり、その耐火性能は他の追随を許しません。 主原料が無機質であるため、炎にさらされても燃えることがなく、有毒なガスや煙も発生しません。 万が一の火災時、隣家からのもらい火を防ぎ、自宅からの出火による延焼を食い止めることで、家族の避難時間を確保し、大切な財産を守ります。住宅が密集する都市部において、この性能は計り知れない安心感をもたらします。
- ②60年を超える耐久性: ヘーベルの内部では、化学的に安定した「トバモライト結晶」が緻密に結合しており、長期間にわたる強度低下が極めて少ないことが実証されています。 その耐久性は60年以上とも言われ、酸性雨や塩害にも強い耐性を発揮。まさに「ロングライフ」を支えるにふさわしい素材です。
- ③優れた断熱性: ヘーベル内部の無数の気泡は、空気の層となって熱の伝わりを効果的に抑制します。その断熱性は、一般的なコンクリートの約10倍にも達します。 さらに、旭化成が誇る高性能断熱材「ネオマフォーム」を組み合わせた「へーベルシェルタードダブル断熱構法」を採用。外壁と内壁の二重断熱により、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を余裕でクリアする高い断熱性能を実現し、夏は涼しく冬は暖かい、一年中快適な室内環境を保ちます。
- ④地震に強い軽量性: 高い強度を誇りながら、比重は0.6と水に浮くほど軽量であることも大きな特徴です。 建物が軽ければ、地震発生時に受けるエネルギー(揺れの力)も小さくなります。この軽量性が、基礎への負担を軽減するとともに、地震時の建物の揺れを抑え、構造体へのダメージを最小限に食い止めます。
- ⑤静かな暮らしを守る遮音性: ヘーベルの多孔質構造は、音を吸収・反射する効果も高く、優れた遮音性を発揮します。外部の車の騒音や近隣の生活音、あるいは室内からのピアノの音や子供の声が外に漏れるのを防ぎ、プライバシーが守られた静かで落ち着いた居住空間を実現します。
ヘーベルハウスは、この優れたヘーベルを、極めて強度の高い鉄骨の骨組みに組み合わせています。
構造体には、商品に応じて軽量鉄骨、または高層ビルにも用いられる重量鉄骨を採用。
この強固な骨格が、地震の巨大なエネルギーをしっかりと受け止めます。
- 「耐震」を超える「制震」という発想: ヘーベルハウスが標準採用する「ハイパワード制震ALC構造」は、地震の揺れにただ耐える「耐震」ではなく、揺れそのものを吸収し、熱エネルギーに変換して放出する「制震」という考え方に基づいています。 構造躯体に組み込まれた制震フレーム「ハイパワードクロス」が、地震の揺れを効果的に吸収。これにより、建物の変形を最大で2分の1にまで低減し、繰り返される余震に対しても効果を発揮し続けます。東日本大震災クラスの巨大地震にも耐え抜いた実績は、その性能の高さを何よりも雄弁に物語っています。
- 自由な空間設計を可能にする「ラーメン構造」: 柱と梁を剛接合することで、筋交いや耐力壁を最小限に抑えながら強靭な骨組みを形成する「ラーメン構造」や「デュアルテックラーメン構造」の採用も大きな特徴です。 これにより、壁による制約が少なくなり、開放的な吹き抜けや柱の少ない広々としたリビング、壁一面の大開口といった、自由でダイナミックな空間設計が可能になります。
手厚いアフターサービスと長期保証
家は建てて終わりではありません。
ヘーベルハウスは「ALL for LONGLIFE」の思想に基づき、建てた後も長期にわたって安心して暮らせるよう、業界でもトップクラスの手厚いアフターサポート体制を構築しています。
- 業界最高水準の「60年保証・点検システム」: 構造躯体と雨水の侵入防止に関しては、初期保証で30年という異例の長さを誇ります。 さらに、専門の認定点検技師が最大60年間にわたり5年ごとに無料点検を実施する「ロングライフプログラム」が付帯。 点検結果に基づき、必要な時期に適切な有償メンテナンスを行うことで、保証を最長60年まで延長することが可能です。 このプロアクティブな保守体制が、住まいの性能を長期間維持し、資産価値を守り続けます。
- 24時間365日の安心を提供する「へーべリアンセンター」: 水漏れや設備の不具合といった緊急トラブルから、リフォームの相談、保険の見直しまで、住まいに関するあらゆる困りごとに対応する総合窓口が「へーべリアンセンター」です。 24時間365日、専門のスタッフが対応してくれるため、いつでも安心して相談できます。また、オーナー専用サイト「HEBELIAN NET.」では、メンテナンス履歴の確認や各種手続きも可能で、オーナーとの長期的な関係性を大切にする姿勢がうかがえます。
都市型住宅と二世帯住宅に関する豊富なノウハウ
ヘーベルハウスは、特に制約の多い都市部での家づくりや、複雑な要望が求められる二世帯住宅において、長年培ってきた豊富なノウハウと実績を誇ります。
- 都市の制約を価値に変える「都市型住宅」: 敷地が狭く、防火規制などが厳しい都市部において、ヘーベルハウスの強みは最大限に発揮されます。高い耐火性能は防火地域での建築に有利であり、強靭な重量鉄骨構造は3階建て、4階建ての建築も可能にします。 天空率や斜線制限といった法規制をクリアしながら、光と風を取り込む「そらのま」のような独創的な空間提案で、限られた敷地でも快適で開放的な住まいを実現する設計力は高く評価されています。
- 40年以上の歴史が育んだ「二世帯住宅」のパイオニア: 1980年に業界に先駆けて「二世帯住宅研究所」を設立して以来、ヘーベルハウスは二世帯住宅のあり方を研究し続けてきました。 その膨大な知見とデータに基づき、完全分離型、部分共有型、完全同居型など、多様化する家族のライフスタイルや将来の変化を見据えた最適なプランを提案します。 生活音への配慮やプライバシーの確保、程よい距離感を保つ共有スペースの設計など、長年の実績があるからこそ可能なきめ細やかな提案力で、多くの家族の円満な同居生活を支えています。
高い資産価値と節税メリット
ヘーベルハウスの住宅は、その卓越した耐久性と手厚い長期保証により、長期にわたって資産価値が落ちにくいという大きなメリットがあります。
これは、将来的な売却や賃貸を考えた際にも有利に働きます。
また、税制面でもメリットが期待できます。
重量鉄骨造の法定耐用年数は34年と、木造の22年に比べて長く設定されています。
これにより、減価償却を長期間にわたって計上できるため、特に賃貸併用住宅などでは固定資産税などの節税効果が期待できるのです。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
ヘーベルハウスの評判と口コミ

ヘーベルハウスは、その堅牢な造りと手厚いサポート体制で多くのオーナーから高い評価を得ていますが、一方でその特性ゆえに価格やデザイン面で好みが分かれる部分もあります。
ここでは、インターネット上の口コミやオーナーの体験談など、実際に家を建てた人々のリアルな声をもとに、その評判を深掘りしていきます。
良い評判・口コミ
ヘーベルハウスの満足度を支えているのは、主に「安全性」「快適性」「長期的な安心感」という3つの柱です。
これらが具体的にどのように評価されているのかを見ていきましょう。
- 地震に対する信頼感: 「震度6強の揺れでも、家の中は物が少し落ちた程度で、構造の損傷は全くなかった」「周囲の家が大きな被害を受ける中、我が家だけはびくともせず、避難所になれた」
- 火災に対する安心感: 「隣家が全焼する火災だったが、我が家は外壁が少し黒ずんだだけで延焼を免れた」
- 「60年無料点検システム」への評価: 「5年ごとに専門の点検員が来て、屋根から床下まで細かくチェックしてくれるので、自分たちでは気づかない劣化も早期に発見できる」「点検結果を写真付きの報告書で丁寧に説明してくれるので、家の状態がよくわかる」
- 「へーべリアンセンター」の迅速な対応: 「給湯器が故障した際、夜中に電話したにもかかわらず、迅速に対応してくれて翌日には修理が完了した」「些細な不具合でも気軽に相談でき、すぐに対応策を教えてくれる」
- 的確な提案力とヒアリング能力: 「私たちの曖昧なイメージを丁寧にヒアリングし、期待以上の間取りプランを提案してくれた」「予算が厳しいと伝えたところ、性能を落とさずにコストダウンできる代替案をいくつも考えてくれた」
- 高い断熱性と気密性: 「真夏でもエアコンの効きが良く、一度涼しくなると快適な温度が続く」「冬は床暖房だけで家中が暖かく、朝起きるのが辛くない」
- 優れた遮音性: 「家の前が幹線道路だが、窓を閉めると車の音がほとんど聞こえない」「大雨の音も気にならず、夜静かに眠れる」
- 大空間・大開口の実現: 「柱や壁の少ない、25畳の広々としたLDKが実現できた」「リビングの壁一面をフルワイドの窓にして、庭と一体化したような開放感を味わえる」
悪い評判・口コミ
一方で、ヘーベルハウスにはいくつかのデメリットや懸念点も指摘されています。
ただし、これらの多くはヘーベルハウスの特性の裏返しであったり、どのハウスメーカーにも共通する課題であったりします。
- ヘーベルハウスの口コミで最も頻繁に指摘されるのが「価格の高さ」です。平均坪単価は約91万円〜130万円と、大手ハウスメーカーの中でも高価格帯に属します。
- 「ヘーベルハウスはどれも同じような四角い家に見える」という意見も散見されます。
- 「思ったよりも間取りの自由度が低かった」という声も一部で見られます。
- 高い断熱性を誇る一方で、「夏は2階が暑い」「冬は足元が冷える」といった口コミも存在します。
ヘーベルハウスの主な商品ラインナップ

ヘーベルハウスでは、画一的な住宅を提供するのではなく、そこに住まう家族の構成、ライフスタイル、価値観、そしてデザインの好みに寄り添うため、多彩な商品ラインナップを展開しています。
デザインと構造で選ぶ
- RATIUS GR(ラティウス ジーアール): コンセプトは「GRACEFUL ROOF(優美な屋根)」。その名の通り、水平に伸びる大きな屋根と深い軒が生み出す陰影が、建物に落ち着きと品格を与えます。軒下の空間は、雨の日でも濡れずに過ごせる半屋外の「アウトドアリビング」となり、自然との一体感を演出。夏の強い日差しを遮り、冬は室内に暖かい光を取り込むパッシブデザインの思想も取り入れられており、日本の四季を心地よく暮らしたい方に最適なモデルです。
- RATIUS RD(ラティウス アールディー): コンセプトは「RESONANCE DESIGN(共鳴するデザイン)」。都市の洗練された景観と共鳴するような、水平・垂直のラインを強調したシャープでモダンなデザインが魅力です。贅沢な素材感と緻密に計算されたディテールが、都会的な暮らしにふさわしい上質感を醸し出します。さらに高みを求める方には、最高級グレードの「FINEST VILLA」も用意されています。
- FREX3 / FREX4(3階建て・4階建てモデル): この構造の強みが最も活かされるのが、都市部の狭小地における3階建て・4階建て住宅です。縦の空間を最大限に活用し、1階にビルトインガレージ、2階に開放的なLDK、3階にプライベートな居室といった、夢の空間構成を実現します。高層ビルで培われた制震技術が応用されており、多層階であっても地震に対する安心感は格別です。店舗や事務所、賃貸住宅との併用など、多様なニーズに柔軟に応えることができます。
ライフスタイルから選ぶ
- my DESSIN(マイデッサン): 「デザインは、選ぶ時代へ。」をコンセプトにした、新しい発想のセミオーダー住宅です。数多くの実績から導き出された優れた間取りプランや、プロのインテリアデザイナーが厳選した内外装のコーディネートパターンの中から、好みのものを組み合わせていくスタイル。一からすべてを決める自由設計の難しさや時間的な負担を軽減しつつ、デザイン性の高い住まいを、価格を抑えて手に入れることができます。
- onefitto(ワンフィット): 新しい生活様式にジャストフィットする工夫が満載のモデル。玄関から洗面所へ直行できる「ただいま動線」や、テレワークに集中できる半個室の「ワークスペース」、おうち時間を充実させる「アウトドアリビング」など、現代の暮らしのニーズにきめ細かく応えるアイデアが随所に盛り込まれています。
- そらのま+(ソラノマプラス): 都市型住宅の傑作ともいえる空間提案。2階リビングに隣接して設けられた、高い壁に囲まれた空に開かれた半屋外空間「そらのま」が特徴です。周囲の視線を気にすることなく、光と風をたっぷりと室内に取り込むことができ、都会の中心にいながらにして、圧倒的な開放感を味わうことができます。
- のきのまent(ノキノマ エント): 玄関を単なる「出入りの場」から「暮らしの場」へと変える新しい提案。深い軒のある広々とした玄関ポーチ空間「のきのま」は、子どもの遊び場やDIYスペース、ご近所さんとのお茶飲み場など、多目的に使えるコミュニケーションスペースとして機能します。
専門特化型モデル
- Asu-haus(アスハウス): 2024年5月に販売が開始された、ヘーベルハウス初の本格的な木造住宅。鉄骨のイメージが強い同社が木造を手掛ける背景には、業界最高水準である断熱等級7を標準仕様とする圧倒的な断熱性能と、鉄骨造では表現しにくいナチュラルモダンなデザインを求める層へのアプローチがあります。ただし、現時点では限定販売となっています。
- LONG LIFE ZEH: ヘーベルハウスが誇る60年以上の耐久性と、国が推進するZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)基準の高い省エネ・創エネ性能を融合させた、未来基準の住まい。光熱費を抑え、環境に貢献しながら、世代を超えて安心して住み継げるという、まさに「ロングライフ」を体現したモデルです。
- 賃貸併用住宅「ESCORT GRAND」: 自宅の一部を賃貸にすることで、家賃収入を住宅ローンの返済に充て、安定した資産形成を目指すプランです。60年という長期にわたる耐久性は、賃貸経営の安定性を高める大きな強みとなります。旭化成不動産レジデンスによる30年一括借上げシステムも用意されており、オーナーの負担を軽減するサポート体制も万全です。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
ヘーベルハウスが向いている人・向いていない人
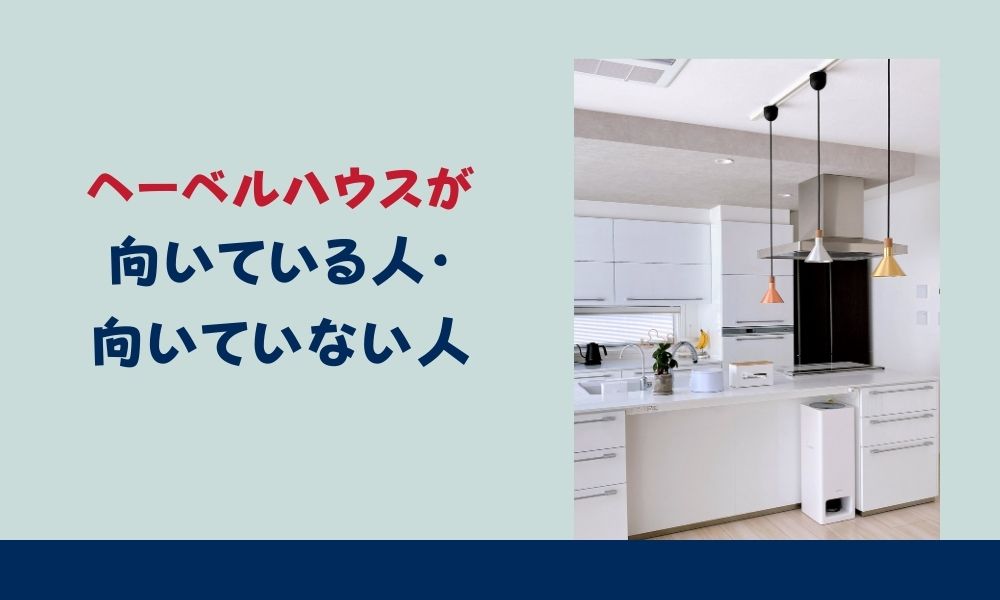
ヘーベルハウスの家づくりは、その明確な哲学と独自の技術に基づいているため、多くのメリットがある一方で、すべての人にとって最適な選択とは限りません。
ヘーベルハウスが向いている人の特徴
ヘーベルハウスを選ぶ人は、単に「家」というモノを求めているのではなく、「長期にわたる安心と快適な暮らし」という価値に対して投資するという意識が強い傾向にあります。
- 将来起こるとされる南海トラフ地震や首都直下型地震といった大規模災害を現実的な脅威として捉え、家族の命を守ることを家づくりの絶対条件と考えている方。
- 初期投資はかかっても、メンテナンスをしながら良い家に長く住み続けたいと考える方。
- 親世帯と子世帯、それぞれのプライバシーやライフスタイルを尊重しつつ、必要な時にはサポートし合える「程よい距離感」を大切にしたいと考える家族。
- 土地代が高い都市部で、防火地域や準防火地域に指定された狭小地や変形地しか手に入らなかったが、それでも広々とした明るい家を諦めたくない方。
- 華美な装飾や奇抜なデザインよりも、素材の持つ重厚感や、直線が生み出すフォルムの美しさを重視する方。
ヘーベルハウスが向いていない人の特徴
一方で、ヘーベルハウスの特性が、ある特定の価値観や要望とは相容れない場合もあります。
- 予算に厳格な上限があり、まずは手の届く価格でマイホームを実現したいと考える方。
- 南欧風の瓦屋根やアール壁、輸入住宅のような装飾的なデザインなど、特定のスタイルに強い憧れがある方。
- 「木の香りに包まれて暮らしたい」「無垢材の床の肌触りや、経年変化を楽しみたい」といった、五感で感じる心地よさを家づくりで最も大切にしたい方。
- 東北、北陸、四国、沖縄など、ヘーベルハウスの営業所がない地域にお住まいの方。
- お子様の小学校入学や転勤など、入居したい時期が明確に決まっており、スケジュールに全く余裕がない方。
建築費用を抑えるポイント

高品質・高性能であるがゆえに、価格帯が高めになるヘーベルハウス。
しかし、「高いから」と諦める前に、いくつかのポイントを押さえることで、予算内で理想の家づくりに近づけることは十分に可能です。
設計・仕様の選択
建築費用に最も大きく影響するのが、設計と仕様です。
家づくりを始めると夢が膨らみがちですが、すべての要望を盛り込むと予算はあっという間に膨れ上がります。
重要なのは、家族にとっての「価値の優先順位」を明確にし、予算を賢く配分することです。
- 最強のコスト効率「総二階」: 1階と2階がほぼ同じ面積・形状の「総二階建て」は、最もコスト効率に優れた形です。凹凸(でこぼこ)の多い複雑な形状にすると、外壁の面積やコーナー部分が増え、基礎や屋根の工事も複雑になるため、材料費と工事費の両方が増加します。外観に強いこだわりがなければ、できるだけシンプルな箱型を目指すのがコストダウンの基本です。
- 屋根の形状を見直す: ヘーベルハウスの象徴でもあるフラットルーフ(陸屋根)は、屋上利用ができるというメリットがありますが、防水工事などにコストがかかります。「新大地」のような一般的な勾配屋根(寄棟や切妻)の方が、コストを抑えられる場合があります。
- 「廊下」と「ホール」をなくす: 廊下や2階のホールは、移動のためだけのデッドスペースになりがちです。リビング階段を採用して廊下をなくしたり、各部屋へのアクセスをリビング経由にするなど、間取りを工夫することで、延床面積を数坪単位で削減できる可能性があります。一般的に、1坪(約3.3㎡)減らすと、数十万円単位のコストダウンに繋がります。
- 窓の数とサイズを最適化する: 窓は壁よりもコストがかかる部材です。採光や通風に必要な場所以外の窓を減らしたり、サイズを小さくしたり、開閉できないFIX窓を効果的に使うことで、コストを抑えつつデザイン性を高めることも可能です。
- 「こだわりポイント」を明確に: 例えば、「キッチンは毎日使う場所だから、最新の食洗機やタッチレス水栓を入れたい。でも、あまり使わないゲスト用のトイレは標準仕様で十分」といったように、家族のライフスタイルに合わせて予算を配分しましょう。
- 施主支給を検討する: 照明器具、カーテン、タオルハンガーといったアクセサリー類は、自分でインターネットや専門店で購入し、ヘーベルハウスに取り付けだけを依頼する「施主支給」という方法があります。デザインの選択肢が広がり、コストを大幅に抑えられる可能性があります。ただし、保証の対象外になったり、取り付け費用が別途かかったり、そもそも施主支給が認められない設備もあるため、必ず事前に営業担当者に確認が必要です。
補助金・減税制度の徹底活用
国や自治体は、良質な住宅の普及を促進するために、様々な支援制度を用意しています。
これらを活用しない手はありません。
- 国の大型補助金をチェック: 「子育てエコホーム支援事業」や「ZEH支援事業」など、省エネ性能の高い住宅を対象とした国の補助金は、数十万~百万円単位になることもあり、非常に大きな助けとなります。これらの制度は年度ごとに内容が変わるため、常に最新の情報を営業担当者に確認してもらいましょう。
- 自治体独自の制度も探す: お住まいの市区町村が、独自に太陽光発電システムの設置や、地場産材の利用に対して補助金を出している場合があります。自治体のウェブサイトなどで必ず確認しましょう。
- 減税制度も忘れずに: 省エネ性能の高い住宅は、「住宅ローン控除(減税)」の控除額が大きくなるなど、税制面でも優遇されます。また、親や祖父母から資金援助を受ける場合の「贈与税の非課税措置」も、賢く活用したい制度です。これらの制度は複雑なため、専門家である営業担当者に相談し、最適な活用法を提案してもらうことが重要です。
賢い価格交渉のテクニック
ヘーベルハウスはブランド価値を重視するため、大幅な値引きは期待できないとされています。
しかし、タイミングや交渉の仕方によっては、満足のいく結果を得られる可能性があります。
- 交渉のベストタイミングは「契約直前」: 他のハウスメーカーとも比較検討していることを伝え、最終的にヘーベルハウスに決めたいという「契約の意思」を明確に示した上で、「この条件であれば即決します」という形で交渉するのが最も効果的です。
- 狙い目は「決算期」: 多くの企業の決算期である3月や、半期決算の9月は、会社が売上目標を達成するために契約を急ぐ傾向があり、交渉が有利に進む可能性があります。
- 「金額」ではなく「サービス」を狙う: 直接的な値引きが難しい場合、「キッチンのグレードを無料でアップしてほしい」「床暖房をサービスしてほしい」といったように、オプション設備をサービスしてもらう「物品サービス」での交渉も有効な手段です。
セミオーダーという賢い選択
完全自由設計のモデルは魅力的ですが、当然ながら費用も高額になります。
そこで検討したいのが、セミオーダータイプの商品です。
- 「my DESSIN(マイデッサン)」を理解する: この商品は、数多くの実績から導き出された優れた間取りプランや、プロが厳選したデザインパターンの中から、好みのものを組み合わせていくスタイルです。プランや仕様を限定することで、設計コストや部材の仕入れコストを合理化し、価格を抑えることを可能にしています。
- 性能はそのままにコストダウン: 設計の自由度は下がりますが、ヘーベルハウスが誇る耐震性・耐久性・断熱性といった基本性能は、上位モデルと何ら変わりません。「デザインに強いこだわりはないが、家の性能や安全性は絶対に妥協したくない」という方にとっては、最も合理的で賢い選択肢となるでしょう。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
後悔しない家づくりの注意点

ここでは「こんなはずではなかった」「もっとこうしておけば良かった」といった後悔を未然に防ぐために、家づくりのプロセスで必ず心に留めておきたい「5つの鉄則」を解説します。
鉄則1:徹底的な「比較検討」
ヘーベルハウスの堅牢性やブランド力に強く惹かれていたとしても、最初から一社に絞り込むのは賢明ではありません。
あえて競合他社と比較検討することで、ヘーベルハウスの本当の強みや、逆に弱点となりうる部分が客観的に見えてきます。
- 何を比較するのか?: 同じ鉄骨造を得意とする積水ハウス、ダイワハウス、パナソニックホームズなどを比較対象にするのが定石です。単に坪単価だけでなく、「標準仕様で何が含まれているか(制震装置、断熱材の性能など)」「保証制度の内容と期間」「設計の自由度」「デザインの方向性」といった多角的な視点で比較表を作成してみましょう。
鉄則2:「総額」で考える
家づくりで最も陥りやすい失敗の一つが、資金計画の甘さです。
建物の「本体工事費」だけを見て予算を組んでしまうと、後から次々と発生する費用に頭を悩ませることになります。
住宅ローンを組む際には、以下の諸経費もすべて含めた「総額」で資金計画を立てる必要があります。
- 登記関連費用: 土地や建物の所有権を登録するための費用(登録免許税、司法書士報酬など)。
- 税金: 不動産取得税、契約書に貼る印紙税など。
- ローン関連費用: 金融機関に支払う手数料や保証料。
- 保険料: 火災保険・地震保険料(長期一括払いが一般的)。
- 付帯工事費: 地盤が弱い場合の「地盤改良費」、上下水道の引き込み工事費など。
- 外構工事費: 駐車場、門、フェンス、植栽など。後回しにしがちですが、総額の10%程度を見ておくのが一般的です。
- その他: 家具・家電購入費、カーテン代、引っ越し費用、仮住まい費用など。
鉄則3:担当者は「相性」で見極める
家づくりは、担当者と二人三脚で進める数ヶ月から1年以上にわたる長いプロジェクトです。
知識や経験はもちろん重要ですが、それ以上に「この人になら本音で話せる」「信頼して任せられる」と感じられるかどうかが、満足度を大きく左右します。
鉄則4:「記録」と「確認」を徹底
- 打ち合わせ議事録: ヘーベルハウスでは通常、打ち合わせ後に内容をまとめた議事録を作成してくれます。これにサインをする前に、内容が自分たちの認識と完全に一致しているか、隅々まで確認してください。この議事録が合意の記録となります。
- 自分でも必ずメモを取る: 議事録には残らないような、担当者との会話のニュアンスや、次回の打ち合わせまでの宿題、ふと浮かんだ疑問点などを自分の言葉で記録しておきましょう。
- 図面は「虫の目」で見る: 間取り図や詳細図面は、ただ眺めるのではなく、虫眼鏡で見るくらいの意識で細かくチェックしましょう。特に、「コンセント・スイッチの位置と数」「窓の種類・高さ・開閉方法」「ドアの開き勝手」「収納内部の棚の仕様」といったディテールは、実際の暮らしの快適性に直結します。メジャーを片手に、家具の配置をシミュレーションしながら確認するのがおすすめです。
鉄則5:客観性で調査してもらう
家づくりに夢中になると、どうしても視野が狭くなり、冷静な判断ができなくなることがあります。
そんな時は、意図的に一歩引いて、利害関係のない第三者の客観的な意見に耳を傾けることが非常に有効です。
- ファイナンシャルプランナー(FP)に相談する: 住宅ローンは、人生で最も大きな借金です。ハウスメーカー提携のFPではなく、独立系のFPに相談することで、現在の家計状況だけでなく、将来の教育資金や老後資金まで見据えた、無理のない返済計画について客観的なアドバイスをもらえます。
- ホームインスペクター(住宅診断士)を検討する: 契約前の図面チェックや、建築中の施工品質チェックを、専門家の第三者に依頼するサービスです。費用はかかりますが、「プロの目でチェックしてもらった」という安心感は何物にも代えがたい価値があります。
- 経験者の「失敗談」に学ぶ: 実際に家を建てた友人や知人の話は、何よりの参考になります。特に聞くべきは、華やかな成功談よりも「こうすれば良かった」というリアルな失敗談です。「住んでみて初めて気づいたコンセントの位置」「意外と使わなかったオプション設備」など、具体的な後悔ポイントは、あなたの家づくりを成功に導く最高の教科書となります。
\【当サイト厳選】後悔しない家づくりのために!/
【ローコスト住宅が中心】LIFULL HOME'Sの無料カタログを取り寄せる⇒
まとめ
これまで、ヘーベルハウスの構造と手厚い保証から、リアルな評判、具体的な商品ラインナップなどを解説してきました。
確かに、初期費用は他のハウスメーカーに比べて高価であり、デザインには一定の制約があります。
しかし、日々の安心感と、60年先まで見据えた資産価値への対価と考えることもできるっでしょう。
最終的にヘーベルハウスがあなたの家族にふさわしいかどうかは、何を最優先事項とするかが重要です。
ぜひこの記事も参考に理想の家づくりを進めてみてくださいね!

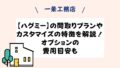
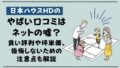
コメント